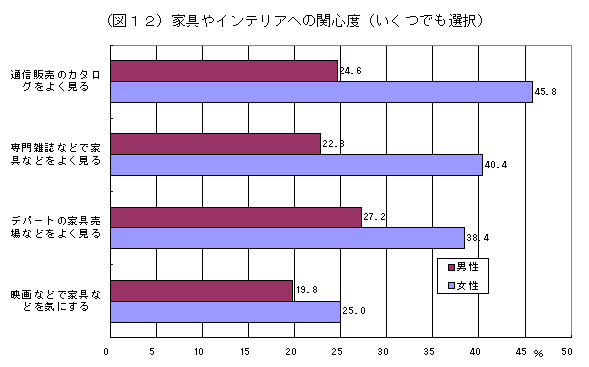-
・デザインに対する選別眼の向上
中小企業事業団が平成9年度に実施した需要動向調査によると消費者の購入で重視した点は表8のとおりとなっている。消費者が最も重視しているのは「大きさサイズ」となっており、「使いやすさ」がこれに続き、「価格」と「デザイン」は3番目で同水準にある。一方、メーカー(企業)は消費者が「デザイン」を最も重視していると考えている。
この消費者と企業の家具選択に対する重視点の相違は、企業が消費者の態度を必ずしも理解していないことを示唆している。また、大手小売業のインタビュー結果では、国内メーカーのテイスト(デザイン)力はまだまだ不十分と言う意見があり、重視している割には成果が上がっていない可能性が高い。
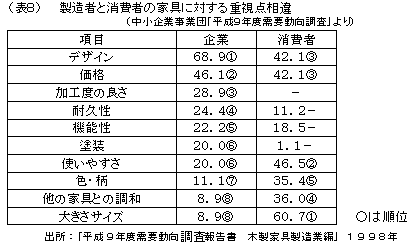
次に、中小企業事業団の同調査によると、図11のように消費者の国産家具に対する評価は概ね良好である。特に、「品質が良い」、「自分の住まいに合う」、「造りが丁重」の項目で70%以上の高い評価を得ている。
一方、「高級感」、「デザイン」の面では消費者の国産家具に対する評価は欧米からの家具に比べて低い。つまり高級家具分野では、欧米諸国産の木製家具のデザイン力に及ばない点がまだあるということであろう。
現在、イタリア家具メーカーは日本人に好まれるデザイン開発に努め、大きさ・サイズも日本仕様に対応した輸出体制ができあがっているという(岐阜県イタリアミラノ駐在員の調査報告による)。このような努力が対日輸出に成功している一因と考えられ、日本の消費者の嗜好を重視するイタリアメーカーの姿勢には見習う点があると言えよう。
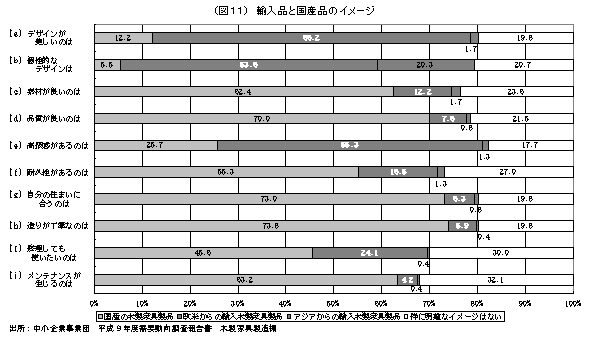
・高齢化社会に伴う機能変化の要求
高齢化・単身高齢世帯の増加によって、バリアフリーや扱い易さといった従来にない機能が家具を含めた耐久消費財に求められつつある。既にベッドでは対応が進んでいるが、脚物分野においてもバリアフリー的要素を持った製品の開発が今後、さらに重要になってくる。
・環境・安全指向の強まり
消費財への高いリサイクル性の要求や化学物質等の環境ホルモン忌避の動きが高まっている。家具においても、廃材等の再利用技術やホルムアルデヒドを放出しない材料・接着剤の利用、揮発性有機溶剤を含まない自然塗料の導入や環境に優しい天然素材を利用した材料の開発など、「環境に優しい家具造り」が求められている。
・オーダーメイド・セミオーダー指向の強まり
飛騨の家具メーカー、販売店へのヒアリング結果によると、消費者の好みは多様化し、従来の大量生産、同規格・同仕様の家具は受け入れられにくくなっている。中小企業事業団の調査でも、女性の約4割がオーダーメイドに関心があり、注文も考えている。
つまり「オンリー・ワン」家具など自分だけの家具を求める傾向が強まりつつある。現に、国内他産地メーカーも既にセミオーダー体制を確立しつつあり、フルオーダー、セミオーダーへの対応はますます必要となろう。比較的容易に消費者のオーダーに応えることのできるソファの張り地や塗装色などから、セミオーダー体制は既に普及しつつある。
オーダーメイド・セミオーダー家具については、中小メーカーにおいても対応できる分野であると考えられ、これら中小メーカーの今後の活路としても重要であろう。
-
家具市場全体は成熟した分野と考えられ、それだけに消費者の嗜好(ニーズ)にあった製品、さらにはニーズを喚起するような提案型の商品開発をすることにより、新たな需要の掘り起こしをする必要性が今後は高まると考えられる。実際、大手小売業者のインタビューでは、消費者の家具を見る目は、クオリティの高い外国製品やバブル期の高額製品の購入経験から、以前と比べて厳しくなっていると指摘があった。
現在でも家具メーカーは消費者ニーズの収集を主として同業者や問屋からという調査結果がある(「平成9年度需要動向調査報告書木製家具製造業編」1998年)。従来の、メーカー→産地問屋→消費地問屋→小売業→消費者 の多段階の流通では消費者ニーズのフィードバックが十分でない。そのため、飛騨の家具メーカーの中には問屋を通さず小売業へ直接販売する割合を増やす企業が見られた。今後も流通チャネルの短縮策は、消費者ニーズ対応力の向上のためにも進める必要があろう。
-
中小企業事業団の調査によると、部屋のしつらえに何らかの形で関心のある消費者は80%を超え、また、家具販売店に望むサービスとして「コーディネートのアドバイス」を挙げる消費者が、特に30歳以下で顕著になっている。
東京の大手家具小売業に対するインタビューでは、これからは消費者に生活環境をトータルで提案する時代であり、そういった販売戦略をとっていかなくてはならない、との指摘があった。また、脚物家具に特化している飛騨の家具メーカーにおいても、他の産地(箱物、ベッド、棚類等)と共同して、消費者に対し住空間の提案を販路拡大策にしていくべきでないかとの助言があった。
飛騨の家具をあこがれの的とする大都市の消費者の態度を踏まえつつ、消費者の住空間全体について提案する商品開発が求められている時期に来ているとも言えよう。