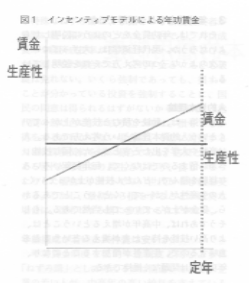
| 特 | 集 | 論 | 文 | 8 経済・労働・雇用 |
大竹文雄
(大阪大学社会経済研究所助教授)
1. はじめに
団塊世代の高齢化は、 日本経済に様々な影響を与えてきた。 日本的雇用制度に与えた影響もその一つである。 第一次ベビーブーム世代が1990年代に40歳代になったことで、 管理職ポストの不足から昇進が困難になった。 人件費の高騰は、 年功的、 一律的な賃金体系の変更を迫っている。 21世紀の初頭には、 第一次ベビーブーム世代はさらに高齢化する。 彼らは、 2010年前後には60歳を超え60歳定年制の下では、 定年退職の対象となっている。
「終身雇用」、 「年功賃金」 に代表される日本的雇用制度が変化してきていると指摘されることが多い。 特に、 1990年代の不況下で、 多くの企業がリストラのために中高年を中心に解雇を行ってきた。 また、 年俸制に代表される能力主義的賃金制度の導入も進んでいる。 このような 「日本的雇用制度」 の変化は、 様々な要因で生じていると考えられる。 長期にわたる不況に加えて、 情報化を中心とした急激な技術革新の影響は無視できない。 しかし、 それに加えて、 団塊の世代の存在という人口要因の影響も大きいと考えられる。
21世紀の初頭には、 団塊の世代の定年退職という事態が生じ、 その後、 労働市場から退出した団塊の世代に関わる年金、 医療、 介護といった社会保障の問題が大きくなることは確実である。 このような団塊の世代の高齢化から発生する雇用制度の変化と、 「日本的雇用制度」 本来の役割は区別して考えることが必要ではないだろうか。 本稿では、 日本的雇用制度の経済学的な解釈と団塊世代の高齢化から発生する問題を区別して議論する。
2. 年功賃金制度は 「ねずみ講型賃金制度」 だったのか?
「ねずみ講型賃金制度」 と年功賃金崩壊論
「年功賃金制度」 とは、 勤続年数が延びるにしたがって賃金も上がっていく制度だと考えられている。 団魂の世代が中高年齢化して賃金が高くなると、 企業経営が成り立たなくなるため、 年功賃金制は見直されなければならないといわれる。
この議論は、 もっともらしく聞こえる。 しかし、 よく考えてみると、 この議論には、 おかしな点がある。 もっとも重要なのは、 労働者の働きぶりと賃金の関係がこの議論には欠けている点である。 このような議論を展開する人たちは、 年功賃金制をどうやら年金制度と同じように見て、 企業のなかで若い人たちが中高年を養っていると考えているようである。 つまり、 賦課方式の公的年金制度と同じように考えているということである。
賦課方式とは、 勤労者が支払う公的年金保険料がそのまま退職者への公的年金給付として支払われるシステムである。 ちなみに、 これに対して若い人たちの保険料を積み立てて、 それが将来当人たちが高齢者になったときに年金給付として支払われるシステムを積み立て方式という。
賦課方式の年金制度は、 「ねずみ講」 に似ている。 ねずみ講のように新たな加入者が増えれば増えるほど、 元の加入者は得をしていく。 新規加入者が永遠に増え続けるなら、 ねずみ講により全ての加入者は利益を得る。 しかし、 ねずみ講は、 遅かれ早かれ新規加入者の獲得に失敗し、 破綻する。 ところが、 賦課方式の公的年金という特殊なねずみ講は、 子孫という新規加入者が無限に続く限り破綻しない。 それでも、 人口成長率や経済成長率が長期にマイナスになることが予測された場合には、 公的年金といえども破綻は免れない。 いくら強制であっても、 損することが分かっている投資を強制することに、 国民の同意は得られるはずがないからである。 「世代間の助け合い」 が成り立つのは、 損をするか得をするかわからない場合に、 それに対処するために保険契約を結ぶ場合である。 結果として、 ある世代が予想より長生きしたり、 貧しくなったりした場合に、 そうでない世代から移転を受ける。 しかし、 最初から損をすることが確実な場合に、 誰もねずみ講に参加するはずがない。
年齢構成が若いと人件費は安いか
年功賃金制度を公的年金制度と同じように 「ねずみ講」 として考えるのは間違いである。 企業の若い人が、 中高年の高い給与を支えていることが年功賃金の理由であれば、 従業員数が減少している企業で、 年功賃金がなりたっているはずがない。 現実には、 従業員の減少が続く企業でも年功賃金的要素が存在する。
公的年金制度であれば、 全国民は強制加入であるが、 若い労働者は企業を選べる。 損をすることがわかっている企業には誰も入らないのは当然である。 最近、 企業年金の解散がめだつ。 企業年金は、 確定給付型でしかも、 運用利回りに規制があるため、 定められた運用利回りより現実の利回りが低くなれば、 現役世代から退職世代への所得移転によってその差額をまかなうことになる。 まさに、 ねずみ講である。 企業の盛衰がある中で、 このような仕組みが成り立つはずがない。 そのような確定給付型の年金ができるとすれば、 より広い範囲で企業の生存リスクをプールする必要がある。 企業の盛衰が当然であるのに、 企業一社で確定給付型で賦課方式色彩が濃い企業年金を維持するのは、 そもそも不可能である。
もちろん、 経済が常に高い成長率を維持している社会を前提にすれば、 ねずみ講型賃金として年功賃金を解釈できないこともない。 若いときに中高年を支えた分と同じ額を自分が中高年になったときに受け取ることができるからである。 しかし、 今後何十年も現行の成長率が同じように続くかどうか誰も予測できない。 過去の様々な産業を見ても、 高い成長率が、 長期間続くことはあり得なかった。 ここ数年間の企業業績の変動を見ても、 今の姿がこれからも不変に続くと思っている人は誰もいないであろう。 そんな中で、 「ねずみ講型賃金制度」 としての年功賃金が存続してきたとはとうてい考えられない。
もし、 ねずみ講型賃金としての年功賃金をとっているから、 過去の日本企業の人件費が安かったのであれば、 それは単に企業価値の評価が正当になされていなかったということである。 退職金制度は、 会計上も将来支払うべき退職金の一部が退職給与引当金として債務として計上されている。 もちろん、 この額は本当に必要な額のほんの一部である。 正確には全額を引き当て、 それに対応する資産を保有しておく必要がある。 もし、 そうしていないのなら、 その企業は本来その資産から得ることができたはずの利回りを受け取っていないことになる。 その分が隠れた損失である。 つまり、 若い人口構成のもとでねずみ講型年功賃金制度をとっているが故に、 日本企業が外国企業なみの利益をあげてきたのなら、 本当の利益はそれより低かったことになる。 つまり、 将来の年功部分の積み立て不足と失った積立金からの利子収益を実際の利益から差し引いて、 企業価値を評価する必要があった。 これらの費用は表だった人件費としては現れない。 しかし、 資本市場が正しく機能していれば、 このようなねずみ講型年功賃金によって表面上業績がよく見える企業の株価は高くならない。 その時点で、 成長が永遠につづかない限り、 将来における人件費の高まりが予測されているからである。
つまり、 企業の情報公開が正しく行われていて、 資本市場が正しく機能しているなら、 その時点の年齢構成と真の意味の人件費は無関係なのである。 従業員を定年まで雇うことを前提にしておれば、 その従業員を採用した時点で生涯にわたる人件費はある程度予想できる。 その人件費を給与や退職金としてどのように支払うかということはその時点、 その時点の企業利益に影響を与えるであろう。 しかし、 将来までの利益の現在価値から計算される企業価値、 すなわち株価とその時点の年齢構成は無関係なのである。 年齢構成が若いが故に、 見かけ上ひくい人件費のためにかつて高い利益を達成することができていたとしても、 その時点で株価は低かったはずである。
国際会計基準
従業員の平均的離職率が分かれば、 その従業員を採用した時点で生涯にわたる人件費はある程度予想できる。 企業年金・退職金については制度をもとに、 既に確定的になった部分について、 その債務を計算することもできる。 ところが、 実際には年金債務に関する情報が広く公表されていなかった。 これには、 退職金や企業年金の受給権が在職中に確定せず、 退職時になってはじめて確定するという日本の制度が大きな影響を与えている。
ここで、 受給権とは、 企業年金や退職金について個々の制度規定に基づいて算出された発生給付額を受け取る権利のことをいう。 米国のエリサ法 (従業員退職所得保障法) においては、 年金制度の加入者に対して受給権を早期に確定的に付与することが義務づけられている。 エリサ法では、 いったん付与された受給権は、 労働者が早期に退職したり、 不正行為を理由に解雇された場合でも、 使用者が没収することは許されていない。 これに対して、 日本では、 企業年金・退職金とも受給権は退職時に成立するものと解釈されている。 そのため、 懲戒解雇に伴う退職金・企業年金の減額・不支給も可能になっている。
退職金・企業年金の受給権が退職時に付与されるという日本の制度のもとでは、 既に発生している退職給付について、 必ずしも使用者の労働者に対する法的な債務負担を意味しない。 しかし、 原則として2000年度から導入が予定されている国際会計基準のもとでは、 退職金・企業年金を包括的に、 発生主義によってとらえることになる。 すなわち、 退職金・企業年金は、 勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生するものと捉え、 その発生した期間に費用として認識し、 それを実際に支払うまでの間は債務となる。 これが企業年金債務である。 もちろん、 企業会計上の債務と、 受給権とは異なる。 しかし、 今まで 「隠れ負債」 であった退職給付が、 企業の財務諸表上明示されることの影響は大きい。
企業年金の未積立債務の存在は、 企業年金や退職金が 「ねずみ講」 によって運営されていたことの証でもある。 同じように年功賃金が 「ねずみ講」 型のものであった可能性も高い。 しかし、 年功賃金は 「ねずみ講」 でないと成り立たないと考えるのも間違いである。
3. 年功賃金をどう理解するか
それでは、 年功賃金をどのように説明したらよいだろうか。 現代経済学は、 大ざっぱにいって次のような三つの考え方でそれを説明している。
人的資本理論
まず第一は、 勤続を積むと技能が上がっていくという人的資本理論という考え方である。 人は高校や大学を出たときとまったく同じ技能レベルに留まるのではなくて、 毎年毎年いろいろな経験を積んで、 どんどん技能が上がっていく。 人の生産性が上がっていくということであるから、 賃金が上がっていっても当然である。 もしそうであれば、 中高年が増えるということは、 より高い技能を持った人が増えるということを意味するので、 生産性が増加することになり、 年功賃金は問題なく維持できる。
インセンティブ仮説
年功賃金の説明方法の二つ目は、 「インセンティブ仮説」 といわれるものである。 労働者がまじめに働いているかどうかを常に監視し続けるのはコストがかかって難しいので、 「まじめに働きます」 と誓約書に書かせる代わりに、 若いときの働きの成果の一部分を供託金として、 その企業に捧げさせる。 そして、 長期間まじめに働いた場合には、 企業はそれを返してやるというシステム、 それが年功賃金システムだと考える。 退職金制度もこれと同じように考えることができる。 途中で、 さぼっていることが発覚して、 解雇された場合には、 供託金としての将来の年功賃金の部分を損することになる。 これが、 さぼることの機会費用を高めるので、 だれもさぼらないということになる。 つまり、 年功賃金制度は積立方式の年金制度に、 さぼらないという受給要件をつけたのと同じだということになる。
図1に、 このモデルの考え方を示してある。 この理論による説明であきらかなことは、 企業は定年を必要とするということである。 なぜなら、 年功賃金による中高年労働者は、 生産性よりも高い賃金をもらっているため、 この企業をやめる動機がない。 したがって、 あらかじめ決められた定年でこの企業から退出することを決めておかないと、 生涯の生産性と賃金の収支が合わなくなってしまう。
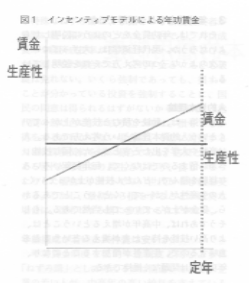
もし、 この制度のもとで中高年が増えたらどうなるか。 実は何も問題は生じない。 中高年社員は若いときに企業に供託金として預けていた部分を返してもらって、 年功賃金として受け取るだけだからである。 したがって、 いまや中高年真っ盛りの団塊の世代は、 肩身の狭い思いをする必要はない。 若いときに我慢した分を返してもらっているだけだからだ。 人件費削減のために中高年をリストラするとなれば、 債務不履行だということになる。 問題なのは、 正しく供託金の運用を行ってこなかった企業だということになる。
ただし、 このモデルがなりたつためにはいくつかの条件が必要である。 第一に、 企業が倒産しないことが必要である。 第二に、 企業には賃金の方が生産性よりも高い中高年労働者を解雇する動機が常にあり、 モラルハザードの問題がある。 この両者は密接な関係にある。 将来、 倒産する可能性が高くなると、 企業にとって労働者の採用を気にする必要がないので、 労働市場での評判を気にする必要性が小さくなってくる。 すると、 モラルハザードが生じやすくなるのである。
適職探しの場としての企業
三つ目は、 人は勤務を経るにしたがって、 だんだん自分に適した職を見つけていくという考え方である。 企業内にはいろいろな職があり、 様々な職種を経験していくうちに、 自分がもっとも生産性を発揮しやすい職に移っていく。 そうすると、 当然のことながら生産性はしだいに上がっていくため、 賃金も上がって何の不思議もない。 この場合は生産性は下がらないのだから、 年功賃金制と従業員の年齢構成とは基本的には関係ないということになる。
4. 年功賃金と能力主義
ねずみ講型賃金制度が、 民間企業でなりたっていたと考えることに無理があり、 経済学の立場からの年功賃金理論でも、 高齢化と年功賃金崩壊説は無関係だということを説明した。 要するに、 中高年が増えたから、 団塊の世代が中高年齢化したから、 年功賃金制は潰れてしまうという議論は必ずしも成り立たない。
技能を蓄積する彼らがまじめに働いているかどうかを監視するコストは大きい。 また労働者の能力を短期間で見分けることは難しいということを考えると、 やはり年功賃金制は望ましいシステムだと考えられる。 そういう意味では、 この制度がなくなることはないといえる。 にもかかわらず、 なぜ年功賃金制が崩壊しているように見えるのだろうか。
技術革新と技能の陳腐化
まず考えられることは、 技能そのものが陳腐化してしまう可能性があるということだ。 技術革新が非常に目まぐるしく起こっている場合に、 その可能性は大きくなる。 たとえば、 長期勤務してコツコツと積み上げてきた経験が、 コンピューターを中心とした技術革新によって、 まったく役に立たなくなる場合のように、 長い間積み上げてきた経験や技能が充分に発揮できなくなってしまうことは日常的に起こっている。
技能に応じた賃金を支払うシステムであれば、 技能が低下してしまえば賃金は上がらなくなってしまう。 その段階では確かに年功賃金制が崩壊したように見える。 しかし、 新しい技術を導入した企業に新しく入社した人にとっては、 年功賃金制は残る。 その意味で、 年功賃金の崩壊が一時的に生じることは起こりうる。 もっとも、 このような技術革新が常に生じているのであれば、 企業と労働者はそのリスクにあらかじめ備えておき、 そのための暗黙的な保険制度を賃金制度に組み込んでいてもおかしくない。
インセンティブモデルと業績給
年功賃金制は供託金制度と理解できると指摘した。 ここにこのシステムの問題点が内包されていることも指摘しておくべきであろう。 つまり、 定年間近になって供託金をすでにかなり返してもらった人は、 働く意欲 (インセンティブ) がかなり低下してしまうということである。 定年間近の人たちにやる気を持たせるシステムを導入しないと、 この人たちのやる気は出ない。 中高年がやる気がないと、 若い人たちにも悪い影響を与える。
そういう人たちについては、 業績によって賃金を変えるというシステムを付加することで、 このような年功賃金システムの弱点を補強することができる。 最近、 管理職層に対して業績主義あるいは能力主義的な人事をとったり、 年棒制を導入する企業が増えている。 それは年功賃金制が崩れている証拠ではなくて、 むしろ年功賃金制を補強するためのシステムだということである。 また、 管理職は、 比較的業績を客観的に把握しやすいのも利点である。
完全な能力主義や年棒制システムを新入社員に導入しようという企業は、 業績を測ることが簡単な職種を除くと、 いまのところ多くはない。 したがって、 管理職になるまでの労働者については、 年功賃金システムは望ましいシステムであり、 これからも間違いなく残っていくと思われる。 激しい技術革新に直面した場合や、 年齢別の役割分担を維持したまま企業の成長率が予想より低下した場合には、 予想されていた年功賃金が支払えない事態が発生することはある。 だからといって、 年功賃金制度がすべて否定されるわけではない。
団塊の世代と賃金
年功賃金の崩壊という現象が、 高齢化というよりも団塊の世代という人口構造のゆがみのせいで、 顕在化している可能性もある。 いわゆる年功賃金の崩壊やリストラの影響を受けているのは、 団塊の世代に典型的に現れている。 団塊の世代の賃金は、 他の世代に比べてどのように違うであろうか。
ベテラン社員と新入社員の仕事は違うものだとしよう。 初任給は、 未熟練労働者の賃金率と考えられる。 団塊の世代が、 学校を卒業して労働市場に入ってきたとすると、 未熟練労働者の労働供給はそれ以前の年に比べて増えるので、 賃金率は低下する。
新入社員の仕事とベテラン社員の仕事が全く同じであれば、 この賃金低下効果は全社員におよぶことになる。 後者の場合だと、 全ての年齢のものが賃金低下を被る。 しかし、 新入社員とベテラン社員ができる仕事が異なっていれば、 団塊の世代が新入社員として入ってきた影響は、 彼らの世代の初任給を低下させるだけになる。
この議論は、 初任給の問題だけではなく、 管理職の給与についてもあてはまる。 管理職の全従業員に対する比率が一定で、 管理職が勤続年数の長い労働者から選ばれるとする。 すると、 団塊の世代の労働者が中高年化してきて管理職適齢になると、 管理職の供給は増えるが、 需要は増えないので、 管理職の給与は低下することになる。 団塊の世代の管理職給与は、 他の世代の給与よりも低くなる。
年齢によってする仕事がある程度決まってくる社会では、 団塊の世代の存在のような年齢構成の変化があると、 人口が多い世代はその世代のみが賃金低下の影響を受けてしまう傾向がある。
アメリカで学歴間格差が拡大した理由に、 高学歴者に対する需要が急速に高まったことがあげられている。 日本でも確かに、 若年層の高学歴者の賃金は相対的に上昇したことはこれと対応している。 しかし、 中高年齢層については、 もともと人口が相対的に多い世代で高学歴化が急速に進んだために、 高学歴者に対する需要増以上に供給増の効果が大きかったといえる。
もちろん、 現在の中高年の雇用不安や賃金伸び悩みの原因は、 単に供給が多いという理由以外にも考えられる。 まず、 急激な技術革新により、 それまで培った技術が急速に陳腐化してしまった可能性がある。 つぎに、 教育訓練の度合いが上司一人あたりの部下の人数が少ないほど高いとすれば、 団塊の世代の人的資本は他の世代よりも低いことになる。 さらに、 高学歴化は単に質の低い大卒をより多く生み出した可能性がある。 もしそうなら、 高学歴化の進展は学歴間賃金格差を低めることを意味し、 その傾向は今後も続くことになる。
5. むすび
日本的雇用制度が崩壊するようにいわれることが多い。 すべての職種や産業で、 終身雇用や年功賃金制度をとることが最適でないことは明らかであろう。 長期間の技能形成が必要な部門、 個々の労働者の能力を時間をかけて審査する必要がある部門では 「長期雇用」 は不可欠であろう。 労働者の働きぶりを不完全にしか監督できない部門では、 年功賃金は有力なインセンティブシステムとして機能する。 ただし、 年功賃金が成立するためには、 企業の倒産確率が低いということも重要な条件である。 このような条件をみたさない経済部門は少なくない。 もともと、 典型的な日本的雇用制度のもとで雇用されていた日本人は、 それほど多いわけではない。 大企業部門を中心として 「日本的雇用制度」 が発展してきたことはよく知られている。 また、 年功賃金制度の経済学的なメリットのうち、 成長を前提とした 「ねずみ講」 型賃金制度の特徴を利用してきた企業もあったと考えられる。
技術革新の進展、 労働者の高年齢化、 規制緩和、 倒産の頻発といった環境変化によって、 従来の日本的雇用をそのまま維持することができない企業が出てきていることは確かである。 しかし、 「日本的雇用制度」 が依然として有効な企業や労働者のタイプが存在することも確かであろう。 21世紀にむけて、 日本の雇用制度は、 企業内での一律的な雇用制度から、 労働者のタイプや仕事のタイプに応じて様々な雇用制度を組み合わせていく方向に変わっていく動きがますます進んでいくと考えられる。
■大竹 文雄 (おおたけ・ふみお)
大阪大学社会経済研究所助教授、 大阪大学博士 (経済学)。
1961年京都府宇治市生まれ。 1983年京都大学経済学部卒業。 1985年大阪大学大学院博士前期課程修了、 同年、 大阪大学経済学部助手。 1988年大阪府立大学経済学部講師。 1990年大阪大学社会経済研究所助教授、 現在に至る。 著書 『労働経済学入門』、 (日経文庫)、 『スタディガイド入門マクロ経済学』 (日本評論社)、 論文 「1980年代の所得・資産分配」 (『季刊理論経済学』、 第45巻、 1994年)、 「高失業率時代における雇用政策」 (『日本労働研究雑誌』 1999年5月号)、 ほか多数。
| 今号のトップ | メインメニュー |