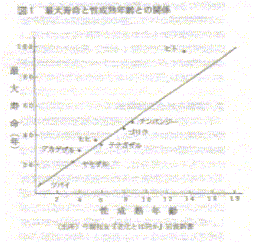
| 特 | 集 | 論 | 文 | 5 医療 |
|
福祉と社会 ――新しい高齢化社会のビジョン |
1. 福祉国家とは何か
「福祉国家」 とは、 Welfare State の訳であるが、 これは実のところそれほど古くからある言葉ないしコンセプトではない。 すなわちそれは、 第二次世界大戦期のイギリスにおいて、 ドイツなどの 「権力国家 power state」 または 「戦争国家 warfare state」 との対比で使われるようになった言葉であり、 また、 福祉国家の理念を明確なかたちで唱い、 戦後イギリスの福祉国家政策を方向づけたいわゆる 「ベヴァリッジ報告」 が出されたのもほぼ同時期 (1942年) であった。
福祉国家というときの 「福祉」 とは、 もちろん狭い意味での 「社会福祉」 ではなく、 たとえば 「人類の福祉の向上」 などというときの 「福祉」 であり、 “幸福、 安寧"と呼びかえてよいような広い意味である。
ここで議論の整理のために、 「福祉」 という言葉について、 次の3つの意味を整理しておこう。 第一は以上のような 「福祉」 という言葉の用法で、 いわば最広義の 「福祉」 である。 第二は、 ほぼ 「社会保障」 と同義に、 つまり医療 (保険) や年金等も含めた意味で使われる 「福祉」 である。 第三は、 社会保障の一分野としての、 いわゆる社会福祉としての 「福祉」 である。 第三の意味の福祉は、 これまで主に 「低所得者対策」 という意味で使われてきたが、 近年ではむしろ心理社会的な支援サ−ビスを広く含んだ 「対人社会サ−ビス (personal social service )」 の意味に拡大・普遍化している。
話を 「福祉国家」 に戻そう。 以上のようにして、 第2次大戦後、 西欧を中心に展開した国家のあり方が福祉国家であるが、 これは単に医療や年金、 社会福祉などの社会保障制度のみをさすのではなく、 政府による公共事業を通じた景気対策や、 完全雇用をめざした経済政策等を広く含むものであった。 つまり、 政府による積極的な 「需要創出政策」、 すなわちケインズ型経済政策ということが、 すなわち福祉国家ということの実質だったのである。 「ケインズ主義的福祉国家 Keynesian Welfare State」 という言葉はこのことをよく表している。
具体的には、 第一に、 政府による所得再分配政策 (高所得者から低所得者への所得移転) は、 結果的に人々の消費の総量を増加させるのだし (なぜなら低所得層のほうが消費性向が高いから)、 第二に、 政府によるいわゆる公共財 (道路、 公園など) の提供も、 それを呼び水として一国の全体の需要を増加させる。 この結果、 「所得の平等化と経済成長」 が、 同時に実現されることになる。 この 「経済と福祉の相乗的な拡大」 ということが、 戦後から70年代まで続いた“福祉国家の黄金時代"を支えた条件でありまた実際の成果であった。 言い換えると、 福祉国家は、 他でもなく 「高度大衆消費社会」 の実現ということと表裏の関係にある理念だったのであり、 それは 「資本主義が空前の成長を遂げた時代」 (ピアソン) と重なっていたのである。 この重なりは偶然ではない。 ちなみに、 この戦後の時代、 福祉国家の理念は、 現在のように 「市場主義」 や自由放任主義の対立物としてではなく、 まったく逆に社会主義ないし共産主義の対立概念として考えられていた、 という、 現在との基本的なコンテクストの違いを忘れてはならない。
(福祉国家に対する根底的な批判)
こうした 「福祉国家」 の理念については、 次のようなふたつの根底的な批判がある。
(a) 福祉国家の 「拡大主義的」 性格に対する批判
(b) 福祉国家の 「ナショナリズム的」 性格に対する批判
このうち (a) は、 特に 「環境」 の視点からの批判であり、 福祉国家が、 これまで述べてきたような 「ケインズ主義的財政政策」 の下で、 潜在的な“有効需要"を積極的に喚起することを通じて、 パイの継続的な拡大と同時に所得分配の平等化を図る、 という基本的な方向づけの中で展開してきたことに着目する。 つまり、 福祉国家とは、 先進資本主義国群における、 いわば 「資源消費の際限なき拡大」 という方向と不可分の関係にあるシステムであり (福祉国家=高度大衆消費社会)、 そうした体制は、 資源の無限性を前提とするならまだしも、 特に地球レベルでの資源制約と環境の限界を考えると、 到底普遍化しえない理念である、 と主張するのである。 端的に言えば、 福祉国家は、 特に地球環境の視点からみた場合 「持続可能 (sustainable)」 なシステムではないのではないか、 ということがこの批判の中心的な論点となる。
一方、 (b) の批判は、 福祉国家の理念のもついわば 「一国完結」 的な視野の狭さに着目し、 その排他的性格を批判するとともに、 それはよりグロ−バルな視野の下で再構築されるべき理念である、 とするものである (代表的なものとして、 ミュルダ−ルの 『福祉国家を超えて』 (1960年))。 たしかに歴史的にみた場合、 福祉国家的な諸政策は、 「国民国家」 の理念と連動するかたちで展開してきた。 また、 そうした政策の拠り所として、 しばしば国民の連帯や国家レベルでの相互扶助がうたわれてきたし、 逆に福祉国家の理念に基づく制度や政策が、 「国家」 としての統合を強める方向にも作用してきた。 さらに、 経済のグロ−バリゼ−ションが進み、 こと市場に関しては国境が消滅しつつあるような現在の状況では、 福祉国家の中核をなす 「社会保障」 という制度こそが、 国の“内と外"を区別する最大の制度である、 とさえ言えるような状況になっている。
そして、 こうした (b) の観点からの批判が、 ミュルダ−ルの時代にはまだ顕在化していなかった (a) の環境の観点からの批判と連動していくと、 それは現代における地球環境問題とそこでの南北の対立軸、 という構図にそのまま重なり合うものとなる。
ところで、 話をもとに戻すと、 1970年代になり、 西欧諸国において人々の需要が次第に 「飽和」 し、 経済が成熟段階に入ると、 先に述べたような、 戦後の福祉国家を支えた 「所得の平等化と経済成長」 の同時達成や 「経済と福祉の相乗的な拡大」 は困難となる。 “福祉国家の危機" (OECDの1981年の報告書の題名) である。 こうして福祉国家の見直しあるいは社会保障政策の再編が不可避となる。 しかも、 同時に本質的なことであるが、 福祉国家や社会保障の中心課題が、 それまでの 「貧困問題」 から、 経済の成熟化の結果として生まれる 「高齢化問題」 へと変容する。 これは構造的といってよい変化である。
これまでの議論をまとめよう。 戦後資本主義の推進力であった人々の 「需要」 の充足とそれに伴う経済の成熟化、 他方における高齢化の着実な進展、 これが 「福祉国家」 の直面する新たな状況となる。 これに経済のグロ−バライゼ−ションと環境問題という二重の地球規模の問題が加わって国家そのものの意味が問いなおされる。 以上の問題群をどう解くかに、 現在そして未来の福祉国家をめぐる論点はすべて含まれているといってよい。
2. 高齢化社会とは何か
1. で述べたように、 現在の福祉国家の中心的な課題は高齢化である。 高齢化社会に関する議論や話題が日常的なものになって既に久しい。 けれどもその大部分は、 高齢化で年金財政がパンクするとか、 労働力人口の減少や社会保障負担の増大によって日本経済が失速する、 等々といった、 ネガテイブなものとなっている。 しかし、 虚心に考えてみた場合、 「多くの人々が長生きできるようになった」 社会というものが、 そう悲観的な社会であるはずがない。 いま求められているのは、 個別の制度論のもっと根底にある、 「高齢化社会とは、 そもそも人間にとってどのような意味をもち、 どのようなビジョンのもとに描きうる社会なのか」 という、 高齢化社会についての原点に立ち返った構想ではないだろうか。
しかも、 2000年には、 日本はスウェ−デンを抜いて世界一高齢化が進んだ国となり、 文字通り 「高齢化のフロントランナ−」 として、 世界の先頭を駆け抜けていくことになる。 したがって、 上記のような高齢化社会のビジョンは、 もはや他の国に出来合いの見本を求めることは困難となり、 日本自らが模索し、 描いていくという、 これまでとは異なる基本的な発想の転換が必要となっている。
では、 そうした 「高齢化のビジョン」 とは、 一体どのようなものとして描きうるのであろうか。 ここでは、 そうした高齢化社会というものについての少し新しい見方について考えてみよう。
(図1) に示されているように、 性成熟年齢と最大寿命との相関関係を人間と他の生物 (哺乳類) とで比較してみると、 ヒトという生き物が、 他の生物のラインからはみ出た 「特異な場所」 に立っていることがわかる。 つまり、 生物の一生は一般に 「成長期→生殖期→後生殖期」 という3つの時期に区分されるが、 生殖を終えた後の 「後生殖期」 が際立って長いところに、 生物としてのヒトの特徴がある。
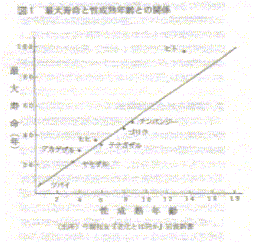
他の生物一般の場合は、 自らの子孫 (ないし遺伝子のコピ−) を残すことが基本的な役目だから、 産卵死するサケの例のように、 「後生殖期」 は積極的な意味をもたない。 構造的に長い後生殖期をもつことは、 人間が有する独自の大きな特質である。 そして、 この 「後生殖期」 とはすなわち 「高齢期 (老年期)」 に他ならないのであり、 したがって、 たんなる生物という存在を超えた、 まさに人間という生き物の独自の意味が、 この (長い) 高齢期にあるといっても過言ではない。
このような見方からすれば、 高齢化社会とは、 人間の歴史の歩みの帰結として、 「『後生殖期』 が普遍化した社会」 である、 ととらえることができる。 それは、 文字通り際立って 「人間的」 な社会、 あるいは人間が本来もつポテンシャルが真に実現される社会であり、 「人類史/生命史の到達点」 とも呼べるような、 積極的な意味をもった社会ではないだろうか。
では、 さらに問おう。 そもそも 「なぜ」 人間の後生殖期ないし高齢期は長いのだろうか。 これを説明するひとつの枠組みとして、 ここで提案してみたいのが、 以下に述べる 「人間の3世代モデル」 である。
(世代間の情報伝達)
そもそも生物は、 何らかの方法ないし媒体を通じて、 世代から世代へと、 「情報」 をバトンタッチしていく存在である。 これには大きく、 形質や行動に関する、 「遺伝子」 そのものを通した情報の伝達 (遺伝子情報の伝達) と、 個体から個体 (親から子) への直接的なコミュニケ−ションによる伝達、 との2種類がある。
こうした視点からみた場合、 単純化して述べると、 まずホニュウ類以外の場合では、 親から子へ伝達されるのは遺伝子を通じた情報のみで、 親と子の直接的なコミュニケ−ションというものはない (例えば魚は卵を産みっぱなしで、 それ以上に親が子に何かを教える、 ということはない)。 ところがBのホニュウ類の段階になると、 文字どおり 「哺乳」 類という言葉が示すように、 「子育て期間」 が存在するようになり、 遺伝子情報の承継以外に、 親が子に対して直接的に何かを教えるということ (学習) が出てくる。
しかし、 このレベルではなお、 そうした情報の伝達は世代ごとに同じことが繰り返されるだけで、 変化ないし発展していくことはない (現在のネコは古代エジプトのネコと変わらない。 言い換えると、 ネコは、 「遺伝子が変わらない限り」 変化しない)。 一方、 人間の遺伝子の組成は、 約3万年前のクロマニヨン人の時代から変わっていないとされているが、 言うまでもなく、 人間の社会や文化は途方もない大きな変化 ―― それを進歩と呼ぶかどうかは別として ―― を経験してきている。
こうした意味で、 人間 (ヒト) の場合の世代から世代への伝達には、 遺伝子情報そして学習の要素に加えて、 さらに 「+α」 の要素があることになる。 では、 この 「+α」 の実質をなすものは何か、 それは何によって可能なのか、 という基本的な疑問が生まれる。
(人間の3世代モデル)
ここで登場するのが 「人間の3世代モデル」 である。 それは、 端的に言えば、 人間という生物の本質は、 それが3世代構造をもっているということ、 とりわけ 「老人が子どもを教える」 という点にある、 というものであり、 要約すると (図2) のような内容となる。
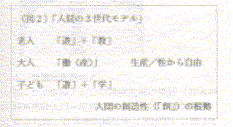
まず 「子ども」 について見ると、、 人間の子どもというのは、 実際の子どもを見ていればわかるように、 自分をとりまく外界の何にでも好奇心を感じ、 何でも 「遊び」 の対象にし、 しかもその過程で次々と新しいものを学び、 吸収していくのであり、 文字通り 「遊び」 と 「学ぶ」 ことは一体のものとなっている。 「遊ぶ」 と 「学ぶ」 とは、 受験勉強などを考えると一見対極にあるように思われるが、 もともとは不可分のもので、 あえて言えば“探索心"といったものが両者の共通項にあると言える。
ちなみに、 歴史家のホイジンガが、 「文化は遊びに始まる」 として、 人間という生き物の本質が 「遊び」 にあると論じたこと (『ホモ・ル−デンス』) はよく知られているが、 それは人間においてこうした 「子ども」 の期間が際立って長いことともパラレルである。 進化生物学的にいうと、 「何にでも好奇心を示す (=何でも遊びの対象とする)」 ことが、 ヒトの 「学習」 ということにとってきわめて重要であることから、 そうした行動の傾向性が、 進化の過程で自然選択を通じて形成されてきたといえるわけである。 子どもにとっては文字通り 「遊びが仕事」 ということになり、 長い 「子ども」 期間とも相まって、 ここに他の動物にはない人間の創造性の根拠があることになる。
他方、 「大人」 の役目はあくまで 「働 (産)」 で、 この場合の 「産」 は、 「生産」 という意味と、 子どもを 「産む」 という生殖機能との両面を指す。 特に狩猟生活や農業など、 産業化社会になる前は、 ほとんどこれ以外には余裕がなかった、 というのが人間の 「大人」 の生活であった。
では、 人間という生き物の特質は、 以上のような 「子ども」 と 「大人」 という時期の特徴で完結するのか? そうではない、 というのがここでの、 つまり 「人間の3世代モデル」 の主張であり、 それはすなわち 「老人」 という存在や老年期という時期のもつ本質的な意味への注目である。
すなわち、 いま述べた 「子ども」 の 「遊」 + 「学」 に、 ちょうど“対"をなすかたちで対応しているのが、 「老人」 という存在であり、 それは 「遊」 + 「教」 ということに象徴される存在である、 ということである。 つまり、 「遊」 すなわち 「大人」 のような労働や生産活動からはリタイヤし解放されている、 という点では子どもと同じであり、 また、 特に重要なことであるが、 子どもの 「学」 のちょうど対になるかたちで 「教」 の役目を担っていたのが老人であった、 ということである。
考えてみると、 産業化以前の社会においては、 「大人」 は農耕など生産活動に忙殺され、 また、 社会そのものの変化が遅いこともあって経験の蓄積に基づく知識の重要性が高かったこともあり、 老人が 「教」 という役割のかなりの部分を担っていたのではないだろうか。 それが産業化社会になると、 生産優位の社会となって老人が背景に退くとともに、 「教育」 はひとつの“制度"となり、 すなわち 「大人」 が行う 「仕事」 となっていった。 こうして教育が制度化される中で、 子どもにとって本来は一体のものであった 「遊」 と 「学」 も分極していった、 と考えられるのではなかろうか。
しかしながら、 私たちがこれから迎えつつある 「高齢化社会=経済が成熟化し人口も均衡化する定常型社会」 においては、 これまでの産業化時代とは大きく異なり、 「老人」 や 「子ども」 が本来もつ意味やポテンシャルが再発見され、 こうした 「子ども−大人−老人」 の関係全体が大きく再編されていくのではないだろうか?
(人間の創造性と老人・子ども)
議論を振り返ると、 先に、 世代間のコミュニケ−ションという点において人間を人間たらしめる要素、 他の生物にはない 「+α」 の要素ということを述べた。 以上のように考えていくと、 実は 「子ども」 と 「老人」 という存在にこそ、 その実質があるといえるのではないか、 という考えが出てくる。 つまり、 他の動物の場合は、 先の (図2) でいえば 「大人」 のところで尽きているわけで、 「産」 つまり生きていくための活動がすべてとなっている。
ところが人間の場合は、 まず 「子ども」 の期間が際立って長いというのが特徴であり (このことは生物学などでも指摘されてきた)、 と同時に、 「老人」 の時期が構造的に長く、 しかも、 それは単に寿命が長いということにとどまらず、 上記のような積極的な意味、 つまり 「遊」 + 「教」 という、 「子ども」 との対の関係を通じて人間を人間たらしめる要素という意味をもっている、 といえるのである。
言い換えると、 「生産」 や 「性 (生殖)」 から解放された、 一見 (生物学的にみると) “余分"とも見える時期が、 「大人」 の時期をはさんでその前後に広がっていること、 つまり長い 「老人」 と 「子ども」 の時期をもつことが、 人間の創造性や文化の源泉と考えられるのではないだろうか。
また、 ここで重要なのは、 「後生殖期」 あるいは 「老人」 という時期を、 それだけを他と切り離してとらえるのは妥当ではない、 ということである。 人間という生物の本質的な特徴は、 「世代間」 相互の (しかも2世代ではなく3世代の) コミュニケ−ションの強さ、 あるいはその 「関係」 性にある。 だから、 しばしば生物学がそうであるように、 「個体」 を単体としてとらえるだけでは本質を見失うおそれがある。
ちなみに、 認知科学の研究者として著名なマ−ヴィン・ミンスキ− (MIT) は次のような大変興味深い指摘を行っている。
「進化は通常、 親が自分の子育てに必要とする期間より長く寿命を持たせるような遺伝子を守らない。 ・・・今日の人間は他の霊長類のほぼ2倍は生きるが、 どのような進化の淘汰圧が作用してこのように長生きするようになったのだろうか? 答えは知能に関係する。 全哺乳類の中で、 幼児期にひとりで生き延びていく能力がいちばん未熟なのが人間である。 私たち人間には生きていくための世話をし、 また、 貴重な生き抜くための助言をしてくれる存在として、 親のみならず祖父母までもが必要となってくるのである。」 (ミンスキ− 「ロボットは地球を受け継ぐか」 『日経サイエンス』 1994年12月号)
いずれにしても、 こうした高齢化社会の意味についての、 自然科学を含めた新しい視点からの研究とビジョンが強く求められているのではなかろうか。
■広井 良典 (ひろい・よしのり)
1961年生まれ。 1984年東京大学教養学部卒業。 専攻は医療政策、 科学哲学。 現在、 千葉大学法経学部助教授。
| 今号のトップ | メインメニュー |