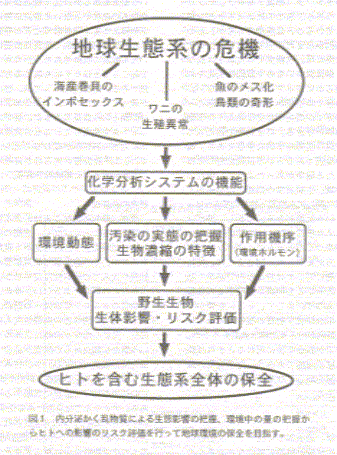
| 特 | 集 | 論 | 文 | 4 環境 |
はじめに
化学工業の発展により、 便利で快適な生活のために多くの化学物質が作られ、 大きな恩恵を受けてきた。 これに伴って、 環境中には人工的に合成された多くの化学物質が放出され、 野生動物の健康に脅威となっている。 今までの環境問題は、 致死作用、 ガン化あるいは催奇形性といった健康影響に焦点があてられてきた。 しかし、 最近見出された多くの事例から、 体内のホルモンを撹乱するといった、 今までにはなかった新たな観点からの研究が必要となってきている。 これらの中には、 エストロゲン様の作用や、 アンドロゲンや甲状腺ホルモンの作用を阻害する化学物質が見出されている。 かつての合成エストロゲン (ジエチルスチルベストロール, DES) を流産防止剤として服用した婦人から生まれた女児に膣癌や子宮の形成不全が発症した例や、 周生期のマウスにエストロゲンを投与すると不可逆的な膣上皮の増殖や多卵性卵胞が多発し、 雄では精子形成能が低下する(1)。 このような事例から、 発生中の胎児から幼児期にかけて内分泌かく乱物質にさらされると、 生殖器の奇形や、 成熟後に生殖障害がおこり、 子孫を残すことが困難になるとの仮説がある。 実験的な証拠、 および野生動物での観察結果からもホルモン作用が明らかにされている。 これらの化学物質は 「(外因性) 内分泌かく乱物質」 とよばれるが、 環境中に放出されてホルモン様の作用を示すことから、 「環境ホルモン」 ともよばれている。 魚、 カエルやワニなどの性の分化や生殖系の発達は、 発生中に内分泌かく乱物質の曝露を受けることによって大きな影響を受ける。 野生動物の研究から、 内分泌かく乱物質の曝露により、 雌雄ともに生殖腺および生殖腺附属器官の発達、 機能分化および体内のホルモンの量に影響が出ている。 多くの野生動物種の生殖系で同様の異常が見られることから、 ヒトに対する影響も懸念されている。 アメリカ、 ヨーロッパをはじめ世界経済協力開発機構 (OECD) 世界保健機関 (WHO) でも、 化学物質のホルモン作用を調べるための試験法の開発が行われている。 ヒトだけでなく野生動物に影響があるような化学物質は使用しないことを前提にした、 魚、 カエルおよび鳥を用いた影響の試験法が開発されつつある。 日本でも、 各国と協調して内分泌かく乱物質問題に対応するために、 環境庁、 厚生省、 通産省、 建設省、 労働省、 水産庁、 農水省、 科技庁、 運輸省が調査・研究を行っている。
歴史的背景
レイチェル・カーソンは1962年の 「沈黙の春」 によって、 野生動物は地球環境の番人であること、 殺虫剤による環境汚染が鳥類などの野生動物に悪影響を与え、 ヒトの健康に悪影響を与える可能性のあることを指摘した。 これにより、 DDTなどの農薬は使用が禁止された。 しかし、 マラリアを媒介する蚊を駆除するために、 東南アジア、 アフリカ、 南米の国々ではまだ使用を続けている。 DDTの半減期は100年とも言われているので、 地球規模ではDDT汚染は続いていることになる。
胎仔期から新生仔期 (周生期) のマウスに女性ホルモン (エストロゲン) を投与すると雌では膣、 子宮、 輸卵管、 雄では前立腺がガン化するという事実が高杉 (元横浜市立大学長) とバーン (カリフォルニア大学バークレー名誉教授、 アメリカ科学アカデミー会員) らによって1960年に発見された。 その10年後には、 ハーブストらにより、 妊娠中に流産防止のために合成エストロゲンのDESを服用した婦人から生まれた女性に膣ガンが発見され (DESシンドローム)、 ヒトで問題になった。 DESを服用した妊婦はアメリカでは600万人とも言われている。 このような事例から、 胎児期における女性ホルモンの曝露は生殖器官にガンを発生させることが考えられる。 さらに、 DDTやPCBなどがエストロゲン類似作用をもつことから 「Environmental Estrogen、 環境エストロゲン」 とも呼ばれている。 ヒトの子宮癌や乳癌の発生が環境エストロゲンによって増加するのではないかとの懸念から、 環境エストロゲンと癌との関連が、 アメリカ環境
健康科学研究所 (NIEHS) のマクラクラン (現、 チューレーン大学教授) らにより、 1979年以来研究され、 哺乳動物の生殖および生殖器官のガン化に対する女性ホルモンの影響に関する会議 「環境中のエストロゲン」 を開催してきた。 1994年1月にワシントンD.C.で第3回目として、 内分泌かく乱物質の問題をも取り込んだ会議を開催した (2, 3) (表1)。 エストロゲン作用以外にも抗アンドロゲン作用を示す化学物質も見つかり、 Environmental Hormones とも呼ばれていた。
| 1962年 | カーソン女史による「沈黙の春」の出版 | |
| 1979年 | 有吉佐和子女史による「複合汚染」の出版 | |
| 第1回環境エストロゲン会議 | ||
| 1985年 | 4月 | 第2回環境エストロゲン会議 |
| 1991年 | 7月 | コルボーン女史によるウイングスプレッド会議 |
| 1994年 | 1月 | 第3回環境エストロゲン会議 |
| 1995年 | 1月 | 英国医学研究審議会のワークショップ |
| 4月 | 英国環境保護庁(EPA)のワークショップ | |
| 7月 | 魚類に関するウイングスプレッド会議 | |
| 1996年 | 3月 | コルボーン女史らによる「奪われし未来」出版 |
| 7月 | 通産省の内分泌かく乱物質関連の研究班発足 | |
| 8月 | EPAによる内分泌かく乱物質スクリーニング法の開発着手 | |
| 10月 | 厚生省の内分泌かく乱物質関連の研究班発足 | |
| 11月 | OECDによる内分泌かく乱物質スクリーニング法の開発着手 | |
| 12月 | 欧州委員会とWHOがイギリスでウエイブリッジ会議 | |
| 1997年 | 1月 | ホワイトハウス・EPAによるスミソニアン会議 |
| 1月 | 環境・通産・厚生・労働・農水による省庁連絡会議 | |
| 2月 | IFCS化学物質安全政府間フォーラムで検討開始 | |
| 3月 | キャドバリー女史による「メス化する自然」出版 | |
| 3月 | 環境庁による研究班発足 | |
| 5月 | G8環境大臣会合で内分泌かく乱物質を討議 | |
| 5月 | サイエンスアイで「環境ホルモン問題」を放映 | |
| 7月 | 環境庁研究班による中間発表 | |
| 9月 | 「奪われし未来」翻訳出版 | |
| 11月 | 横浜での国際比較内分泌学会でシンポジウム | |
| 1998年 | 3月 | OECDによる試験法に関する専門家会議を開催 |
| 5月 | 環境庁による環境ホルモン戦略計画SPEED’98を公表 | |
| 6月 | 日本内分泌撹乱化学物質学会(通称 環境ホルモン学会)設立 | |
| 7月 | 米国で「内分泌かく乱物質」のゴードン会議開催 | |
| 12月 | 環境庁主催による「国際内分泌撹乱化学物質シンポジウム」を京都で開催 | |
| 12月 | 通称環境ホルモン学会を京都で開催 | |
| 1999年 | 1-2月 | レイクタホにて「内分泌撹乱化学物質」のキーストン会議開催 |
一方、 世界自然保護基金 (WWF) のコルボーンは、 五大湖を含め多種類の野生動物種で性器異常、 生殖異常がみられ、 化学物質の影響を受けたことが原因ではないかと考え、 1991年7月にこれらの問題に取り組んでいる科学者をウイスコンシン州のウイングスプレッドに集めて会議を開いた。 このような化学物質の野生動物、 実験動物およびヒトへの影響について議論し、 人工化学物質の中には生体内でエストロゲン類似作用をし、 ホルモンを撹乱させる作用を持つものがあり、 多くの野生動物種はすでにこれらの化学物質の影響を受けており、 人体にも蓄積されている、 などの合意を得た。 このような作用を示す一連の化学物質は内分泌かく乱物質 (Environmental Endocrine Disruptors;Endocrine-Disrupting Chemicals; EndocrineDisruptors) と呼ばれている。 「内分泌かく乱物質は、 生体の恒常性、 生殖、 発生あるいは行動に関する種々の生体内ホルモンの合成、 貯蔵、 分泌、 体内輸送、 受容体結合、 ホルモン作用あるいはクリアランス等の諸過程を阻害する外因性の物質」 という定義がある。 WWFのリストには約70の化学物質があげられており(4,5)、 エストロゲン類似作用をもつ化学物質が多い。 アンドロゲンに拮抗する化学物質としては農薬のDDEとビンクロゾリンが見出されている。 また、 甲状腺ホルモンの作用をじゃまする物質もある。 ヒトでの被害も近い将来顕在化するおそれがあるため, ヒトへの影響に対する研究を優先的に実施する必要があるとした。 内分泌かく乱物質は 「環境」 中に放出されて、 体内の 「ホルモン」 の様に働くことから、 「環境ホルモン」 と呼んだ。
同時多発的な現象
このような内分泌かく乱物質の問題は, 1980年代後半から1992年頃にかけて、 アメリカだけでなく、 デンマーク、 イギリスでも同時多発的に起こり、 新たな環境問題としてクローズアップされてきた。
イギリスの河川で雌雄同体のコイ科の魚が見つかり、 河川中にホルモン様化学物質が流れ込んでいるのではないかという疑問から研究が始まり、 イギリスの環境庁とブルーネル大学の、 雄のニジマスを用いた共同研究から、 羊毛加工工場の排水中から界面活性剤として用いられたノニルフェノールポリエトキシレートの代謝産物のノニルフェノールが見出された。 イギリスの河川では天然のエストロゲンや経口避妊薬のエチニルエストラジオールも河川水中に見つかっている。 一方、 デンマークのスカキャベクらは過去の文献調査を行い、 この50年間でヒトの精子数が半減していることを報告した。 また、 エジンバラMRCのシャープもスカキャベク、 サンプターらと共同研究を行い、 環境中のエストロゲン様化学物質と精巣ガンの増加、 精子数の減少とを関連づけて考え始めた。 イギリス、 デンマーク、 アメリカで、 ほぼ同時に起こった内分泌かく乱物質と生殖異常との関連を、 イギリスのBBCが 「邦題、 精子が減っていく」 にまとめて放映した。 日本でも1996年暮れにBSで放映された。 これによってこの問題が広く世に知られることとなった。 この番組のプロデユーサーが取材経過を 「メス化する自然」 (集英社) にまとめている。
環境に放出された化学物質は主に水系に入ることから、 1995年7月にウイングスプレッドに魚類の研究者が集まり、 「化学物質による魚類の発生・生殖の変化」 に関する会議を開き、 内分泌かく乱物質の魚類の発生・生殖・生理に対する影響について議論し、 以下のような研究の必要性をまとめた。 (a) 水系に存在する合成化学物質の幾つかは魚類の内分泌・免疫系・ 神経系・成長・ 発生を撹乱する。 (b) これらの化学物質により、 奇形や機能変化がおこる。 発生中の胚や 幼生は成体より化学物質に対して感受性が高い。 (c) 多くの魚類の数は化学物質により減少している。 (d) 化学物質に対する最も感受性の高い発生時期を知る必要がある。 (e) 化学物質の作用機構、 作用部位を明らかにするための基礎研究が必要である。 (f) 発生・生殖に影響を与える物質の検出系が必要である。 (g) 政府及び民間の研究者の長期にわたる国際的な研究が必要である。
1996年3月にはコルボーンらの Our Stolen Future 「奪われし未来」 (翔泳社) が出版され、 ゴア副大統領が序文を書いたこともあって、 内分泌かく乱物質に対する関心が高まってきた。
以上の流れを受けて、 内分泌かく乱物質の研究はオゾンホール、 地球温暖化、 生物の多様性と同様に世界的な研究が必要であるとの意識が高まり、 1997年1月にワシントンD.C.で、 ホワイトハウス、 スミソニアン財団、 アメリカ環境保護庁 (EPA)、 UNEP等の後援により、 EndocrineDisruptor Workshopが開催された。 各国の研究の現状を紹介すると共に、 政府の取り組みに関しても紹介し、 それを基に研究の方向付け及び世界的なコンセンサスをまとめることを目的にしての会議であった。 国際共同研究の必要性、 国際的なデータベースの作成、 濃度ー反応関係の確立、 受容体に基づいたアッセイの改良、 スクリーニングの評価、 などが話し合われた。
日本の対応
1997年3月より環境庁の 「外因性内分泌かく乱物質問題に関する研究班」 が発足し、 7月に中間報告書をまとめた。 また、 通産省は 「内分泌 (エンドクリン) 系に作用する化学物質に関する調査研究班」 (日本化学工業協会に委託)、 厚生省は 「化学物質のクライシスマネジメントに関する研究班」 が報告書を作成している。
日本では環境庁が、 河川水、 底質、 魚介類での化学物質のモニターを行っている。 しかし、 この問題の研究者も極めて少ない。 また、 世界的な精子数の減少といった問題に関しても、 日本にはきちっとしたデータがなかったが、 厚生省の研究班で調べ始めている。 平成10年度には、 環境庁、 厚生省、 通産省、 労働省、 建設省、 水産庁などが研究班を組織し、 補正予算もついたことから、 環境中、 野生動物体内および人体の内分泌かく乱物質の濃度や、 悪影響の可能性、 体内動態などの調査研究が、 各省庁で急速に行われようとしている。
新たな観点の研究が必要
内分泌かく乱物質のリストには、 毒性、 蓄積性や発ガン性の観点から、 ダイオキシン、 PCBや DDTのように規制されている物質の他に、 毒性の面からは問題にされておらず、 規制もなく大量に使用されて環境中にも多く出ている物質がある。 内分泌かく乱物質はすべて猛毒であり、 食物連鎖により生物濃縮し、 超微量で大変強い作用を及ぼし、 成人にも悪影響があるとの誤解もある。 化学物質によってはこのどれかに相当するものもあるが、 内分泌かく乱物質にリストされたものが全てこの3つを満足するものではない。 どの化学物質を考えるのかにより取るべき対応がことなる。 勿論、 摂取しないにこしたことはないが、 ヒトでは胎児影響、 野生動物では卵からの発生中への影響が中心に考えられているのである。
野生動物にみられる生殖異常(表2)
ダイオキシン、 PCBなどを空気、 飲料水、 食品から取り込んでいる。 これらは分解されにくく体内の脂肪に蓄積され、 母乳から乳児への曝露が問題となっている。 他の内分泌かく乱物質では、 体内への蓄積性、 分解性などについての詳しい研究がない。
| 生物 | 化学物質 | 影響 |
| 海産巻貝 | トリブチルスズ | 雄性化 |
| ローチ | 生活排水、下水 | 雌性化 |
| ニジマス | ノニルフェノール・エストロゲン | ビテロジェニン |
| サケ | PCB,ダイオキシン,有機塩素系殺虫剤 | 甲状腺機能異常 |
| サッカー | 製紙工場排水 | 脱雌性化、生殖の減少 |
| ニベ科の魚 | 鉛,カドミウム,ベンツピレン,PCB | 脱雌性化 |
| セグロカモメ | PCB,ダイオキシン,有機塩素系殺虫剤 | 甲状腺機能異常 |
| アメリカオオセグロカモメ | DDT,DDE | 雌性化 |
| メリケンアジサシ | ダイオキシン,PCDD,PCB | 孵卵率の減少 |
| ハクトウワシ | DDT,DDE | 孵卵率の減少 |
| スッポン | PCB,ダイオキシン,フラン類 | 孵卵率の減少 |
| ワニ | 有機塩素系殺虫剤 | 脱雄性化 |
| フロリダヒョウ | 水銀,DDE,PCB | 脱雄性化 |
| ヒツジ | 植物性エストロゲン | 不妊 |
日本を含めた世界の沿岸域では船底防汚塗料のトリブチルスズが原因となって、 メスの海産巻貝にペニスができたり (インポセックス)、 イギリスの河川では雌雄同体のローチ (コイ科の魚) が見つかっているし、 工業用洗剤からのノニルフェノール、 エストラジーオールやエチニルエストラジオールも検出されている。 内分泌かく乱物質の曝露を受けた雄の魚が、 本来は雌しかつくらない卵黄タンパク (ビテロゲニン) を産生する例がある。 また、 アメリカフロリダ州のアポプカ湖では、 DDTやその代謝物質の曝露をうけたワニが生んだ卵は孵化率が悪く、 孵化した雄では男性ホルモンが少なく、 ペニスが通常の半分以下の大きさしかなくて、 生殖はできなくなっている(6)。 内分泌かく乱物質の曝露を受けた野生動物の生殖にかく乱が生じており、 次世代を残せなければその生物種は絶滅へと向かうことになることから、 原因物質の特定、 その規制等が早急に検討されなくてはならない。
ヒトへの影響はあるのか?
ヒトでは、 過去20年間に尿道下裂が2倍になっているという報告(7)、 過去50年間に精子数が半減しているという報告がある(8)。 また、 精巣がんは各国で増加しており(9)、 精巣がんの多い年齢が30歳代であることから、 工業化が進み、 農薬の散布が大量に行われた時期に母親が妊娠していたと考えられる。 動物実験からも、 ダイオキシン、 界面活性剤、 エストロゲンを胎仔期から新生仔期に投与すると、 精子形成の低下がおこる。
因果関係の立証の困難さ
内分泌かく乱物質に関しては、 世界的にも原因物質とその影響が明らかになっている例が少ない。 我々が調査している多摩川では雄のコイの半数に雌のタンパク (卵黄タンパク、 ビテロゲニン) がみつかり、 水の中にエストロゲン類似物質が流れていることは推測できるが、 どの化学物質が原因かはまだ不明である(10)。 野生動物の調査結果には、 実験室での実験とは異なり対照となる個体群がいなので原因物質とその作用結果が明らかになっているものは少ない。 しかし、 実験室での結果から野生動物で起こっている現象の多くが発生中に受けた人工化学物質の曝露で説明ができる。 野生動物で起こっている問題の発見は生態疫学的に重要である。 喫煙が肺ガンの原因であるという仮説に対しては20年以上にわたる論争があったように、 現在の野生動物の健康、 生殖異常の問題と内分泌かく乱物質の曝露に関しても原因ー結果の関係がはっきりしないという反論がある。 しかし、 肺ガンの疫学調査により喫煙と肺ガンの関係を詳細に研究する気運をつくるとともに、 タバコに対する社会の考え方が変わった。 同じように、 特にヒトの健康影響に対しては特定の内分泌かく乱物質が原因であることを明確に証明するのは極めて難しいであろう。 まして、 ヒトに影響が明確に現れない限りは化学物質の規制はできないとなれば、 犠牲者が出るまで待つのであろうか。 胎児影響の結果が数十年後に現れるとすれば原因の特定はほぼ不可能であろう。 化学物質の環境中への放出量を減らす政策的な手段を考えることが重要である。
問題点
疫学調査では、 過去20年に乳ガン、 生殖腺のガン、 不妊、 生殖腺附属器官異常などの多くの生殖異常が増加しており、、 これらは胎児期に原因があるとする仮説がある。 野生動物に起こっている問題は、 ヒトに起こっている、 あるいはこれから起こるかもしれないと謙虚に考えるべきではなかろうか。 野生動物に悪影響があれば必ずヒトにも悪影響がでるとは言えないことは勿論である。 野生動物でも実験動物でもヒトでも、 発生中に起こったことが原因であるらしいとすれば、 原因を環境中に探し、 色々な仮説の中で検証することが重要である。
ともすれば 「内分泌かく乱物質」 という新しい用語に振り回されて、 新たな環境問題がおこったと錯覚することもあるが、 DDTや PCBの例からもわかるように、 化学物質の問題は今に起こったことではない。 化学物質がすべて悪者で環境中から人工化学物質を排除してしまおうという動きもあるが、 化学物質は量によっては安全なものはないともいえる。 冷静に見据えて化学物質とうまく付き合うことが重要である。 ヒトに対する内分泌かく物質の影響については大いなる仮説の段階であろう。 しかし、 実験動物で起こることはヒトにも起こると考えるのが自然である。 動物種によっては、 性の分化の仕方が違っているために、 すぐにヒトにつなげるのは問題という意見もあるが、 性ホルモンは魚からヒトまで共通しているし、 発生段階でホルモンに対する感受性が変わることも共通である。 また、 ヒトに影響が出なければそれでよいという発想はあまりに短絡的である。
研究の必要性
現在、 最も必要なことは、 人工化学物質を全て排除することではなく、 実際の使用形態に合わせた試験の上で、 内分泌かく乱物質の溶出があるのか、 その溶出量で胎児影響があるのか、 胎児や大人での分解性は良いのか、 蓄積性はどうかなどの研究である(11)。 また、 内分泌かく乱物質のホルモン受容体への結合方式や、 転写因子の発現機構などの基礎研究も重要である。 毒性、 発がん性などの他に、 ホルモン様作用という新たな観点からの研究が必要であり、 経済協力開発機構 (OECD) や、 日本でも各省庁による環境ホルモンの調査・研究が始まっている。 この結果を待って冷静に判断することが必要である。 アメリカでは身近にある化学物質75,000種の中から年間4.5トン以上生産される人工化学物質15,000種のホルモン作用の調査が始まっている。 多くの化学物質の中に暮らす我々は、 結論が出るまで待つのではなく、 ライフスタイルを見直して人工化学物質を少なくする努力も必要である。 また、 急性毒性はないからといって化学物質を自然界に放出し、 浄化は自然界にまかせっきりという状態は望ましくない。 環境中への化学物質の放出を極力減少させる努力をしなければならない。 地球上に生きる生物がこれ以上絶滅することのないように、 ヒトを含めた野生動物の健康を世代を越えて守るためにも、 むやみに化学物質を環境中に出さないように、 現在できることから対応すべきであろう。 これによって野生動物やヒトへの化学物質の影響がより少ない環境を作り、 できるだけきれいな環境を次世代へ残すことができるのである。 オーストリアでは3歳以下の子供が使う、 可塑剤の入ったプラスチックのおもちゃを売らないとしている。
悪影響を与えるという研究結果が出たのではなく、 疑わしいものはやめておくとする予防原則に立った決定であろう。 人工化学物質の中には大気に拡散して、 あるいは水に溶解して地球規模で広がるものもあるので、 地球温暖化やオゾン層の破壊と同じように、 地球規模での環境問題ととらえなくてはならない。 環境中への化学物質の放出が減ればヒトのみならず野生動物への影響も少なくなる。 化学物質のヒトへの影響に関しては研究されているが、 野生動物に対する影響に関しての研究は少ない。 ヒトのことだけを考えるのではなく野生動物の生活を守ることも考えなくてはならない。 また、 予防原則に則った政策の決定が必要となるであろう (図1)。
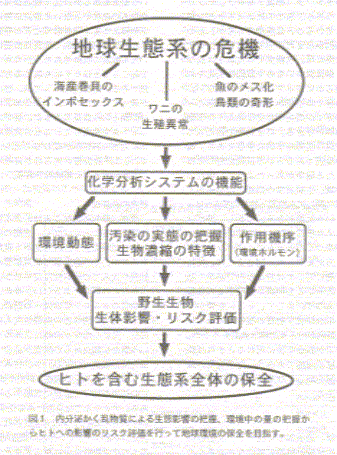
―― 引用文献 ――
■井口 泰泉 (いぐち・たいせん)
1951年生まれ。1974年岡山大学理学部生物学科卒業。1976年同大学大学院理学研究科修士課程修了。1981年理学博士 (東京大学)。1987年横浜市立大学文理学部助教授、1992年同教授。1995年横浜市立大学理学部教授 (学部改組)。1997年環境庁「外因性内分泌撹乱化学物質問題に関する調査研究班」班員、通産省「化学物質のホルモン影響作用標準測定法開発技術委員会」 委員、厚生省「環境エストロゲン様化学物質に関する研究班」班員、環境庁「鳥類・哺乳類のダイオキシン汚染状況の調査研究」班員。1998年エンドクリン影響調査委員会委員。著書に『器官形成』(培風館、1988)、『生殖異変』(かもがわ出版、1998)、『環境ホルモンを考える』(岩波科学ライブラリー、1998) などがある。
| 今号のトップ | メインメニュー |