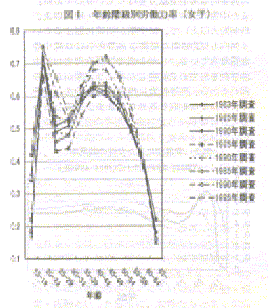
| 特 | 集 | 論 | 文 | 3 ジェンダー・ジェネレーション |
1. 高学歴女性とM字型就労
過去およそ一世紀間における、 日本女性の高学歴化には、 目をみはるものがある。 それは1910年頃に中等教育レベルの拡大から始まったが、 戦後は高等教育レベルも急速に拡大し、 1990年代には、 女性の高等教育進学者の比率が男性を追い抜くに至っている (1) 。
ところでこの日本社会には、 既に明治の頃から、 高学歴を社会移動の跳躍台とみる見方が生れていた。 高い学歴を得れば、 威信の高い職業に入職し、 立派な肩書きをもって一生を送れる、 あるいは威信の高い職業に至るエスカレーターに乗れると、 考えられたのである。 そしてこのような考えを抱くかなり多くの男性が、 学歴取得競争へと突き進み、 急速な高学歴化をもたらしたのだった。 とすれば、 やや遅れて始まった女性の高学歴化の背景にも、 男性と同じく、 社会移動への強い志向があるのであろうか。
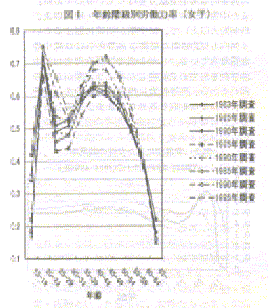
日本女性の就業の特徴をトータルでみると、 高学歴化の進んだここ数十年間、 就業構造は一貫して 「M字型」 のパターンを持ち続けている。 M字型とは、 女性の労働力率の年齢的な変化の特徴を表すものである。 図1にみるように、 20〜24歳と35歳以降を中心とする二つのピークをもつ、 独特な就労形態が 「M字型就労」 なのである。 このM字型就労は、 欧米でもかなり広くみられたが、 近年では消滅の途を辿っている。 ところが日本では、 このM字型就労が、 全体に底上げされてはきたものの、 現在なお根強く残っているのである。
しかもこの再就労は、 多くがパートタイマーとしての就労であり、 始めの就労との連続性を欠くことが多い。 このように、 女性の職業的地位が持続性をもつものでなく、 彼女が一生のものとしての職をもつことができずにいるとしたら、 職業が彼女の社会的地位を表示するほど重要なものとなることは難しい。 この女性は、 いかに威信の高い職に就いても、 この就業を一時的なものとのみ見て、 社会移動の達成とはみなさない可能性が高い。 その意味で、 M字型就労の存在は、 日本女性の多くが現在に至るまで、 社会移動への志向をあまりもたずにきたことの、 証のように思われるのである。
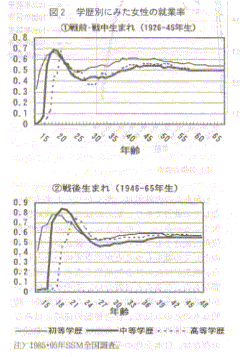
このM字型就労は、 高学歴女性とも無縁ではない。 図2は、 1985年と1995年に行われたSSM (社会階層と社会移動) 全国調査のデータ (2) で、 女性の就業率の学歴による違いをみたものだが、 そこにはむしろ、 M字型就労と高学歴との深い結びつきがみられるのである。 すなわち、 戦前・戦中生まれ世代でも、 戦後生まれ世代でも、 たしかに初等よりは中等のほうが就業率のピークは高めだが、 その後に訪れる谷の深さは、 中等のほうがむしろ深い。 また復帰後の第二ピークでの比率も、 初等より中等が低くなっている。 つまり中等学校を卒業した女性のほうが、 むしろ典型的なM字型就労を行っているのである。 また中等に比べて高等 (旧制高専・短大以上、 新制短大以上) で、 M字型が明確に弱まるという傾向も見出されない (3) 。 高等の谷はほぼ中等と重なっている。 しかも高等学歴取得者は、 中等学校を出てすぐ就職した者より就業がかなり遅れるから、 高等教育に投資された分を、 中等卒女性ほどにも取り返せないまま、 退職していることになる。
ここにみる限り、 高学歴の女性がそうでない女性よりも、 就労に対して積極的だとは、 決していえない。 それどころか、 女性においては学歴の高さと就労への消極性がプラスの相関関係にあるという、 男性と対照的な特徴が、 見出されるのである。
歴史的にみても、 高学歴化と就労への消極性との間には、 密接な関わりが窺える。 高学歴化の始まった1910〜20年代において、 当時の高学歴女性 (高女卒程度) が就労するのは、 電話交換手・タイピスト・車掌・店員などの新しい職種であったが、 その多くは未婚を就労の条件とするという、 かつてない特徴をもつ職業であった (4) 。 またその後も、 図1にみるとおり、 1975年まで、 M字の谷の深さは一貫して増加している。 つまり女性の高学歴化と、 M字型就労の普及は、 相携えて進行してきたものなのである。
2. 「家庭責任の主体」 としての高学歴女性
高学歴女性が、 短い就労ののち退職してしまう理由としては、 その職場の問題が指摘されることが多い。 すなわち、 男女の賃金格差や、 女性の昇進の遅さ、 仕事のやりがいのなさや訓練機会のなさなどが、 彼女らに、 就労継続への熱意や可能性をなくさせ、 結婚・出産退職へと追いやっているというのである。 だが、 賃金や昇進における格差が解消されても、 高学歴女性は必ずしも就労を継続するようにはならなかった。 男性なみの訓練のチャンスを、 積極的に受け入れる様子もなかった。 このことは、 1986年の男女雇用機会均等法施行後も、 あえて一般職を選択し結婚・出産退職する道を選んだ女性の多さによって、 十分立証されている。
この問題に関して重要なのはむしろ、 この社会に流通している、 「高学歴の女性」 に関するある独特な意味付けである。 それはこの社会の人々により、 また女性たち自身によって共有されてきたものであり、 近代に特有な人間 (女性) 類型といってもよいものである。
既にみたとおり、 「高学歴の男性」 とは、 高い社会的地位を保証された人を意味する。 それは彼らが、 肉体労働者でなくて頭脳労働者に、 なかでも大企業や官公庁のホワイトカラーになることによって、 一生涯にわたり高い俸給を得る人であり、 短い昇進年数で管理職に到達する人でもあるからである。 そして企業のこうした仕組みに対応して、 各種教育機関も、 職業教育や専門教育の部門を充実させてきた。 これらの諸制度に支えられて、 「高学歴の男性」 は、 上記のような属性をもち続けてきたのである。
ところが 「高学歴の女性」 は違う。 こちらは、 「家庭責任の主体」 となるに相応しい教養を身につけた人を意味する。 たしかに女性も、 高い学歴を取得すれば、 事務員や店員などといったホワイト系の業種に就くことができ、 大企業に入社する可能性も広がる。 だが高い学歴は、 彼女らに高い社会的地位を保証するためのものではない。 やがて家庭をもち子育てをするときに、 教養ある母親として子供の 「正しい」 養育や教育を行い、 家庭を守る力を養うためのものなのである (5) 。 女性が高学歴化し始めた1910年代の婦人雑誌がすでに、 女性の教育と育児の問題を、 車の両輪として語り始めている。 教養ある女性とは、 よい家庭を築き子供を立派に育てる使命を全うしうる人、 に他ならないのである。
教育の場面でも、 同じ頃から、 高学歴女性を 「家庭責任の主体」 として育成する諸制度が整えられてきた。 女性に固有な学問としての家政学が重視されるようになり、 戦前の女子教育の基調をなした。 また戦後は1970年代までのほとんどの時期で、 教育の基本方針は男女別教育であった。 就学者は、 男女別出席名簿を始めとして、 家庭科、 短大、 文学部・家政学部などといった、 性別に準拠した諸制度を経験する。 就学年数の長い女性ほど、 男女別教育に接する期間も長くなるから、 高学歴の女性ほど、 そうした役割期待を内面化しやすい立場に置かれたといってよいだろう。
また職場でも高学歴を取得して事務職などに就いた女性は通常、 コピーや書類整理などのように、 熟練をあまり要さず、 したがって入社直後からでき、 新入社員が入れば容易に引き継ぎうる単純な仕事を任される仕組みになっている。 企業は、 彼女らが数年で退職するという想定のもとに、 低い俸給、 遅い昇進を彼女らに課す。 企業社会における 「高学歴の女性」 とは、 サラリーマンである夫のために日常の細々した雑用を、 ちょうどOLとして行っていたと同じように家庭でも行って、 夫が疲労回復しまた仕事に専念できるようにするとともに、 その教養をもって子供の養育・教育にあたるという、 実質的には 「サラリーマンの再生産」 ともいうべき作業を行う存在に他ならないのである。
数十年前に生れたこの近代的人間類型、 「家庭責任の主体としての高学歴女性」 は、 教育制度や企業の仕組みによってかく強固に支えられると同時に、 女性たち自身によって受容されることによって、 現在までリアリティを保ち続けてきた。
そして女性の高学歴化が進むにつれて、 高学歴女性の比率は高まり、 その動向は、 日本女性全体の動向を左右する重みをもつようになった。 先の図1において、 M字曲線の谷が1975年まで一貫して深まる方向へ動いているのは、 この時期に高学歴女性の量的な拡大が進んでいたことに、 一つの大きな原因をもつのである。 その結果、 先のような属性を読み込まれた 「高学歴女性」 と 「女性」 は、 次第に区別されなくなってきた。 あたかも生物学的属性に由来するものであるかのように、 「家庭責任の主体としての女性」 という概念が日本社会のなかで普遍化されてきたのである。
3. 新しい 「女性」 の構築へ向けて
では、 このような意味合いをもつ 「高学歴女性」 は、 今後も日本女性を代表し続けるのだろうか。
たしかに変化の兆しはある。 1980年代には、 男女雇用機会均等法の施行などが行われた。 つまり女性の先のような属性を支える諸制度のうち、 企業の仕組みの一部が、 変わり始めた。 多くの企業に、 一般職と総合職との新たな区分が生れ、 女性にも管理職等へのキャリアの道が開かれた。
ところが実際の選択に当たり、 大部分の女性は一般職を選び取る。 そして一般職に位置づけられることは、 将来の可能性がないことの宣告にほぼ等しいため、 彼女らは、 M字型就労へとかえって強く方向づけられる結果となっている。 かくも総合職女性が増えにくいのは、 転勤・残業・夜勤といった要求に、 女性たちの多くが応じられない事情をもつからである。 そしてそれは、 彼女らが今なお、 「家庭責任の主体」 というあの古典的な役割から自由でないことに起因している。 たとえ保育所が整備されても、 育児休業制度が整備され、 さらには男性まで適用されるようになっても、 それらを利用する女性たちは、 あの役割期待に反するふるまいをしている自らに対し、 良心の呵責を感じ、 あるいは周囲からの非難にたえなければならない。 そのために、 総合職への一歩を踏み出せない女性も、 少なからずいるのである。
また1980年代は、 男女別教育の方針が転換したという意味でも重要な時期であった。 その結果、 女性にも職業的に有用な学問が教えられるようになり、 就労継続を促進するような風潮が現れてきた。 しかし本人の教育はいざ知らず、 その子供の教育となると、 事態は決して同じではない。 子供が問題行動など起こせば、 非難されるのは家庭であり、 なかでも 「鍵っ子にしている家庭」、 「母親が就労しているため子供に目が届かない家庭」 への風当たりは強い。 学校行事等も、 母親が昼間家にいることを想定して組まれており、 不参加者に対しては、 同じ女性たちからの非難の目がむけられるだけでなく、 働く母親自身も、 フルタイマーなら3人に2人、 パートタイマーでも3人に1人は、 「子供にすまない」 という気持をもちつつ、 働いている (6) 。 そして、 「母親が学ぶことでより良い子育てを」 という古典的な指針は、 今なお行政の基本的姿勢を形作っている。 中学・高校受験等の重圧が弱まる兆しはみえず、 「子育ての責任者としての母親」 という役割が、 女性のうえから取り除かれる気配はない。
さらに政府の施策などでも、 女性は福祉の担い手などとして、 「家庭責任の主体」 という属性をむしろ強化される傾向にある。 年金制度等も、 女性をそういう位置づけのもとに保護する性格のものであることは、 よく知られている (7) 。
このように、 現代日本の女性たちの多くがなお捨てられずにいる 「高学歴の女性」 人間類型は、 多様な役割期待の束を個々人に被せてくるものである。 この人間類型は、 これらの役割期待を相互にぶつかりあわないような形で、 人の一生にうまく配分しているモデルなのである。 この社会が基本的にこの人間類型に基づいて女性を定義し、 女性自身もその定義を受け入れている限り、 これと相容れない役割を引き受け、 以前と異なるふるまいをしはじめるのは難しい。 つまり、 女性の一生に関する新しいモデルをもたないままでは、 容易に動くことができないのである。
なるほど1970年にはウーマン・リブ運動が日本にも上陸して、 「女性の自立」 が叫ばれるようになった。 これは、 「育児・家事を女性の当然の役割」 とする常識を、 覆そうという、 今からみても興味深い契機を含むものであった (8) 。 しかしこの運動の担い手の大半は、 未だ 「家庭責任の主体」 ではない未婚女性たちであったため、 先のような契機は、 やがて立ち消えてしまった。 またその後を継いだとされるフェミニズムの諸潮流も、 広く受容される 「女性」 像を示すことは、 未だできずにいる。
おそらくこれらの結果として、 女性はなお、 M字型の就労を続けているのである。 彼女らが子供の教育にかける熱意は結局、 教育費を稼ぎ出すためのパートという形でしか現れえず、 そのことが再び企業の仕組みを支える結果となっている。 労働力調査でも、 労働力率は未婚女性でこそ過去10年ほどの間に上昇しているが、 有配偶女性では逆に低下しているという結果が示されている (9) 。 これらをみれば、 あの 「高学歴の女性」 はまだ当分、 日本女性の典型であり続けるだろうと、 考えざるをえない。
ただし、 現代の若い未婚女性がやがては既婚となるのかどうか、 また既婚となったときにどんな生き方を選び取っていくかが、 一つの鍵であろう。 彼女らは、 かつてならばとうに結婚退職している年齢となっても、 結婚・出産をせずに、 就労を続けている。 彼女らの比率の増加が、 1975年以降のM字型曲線を、 全体として底上げする一因となってもいるのである。 彼女らは、 別な 「女性」 像あるいは 「高学歴女性」 像を模索している途上のようにもみえる。 彼女らがやがて未婚状態を脱し、 子供の教育に熱心な母親になっていくのであれば、 日本の 「女性」 は変わらないだろうが、 そうでなかった場合、 日本の 「女性」 が、 別な属性を持ち始めることもありうるのである。
また年配の人々の間では、 最近の不況とそれによる失業者の増加が、 皮肉にも、 新しい 「女性」 を生み出すきっかけになる気配をみせている。 夫の所得が減ったり失業したりした家庭が増えれば、 「外で働く女性」 や 「専業主夫」 が増える。 こういう余儀ない事情に促され、 そのおかげで 「良心の呵責」 や 「世間の非難」 にあまりさらされることなく、 新しい生き方を既に始めてしまった妻や夫、 そして家族が生れているのである。 ここにも、 高学歴女性の能力が別な方面に活かされ、 「女性」 が変わる一つの可能性がある。 そうすれば、 いつの日か、 日本においても女性の社会移動を語り得る日がくるのかもしれないのである。
注
■中村 牧子 (なかむら・まきこ)
1962年東京生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程修了。社会学博士。法政大学非常勤講師を経て現職。論文に「紛争処理手続きを巡る比較社会論」(『社会学評論』178号1994年)、著書に『分析・現代社会』(1997年 八千代出版共著) などがある。
| 今号のトップ | メインメニュー |