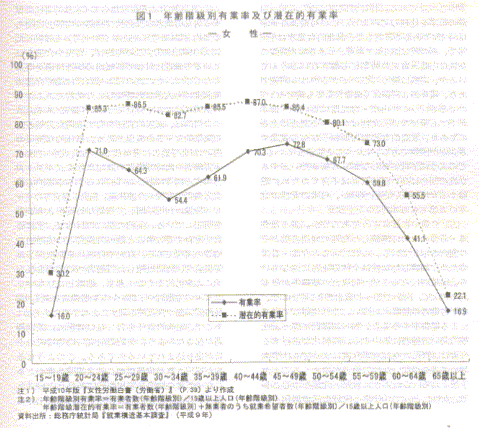
| 特 | 集 | 論 | 文 | 3 ジェンダー・ジェネレーション |
| 仕事と家庭生活との調和に向けて |
| ――女性の就業と家族的責任 |
1 はじめに
今、 仕事と家庭・地域生活との 「調和」 が求められている。 例えば日本の男性サラリーマン。 1990年の統計では日本の年間総実労働時間は2214時間であった。 今や不況のあおりを受けて1993時間 (1996年現在) まで減少したものの、 欧米先進諸国、 とりわけドイツ、 フランスといった大陸ヨーロッパの国々に比べれば依然として長時間労働であるという現実に変わりはない1) 。 「過労死」 が 「Karoshi」 として英語化された当初から比べれば、 「失業」 や 「リストラ」 の陰に隠れてしまった感があるが、 「24時間戦えますか」 というテレビ・コマーシャルが登場する社会、 すなわちkaroshi= 「死ぬまで働くこと」 を煽るような社会・文化的土壌はやはり尋常ではない。 今でも日本の男性サラリーマンは長時間労働しているという事実に大きな変化はないし、 家庭生活や地域生活とのバランスを失って働かざるを得ない社会システムに対しては、 やはり何らかの処方箋が必要であろう。
一方、 同じ日本社会にあって、 働きたくても働けないという多くの労働者がいることも忘れてはならない。 中高年の失業者もそうであるが、 育児や介護といった家庭的な役割を担いつつ働くことを希望する多くの女性にとっては、 家庭生活と調和できるような働き方が見つからないために、 働きたくても働けないという状況が存在する。 そのような家庭の役割を持つ女性にとっては、 長時間労働の男性サラリーマンの置かれた状況とは逆の意味で 「家庭生活と調和のとれた働き方」 を必要としている。 男性サラリーマンの多くが企業中心的な生活におかれ、 家庭や地域生活から乖離した状況は上に指摘したとおりであるが、 そのために家庭内の役割の多くは女性が担うという、 いわば 「性別による役割分業」 が生み出されてきたのが日本社会の特徴の一つである。 もちろん 「働きたくない女性」 も存在するし、 働くことは個々の労働者の意志と選択にゆだねられる。 しかし、 育児などの家庭生活との調和をはかりつつも仕事を継続したいという女性も多く、 その傾向は徐々に強まっていることもまた事実である。 そのような家庭生活との調和をはかりつつ働くことは、 労働者の権利として認められるべきであり、 またそのような労働者を社会的に支援していく必要がある。 以下では、 日本の女性の就業の諸特徴を明らかにし、 さらに国内外の 「仕事と家庭生活の調和」 に関する政策的な対応について若干の考察をしてみたい。
2 女性の就業の実態
男女雇用機会均等法や育児休業法の改正に見られるように、 政策的対応は女性にとっても仕事と家庭生活の調和をはかれるような方向へと進んではいる2) 。 しかし現実には、 仕事と家庭生活の両立にはいくつかの障壁が立ちはだかっている。 子育てや介護をしながら就業を継続することは様々な要因から難しい状況になっており、 とりわけ日本の女性は出産・育児を機にいったん退職し、 子育て終了後に再び働くという傾向が強い。 また、 近年は高学歴化とともに女性の就業意欲が高まっており、 たとえ出産・育児のために就業を中断しても、 育児を終えた後に自分の能力を活かした仕事に就きたいと考える女性も増えている。 しかし、 そうした女性の子育てを終えた後の再就職の機会もきわめて限られたものであり、 再就職したとしてもフルタイムと格差の大きいパートタイムでの不安定な就業となりがちである。
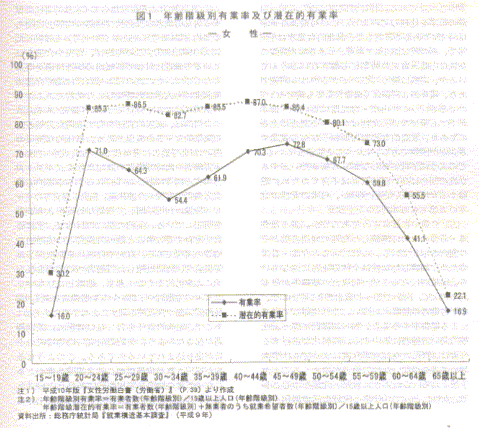
ここで、 日本の女性の就業の実態をみてみよう (図1)。 まず実線の折れ線グラフの方は、 日本の女性の有業率を年齢別にみたものである。 これをみると日本の女性の有業率はアルファベットのM字型を描くことがわかる。 つまり15〜19歳の16.0%から20〜24歳までに有業率が上昇し71.0%に達する。 しかしその後25〜29歳層では64.3%と減少する。 30〜34歳層では54.4%と最も低い水準となり、 40歳以降に再び有業率は上昇するのである。
そして50〜54歳では72.8%と最も高い水準となる。 このように20歳台後半から30歳台にかけて有業率が低下するというM字型のパターンは、 日本の女性の就業の大きな特徴である。 つまりこの年齢層においては、 出産・育児という家庭の役割によっての女性の労働市場からの撤退という現象がみられる。 一般にスウェーデン、 デンマークといったスカンジナビアの諸国、 あるいはアメリカ、 カナダといったアングロサクソンの国々では、 出産・育児の時期においても、 女性の有業率は低下することがなく、 グラフの形は台形の線を描く。 それに対して日本の女性の就業は出産・育児の影響がきわめて大きいのである。 では、 このように出産・育児を機に退職する女性は、 その時期に働きたいと考えているのだろうか。 もし出産・育児にかかわらず働きたいと考えているならば、 実際に 「働きたくても働けない女性」 の割合はどのくらいいるのだろうか。
そこで、 図1で有業者と潜在有業者 (就業希望者) を加えた 「潜在的有業率」 の変化をみてみよう3) 。 「潜在的有業率」 とは実際に就業している有業者に、 働いていない者のうち就業を希望する者を加算し、 それを15歳以上の人口で除したものである。 すなわち 「潜在有業率」 は、 働きたくても働けない女性を含めて、 実際にどのくらいの有業率が見込めるかを推定したものである。 この 「潜在的有業率」 の年齢別の変化はグラフの点線で示している。 これをみると、 実際の有業率と大きく異なることがわかるであろう。 つまり、 実際の有業率は20歳台後半から30歳台にかけて大きく落ち込むが、 潜在的な有業率はフラットな線を描いている。 ここで注目すべきは有業率と潜在的有業率との差である。 特に育児期に当たる30〜34歳の数字を比較してみよう。 この時期は有業率は54.4%であるのに対して、 潜在的有業率は82.7%で、 その差は28.3%である。 つまり約8割強の女性は出産・育児の時期にも働きたいと考えているが、 実際に働くことのできるのは5割強であり、 残りの3割弱は 「働きたくても働けない」 のである。 つまり出産・育児期において 「働きたくても働けない」 女性はかなりの割合に上るのであり、 家庭的な役割と調和しながら就業することが困難である、 ということを示している。 このように子育てをしながらも働きたいとする女性の割合は高いが、 現実は子育てのために離職する女性が多いというのが、 日本の女性の就業の実態でもある。
一方、 介護の影響はどうであろうか。 表1は介護・看護のために離職した女性の雇用者数とその割合を示している。 これによると介護・看護のために離職した女性は全体の4%に達している。 年齢別にみると50〜59歳台の離職率が最も高く10.2%、 次いで40〜49歳台の9.1%であり、 中年労働者の離職率が高い。 これに対して育児による離職率をみると、 20〜39歳台に高く、 比較的若い労働者に集中する。 高齢化が進行する今後は、 育児のみならず介護によっても仕事を辞めざるを得ない女性労働者が増えくることが予想される。 このように育児・介護を中心として、 女性にとって 「仕事と家庭生活の調和」 が難しい状況にあることが理解できるであろう。 では、 このような 「調和」 に対する政策的な対応はどのようになっているであろうか。
| 合計 | 総数 | 介護・看護のため | (育児のため) |
|---|---|---|---|
| 1924 | 77 ( 4.0) | 222 (11.5) | |
| 年齢 | |||
| 29歳以下 | 805 | 8 ( 1.0) | 137 (17.0) |
| 30〜39歳 | 334 | 9 ( 2.7) | 75 (22.5) |
| 40〜49歳 | 253 | 23 ( 9.1) | 7 ( 2.8) |
| 50〜59歳 | 266 | 27 (10.2) | 3 ( 1.1) |
| 60歳以上 | 267 | 9 ( 3.4) | 1 ( 0.4) |
3 国内外の政策的な対応
ILOは1981年の第67回総会で 「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等」 に関する条約 (第156号) と勧告 (第165号) を採択した(ILO,1992,1993)。 この条約は、 育児や介護をしている労働者に対しての雇用の均等待遇を明言したもので、 その後の日本の育児休業や介護休業制度にも大きな影響を与えた条約である。 この条約には大きく分けて2つの目的がある。 第一の目的は、 家族的責任を有する男女労働者間の実効的な平等の実現である。 具体的な施策の内容は165号勧告に書かれているが、 パートタイム労働者や臨時労働者の雇用条件をフルタイム労働者と同等にあつかうべきとすることや、 男女労働者の育児や介護休業、 転勤、 保育等のサービス施設の利用に関して適切な処置をとることを明記している。 条約の第二の目的は、 家族的責任を有する労働者と他の労働者との実効的な均等の実現である。 育児や介護休業を取得した労働者や、 時間短縮した労働者への差別をなくすことを目的とする一方で、 結婚していないシングルの労働者や子供のいない労働者に対して、 長時間労働や深夜業を課すことは不当であろう。 そこで、 家族的責任を有しない労働者に差別待遇が起きないよう、 条約の前文に均等措置の主旨が盛り込まれているのである。 このような条約が採択された背景には、 欧米諸国を中心とした女子労働の増加や家族形態の多様化といった動きがある。 とりわけ女性の労働力率の上昇は1960年代以降は顕著であり、 育児を中心とした家族役割の多くを担っていた女性を保護するとともに、 男女の雇用機会を均等にすべきという動きが世界的に活発になっていたことを背景としている。
日本では1995年6月には 「育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」 が成立し、 この中に 「介護休業法」 が盛り込まれることになった (松原,1996)。 これによって、 ILO156号条約は、 時を同じくして1995年6月に批准に至った。 日本の政策は、 育児休業と同時に介護休業という形をとっている点で特徴的である。 無給の介護休業を法的に制度化しているアメリカ合衆国を例外として、 他の欧米の先進諸国においては日本と同様の介護休業制度はそう多くはない。 高齢化が進む日本では、 家族以外の専門的サービスの充実が求められることはいうまでもないが、 過渡的な措置として 「介護休業制度」 が法的に整備された意義は大きい (前田,1999)。
しかし、 介護休業制度にはいくつかの問題も残る。 例えば、 介護の担い手として 「家族」 にどの程度介護力を期待できるのか、 といった疑問が出てこよう。 つまり、 欧米先進諸国、 とりわけスウェーデン等の北欧諸国では介護の役割は基本的には国家 (公的機関) の役割であり、 家族が高齢者の介護に関わることは実質的には少ない。 そのため、 高齢者の介護が必要になった場合は、 労働者はその介護のために仕事を中断したり、 離職したりするというようなケースは、 非常に限られてくるし、 あえて 「介護休業」 を法的に制度化する必要もない、 というのが現状であろう。 これに対して日本では、 家族以外の公的機関が十分に高齢者の介護をするだけのマンパワーは不足しており、 そのため家族と公的機関は 「相互補完的に」 高齢者の介護をしなくてはならない事情が出てくる。 日本における老人福祉は在宅福祉を原則として考える傾向があるが、 実際には老親との同居形態が多いために、 同居の家族が介護を行うという事態が少なくない (前田,1998a, 佐藤,1993, 庄司,1993)。 介護休業制度は労働者の介護による離職を少なくする上で有効であることは認められるものの、 将来的には介護福祉のマンパワーの充実といったような福祉政策と連動すべきであろう。
4 仕事と家庭生活の調和に向けて
本稿では 「仕事と家庭生活の調和」 について、 とりわけ女性にとって困難な状況が存在すること、 そして 「調和」 に向けての国内外の政策的な対応を簡単に紹介した。 最後に 「仕事と家庭生活の調和」 に向けて若干の課題を提起してみたい。
すでに言及したように、 ILO条約や日本における育児休業法等の政策は、 「仕事と家庭生活の調和」 をはかっていく上で重要な役割を果たしている。 しかしそれは、 「仕事と家庭生活の調和」 に向けてのいわば最低基準のようなもので、 これに加えて、 労働者、 労働組合、 企業、 あるいは地方自治体それぞれは具体的な取り組みをしていく必要があろう。
まず第一に、 家庭内役割の調整という課題がある。 これは労働者の個々の責任として行われるべきであろう。 とりわけ育児・介護は女性の役割、 という固定的な発想から脱却して、 家庭内での性別役割分業の見直しと役割の柔軟な調整が行われるべきであろう。 これは労働者自らが固定的な性別役割の意識を変革するという責任を担うことを意味していよう。
しかし、 家庭内の役割調整のみで仕事と家庭生活の調和がはかれるわけではない。 第二に指摘すべき点は、 家庭生活との調和をはかれるような柔軟な働き方を整備することである。 ここでは 「働き方の柔軟化と多様化」 を提起したい。 具体的にはフルタイム労働のみならず、 パートタイム労働、 派遣労働、 在宅勤務、 起業家といった働き方を促進し、 またフルタイム労働者との格差を是正していくことが必要である4) 。 育児や介護をしながら就業を希望する女性にとって、 一日の労働時間が固定化されたフルタイム就業よりも、 労働時間の柔軟な働き方を望むことが多い。 「フルタイム」 か 「無職」 かといった二元的な発想ではなく、 多様な働き方を認めていくことは、 仕事と家庭生活の調和をはかる上でも重要である。 またこのような働き方の多様化は、 労働者にとってのみならず雇用者にとってもメリットは大きいはずである。 労働力人口が減少するなかで、 企業にとっては女性労働力は貴重なリソースとなる。 女性がいったん家庭生活のために仕事を中断しても、 再び働くことができるような再雇用制度とともに、 継続就業のための働き方の柔軟化は是非とも必要であろう。
第三の課題は外部サポートの充実である。 具体的には育児のための保育施設や、 介護に関してはヒューマン・サービスやデイケア施設の整備の充実が必要である。 これとあわせて、 ケースワーク等を含めたトータルなサポートが必要であろう。 育児や介護といった問題は、 休業の取り方、 施設入所のための手続きに加えて、 状況に応じて様々な専門家が必要とされる。 場合によっては、 予測できない病気やけがの緊急の対応に追われることになり、 複雑な制度を利用することには予想以上の困難が伴う。 そのため施設の利用や休業法制度の活用、 さらには専門家の間に立って、 それぞれの家族の事情に応じて対応を相互に調整するようなケースマネージメントが必要になる。 相談、 ケースワーク、 ケースマネージメント、 カウンセリングといった専門家は、 制度として用意されたサポート機能を調整する上でもきわめて重要になってくるものと思われる。 育児や介護を初めて経験する場合には、 どんな制度をどのように利用すべきか、 皆目検討がつかない場合が多く、 家族が一人で悩んだり、 あるいは問題をひとりで抱え込む事態がおこる。 そのような場合には、 その家族の状況や育児の経過、 介護の状態を適切に把握し、 制度や専門家を利用できるような助言をするマネージメントが必要になってこよう。
注1) 最新のデータについては日本労働研究機構(1999)を参照。
注2) 育児休業法の成立とその背景については藤井(1992)を参照。
注3) 「潜在的有業率」 の概念については労働省(1999)を参照。
注4) パートタイムを積極的に推進しているオランダが参考になる。 オランダにおけるパートタイム労働については前田(1998b,1999)を参照。
―― 参考文献 ――
藤井龍子 1992 「育児休業法制定の背景とその概要」 『季刊労働法』 163号, 29-44頁
ILO, 1992., International Labour Conventions
and Recommendations:1963−1991
(Volume II), International Labour
Office Geneva.
ILO, 1993., Workers with Family
Responsibilities, International
Labour Office Geneva.
前田信彦 1997 「オランダにおけるパートタイム労働と労働者生活」 JILリサーチ, No,31, 6-39頁
前田信彦 1998a 『家族のライフサイクルと女性の就業−同居親の有無とその年齢効果』 日本労働研究雑誌 No.459, 25-38頁
前田信彦 1998b 『オランダにおけるパートタイム労働の動向と家庭生活の変化』
海外社会保障情報 No.124, 89-103頁
前田信彦 1999 『仕事と家庭生活の調和−ILO条約の日本的適用』 研究紀要 (日本労働研究機構)
松原亘子 1996 『詳説育児・介護休業法』 労務行政研究所
日本労働研究機構 1999 『労働統計国際比較資料集 (1999年版)』
労働省 1999 『平成10年版 女性労働白書−働く女性の実情』 21世紀職業財団
佐藤進 1993 「在宅ケア推進をめぐる法制度政策の現状と課題」 『高齢社会と在宅ケア』 ジュリスト増刊, 有斐閣 24-32頁
庄司洋子 1993 「現代家族の介護力−期待・現実・展望」 『高齢社会と在宅ケア』 ジュリスト 増刊, 有斐閣 190-196頁
■前田 信彦 (まえだ・のぶひこ)
1992年上智大学大学院博士課程 (社会学) 修了。1997〜1998年エラスムス大学 (オランダ) 客員研究員。現在、日本労働研究機構副主任研究員。
| 今号のトップ | メインメニュー |