地震防災における先端的技術とその未来
山崎文雄
(東京大学生産技術研究所助教授)
1. はじめに ―― 地震と防災技術の発展
20世紀は科学技術の時代であった。 土木工学や建築学の分野でも、 高速道路、 長大橋、 超高層ビルなどを設計・建設する技術が開発され、 それらが実際に多数建設された。 そのような構造物の建設を可能にするためには、 日本や米国などの地震活動が活発な地域では、 地震に対する安全性の確保が課題となり、 「耐震工学」 という研究分野が生まれた。 この耐震工学の進歩により、 構造物の地震に対する応答を計算し、 壊れない強い構造物を実際に設計・建設することが可能になった。
明治維新以降、 近代的な構造物が作られるようになってから、 最初の大きな地震の洗礼は1890年の濃尾地震である。 この地震による被害の様子が、 当時、 東京帝国大学に教授として赴任していた英国人によって写真に写されており、 木曽川に架かる鉄道橋の落橋の状況などは、 今日でも充分起こりうると思われるほど生々しいものである。 20世紀に入ってからも、 日本は度々大地震に襲われ、 それらから得た教訓から耐震工学が発展していった。 第二次世界大戦後は、 戦後間もない1948年の福井地震で壊滅的な被害が生じて以降、 高度成長期は大きな地震の洗礼を受けないままに、 さまざまな大型構造物の建設が進んだ。 これらが、 兵庫県南部地震 (阪神・淡路大震災) で手痛い被害を受けたのも、 構造物の設計技術の問題もさることながら、 実際に地下の活断層が動いたらどれほど強い揺れが生ずるか、 充分には分っていなかったことが大きいといえる。 これは、 直下地震による断層近傍での揺れを地震計が記録した例が、 ほとんどなかったことが最大の理由といえよう。 また、 活断層の活動履歴がよく分かっておらず、 どの程度の地震発生の切迫性があるか、 情報が不足していたことも、 地震に対する備えが甘くなった原因ともいえる。
阪神・淡路大震災の教訓は多岐にわたるが、 地震防災に関しては、 構造物を強く造るという従来の耐震工学から、 ハード面では免震・制震といった制御技術が注目され、 それ以上に、 ソフトな防災技術や情報の重要性が叫ばれるようになった。 地震のように発生頻度が低いが一度起きれば大きな影響が及ぶ事象に対しては、 予防対策だけで被害を防止することは不可能との認識で、 地震発生後の適切な対応により被害の拡大を防ぐことが重要だということが、 世間一般でも理解されるようになった。 地震災害の様相は時代とともに変化し、 21世紀に起きる大地震では、 神戸で起きなかったような被害が問題になることもあろう。 このような認識に立つと、 われわれはまだまだ謙虚に災害から学び、 次の災害に備える必要がある。 本文では、 21世紀初頭において、 一層研究開発を進めるべき地震防災のソフト技術を紹介しその展望を論ずる。
2. 揺れを計る ―― 高密度な地震動モニタリング
日本には以前より、 世界で最も多くの強震計 (強い揺れを計る地震計) が設置されていた。 しかし、 兵庫県南部地震では 「震災の帯」 と呼ばれる震度7と判定された地域にほとんど地震計がなかったことなどの反省から、 より多くの強震計が配備されることになった[1]。 気象庁は、 1993年に奥尻島を中心に大きな津波被害が発生した北海道南西沖地震と兵庫県南部地震をきっかけに、 津波警報の迅速化と、 震動被害の甚大な地域を見逃さないため、 強震観測点を全国約600箇所にまで拡大した。 また、 地震直後において、 神戸海洋気象台からの通信が一時途絶えた経験より、 通信手段もNTT回線を2ルート化するとともに、 気象官署と都市部では衛星回線も利用できるようにした。 また、 消防庁は全国の各市町村に1台づつ強震計を設置する事業を行い、 科学技術庁も全国をほぼ25kmメッシュでカバーするように、 1,000台の強震計からなる観測網(K-NET)を展開した。 このように従来の数十倍の密度の強震計が設置されたことにより、 地震発生時の揺れの強さの分布が正確にかつ迅速に得られるようになったことは大きな進歩である。 また、 これらの強震計ネットワークから震源近傍での強い揺れのデータが蓄積され、 地震動の強さや空間分布に対する知識が深まれば、 構造物の設計にも反映できる。
このような新しい強震計ネットワークの中でも、 最も高密度な横浜市と東京ガスの例を紹介しよう。 横浜市は、 市内に150観測点と3箇所のセンターからなる高密度強震計ネットワークを97年に完成させた。 強震計は市内をほぼ2km間隔でカバーし、 地震発生後3分以内に、 震度などの情報をNTTのISDN専用回線で収集し、 初動対応の判断材料とするとともに、 関係機関へ震度データを素早く伝達する。 また、 震度情報を用いて建物被害などを即座に推定するシステムの構築も進めている。 これまでにこの強震計ネットワークで得られた地震記録の解析も進められており、 小さな揺れのレベルではあるが、 地盤や地形条件などの違いにより、 近接した地域でも震度で2程度の差が生ずることが明らかになっている。 このように、 地震の揺れという自然現象に関しても、 これまでこのような高密度観測システムがなかったために知られていなかったことが、 実際のデータとして得られるようになったことは大きな進歩といえよう。
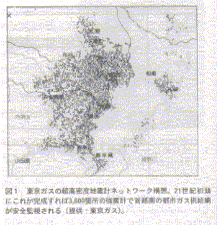 東京ガスは、 従前より地震防災対策に力を入れている企業で、 兵庫県南部地震の1年前には、 331箇所の強震計からなる観測網を構築し、 この強震計から専用無線で送られてくる地震情報と、 地理情報システム(GIS)上に整備した地盤、 埋設管、 需要家建物などの数値地図情報を用いて、 地震被害を推定するSIGNALという早期被害推定システムを完成させた[2]。 その後、 地震計や通信設備にする技術開発を進めた結果、 従来、 揺れの強さによりガス導管の自動遮断を行っていた地区ガバナ (ガスの圧力を下げる設備) においても、 揺れの強さやガス流量の遠隔監視が可能になった。 21世紀初頭にこの監視システムが全て完成すると、 なんと首都圏で約3,600箇所の地区ガバナにおける地震動がモニタリングできるようになる(図1)。
東京ガスは、 従前より地震防災対策に力を入れている企業で、 兵庫県南部地震の1年前には、 331箇所の強震計からなる観測網を構築し、 この強震計から専用無線で送られてくる地震情報と、 地理情報システム(GIS)上に整備した地盤、 埋設管、 需要家建物などの数値地図情報を用いて、 地震被害を推定するSIGNALという早期被害推定システムを完成させた[2]。 その後、 地震計や通信設備にする技術開発を進めた結果、 従来、 揺れの強さによりガス導管の自動遮断を行っていた地区ガバナ (ガスの圧力を下げる設備) においても、 揺れの強さやガス流量の遠隔監視が可能になった。 21世紀初頭にこの監視システムが全て完成すると、 なんと首都圏で約3,600箇所の地区ガバナにおける地震動がモニタリングできるようになる(図1)。
まさに断然世界一となる地震観測網である。 これは機器更新に合わせて、 経済的で機能の優れた地震計を開発したことにより可能になったことであるが、 このような防災への継続した努力は、 低成長時代にも社会的責任として必須のものといえよう。
3. 地震波を先回り ―― 早期地震検知システム
リアルタイム地震防災システムと呼ばれるものが、 最近、 我国や米国でブームとなっている[1]。 その先駆けとなったのが、 JRが既に10年程前から実際に新幹線などに配備しているユレダス(UrEDAS)と呼ばれるシステムである。 鉄道は、 地震が発生した場合、 列車を緊急停止させるなど、 最も迅速な対応を要求される。 しかし、 高速で走っている列車はすぐに停止できないことから、 大きな揺れが来る前の初期の小さな揺れを検知することと、 線路に揺れが到着する前に震源の近くで揺れを検知すること、 の2つが警報を早めるための手段として考えられる。 このようなアイデアを取り入れた世界最初の早期地震検知システムがユレダスで、 単一地点で観測されたP波(縦揺れ)初動部より、 地震のマグニチュードと震源位置を瞬時に推定し、 S波(横揺れ)が到着する前に、 信号を送って地震波を先回りし、 列車を減速・停止させようというものである。
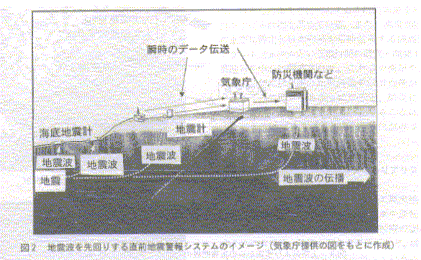 気象庁でも、 ユレダスと同様に地震波を先回りして警報を出すシステム(NOWCAST)の研究開発を最近開始した(図2)。
気象庁でも、 ユレダスと同様に地震波を先回りして警報を出すシステム(NOWCAST)の研究開発を最近開始した(図2)。
もし、 地震波の主要動が到達する前に、 警報を交通機関、 工場・危険物施設、 建設現場などに伝達することができ、 その後に安全措置を施す余裕時間があれば、 人的・物的被害の軽減が可能となろう。 しかしながら、 震源近くでは殆どP波とS波の到達時間差が稼げないこと、 および警報を早めるほどその信頼度が落ちるというジレンマもある。 全ての地震に対して有効とはいえなくとも、 21世紀初頭には、 気象庁が実際に地震直前警報を流す日が来るものと思われる。
海外でも、 同様の直前地震警報システムの開発が試みられている。 メキシコ市では、 1985年のメキシコ地震の際の建物倒壊による惨事を繰り返さないため、 約320km離れた太平洋岸で発生が予測されるマグニチュード6以上の地震に対して、 地震発生後、 同市に先回り直前警報を行うことにより、 人的被害や混乱を軽減しようとしている。 太平洋岸に沿って配備された地震計で地震発生が感知されると、 その情報はメキシコ市まで二重の無線回線で通報され、 この間の距離により、 メキシコ市では地震波到達までに約60秒間の余裕が生じる。 警報受信機は、 市内の小学校、 ラジオ放送局、 民間事業所や官庁、 大学、 公共サービス機関、 集合住宅などに置かれ、 警報が流されるとともに、 ラジオ放送を通して一般市民にも伝達される。 まだ実験段階とはいえ、 このように一般市民をも対象とした地震波到達前の警報システムの試みは、 世界でも画期的といえる。
直前の地震警報が有効な交通機関としては、 鉄道とともに高速道路も挙げられる。 しかし、 こちらの難しい点は、 鉄道は列車自動制御装置により走行中の列車に瞬時に情報伝達できるのに対し、 高速道路走行中の車両にリアルタイムに一斉通報する手段が現状ではないことである。 電光表示板を密にすることは限界があるし、 道路交通情報通信システム(VICS)も普及率が低い。 しかし、 専用の安価な受信機を作成することも考えられるし、 さらに21世紀に実用化するであろう、 自動走行レーンなど、 車と道路が情報交換するシステムにおいては、 緊急警報の一つとして地震直前警報は必須のものとなるであろう。
4. 上空・宇宙からの被害把握 ―― 宇宙防災科学のあけぼの
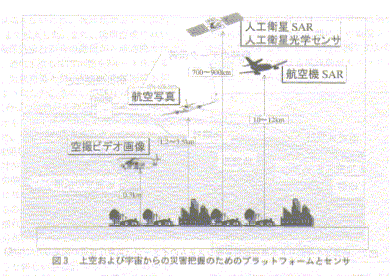 災害発生初期における被害情報の重要性は、 兵庫県南部地震において誰もが痛感したことである。 被害が広域・多岐にわたる都市直下地震においては、 被害把握に時間がかかるため、 地震動モニタリングとGIS上に準備したデータベースに基づいて早期被害推定を行うシステムの開発・導入が盛んになってきている[1]。 しかし、 この結果はあくまでも推定であって推定幅も大きく、 なるべく早期に実際の被害状況の大まかな把握を行うことが必要となる。 被害把握の方法は、 対象地域の広さ、 必要精度、 所要時間などのバランスで選択すべきである。 建物被害についていえば、 地上踏査による1棟1棟の被災度調査は、 応急危険度判定や罹災証明発行等のためにはもちろん必要である。 しかし、 もっと早く数時間から数日のオーダーで、 被害の大まかな分布と程度を把握することも、 緊急対応や応急復旧計画の立案のために極めて重要である。 その方法として、 ヘリコプター、 航空機、 飛行船、 人工衛星などのプラットフォームによって、 上空や宇宙から被災地域を画像・映像により観測することが考えられる(図3)。 また, 搭載するセンサについても, カメラや光学センサのほかに, マイクロ波を用いる合成開口レーダー(SAR)なども, 最近は利用が広がってきている。
災害発生初期における被害情報の重要性は、 兵庫県南部地震において誰もが痛感したことである。 被害が広域・多岐にわたる都市直下地震においては、 被害把握に時間がかかるため、 地震動モニタリングとGIS上に準備したデータベースに基づいて早期被害推定を行うシステムの開発・導入が盛んになってきている[1]。 しかし、 この結果はあくまでも推定であって推定幅も大きく、 なるべく早期に実際の被害状況の大まかな把握を行うことが必要となる。 被害把握の方法は、 対象地域の広さ、 必要精度、 所要時間などのバランスで選択すべきである。 建物被害についていえば、 地上踏査による1棟1棟の被災度調査は、 応急危険度判定や罹災証明発行等のためにはもちろん必要である。 しかし、 もっと早く数時間から数日のオーダーで、 被害の大まかな分布と程度を把握することも、 緊急対応や応急復旧計画の立案のために極めて重要である。 その方法として、 ヘリコプター、 航空機、 飛行船、 人工衛星などのプラットフォームによって、 上空や宇宙から被災地域を画像・映像により観測することが考えられる(図3)。 また, 搭載するセンサについても, カメラや光学センサのほかに, マイクロ波を用いる合成開口レーダー(SAR)なども, 最近は利用が広がってきている。
ここでは, 兵庫県南部地震を対象として, ヘリコプターからのハイビジョンビデオ映像, 人工衛星からの光学画像, 人工衛星からのSAR画像から, 筆者らが被害判読を行った結果について紹介する[3]。 空撮ハイビジョン映像を用いた建物被害判読は, 兵庫県南部地震発生の10日後に, NHKが高度約300mを保持して, 被災地全域をヘリコプターから撮影した膨大な映像記録の一部を用いて行った。 上空から斜め下方を撮影した映像であるため, 真上からの映像では認識が難しい, 建物の層崩壊や壁面損傷などの被害状況の把握についても有効であった。 判読結果を地上踏査結果と比較したところ, 「一部損壊」 程度の軽微な被害の判読は困難であるものの, 倒壊や火災による消失, 外観からの明らかな被害は, 映像から概ね把握可能であることが示された。
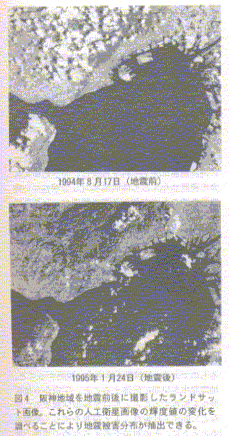 人工衛星に搭載された光学センサを用いた地震被害判読の試みとしては, 可視域の青色光から熱赤外域までの広い波長帯域で輝度情報が得られる, 地上分解能が約30mのランドサットの画像を用いた。 地表を被覆する植物, 土, 水などの反射率は波長によって異なり, 幾つかのバンドをもった光学センサで反射率を観測することにより, 地表の状況を判読することが可能である。 神戸を中心とする地域について, 地震発生前後の2時期のランドサット衛星データを用いて, 液状化と建物被害の検出を試みた(図4)。
その結果, 液状化が発生した地域や, 建物焼失・建物倒壊が多い地域は, 地震前後の人工衛星画像に輝度値の変化が見られ, これらを利用して, 液状化や建物焼失地域は精度よく, また建物被害が甚大な地域も比較的よく判別できることが分かった。
人工衛星に搭載された光学センサを用いた地震被害判読の試みとしては, 可視域の青色光から熱赤外域までの広い波長帯域で輝度情報が得られる, 地上分解能が約30mのランドサットの画像を用いた。 地表を被覆する植物, 土, 水などの反射率は波長によって異なり, 幾つかのバンドをもった光学センサで反射率を観測することにより, 地表の状況を判読することが可能である。 神戸を中心とする地域について, 地震発生前後の2時期のランドサット衛星データを用いて, 液状化と建物被害の検出を試みた(図4)。
その結果, 液状化が発生した地域や, 建物焼失・建物倒壊が多い地域は, 地震前後の人工衛星画像に輝度値の変化が見られ, これらを利用して, 液状化や建物焼失地域は精度よく, また建物被害が甚大な地域も比較的よく判別できることが分かった。
SARは, 人工衛星等から照射したマイクロ波パルスの地表での反射強度および送受信したパルスの位相差を測定するセンサである。 SARで用いるマイクロ波は, 雲などの影響や明るさの制約を受けないため、 地震や火山活動に伴う地殻変動や災害状況等の把握において、 最も期待されているセンサである。 たとえば、 人工衛星SAR画像の位相情報を用いて、 1992年ランダース地震における地殻変動が検出され、 科学雑誌ネイチャーの表紙を飾っている。 筆者らは、 兵庫県南部地震前後に阪神地域を観測したERS-1衛星のSAR強度画像を用いて、 建物被害の大きい地域の判読を試みた。 その結果、 大きな被害を受けた地域は、 無被害地域と比較すると反射波強度が小さく、 観測時には建物撤去等により空地になっていたことで、 この変化を説明することができる。
とくに短期・即時的な被害把握技術としては、 航空機に搭載したSARの利用が考えられる。 日本では、 郵政省通信総合研究所と宇宙開発事業団の共同開発による航空機搭載多機能SARがその代表的なものある。 その画像からは、 道路や建物のような小さい対象物も判読可能で、 高分解能で機動的なリモートセンシング技術として、 地震被害分布の詳細かつ早期の把握に利用が期待されている。
21世紀初頭になると、 更に解像度の高い人工衛星画像が得られるようになる。 欧米諸国が高解像度の商業衛星を次々打ち上げる予定であるし、 日本も防衛を主目的とする多目的衛星を4基打ち上げる計画を進めている。 また、 高度20kmの上空に静止し日本列島を常時監視する成層圏プラットフォームという飛行船の研究・開発も、 郵政省を中心に開始された。 これらの衛星や飛行船からの高解像度の光学画像やSAR画像がリアルタイムで得られるようになると、 防災における利用も飛躍的に拡大・高度化することになろう。 まさに、 「宇宙防災科学」 の時代が近づきつつある。
5. 災害の擬似体験 ―― バーチャルリアリティ技術
近年、 バーチャルリアリティ (人工現実感、 VR) の利用は、 フライトシミュレータや運転シミュレータ、 ロボットの遠隔操作、 医療の訓練やミクロな手術、 建築空間の意匠選択など、 様々な分野において試用や実用が広がっている。 現実の世界では体験しにくいことを仮想体験できるとか、 条件を容易に変更してパラメータ・テストをいろいろ行えるというVRの利点を考えると、 防災教育や防災訓練、 さらには災害発生時の人間行動の把握などへの利用は大いに有望と考えられる。
筆者らは、 そのようなVRの防災への応用の試みの一つとして、 数年前に避難行動の疑似体験システムを試作した[4]。 建物などからの避難行動の研究は、 これまで、 実災害事例の調査、 行動動態調査や動物実験を含む被験者実験、 コンピュータ・シミュレーションの3通りの方法が主体であったが、 いずれの方法にも適用に制約があった。 被験者実験は危険性のあるものはできないため臨場感に乏しい。 シミュレーションはモデルやパラメータへの依存度が大きく、 それらの設定のための基礎データが得にくい。 また実災害事例はそもそも数が少なく定量的データに欠けるとともに、 犠牲者の行動は詳細には分からない。 このような背景から、 被験者実験とコンピュータ・シミュレーションを組み合せた方法として、 VRの利用を思い立った。 以前に研究で行った迷路から脱出する被験者実験をVRで再現することを目指して、 コンピュータ・グラフィクス(CG)によりVR空間を作成し、 パソコン用アプリケーション・ソフトによる避難シミュレータの開発を行った。 このシミュレータを用いて被験者実験を行った結果、 VRによる体験が学習効果として実際の迷路に入った場合の避難行動を円滑にすること、 経路選択などの行動はVR上においてもほぼ同じであること、 などVRの避難行動への応用における有用性を示す結果が得られた。 この研究とほぼ期を同じくして、 VR技術の防災体験・訓練への応用が盛んとなり、 岐阜市には 「バーチャル大地震体験館」 なる施設も開業し、 一般の人もある程度の災害疑似体験ができるようになった。
 筆者らは最近、 地震発生時の高速道路走行中の運転者への地震動の影響に関する研究を開始した[5]。 これは、 高速道路の地震発生時の通行規制値を見直す上で、 このことが必要な検討事項と考えられたからである。 高速道路走行中の運転者の挙動については、 渋滞の原因究明や対策、 道路線形・景観の心理面への影響などの観点から、 実車やコンピュータ・シミュレーションそれに運転シミュレータを用いた研究が行われている。 ここで、 地震の揺れによる走行性への影響など、 通常の評価や試験が困難な事象については、 運転シミュレータの利用が有効と考えられる。 しかし、 本格的な運転シミュレータは、 我が国で数台あるのみで、 さらに地震動を加えるとなると技術的な開発も必要となる。 そこで、 第一ステップとして、 運転ゲーム機を振動台で加振することにより、 模擬的に地震動の走行安定性への影響を調べた (図5)。
筆者らは最近、 地震発生時の高速道路走行中の運転者への地震動の影響に関する研究を開始した[5]。 これは、 高速道路の地震発生時の通行規制値を見直す上で、 このことが必要な検討事項と考えられたからである。 高速道路走行中の運転者の挙動については、 渋滞の原因究明や対策、 道路線形・景観の心理面への影響などの観点から、 実車やコンピュータ・シミュレーションそれに運転シミュレータを用いた研究が行われている。 ここで、 地震の揺れによる走行性への影響など、 通常の評価や試験が困難な事象については、 運転シミュレータの利用が有効と考えられる。 しかし、 本格的な運転シミュレータは、 我が国で数台あるのみで、 さらに地震動を加えるとなると技術的な開発も必要となる。 そこで、 第一ステップとして、 運転ゲーム機を振動台で加振することにより、 模擬的に地震動の走行安定性への影響を調べた (図5)。
現実感に問題は残るものの、 この実験の結果、 運転者は震度5強程度の揺れの強さになると、 ハンドル操作に支障が出ることが分かった。 また、 ごく最近、 筆者の研究所に本格的な運転シミュレータが導入されたため、 今後は、 これを用いてより現実感を高めた地震時の走行安定性に関する研究を行い、 高度道路交通システム(ITS)の開発において必要となる情報を提供したいと考えている。
バーチャルリアリティ技術は、 このほかにも様々な地震防災分野での利用が考えられる。 災害発生時の緊急対応を模擬した図上訓練システムなどもその一つであろうし、 21世紀に向けて、 今後ますますの技術的発展と実際的な利用拡大が期待される。
6. おわりに ―― 地震防災技術の未来
地震防災に関する科学技術は、 20世紀中に大きく発展した。 とくに地震に対して壊れない建造物を造るというハード面の技術は、 かなり成熟したといってもいいであろう。 しかし、 災害は単なる自然現象ではなく、 自然現象が人間社会に作用して発生するものである。 社会の変化は、 21世紀に入っても、 我々の想像を超えて進むであろう。 したがって、 災害の形態や様相についても、 これまで我々の想定してこなかったものが生ずる可能性も大きい。 そのような場合には、 防災技術の中でも、 ソフトな対応技術の果たす役割が一層期待される。
本文で紹介した先端技術は、 20世紀後半に生まれ、 21世紀になってますます発展が期待されるものである。 地震動を高密度に観測すること、 地震発生を早期に伝達すること、 宇宙から被害発生を監視すること、 災害を疑似体験することなどに関する技術は、 まず現象を正しく把握するとともに、 その対策を考えるための想像力を養う上で、 大きな役割が期待される。 成熟社会の中で、 災害リスクのみが成長することのないよう、 我々は今後とも、 研究開発とその成果の活用を考えていく必要があろう。
―― 参考文献 ――
[1] 山崎文雄:リアルタイム地震防災システムの現状と展望, 土木学会論文集, 577/I-41, 1997.
[2] 山崎文雄, 片山恒雄, 野田茂, 吉川洋一, 大谷泰昭:大規模都市ガス導管網の地震時警報システムの開発, 土木学会論文集, 525/I-33, 1995.
[3] 山崎文雄, 松岡昌志、 小川直樹、 長谷川弘忠、 青木久:上空および人工衛星からのリモートセンジング被害把握技術, 第10回日本地震工学シンポジウム パネルディスカッション資料集, 1998.
[4] 目黒公郎、 芳賀保則、 山崎文雄、 片山恒雄:バーチャルリアリティの避難行動シミュレータへの応用, 土木学会論文集、 507/I-30, 1997.
[5] 山之内宏安、 山崎文雄:運転シミュレータを用いた地震時の走行安定性に関する検討、 第25回地震工学研究発表会講演論文集、 土木学会地震工学委員会、 1999.
■山崎 文雄 (やまざき・ふみお)
1953年石川県生まれ。 1976年東京大学土木工学科卒業、 1978年東京大学大学院工学系研究科修士課程終了。 工学博士、 一級土木施工管理技師、 一級建築士。 現在、 東京大学生産技術研究所助教授、 理化学研究所地震防災フロンティア研究センターチームリーダー (兼任)。 専攻:地震工学、 都市防災。
情報誌「岐阜を考える」1999年記念号
岐阜県産業経済研究センター
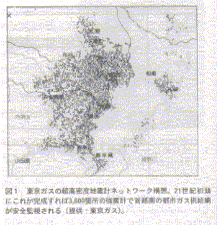 東京ガスは、 従前より地震防災対策に力を入れている企業で、 兵庫県南部地震の1年前には、 331箇所の強震計からなる観測網を構築し、 この強震計から専用無線で送られてくる地震情報と、 地理情報システム(GIS)上に整備した地盤、 埋設管、 需要家建物などの数値地図情報を用いて、 地震被害を推定するSIGNALという早期被害推定システムを完成させた[2]。 その後、 地震計や通信設備にする技術開発を進めた結果、 従来、 揺れの強さによりガス導管の自動遮断を行っていた地区ガバナ (ガスの圧力を下げる設備) においても、 揺れの強さやガス流量の遠隔監視が可能になった。 21世紀初頭にこの監視システムが全て完成すると、 なんと首都圏で約3,600箇所の地区ガバナにおける地震動がモニタリングできるようになる(図1)。
東京ガスは、 従前より地震防災対策に力を入れている企業で、 兵庫県南部地震の1年前には、 331箇所の強震計からなる観測網を構築し、 この強震計から専用無線で送られてくる地震情報と、 地理情報システム(GIS)上に整備した地盤、 埋設管、 需要家建物などの数値地図情報を用いて、 地震被害を推定するSIGNALという早期被害推定システムを完成させた[2]。 その後、 地震計や通信設備にする技術開発を進めた結果、 従来、 揺れの強さによりガス導管の自動遮断を行っていた地区ガバナ (ガスの圧力を下げる設備) においても、 揺れの強さやガス流量の遠隔監視が可能になった。 21世紀初頭にこの監視システムが全て完成すると、 なんと首都圏で約3,600箇所の地区ガバナにおける地震動がモニタリングできるようになる(図1)。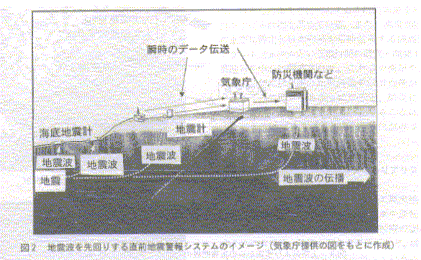 気象庁でも、 ユレダスと同様に地震波を先回りして警報を出すシステム(NOWCAST)の研究開発を最近開始した(図2)。
気象庁でも、 ユレダスと同様に地震波を先回りして警報を出すシステム(NOWCAST)の研究開発を最近開始した(図2)。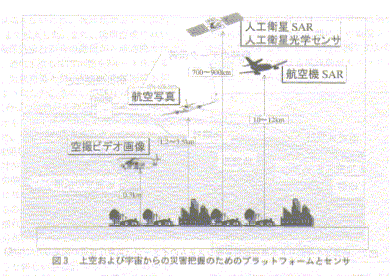 災害発生初期における被害情報の重要性は、 兵庫県南部地震において誰もが痛感したことである。 被害が広域・多岐にわたる都市直下地震においては、 被害把握に時間がかかるため、 地震動モニタリングとGIS上に準備したデータベースに基づいて早期被害推定を行うシステムの開発・導入が盛んになってきている[1]。 しかし、 この結果はあくまでも推定であって推定幅も大きく、 なるべく早期に実際の被害状況の大まかな把握を行うことが必要となる。 被害把握の方法は、 対象地域の広さ、 必要精度、 所要時間などのバランスで選択すべきである。 建物被害についていえば、 地上踏査による1棟1棟の被災度調査は、 応急危険度判定や罹災証明発行等のためにはもちろん必要である。 しかし、 もっと早く数時間から数日のオーダーで、 被害の大まかな分布と程度を把握することも、 緊急対応や応急復旧計画の立案のために極めて重要である。 その方法として、 ヘリコプター、 航空機、 飛行船、 人工衛星などのプラットフォームによって、 上空や宇宙から被災地域を画像・映像により観測することが考えられる(図3)。 また, 搭載するセンサについても, カメラや光学センサのほかに, マイクロ波を用いる合成開口レーダー(SAR)なども, 最近は利用が広がってきている。
災害発生初期における被害情報の重要性は、 兵庫県南部地震において誰もが痛感したことである。 被害が広域・多岐にわたる都市直下地震においては、 被害把握に時間がかかるため、 地震動モニタリングとGIS上に準備したデータベースに基づいて早期被害推定を行うシステムの開発・導入が盛んになってきている[1]。 しかし、 この結果はあくまでも推定であって推定幅も大きく、 なるべく早期に実際の被害状況の大まかな把握を行うことが必要となる。 被害把握の方法は、 対象地域の広さ、 必要精度、 所要時間などのバランスで選択すべきである。 建物被害についていえば、 地上踏査による1棟1棟の被災度調査は、 応急危険度判定や罹災証明発行等のためにはもちろん必要である。 しかし、 もっと早く数時間から数日のオーダーで、 被害の大まかな分布と程度を把握することも、 緊急対応や応急復旧計画の立案のために極めて重要である。 その方法として、 ヘリコプター、 航空機、 飛行船、 人工衛星などのプラットフォームによって、 上空や宇宙から被災地域を画像・映像により観測することが考えられる(図3)。 また, 搭載するセンサについても, カメラや光学センサのほかに, マイクロ波を用いる合成開口レーダー(SAR)なども, 最近は利用が広がってきている。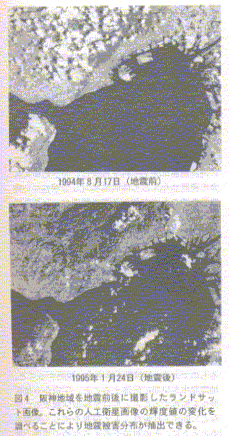 人工衛星に搭載された光学センサを用いた地震被害判読の試みとしては, 可視域の青色光から熱赤外域までの広い波長帯域で輝度情報が得られる, 地上分解能が約30mのランドサットの画像を用いた。 地表を被覆する植物, 土, 水などの反射率は波長によって異なり, 幾つかのバンドをもった光学センサで反射率を観測することにより, 地表の状況を判読することが可能である。 神戸を中心とする地域について, 地震発生前後の2時期のランドサット衛星データを用いて, 液状化と建物被害の検出を試みた(図4)。
その結果, 液状化が発生した地域や, 建物焼失・建物倒壊が多い地域は, 地震前後の人工衛星画像に輝度値の変化が見られ, これらを利用して, 液状化や建物焼失地域は精度よく, また建物被害が甚大な地域も比較的よく判別できることが分かった。
人工衛星に搭載された光学センサを用いた地震被害判読の試みとしては, 可視域の青色光から熱赤外域までの広い波長帯域で輝度情報が得られる, 地上分解能が約30mのランドサットの画像を用いた。 地表を被覆する植物, 土, 水などの反射率は波長によって異なり, 幾つかのバンドをもった光学センサで反射率を観測することにより, 地表の状況を判読することが可能である。 神戸を中心とする地域について, 地震発生前後の2時期のランドサット衛星データを用いて, 液状化と建物被害の検出を試みた(図4)。
その結果, 液状化が発生した地域や, 建物焼失・建物倒壊が多い地域は, 地震前後の人工衛星画像に輝度値の変化が見られ, これらを利用して, 液状化や建物焼失地域は精度よく, また建物被害が甚大な地域も比較的よく判別できることが分かった。  筆者らは最近、 地震発生時の高速道路走行中の運転者への地震動の影響に関する研究を開始した[5]。 これは、 高速道路の地震発生時の通行規制値を見直す上で、 このことが必要な検討事項と考えられたからである。 高速道路走行中の運転者の挙動については、 渋滞の原因究明や対策、 道路線形・景観の心理面への影響などの観点から、 実車やコンピュータ・シミュレーションそれに運転シミュレータを用いた研究が行われている。 ここで、 地震の揺れによる走行性への影響など、 通常の評価や試験が困難な事象については、 運転シミュレータの利用が有効と考えられる。 しかし、 本格的な運転シミュレータは、 我が国で数台あるのみで、 さらに地震動を加えるとなると技術的な開発も必要となる。 そこで、 第一ステップとして、 運転ゲーム機を振動台で加振することにより、 模擬的に地震動の走行安定性への影響を調べた (図5)。
筆者らは最近、 地震発生時の高速道路走行中の運転者への地震動の影響に関する研究を開始した[5]。 これは、 高速道路の地震発生時の通行規制値を見直す上で、 このことが必要な検討事項と考えられたからである。 高速道路走行中の運転者の挙動については、 渋滞の原因究明や対策、 道路線形・景観の心理面への影響などの観点から、 実車やコンピュータ・シミュレーションそれに運転シミュレータを用いた研究が行われている。 ここで、 地震の揺れによる走行性への影響など、 通常の評価や試験が困難な事象については、 運転シミュレータの利用が有効と考えられる。 しかし、 本格的な運転シミュレータは、 我が国で数台あるのみで、 さらに地震動を加えるとなると技術的な開発も必要となる。 そこで、 第一ステップとして、 運転ゲーム機を振動台で加振することにより、 模擬的に地震動の走行安定性への影響を調べた (図5)。