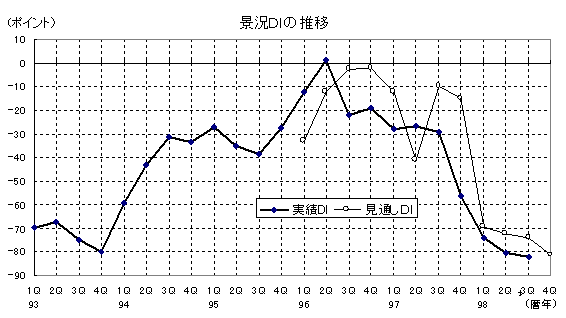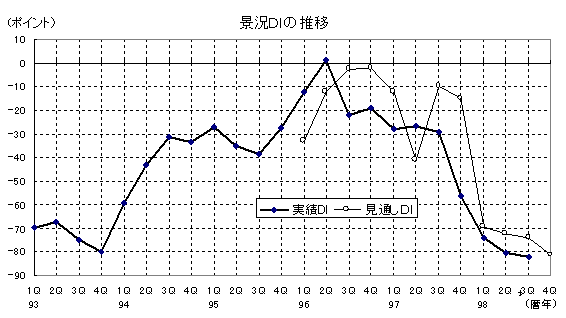岐阜県の景況調査
98年7〜9月期実績、 98年10〜12月期見通し
概況:バブル崩壊後最悪
景況悪化のなか明暗分ける製造業、底打ち期待に反し悪化続く非製造業
- 前回6月時点の調査では、7-9月期の岐阜県景況は改善するとの見通しであったが、7-9月期の景況DI実績はマイナス82.1と前期に続き悪化、バブル崩壊後の最低水準を更新した。予想を上回る悪化は、製造業に加え、7-9月期には最悪期を脱すると見込んだ非製造業の急激な悪化によるものである。
- 景況が悪化するなか、輸出向け売上高は逆に予想以上の堅調さを保っている。これを受ける形で製造業のなかで景況[好転]とみる企業が現れてきており、製造業において[良い企業]と[悪い企業]との差が鮮明となってきている。
- 在庫調整のテンポが7-9月期予想以上に鈍化。先行きについてもこの状況が続くとみているため、在庫調整に時間がかかりそうである。
- 資金繰り・借入の状況をみると、7-9月期において一時的に改善した模様であるが、先行きについては再び厳しい目で見ている。
- 雇用環境をみると、製造業で[過剰]と考える企業が4割を超え、非製造業でも急激に雇用過剰感が高まってきている。
|
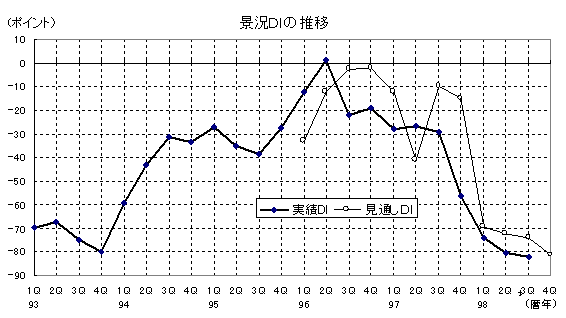
平成10年10月7日
(財)岐阜県産業経済研究センター
第3回岐阜県景況調査説明会議事録(未定稿)
| 1 | 日時 | 平成10年9月25日(金) 13:30〜15:30 |
| 2 | 場所 | 岐阜県県民ふれあい会館 大会議室(岐阜市藪田南5―14―53) |
| 3 | テーマ | 「世界と日本、岐阜県の役割」 |
| 4 | 出席者 |
| [企業経営者等 50音順] |
| 岡本太右衛門 氏 | ((株)ナベヤ会長) |
| 桜井 美国 氏 | ((株)桜井グラフィックシステムズ社長) |
| 佐藤 弘 氏 | ((株)名紳社長) |
| 原 耕平 氏 | ((株)大和総研理事) |
| 三井 栄 氏 | (岐阜大学地域科学部講師) |
| [調査結果報告・司会] |
| 高津 定弘 | ((財)岐阜県産業経済研究センター副理事長) |
| 5 | 議事内容(要約) |
高津
- 7〜9月期の産研センターの岐阜県景況調査による景況DI(全業種)は▲82.1となり、バブル崩壊後最悪。
- 業種別にみると、製造業は、輸出関連企業を中心に予想以上の堅調さをみせ、「良い企業」と「悪い企業」の二極分化が進んでいる。特にヨーロッパ・アメリカ向けの機械3業種(一般・輸送・電気機械)の好調さが反映しているとみられる。一方、非製造業は、前期の底打ち期待に反し悪化。
- 受注は、10〜12月期予想では「増加」見込企業の割合が初めて1割を切った。
- 消費者物価指数、卸売物価指数、日経商品指数の前年比がマイナスとなり、製品販売価格、原材料仕入価格がマイナス基調であるにも関わらず、在庫調整は進展していない。
- 日本開発銀行の調査によれば、設備投資は全国ベースではマイナス基調にあるが、東海地域は堅調。岐阜県は、中枢的研究機能、大企業の本社がないのを主因に低迷。
- 製造業の4割以上、非製造業の3割近くが雇用過剰感を感じていることから、もう一段の雇用調整が現実化する可能性がある。
- 個別企業ヒアリングでは、製造業においては情報機器を活用し、デイリーに市場の需給変化に対応しているという印象を受けた。そうした生産体制がとれない企業は今後伸びないだろう。
- 県民所得統計から岐阜県の労働需要と産業構造をみると、製造業の就業者比率が全国平均を大きく上回ること、農林水産業の就業者比率が非常に小さく、第2次石油危機前後において水準低下が著しいこと、サービス経済化のテンポが全国に比べて遅く、構成率からみて全国との乖離幅が拡大していることがあげられる。
- 岐阜県は自営業主、家族従業者の比率が全国ベースに比べて高く、その傾向は製造業において顕著。非製造業における卸小売業においては、零細、小規模店が多く存在し、情報・流通革命など大きな変化が進展している業種として、今後大きな問題になるかもしれない。
- 産業別の生産性をみると、製造業の伸びが高い一方で、卸小売業の生産性の低下が著しい。これは、郊外型の大規模店の出店による雇用増の裏で、自営・家族業者の淘汰が全国並みに進んでいないのが原因と推測される。
- 全国においては、90年代以降95,6年にかけて製造業がリストラを進め、それを建設、サービス、卸小売業が支えていたという構図がある。これまで岐阜県も同じような傾向にあったが、97年以降は卸小売飲食の部門で猛烈なリストラが進み、製造業・建設業においても雇用調整が始まっている。産研センターの試算によると、岐阜県の今年1〜7月までの失業者増は5〜6,000人、完全失業率は3.2%とみられ、深刻な問題と考えている。
岡本
- 製造業の売上高に関して、輸出関連企業の約2割が今期・来期とも「増加」するとの調査結果であるが、実感が湧かない。自己商品を開発して海外に輸出できるのが理想だが、県内企業の現状をみると、地場産業、とりわけ零細企業が多く経営的には非常に厳しい。
- 岐阜県の企業が生き残るには、オリジナリティーあふれる商品を開発することが必要。そのためには、大企業や公的部門で開発された新技術を中小企業が利用できるような仕組みをつくることが重要。
- 公的機関における専門職の人事ローテーションを見直し、研究開発に継続性を持たせることが必要。
- 産研センターは、大学の研究者やハイレベルな技術者と実業界とを結ぶ産官学のコーディネーターとして活躍してもらいたい。
- サービス産業が全国的にみて劣っている顕著な例は鵜飼である。岐阜県の場合、他地域と比較して観光産業の面では改善の余地があるとみられるので、是非行政にご尽力いただきたい。
桜井
産業の発展には、それを支えるバックグラウンド(インフラ、流通、周辺技術等)の整備が重要である。岐阜県は東京、中部、関西の経済圏に近いという恵まれた地域であり、今後、発展の可能性は大いにある。
企業が発展するには情報収集が不可欠であり、岐阜にいても世界各地の情報が的確に入手できる仕組みづくりを岐阜県にはお願いしたい。
アメリカにおける住宅ローン金利の所得控除制度や、イギリスのサッチャー政権下で行われた選択償却制などに代表されるような大胆な改革により景気は回復すると考える。
佐藤
流通産業はオーバーストア状態であり、完全にデフレスパイラルに入っていると認識している。
首都機能移転の対象地として東濃は素晴らしい地域だとは思うが、岐阜とのアクセスが悪いという印象を持っている。道路行政に尽力していただきたい。
政治家が強力なリーダーシップを発揮し、マスコミが報道姿勢を改善することにによって消費マインドを盛り上げて欲しい。
原
戦後の日本経済において雇用調整が行われたのは、オイルショック時と現在である。前者が供給不足の中で物価が高騰したのに対し、後者は製品輸入が6割に達するなかでの供給過多という全く対照的な環境のなかで起こったことに特徴がある。
大和総研では、今年度の実質経済成長率をマイナス1.8%、来年度もマイナス成長とみており、設備投資は今後1年は回復せず、相当な雇用調整があるとみている。その結果、個人消費がかなりのダメージを受けるだろう。
岐阜県の景気回復には、従来型の公共投資という手法ではなく、投資減税、住宅ローン減税が有効である。
大学での研究を充実させ、積極的に産業界へ技術移転を行うべきだ。
世界経済の状況をみると、各国経済も悪化しつつあり、もはや日本経済は輸出には頼れない。内需拡大のためには、需要を喚起し雇用環境を改善することが重要。そのカギは設備投資と住宅投資にあり、併せて社会保険負担の低減や失業保険の見直しをすべきである。
三井
岐阜県の景気は全国に遅行した動きになっている。その原因は産業構造の違いにある。具体的には製造業の割合が高いのに比べ、経済のサービス化が遅れていること、都市部に比べ情報収集の点で劣ること、零細、家族経営的な企業が多いことの3点である。経営形態の改革が岐阜県の課題である。
過剰雇用の問題を論ずる際に重要な指標は、完全失業率よりも有効求人倍率であると考える。過剰雇用の解消のためには、社会福祉分野、法曹界、徴税部門、金融監督庁、情報通信部門に注目すべきであり、岐阜県においてはとりわけ介護、情報通信の分野における産業発展を目指すべきだと考える。
地方分権の推進に伴い、各自治体には責任ある行政が求められる。公共投資も短期的なものでなく長期的視野に立った産業全体のレベルアップ、雇用の拡大につながるようなものを行って欲しい。
日本の消費者教育は国際的にみて非常に遅れている。消費者教育の充実を岐阜県に対し要望したい。