日本経済は現在、戦後最悪とまで言われる経済成長率の低下、雇用環境の悪化をはじめとする閉塞した状況にある。また、この対応策として今日まで数次にわたる財政・金融政策による経済対策が講じられてきたが、その顕著な効果は過去の経験に照らして非常に弱いものとなっている。このような状況の下、日本経済には従来型の需要面への刺激策ではなく、供給構造を含めた経済構造の抜本的な改革が必要であるという指摘がなされるに至っている。
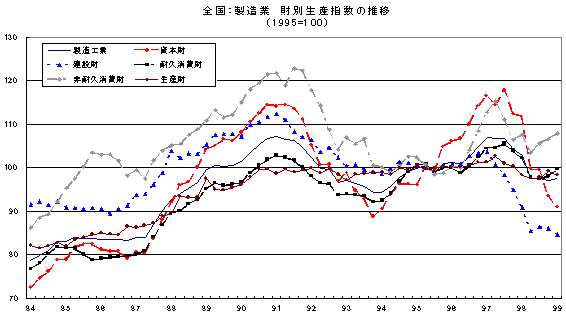
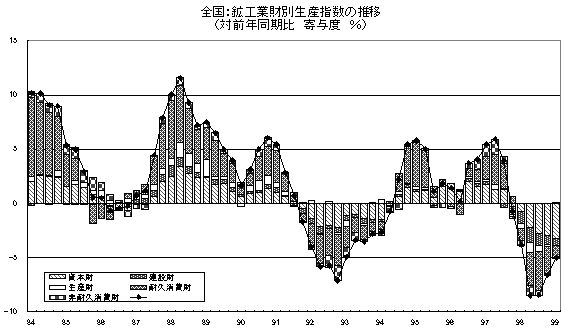
製造業の生産をみると、91年年初にバブル景気のピークを打った後、93年秋口まで下落を続けた。その後政府の景気回復宣言にもかかわらず生産は伸び悩み、回復は95年の円安転換まで待たねばならなかった。その回復も97年以降の消費税率引上げ、金融機関の経営破綻に代表される不良債権問題、さらにアジアの通貨・金融不安などにより急激な下降基調に転じた。、98年末ごろから底打ちの様相を呈してきてはいるが、その動きには未だ力強さは感じられない。
このような生産の動きの裏で93年以降製造業の雇用調整が行われ、97年前半に雇用の回復がみられたものの再度調整に転じ、その規模も戦後最悪の状態にあり、深刻さを物語っている。
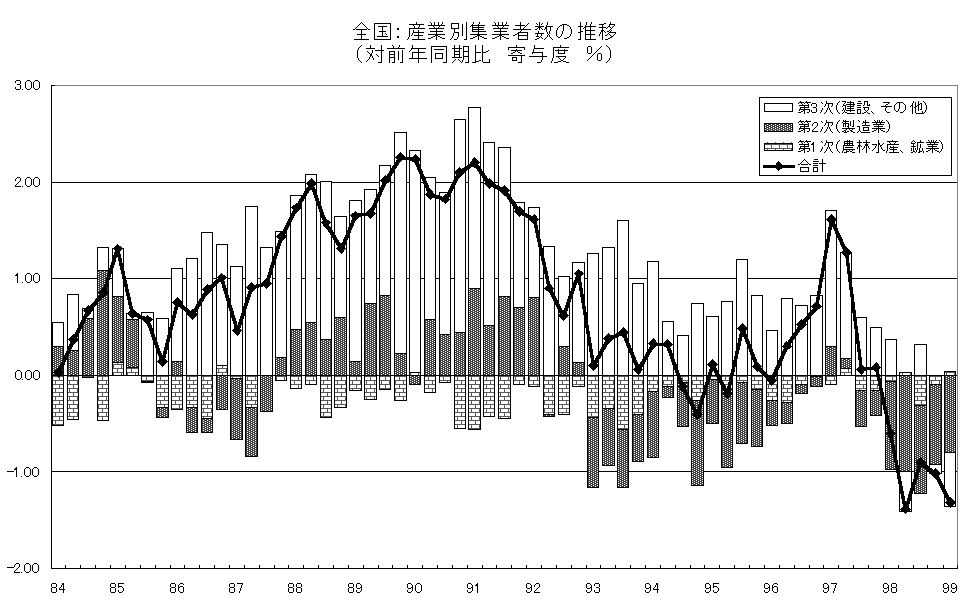
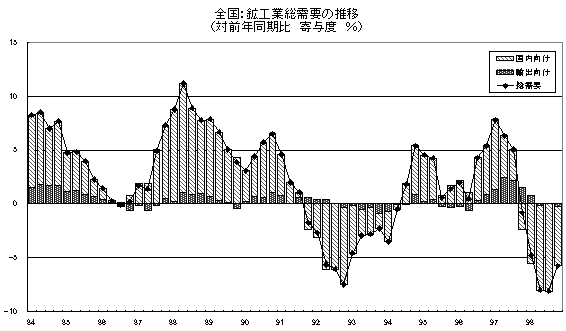
97年以降の下降局面において、財別に見た場合、年央に建設財、年末には資本財、非耐久消費財が下落に転じている。98年に入ると資本財、耐久消費財の減少幅は大きく拡大した。98年末から99年当初にかけ消費財、生産財などが回復基調を示していることに比して、資本財は依然として減少傾向の拡大が続いており、改善の兆候がみられない際立ったものとなっている。このことは、ここ最近における設備投資をはじめとした企業の生産拡大が図られていないことを示しており、経済活動全般が構造調整という名の下、縮小傾向に向かいつつあるというデフレ的色彩の強い今回の不況の深刻さを示すものである。
(a) 需要
この生産動向に対し需要の動きをみると、96年年央から97年夏場における回復期には外需、つまり輸出の寄与度が相対的に高まっていたということが分かる。また、98年末下降局面でも輸出は比較的堅調に推移し、反面内需の落ち込みが深刻なものとなっている。
さらに、需要構造を財別にみた場合、国内向け出荷は97年年央以降、資本財及び生産財の低迷が、需要低迷の大きな要因となっている。他方、輸出向け出荷は96年以降の回復期には、それまで停滞あるいは減少傾向を示していた資本財及び耐久消費財が大きな伸びを示し、また、98年以降、資本財が若干減少する中で耐久消費財は前年と同程度の水準で推移している。
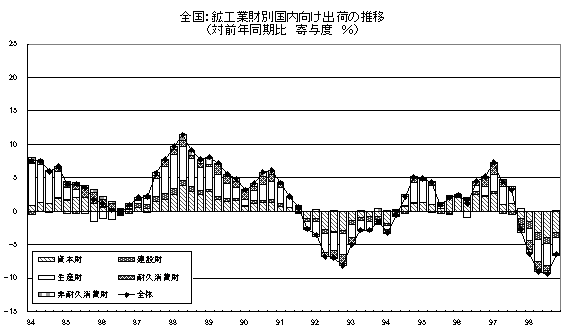
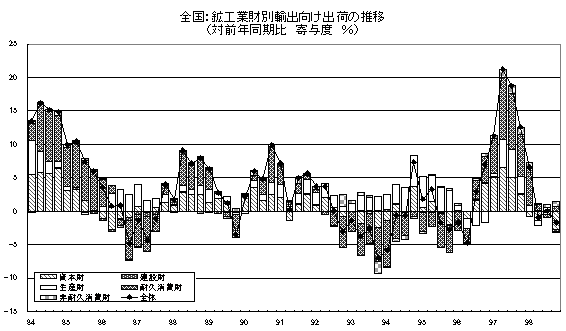
(b) 供給
次に供給面からみると、92年から96年前半にかけて、輸入の伸びが目立っていることが分かる。特に92年から94年前半にかけ国内生産が大幅な下落を続けるなかでも輸入は堅調に推移しており、これはこの時期を契機に国内の企業や消費者の需要に対して国産品ではなく、輸入品によって賄われる割合が相対的に高くなったことを意味している。
さらにこれを財別に見た場合、まず非耐久消費財、そして資本財、建設財、耐久消費財とその伸びを高め、94年に入ると製造業の生産工程における中間投入分である生産財が大幅な増加を示した。また、97年以降の下降局面では全般的な内需の低迷を背景に、消費財がまず先行して落ち込み、98年に入ってから生産財及び資本財についても減少傾向を示している。
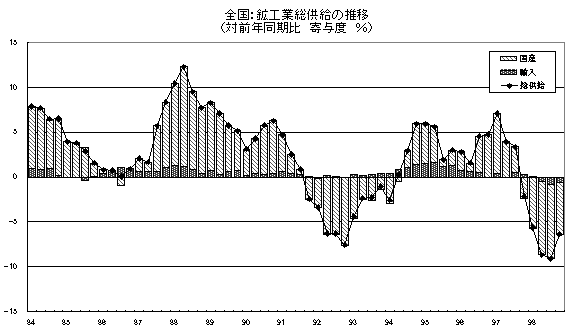
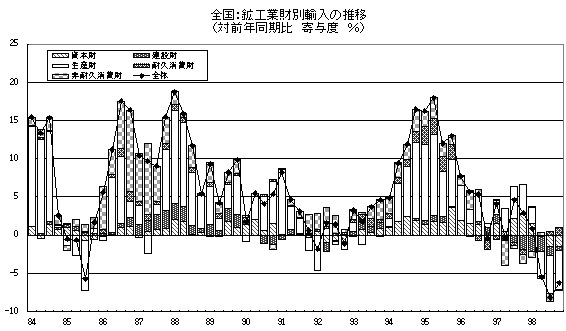
(c) 輸出入比率
これらを踏まえ、この需給構造の変化を輸出入比率の対比とからみると、全般的には輸出比率、すなわち需要構造ではこれまで12〜14%の範囲で推移していたが、98年に入って内需の低迷に伴う輸出シフトによりその水準を超え、内需の低迷がより深刻であることを示している。
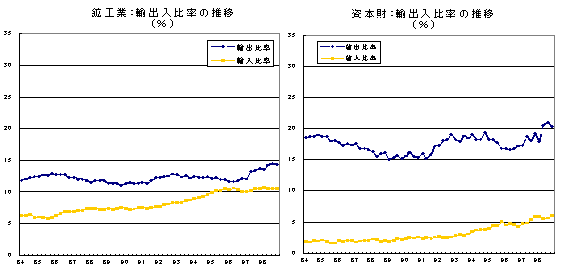

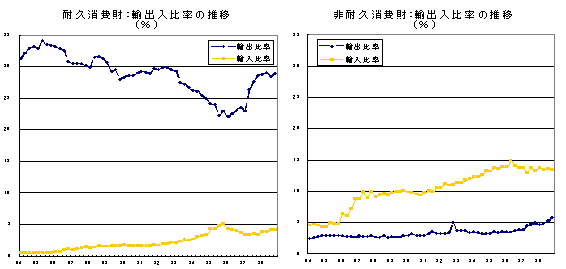
これに対し輸入比率は80年代後半、いわゆるプラザ合意による円高で上昇に転じ、92年から95年まで急激な増加傾向を示した。96年以降その勢いはなくなったものの、10%以上の水準で推移している。
これを財別にみると、資本財及び耐久消費財は輸出比率がともに20〜30%と高い水準にあり相対的に輸出依存型の構造を有しているが、他方で輸入比率も現状5%前後の低位ながら耐久消費財は85年以降、資本財は92年以降、上昇傾向を示している。また、建設財及び非耐久消費財は輸出比率が低く内需型であるが、85年以降輸入比率が輸出比率を急激に上回っており、さらに92年以降その水準を一段と高めてきている。また、生産財は輸入比率が一貫して上回っているが、その増加傾向に相応して輸出比率も上昇してきている。
これらのことから、財別にみた日本経済の需給構造の変化として、需要面では資本財及び耐久消費財の輸出が堅調に推移していることがある。しかし他方でいずれの財も供給面では輸入圧力の上昇がみられ、このことは非耐久消費財及び生産財でとくに顕著である。したがって、消費財は国内市場における国産品と輸入品との競合を招いているということ、また、生産財は企業行動のボーダレス化による国際的な分業体制が進展していることが分かる。
(2) 業種別に見た需給構造の変化 ↑top
次に、この需給構造の変化を製造業における業種別にみることとする。まず、製造業の業種別生産動向をみた場合、機械産業等の加工組立型については93年以降、最も顕著な上昇傾向を示している反面、97年終盤以降の落ち込み傾向も急激なものとなっており、さらにこの傾向は99年に入っても続いている。また、基礎素材型も93年以降、加工組立型ほどではないものの上昇傾向を示しているが、下降局面に達したのは加工組立型よりも早く96年末から97年当初にかけてである。しかし、基礎素材型産業は99年に入ってほぼ前年並みの水準まで回復を示している。さらに、他の雑貨型及び地方資源型については93年以降、目立った上昇傾向を示しておらず、とくに地方資源型において90年代に入って一貫した停滞傾向を示した後、96年当初を境にさらに急激な下降局面に入っており、今日まで回復の兆候は見られない。
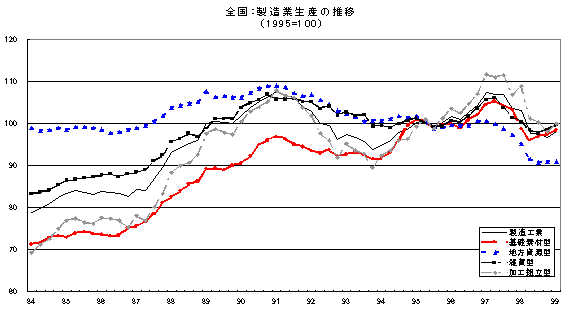
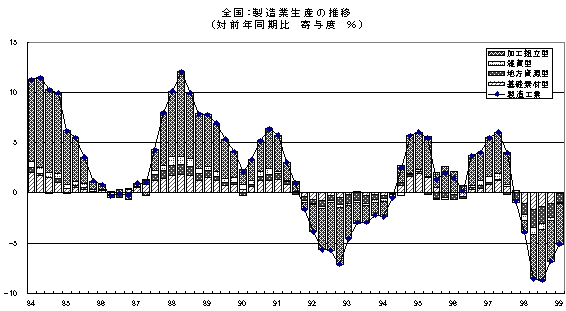
(a) 需要
次に、これらの業種別の推移を需要面からみると、国内向け出荷では最も大きなウエイトを占める加工組立型の業種の寄与度が高い。さらに、この業種は輸出向け出荷でもその増加要因の大半を占めており、他と比較して日本の産業構造が加工組立型にシフトし、対外的にもそれを主軸に動いていることが分かる。これに対し、他の基礎素材型や地域資源型等の素材型の業種については、国内向け出荷への寄与度に比較して輸出向け出荷に対する寄与度が低く、相対的に内需依存型であり、国内の景気動向に大きく左右されながら推移している。
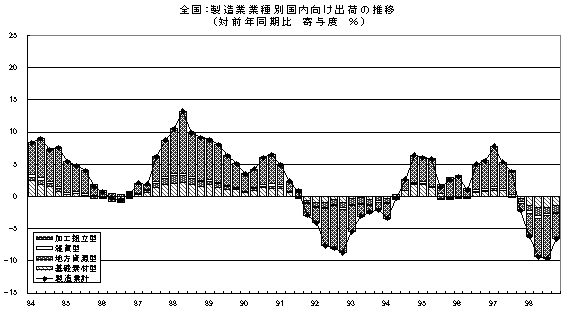
さらにこのことは輸出比率にも現れており、まず加工組立型については内需の動きにも左右されながら、若干の増減はあるものの15〜20%程度の高い水準で推移していることからも分かる。他方、これに対し、素材型は相対的に輸出比率が低く、地方資源型については5%程度、雑貨型については3%程度の低い水準で推移している。これらの業種の輸出比率については若干の増減はあるものの、期間を通じてほぼ一定の水準で収まっており典型的な内需型といえる。基礎素材型については水準的には内需型といえるが、92年以降徐々にその輸出比率を引き上げ、98年以降は10%を超え、過去の水準から切り上がってきている。
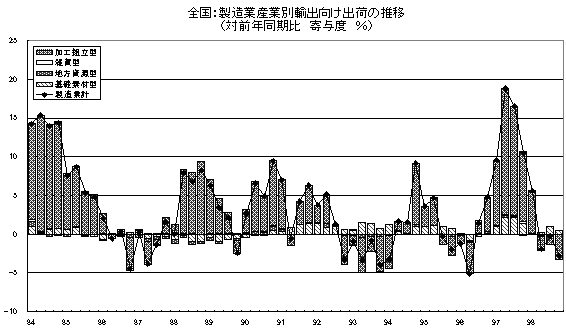
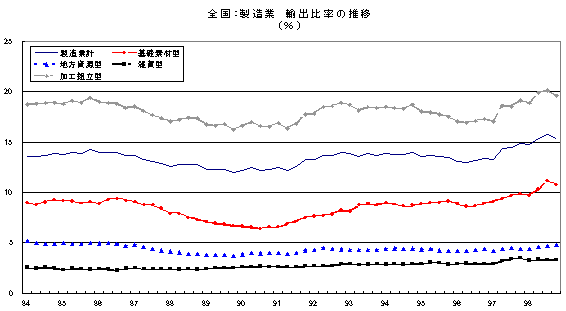
(b) 供給
しかし供給面からみると、その構造は80年代後半以降、大きく変化していることがいえる。86年以降、90年までは輸入増の主な要因は基礎素材型であり、続いて地方資源型、加工組立型であった。これは85年以降の円高を契機として供給構造が急激に変化したことを示している。しかし、92年以降は輸入に対する大きな寄与を示しているのが加工組立型、続いて地方資源型、基礎素材型となり、93年半ばから96年当初にかけ顕著な増加傾向を示している。これをみると、80年代後半の円高により原材料安や内外価格差により輸入が増加に転じた一方、92年以降の輸入増の背景には、海外での生産基盤の整備による輸入代替が急速に進展したことがあると考えられる。その意味でも内需型である地方資源型及び雑貨型の産業の輸入比率が80年代後半以降、ほぼ一貫して増加傾向にあり、国内市場での輸入品との競合が止まることなく進展しているということが分かる。
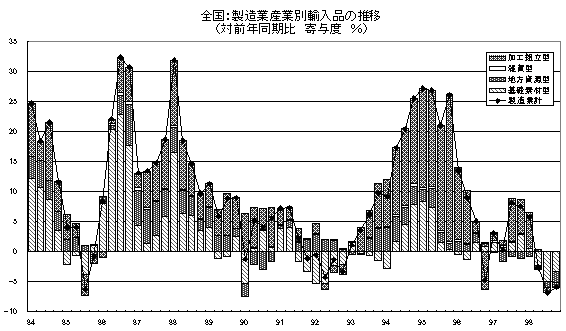
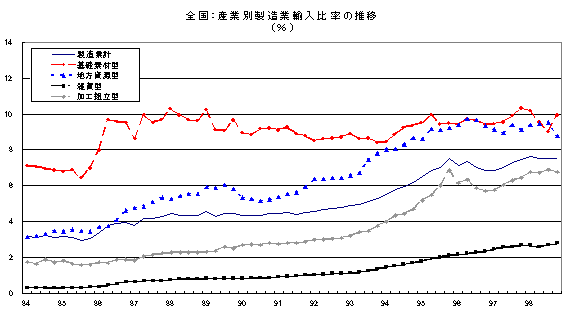
次にこの動きを業種別の輸入比率からみると、まず最も高い水準で推移しているのは基礎素材型産業であり、これは日本が資源少国であることからも理解できる。当該業種は先述したとおり85年の円高以降、急激に上昇した後、約10%前後の一定した水準で推移しており、この時点を機に供給構造が固定化している。その一方で、他の3業種はいずれも90年代に入って以降も輸入比率が上昇傾向を示している。まず、地方資源型は一貫して増加傾向にあるが、特にそれが顕著となったのは85年からと92年からの二つの時期であり、その結果、内需型とされる地方資源型の輸入比率は95年以降約10%程度となり、輸入依存度が高い基礎素材型に並ぶものとなっている。同様に内需依存の雑貨型も水準自体は依然2〜3%程度と低位ながら、一貫した上昇傾向を示している。また、対外的にも供給産業として存在する加工組立型も92年頃から輸入比率が急激な上昇傾向を示し、結果として80年代前半の2%程度から90年代後半には約7%と供給構造、供給体制の変化が進んでいることを示している。
(c) 各業種の輸出入比率と需給構造
これらを踏まえ、需給構造の変化を各業種における輸出入の寄与度でみてみることとする。
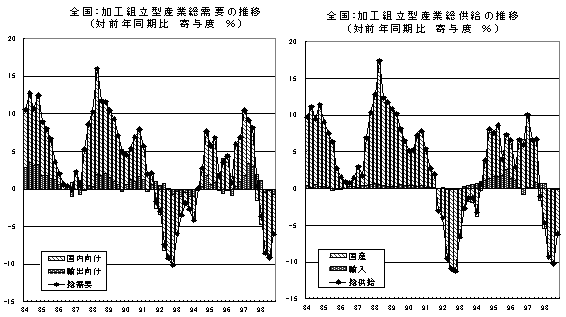

まず加工組立型は需要の回復にいずれも輸出が大きな役割を示していることに対し、供給面での輸入の役割はとくに92年半ばを契機に大きくなっている。したがって輸出入比率を対比した場合、輸出比率が一定の水準で推移していることに対し、輸入比率はこの時期を境に上昇傾向を示していることが分かる。また、この輸出入比率を各業種についてみると、精密機械、輸送機械、一般機械、電気機械と輸出比率が非常に高く、需要面ではいずれも輸出依存型の構造を有していることが分かる。
しかし供給面では一般機械及び輸送機械の輸入比率が上昇基調にありながらも2〜5%程度で推移していることに対し、電気機械及び精密機械は90年代に入って輸入比率の増加傾向が目立ってきており、それぞれ10%程度、30〜40%程度と高い水準に達し、特に精密機械では輸出入比率が90年代半ばには拮抗するような状態に至っている。
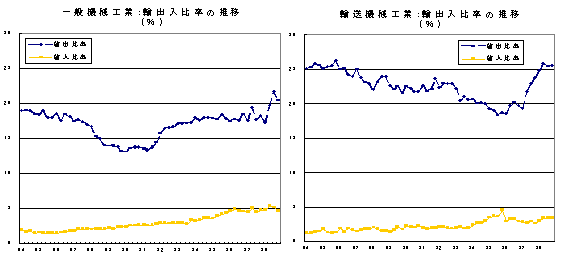
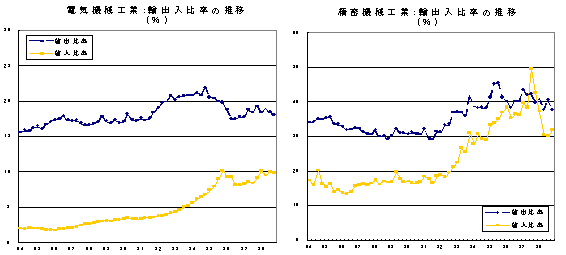
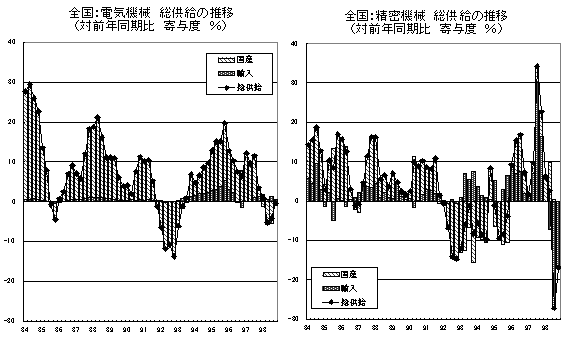
とりわけ、この電気機械及び精密機械は輸出入比率が他と比較して相対的に高いことに加え、総供給の推移に対する輸入の寄与度が90年代以降、非常に高いものとなっている。このことは、これらの業種の需給構造の変化の背景に、80年代後半以降の円高とそれによって進展した海外直接投資による生産拠点の移転があると考えられる。すなわち、輸入比率の顕著な上昇傾向には、それまで都市集積型生産体制から国内における地方へと展開してきた量産体制が本格的な円高の出現により、大企業を中心とした多国籍戦略の中でより人件費や地価の安い東南アジア等へと移転していることが背景にある。このような流れの中で、国内からは生産設備を中心とした資本財を輸出する一方で、海外からは生産財及び消費財を輸入するという国際分業ともいえる体制が92年以降本格的に稼動し始めたことを示唆している。
また、金属製品については輸出入比率とも相対的に低く、これらの中ではむしろ内需型の業種であるが、輸出比率が80年代半ばを契機に急低下したことに比して、輸入比率は一貫した増加傾向を示し、90年半ばには輸入比率が輸出比率を上回ってきている。
次に、基礎素材型産業についてみると、輸入比率及び輸出比率とも10%前後の水準で推移しているが、特に輸入比率については80年代半ばの円相場の急騰を背景に大きく上昇し、その後、この供給構造が固定化されてきている。他方、輸出比率については円高を背景に90年代当初まで減少傾向にあったが、その後再び上昇傾向に転じている。
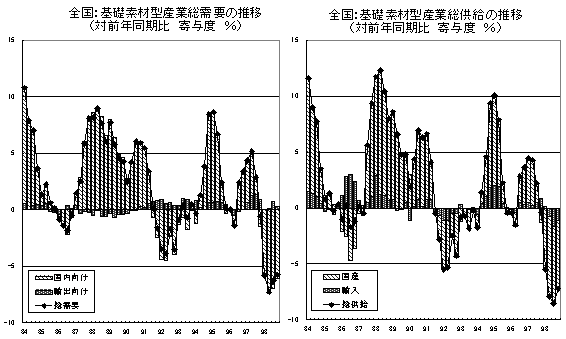
さらに各業種ごとの輸出入比率の推移をみると、国内で原材料となる天然資源が乏しい非鉄金属加工業及び石油・石炭製品は双方とも輸入比率が輸出比率を大きく上回っている業種であり、供給面での構造変化が80年半ば以降顕著である。
他方、化学工業は両者がほぼ拮抗した動きのなかで90年頃までは輸入比率が輸出比率を上回っていたが、91年以降はむしろ、輸出比率が急上昇、輸入を上回っている。また鉄鋼業は輸入比率が2〜4%程度で安定狸に推移する中で輸出比率は87年以降90年にかけ大幅に低下、その後10%程度の水準に戻り、97年からは再びその比率を上昇させている。これらの業種は高度成長期以降の産業施策で臨海コンビナートを中心とした産業基盤が形成されてきたが、円高、逆オイル・ショックと呼ばれた原材料価格の下落という環境変化に晒された業種であり、90年代に入り、両業種の輸出比率が上昇に転じたことは、それまでの内需依存型から外需型として構造変化を強めていることが分かる。
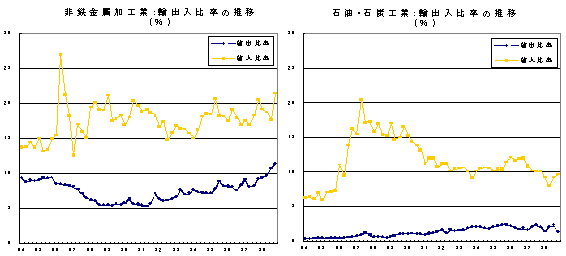
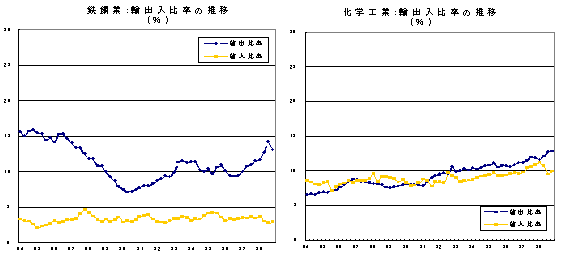
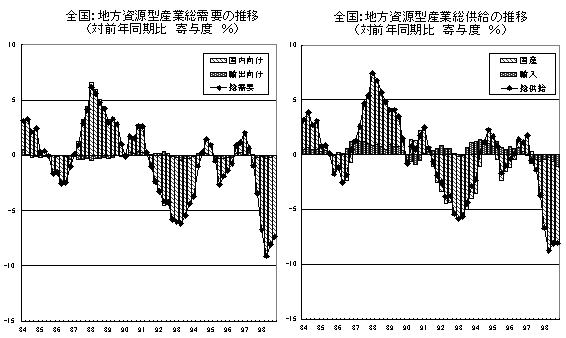
次に地方資源型についてみることとする。当該業種は需要面で輸出の寄与する割合が相対的に低く、内需依存型であるといるが、問題は内需型として生きている産業において、80年代後半さらには92年以降、輸入の割合が次第に高くなっていることである。地方資源型を業種別にみた場合、パルプ・紙加工業は非常に低い水準ながら90年にかけて輸出比率が下降する反面、輸入比率が上昇、同様なことが93年から96年にかけてみられており、また、窯業・土石及び繊維工業は輸入比率が一貫して増加傾向にある。特に繊維工業はその上昇傾向が顕著であり、80年代半ばには約5%程度であったが90年代後半には20%に近い水準にまで達している。
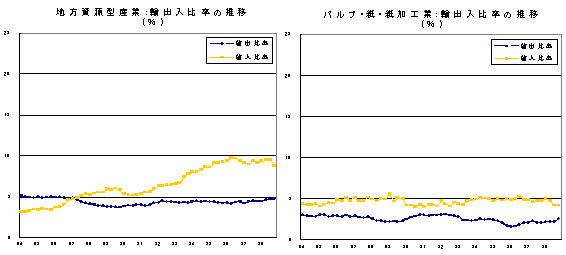
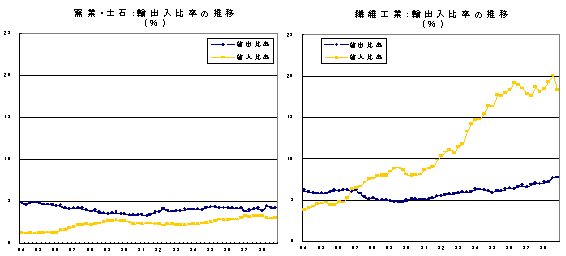
この繊維産業における需給構造についてさらに詳しくみると、まず、需要面からは輸出の寄与する割合は相対的に低く、国内の繊維工業がほとんど内需に依存して推移しているということが分かる。しかしながら他方で、供給面については80年代後半及び90年代前半から輸入の寄与する割合がかなり高くなってきており、国内市場における国産品と輸入品との競合が激化してきている結果となっている。
次に、雑貨型産業についてみてみることとする。当該業種については輸出・輸入比率とも他と比較して相対的に低く、約2〜3%程度の水準で推移しており、基本的に内需依存、国内供給型であるということがいえる。しかしながら、低位であるとはいえ、輸出比率がほぼ一定の水準で推移する中で輸入比率は上昇傾向を示しており、地方資源型産業と同様、国内市場における輸入品との競合が徐々に激化してきていることを示している。
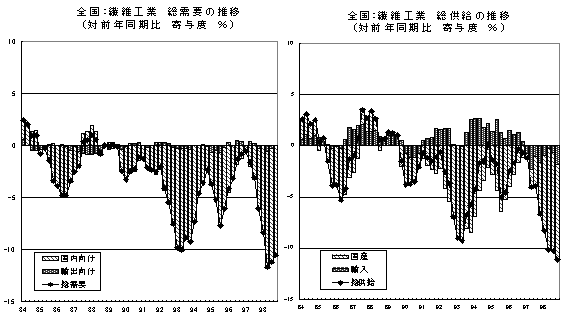
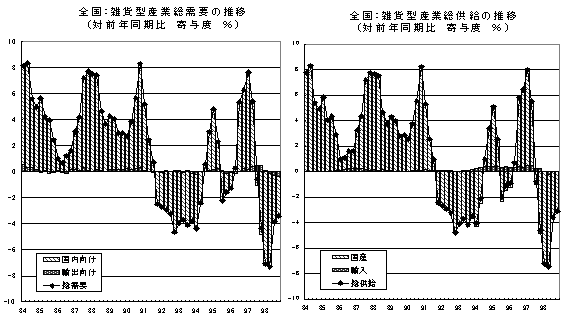
(3) 日本経済における需給構造の変化 ↑top
このような需給構造の変化は、80年代以降今日まで主として二つの要因によって進んできたと考えられるが、このことは地域別の輸出入の推移からみてみるとより明確になる。
第一に、85年のプラザ合意により急激な円高によって動き出したアジアを中心とした海外への直接投資、つまり生産拠点の海外移転である。 この動きの日本経済に対する需要面での変化は、外需、つまり輸出の相手先の変化に現れてきている。97年に発生したアジアの通貨・金融危機に直面するまで、その大きな牽引役として一貫して輸出増加傾向を示してきたのはアジア向け輸出であったことからも分かる。これを先に述べた財別及び業種別の需要構造とあわせて考えた場合、とくに加工組立型産業、とりわけ電気機械や精密機械といった機械工業における海外直接投資により、消費財よりもむしろ資本財や生産財といった、企業内分業のための生産要素が輸出される比重が高まったと考えることができる。
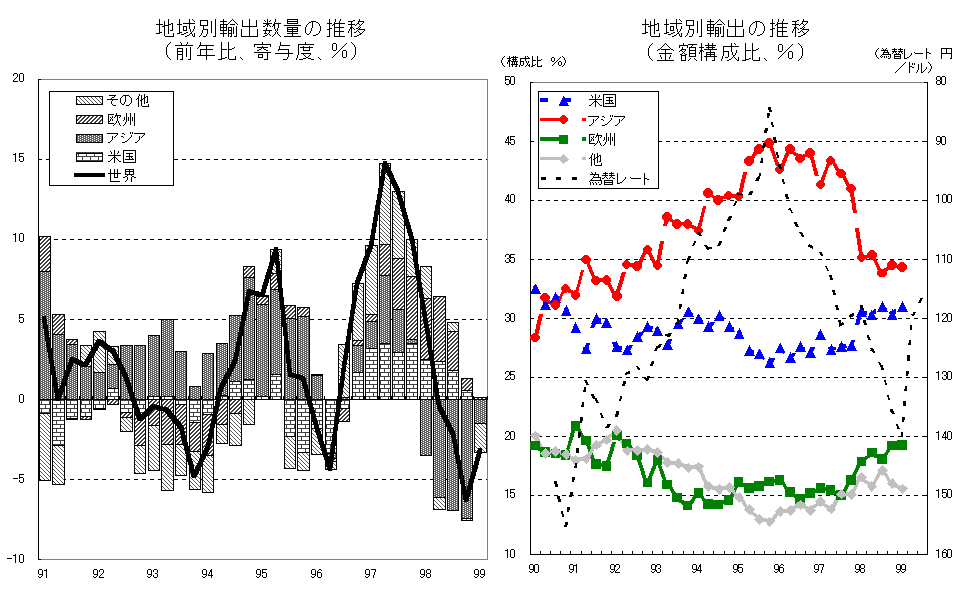
また、このことを反映して、輸出に占めるアジア向けの構成比は90年当初から後半にかけて比重を高め、96〜97年には輸出全体の5割近い水準に達しており、これは逆に対米、対欧州輸出比率が低下していくなかで起こってきている。さらに、この輸出需要の変化が構造的な要因であるということを指摘できる端的な現象としては、95年春に1ドル80円を超える円高基調にあっても、他地域向けの輸出が減少傾向を示す中で唯一アジア向け輸出のみは一貫して高い伸びを続けているということからも分かる。
つまり、日本企業の国際分業ともいえる生産体制の広域化、国境を超えたグローバル化が生じており、そのことが特に加工組立型の業種における資本財の輸出と消費財の輸入という傾向をもたらしているのではないかと考えられる。
また、次に供給面から地域別の輸入の推移をみてみると、先に述べた需給構造の変化を促すもう一つの要因がみえてくる。それは先述の85年以降の円高、92年以降の海外直接投資によるアジアなどの海外生産現場からの生産財や消費財の輸入増である。また、これに加え、90年代以降の旧共産・社会主義圏などの地域からの輸入増、つまり90年代以降旧共産・社会主義経済体制の国々が世界的な市場経済化の流れの中になだれ込んできたということもある。すなわち、これは「平和の配当」による製品輸入の増大であり、この旧共産・社会主義国の資本主義市場への参入が世界的な製品供給力の増大につながり、国内では内外価格差の大きな消費財を中心とした輸入が増加してきているのである。
このことは、輸入価格の推移に対しても反映されている。図から分かるように90年代前半における輸入価格の低下を招いたのはアメリカやヨーロッパよりも、むしろアジアやその他の地域からの輸入品によるものとなっている。これにより大きな影響を受けるのは、地域の特性を生かした地場企業を中心として営まれてきた繊維工業などの中小地方資源型を中心とした素材型産業や、都市圏における消費財生産を中心とした加工組立型の中小下請企業であり、これらの企業の生産する消費財と輸入品との競合が国内市場においてより激しいものとなってきている。これは、国内需要が低迷する現時点においても、輸入金額に占める製品輸入総額が6割を超える水準を維持していることからも明らかである。
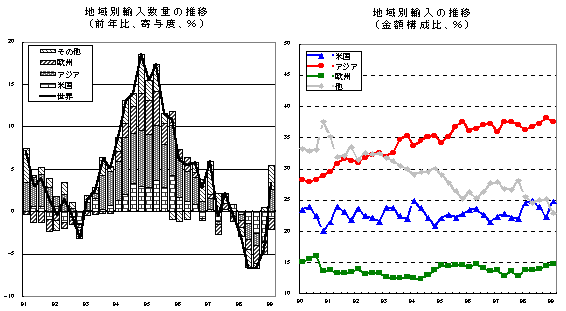
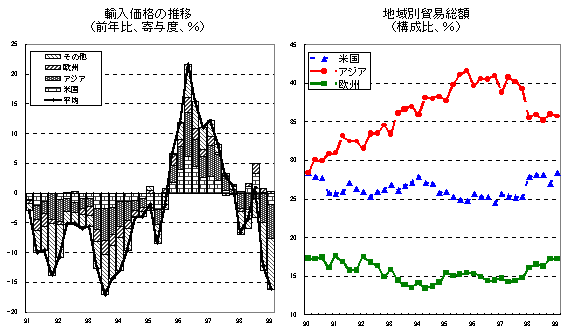
このように、今日、日本経済においてはこのような二つの要因による海外供給力の上昇ともいうべき状況が生じている。つまり、一方には加工組立型を中心とする業種における生産現場の海外への移転に伴う既存下請中小企業の衰退という問題があり、もう一方には地方資源型などの内需依存型である素材型産業の、国内市場における輸入品との競合による衰退という問題が生じている。
製品輸入とは、原材料輸入とは全くその意味合いが異なる。製品輸入とは、輸出も含めた需要に対して、海外の人、設備、土地を使って供給することであり、逆にいえば、国内の人、設備、土地が余るということを意味している。そしてこれらのことが、今日における日本経済の供給過剰感ともいうべき状況を通じて、企業におけるリストラを加速させ、失業率の上昇といった経済指標に反映されてきている。したがって、今、日本経済の回復のためにはこの供給構造の抜本的な改革がなされなければならない。
(1) 業種別に見た各地域の生産動向 ↑top
次に、このような日本経済全体の需給構造の変化を踏まえ、このことが各地域においてどのような形態で現れているのかという点について考察する。
まず、各地域ごとの製造業の生産について全国の動向との比較を行ってみると、三大都市圏を含む関東、東海、近畿では生産指数がほぼ横ばいで推移しており、そのうち東海は96年に入って特に輸送機械の伸長等により上昇に転じているが、関東は96年後半以降下落傾向にあり、近畿については95年以降落ち込み、回復力が非常に弱い。
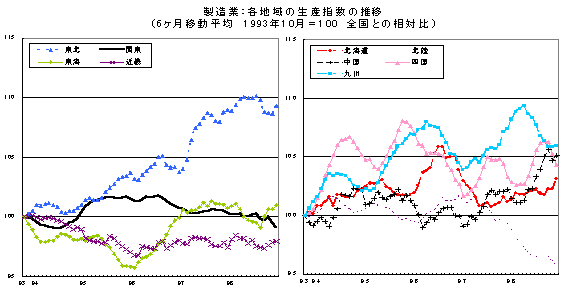

他方、その他の地方圏では東北が95年以降、上昇基調で推移し、九州及び四国は上昇と下降を繰り返しながらも全国以上の水準で推移している。また、96年まで上昇基調にあった北海道は97年半ばにかけて停滞を続けたが、その後徐々にではあるが回復基調にある。中国も97年以降、上昇傾向がみてとれる。北陸は96年末までほぼ全国並みの水準で推移してきたが、97年に入って一貫して下降基調に転じている。
また、この点を全国の生産指数の推移に対する各地域の寄与度でみた場合、まず製造業全体の約4割程度のシェアを誇る関東では、その増加寄与度の低下傾向がみてとれる。すなわち、94年後半から95年前半における回復期には電気機械産業等の好調により全国の生産指数の推移に対して約5割程度の寄与を示していたが、96年から97年当初の回復期にはそれほどの伸びを示しておらず、さらに98年に入って最も著しい減少傾向を示している。また、他の都市圏、すなわち東海及び近畿は関東がそれほどの増加寄与を示さなかった96年から97年にかけて大きな増加寄与度を示しているが、これは前者は輸送機械、また後者は電気機械の伸長によるところが大きいと思われる。しかし、この両者も全国の製造業に占めるシェアは15〜18%であるが、98年以降の下降期にはシェア以上の減少寄与を示している。
次に製造業における業種別にみてみることとする。まず、基礎素材型産業については、全国に対する各地域の寄与度からみた場合、上昇及び下降局面とも全体の約4割程度のシェアを有する関東の寄与度が相対的に高いが、北海道が比較的好調な推移をみせ、四国がそれに続いている。逆に東北、近畿および九州については全国以下の水準で低迷している。さらに98年にはいってからは、東海、北陸も全国以下の動きに停滞してきている。
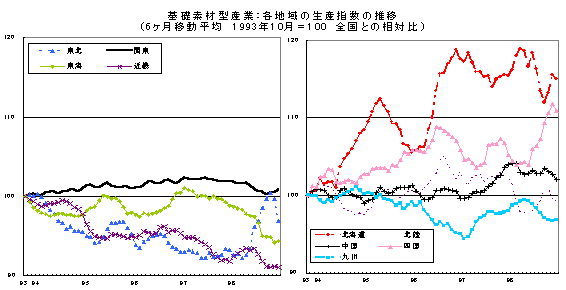
次に、地方資源型産業についてみると、都市圏については近畿が95年以降とくに97以降好調であり、関東は96年以降全国と同水準に戻った程度であり、東海は低迷を続け、ここにきてようやく全国並みとなった。また、地方圏では98年以降、、北海道及び四国については上昇基調を示し、また北陸地方については下降基調を示している。
この地方資源型産業のうち、特に製品輸入比率の急上昇がみられる繊維産業の各地域の生産動向をみてみることとする。当該業種は先に指摘した内需型産業の中でもとりわけ、国内市場における輸入品との競合等によって全体的に衰退傾向にあることと、しかしながら、その中でもそれぞれの地域のおかれた位置付け、つまりコストや付加価値等の比較優位性によって衰退する地域と比較的好調な地域とに二極化してきているということが考えられる。
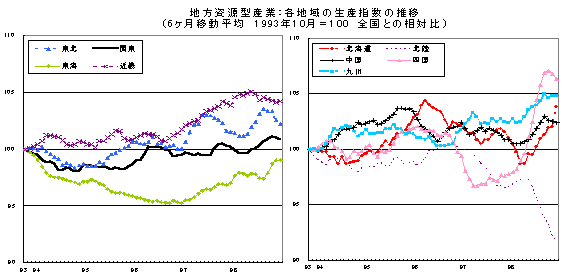
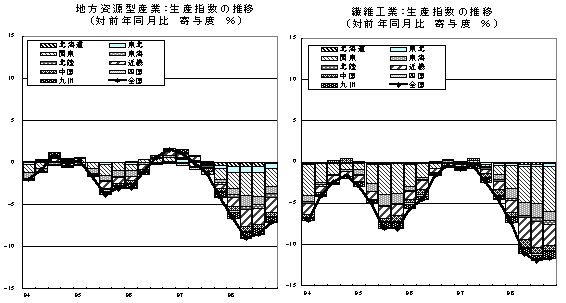
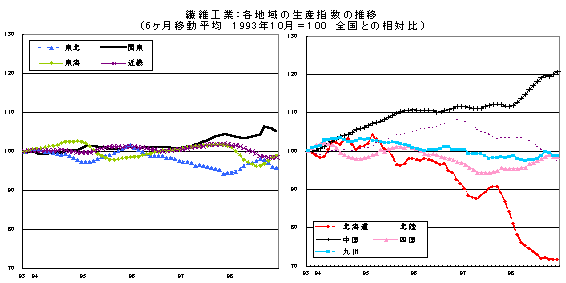
多くの地域がほぼ全国と同様の推移を示している中、地方圏のうちいくつかは特徴的な推移を示しており、まず北海道については96年頃から衰退傾向が顕著であり、期間中一貫して全国を下回る水準で推移している。これと対照的であるのは中国であり、一貫して全国を上回る水準で推移している。北陸も96年末までは比較的好調な推移をみせていたが、97年に入って低迷してきている。また、これら地域別生産の全国に対する寄与度をみてみた場合、97年以降の下落局面で、関東、近畿、東海の影響が大きいが、特に近畿の落ち込みが過去と比べ大きい。
次に、雑貨型産業についてみてみると、都市圏については東海が比較的、全国並みの水準で推移していることに対して、関東及び近畿では全国を下回り、その動きも期を追って落ち込みが大きくなっている。他方、地方圏については東北が全国並み、北海道は97年中が以降上昇基調にある。その他は四国が近畿型、九州は96年から急激に下落、北陸、中国は95年前後から低迷、北陸は98年から再度その落ち込みは大きくなっている。
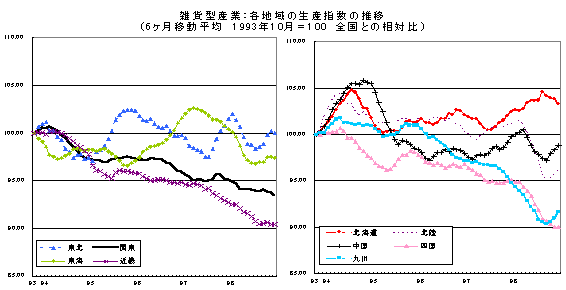
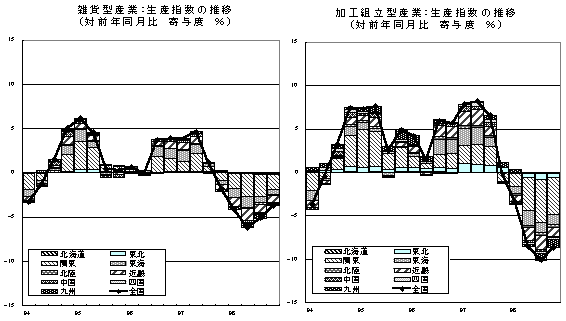
最後に加工組立型産業についてみると、その傾向は地域によって大きく分かれている。規模が大きい都市圏では、関東は97年以降全国水準を期を追って割り込んできており、近畿は全国以下で推移、東海が逆に97年以降全国水準を上回ってきている。一方、四国が94年から、九州、北海道が96年から全国水準を10%上回る水準に達し、97年から東北、ここにきて中国がそれに並んできた。しかし、地方圏のうち唯一北陸のみは全国並みの水準しか示していない。
さらに、その地域ごとの寄与度についてみてみた場合、まず、加工組立型産業における大きなシェアを誇る関東地区の衰退傾向が目立つ。関東は95年をはさんだ回復期には最も大きな上昇傾向を示し、国内の当該業種の成長を牽引してきていたが、97年以降の回復期には以前ほどの増加寄与を示しておらず、さらに98年に入って最も大きな減少傾向を示している。さらに、他の都市圏である東海及び近畿は97年の回復期に関東に代わって大きな増加寄与を示したが、98年以降の減少傾向も顕著なものとなっている。これらから、今日の加工組立型産業の衰退は、地方圏よりもむしろ都市圏の問題であるということが考えられる。
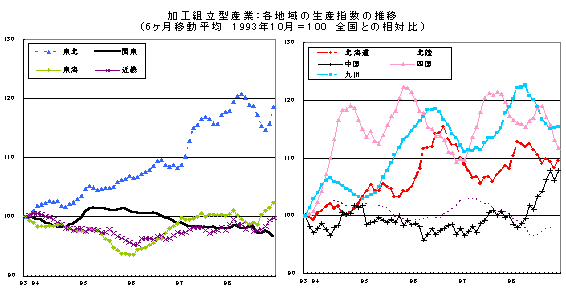
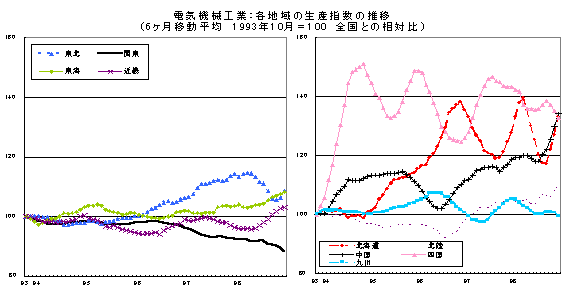
この加工組立型産業について、さらにいくつかの業種別の構成についてみることとする。まず、電気機械工業では生産指数の水準からみた場合、とくに好調な推移を示しているのは北海道、中国及び四国である。また、全国の生産指数に対する寄与度からみた場合、95年末までは全体に占めるシェアの大きい関東の増加寄与度が高かったが、96年以降、この割合は下降しており、代わってこの時期には東海及び近畿が大きな増加寄与を示している。さらに、98年以降の当該業種の下降傾向はそのほとんどの要因が関東の停滞によるものであり、先に述べた加工組立型における関東の低迷は電気機械の影響によるものが大きいと考えられる。
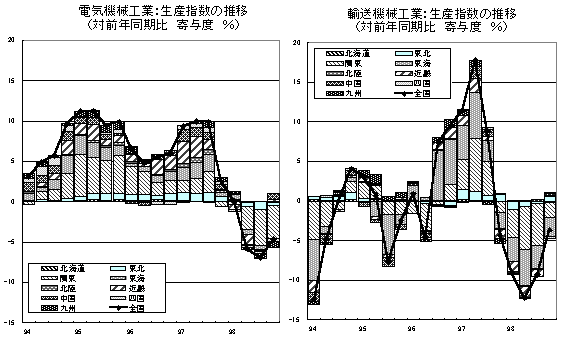
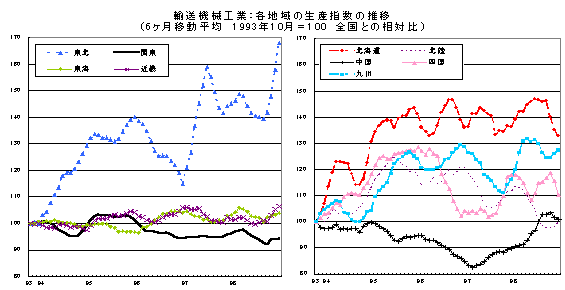
また、輸送機械についても都市圏が停滞傾向を示す中で北海道、東北、九州、四国等の地方圏が好調な推移をみせている。しかしながら、当該業種については都市圏、とくに関東及び東海の占めるシェアが大きいため、全国に対する増加寄与でみると当該2地域の推移が大きな影響を与えている。96年半ばから97年半ばにかけての回復期には東海地域の上昇に負うところが大きく、先に述べたこの時期の加工組立型産業回復の一役を当該地域が担ったのは、主としてこの輸送機械の堅調な推移によるところが大きい。
さらに精密機械では、各地域の動向が大きく分かれている。これは先に指摘したとおり、当該業種における国際分業の進展がこの90年代に入ってより著しいものとなったことに起因しており、生産システムの中での各地域の位置付けが、このような分化を示す結果となっている。指数及び全国に対する寄与度からも分かるように、95年から96年後半までの時期に顕著な増加傾向を示していたのは中国及び近畿であったが、96年以降、東海が次第に成長傾向を示しており、98年以降の他地域が減少傾向を示す中でも好調な推移を示し、さらに97年半ば以降はこれに東北も加わっている。しかしその一方、この業種が比較的早くから立地し、地域産業の大きな柱となっていた関東、近畿は98年に入ってその落ち込みが目立つ。
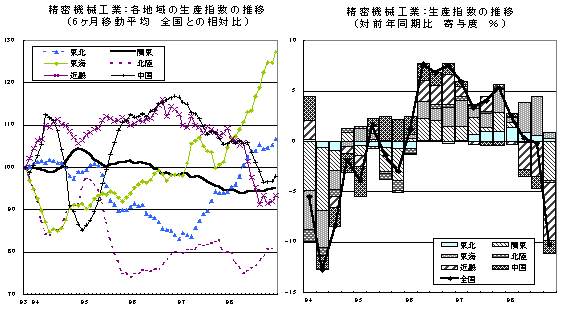
これらのことから、まず、素材型産業については、とくに地域を問わず全体的に衰退傾向にあるが、このことは先にも指摘した製品輸入の増加によるところが大きい。つまり、これらの産業は基本的に内需型であるために、国内市場への安価な輸入品の流入に伴う競合が激化するなかで次第に衰退しつつあるといえる。さらに、その中でも繊維産業でみられるように、地域的にはその比較優位性などの競争条件により、相対的に堅調に推移しているところと、極端に衰退しているところとの二極化が進んできているものと思われる。
また、他方の加工組立型については地域的な動向が分かれており、これまでこれらの産業の中心地的存在であった都市圏については衰退の傾向を示している。その一方で、地方圏については東北や九州、四国など比較的好調な推移を示している地域と、北海道や中国、北陸のように全国並、またはそれ以下の水準で推移している地域とに二極化されている。
これは大きく二つの要因が考えられ、まず、一つには繊維産業、精密機械、電気機械でみられたような製品輸入による国内市場での競合という問題がある。この点については消費財市場、とくに都市圏における競合により、都市圏における地場産業とも言うべき中小下請企業の衰退という結果を招いているものと考えられる。
さらに地方圏の二極化の問題はより複雑であり、このような製品輸入増加の問題の他に、今日の大企業の企業行動が80年代後半の海外直接投資を契機としてグローバル化していることに起因する。このような企業戦略により新たな生産拠点として組み込まれている地域は新しい産業基盤の立ち上がりを受け、比較的堅調な推移を示しているが、その枠組みから外れた地域はこれまでの生産基盤の体制自体を失い、より直接的に衰退の道を辿っている。
(2) 需給構造の変化と地域における産業構造の再編 ↑top
次に、このような産業動向の推移を受けて、各地域における産業構造がどのように変化してきたかという点について考察することとする。まず、全地域にわたってみられる傾向としては、素材型産業から加工組立型産業へのシフトである。
変動相場制に移行後、石油危機を除いて、日本経済は常に円高圧力に晒され、円高対抗策として、合理化投資など常に海外競争力を高める戦略を採り続けてきた。これが基本的には、加工組立産業の育成、大幅躍進を生み出した。しかし、この動きは更なる円高圧力の火種となり、85年のプラザ合意により本格的な産業調つまり、海外への生産拠点のシフトへと繋がった。
この結果、先に指摘した基礎素材型産業における為替動向との関連や、地方資源型産業における低コストの途上国及び旧共産主義国からの製品輸入比率の上昇という要因により、都市圏及び地方圏を問わず、素材型産業の位置付けは低下傾向にある。とくに、この素材型産業においても比較的、地域の資本や資源を用い、中小の地場産業から構成されている割合が高いと思われる地方資源型産業の衰退が最も著しい。
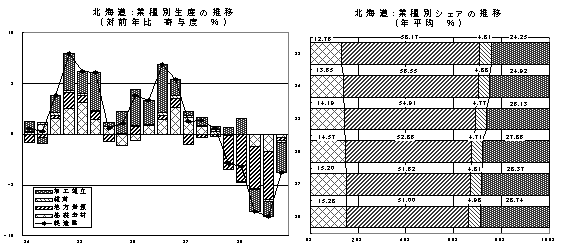
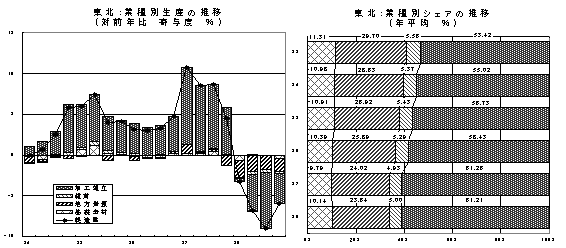
また、この素材型から加工組立型へのシフトという傾向は、都市圏よりも、東北や九州などの地方圏において顕著である。このことの一つには、まず、今日においても大企業を中心とした機械工業等の加工組立型産業の再配置、量産現場の地方への移転が進んでいるということがある。しかし同時に、既存の地場産業型の製造業、つまり繊維や食料品などの分野における低価格の輸入品との競合、衰退という問題が生じ、結果的にこの双方の要因から都市圏と比較して相対的に地方圏で産業構成の変化が大きくなっているということがいえる。
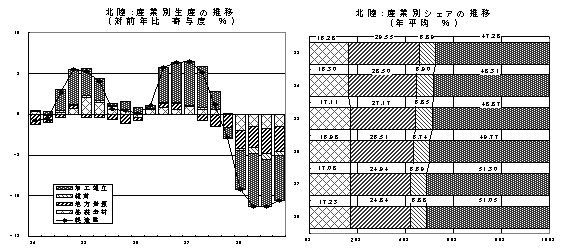
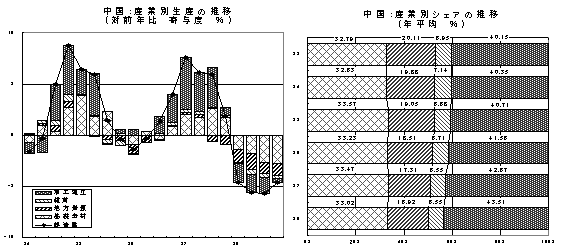
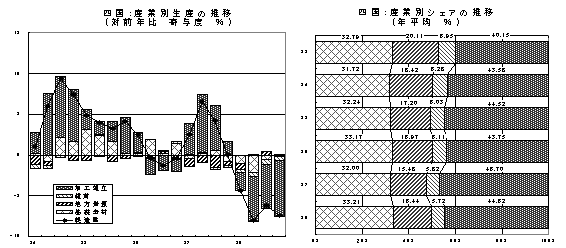
他方、都市圏では問題はより深刻である。都市圏における製造業の業種構成は地方圏と比較して相対的に大きな変化は生じていない。しかしながら、これらの地域の製造業の推移が安定しているからではなく、むしろ素材及び加工組立を含めて全般的に停滞しているということに起因している。

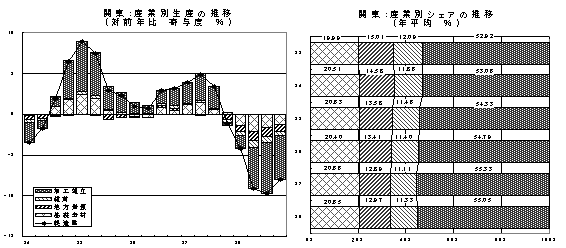
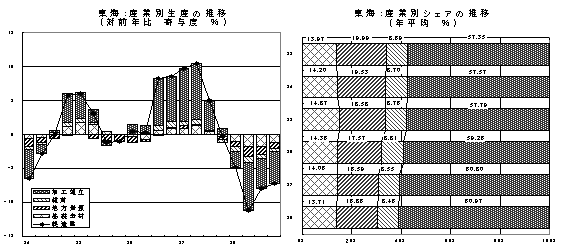
つまり、これらの地域においては地方圏で伸びている加工組立型の産業についても、成長分野とはなっていないのである。特に都市圏における加工組立型の企業とは大消費地を抱える都市集積型で、大企業の下請け等の中小企業が多くを占めている。このような基盤の下で、80年代半ば以降の海外直接投資に代表されるような生産現場の移転という直接的な影響に加え、消費財を中心とした製品輸入という間接的な影響を受け、関東にみられるようにその力は弱まってきている。したがって、都市圏では地方圏のような素材型産業の低迷に加え、加工組立型産業の衰退があり、さらにその背景にこの都市圏地場産業ともいうべき中小下請企業の衰退が生じているのである。
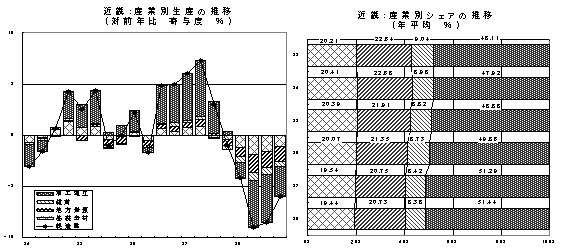
(3) 産業構造の変化と地域政策の課題 ↑top
このように、80年代半ばを契機とした円高、海外直接投資をはじめとする企業活動のグローバル化により、輸出主要製品、輸出相手国の変化、90年代からの製品輸入の増加は、国内における各地域に多面的な動きとなり、それぞれの産業構造に大きな変化をもたらしてきている。
このような流れのなかで、従来から地域の資源や特性を生かして営まれてきた中小の地方資源型の地場産業は海外からの安価な製品の大量輸入により、国内市場における競合を余儀なくされてきている。また、他方で高度成長期以来、産業再配置施策の名のもとに都市圏及びその周辺部を中心として築き上げられてきた加工組立型産業の重層的な分業体制は、その範囲が国家の枠を超えて海外にまで及ぶに至り、その裾野ともいえる都市周辺部の下請企業の衰退をもたらしている。
このようなことからまず、今日における日本経済の長期不況、供給過剰の真因は、まさにこの部分にその一つの要因をみいだすことができる。つまり、バブルの崩壊以来、「財政再建」期を除いて幾度となく行われてきた従来型の公共投資とは、あくまでも需要面での底上げの施策であり、このような施策によってつくりだされた有効需要は、過去と比べて製品輸入の増加によって国内需要を賄われてしまう割合が高い。すなわち海外をも視野に入れた重層的生産分業体制の見直しの下では、所得の海外流出、あるいは地域間の所得移転いう問題が存在しており、景気対策として行われている従来型の公共投資の経済的な波及効果は従来ほどのものとはならないのである。加えて、金融自由化の進展に伴い、景気回復、金利上昇、円高という連鎖関係がより鮮明なものとなってきている。これは、国際的な競争力のある産業とそれに対して競争力が低下している産業が混在している場合には、景気刺激の名の下での公共投資は円高を生みやすく、ひいては競争力の低下している産業の市場からの退出を早める結果となる。すなわち、地場産業を衰退に追い詰めることにもつながりかねない。
したがって、今日求められるのはこのような需要面での直接的な対応ではなく、むしろ供給側の構造改革である。製品輸入による地場産業との競合や、海外直接投資による生産現場の移転という問題の背景には、雇用面を中心とした日本経済における供給力の過剰という問題が存在するが、この過剰な生産資源をどのように活かし、どの分野に振り向けていくかという課題が、まず問われなければならない。
さらに、この供給側の構造改革についても、これを地域経済という観点からみた場合、従来型のインフラ整備や補助金行政、目的や主体性、戦略性のない企業誘致では対応できない。高度成長期以降、日本経済は大企業を中心とした生産システムの効率化を都市への本社や研究開発等の中枢部門の集積と、地方への量産現場の展開という地域間の分業体制をつくりあげることによってなしとげてきた。さらにその背景には、数次にわたる全国総合開発計画による産業再配置計画と、地方における工場団地への誘致施策や都市を中心とした道路・鉄道などの物流システムの整備といった行政施策がある。さらに、金融部門においては、地方銀行が獲得した預金を中央の都市銀行へと循環し、その資金が大企業を中心とした産業部門に配分されるという構造が形成されてきた。これらのことが意味することは、都市を頂点とした国内の産業構造の階層化であり、東京など都市圏を中心とし、地方を裾野とする地域間の生産システムの形成により、生産効率の向上を実現することであった。
しかしながら、今日、この生産システムの階層構造に、裾野の部分から崩壊が生じてきており、その一端は関東や近畿などの都市圏の加工組立型産業の生産の低迷に現れてきている。製造業を加工組立及び素材の2業種に大別し、その地域ごとの構成比をみてみた場合、先に指摘したとおりまず、素材型産業については全地域にわたって衰退の傾向を示しているため、構成比そのものにも大きな変化はない。しかしながら加工組立型産業については図からも明らかなように関東、近畿及び東海といった既存の都市圏の地位が相対的に低下している反面、東北や九州といった地域におけるシェアが増加してきている。この背景にあるのは、都市圏における従来型の生産システムの裾野部分に当たる中小下請企業の衰退という問題であり、これらの都市型地場産業においては、従来から大企業による下請・系列化のもとで安定した受発注関係を保証することを条件に、生産コストの削減と品質の規格化のみが追求されてきたのだが、そのことが逆に独自の技術情報の蓄積を妨げ、またマーケティング等の市場開拓力の育成をも阻害してきた。そして今日、これらの中小企業やその背景にある地域と、大企業の利益というものが、従来の右肩上がりの時代のようには整合しなくなった時代に、これらの企業や地域はその位置付けを見失いつつあるのである。
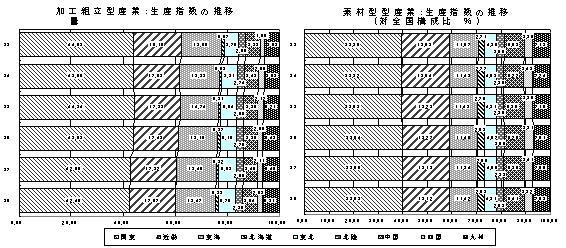
企業の利益がもはや地域や国家の利益とは必ずしも整合しなくなった現代、産業振興策についてもこれまでの企業や産業の側からの発想だけではなく、個々の地域の側からの発想も必要とされるのではないか。つまり、例えば企業誘致という施策一つについても、ただやみくもに大企業を誘致すれば良いというものではない。現代社会において企業は個別の利益をうるために、人件費や地価などのより低コストな経営を目的として、その行動範囲は国内にとどまらないものとなっている。したがって、これまでの産業再配置という観点から、単に雇用や所得の創出という経済規模の拡大のために量産現場を誘致するだけでは、この点での海外との比較優位を常にチェックする大企業の生産システムに組み込まれ、地域の命運をこれらの企業の経済合理性の観点からの意思決定にまかせることを意味するだけである。国家の枠組みを超えた地域間の競争が現実のものとなっている今日、地域における産業政策の一つの課題とは、まず、それぞれの地域が競争上の比較優位性、あるいは独自の付加価値といったものをどこに求め、そのためにどのような企業を必要とするのか、という主体的で戦略的な発想が必要である。
さらに、このような観点からは従来型の大企業の誘致という施策だけでなく、むしろその流れの中で見捨てられてきた地場企業の振興が必要である。なぜなら、大企業が生産性の向上をスケールメリットを基本として追及する限り、そこにあるのは画一化、均質化の論理であって、それでは各地域の独自性、比較優位性にはつながらないからである。戦後の高度成長期から今日に至るまで、わが国における官民一体となった効率性第一の特定分野に偏重した資源配分がもたらしてきたのは、個々の地域において本来であればベンチャーとなるべきだったこの中小企業の機動性や先駆性の阻害であった。このような観点から90年代以降、ベンチャー企業の振興策として独自の技術開発を支援するインキュベーター施設等の箱モノ整備も行われたが、今日までそれが身を結んだのは限られた事例のみである。このような施策に欠けていたのは、ビジネスを展開するに当たっての他の条件整備が不充分であったということを意味する。
今後の地域における産業振興の一つには、まず、従来まで大企業、あるいは都市圏に偏重して配分されてきた資本の還流のための制度、つまり金融面でのリスク負担が可能な資本を呼び込むための資金調達の場を形成しなければならない。また、もう一つの方向性としては、これらの地場企業が大企業との安定した取引関係の中で培われてこなかった経営面、特に市場開拓のためのマーケティング能力の育成、支援が必要であり、中小企業といえども、あるいは地場産業であってもアジアを含めた海外を市場とした展開が必要な時代となってくる。このことは昨今のアメリカにおけるベンチャービジネスの展開をみても分かるように、店頭公開市場などのリスク資本が中小企業に投資される制度が整備され、また単に産業技術的な側面で秀でた人材だけでなく、マーケティングに精通した経営者による新規開業が行われてきている。
これからの時代、地域経済の比較優位と独自性を築いていくのはそれぞれの地域の資源や文化を背景とし、そこに根付いた資本である地場産業である。但し、地場産業といえども、これからは決して内需型であってはならない。内需型にとどまるのであれば、早晩海外からの製品輸入に侵食されるであろう。90年代に入って、日本経済とアジア経済がより密接な関係を作り上げてきている。地場産業といえどもアジアを視野に入れた展開が、逆に地場における産業の体質改善を助けてくれるであろう。このようなソフト面での施策を通じて、地域の資源や情報蓄積を生かしながら、各地域の経済がそれぞれに固有の軸となる産業を育成していくという方向性が求められるのである。