少子化と高齢者介護
──飛騨におけるフィールドワークから── |
田 原 裕 子 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手 |
| 特 | 集 | 論 | 文 |
|---|
 |
田 原 裕 子 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手 |
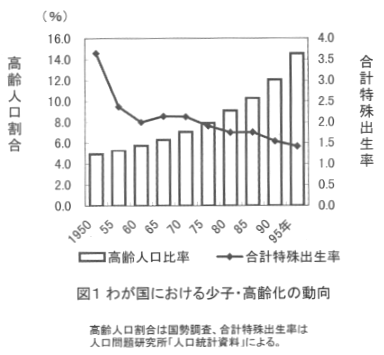 本稿に課せられたテーマは高齢者介護の観点から少子化を考えることにある。ここでは飛騨圏における事例調査に基づいて、地域や家族の視点からこの問題を検討してみたい。
本稿に課せられたテーマは高齢者介護の観点から少子化を考えることにある。ここでは飛騨圏における事例調査に基づいて、地域や家族の視点からこの問題を検討してみたい。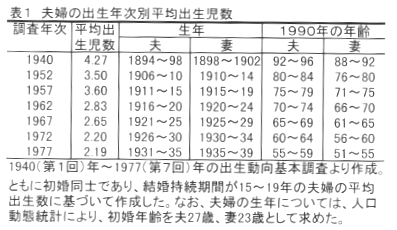 他方、家族に視線を移すと、第一の少子化の帰結として1990年代に入ると、子どもの少ない高齢者が登場するという大変化がもたらされた。表1は厚生省の出生動向基本調査に基づき、夫婦一組あたりの平均出生児数を夫婦の出生年次別に整理したものである。これによると夫1894〜98年、妻1898〜1902年生まれの夫婦の平均出生児数は4.27、同1911〜15年、1915〜1919年生まれの夫婦で3.60と3を大きく上回っていたのが、1916〜1920年、1920〜24年生まれの夫婦では2.83と急激に減少し、その後も世代が下がるほど減少している。そして、出生力の転換点となった1916〜1920年、1920〜24年生まれの夫婦が高齢人口に参入したのが1990年である。つまり、1990年以前には高齢の親の多くが3〜4人、またはそれ以上の子どもを持っていたのに対して、1990年以降は2人しか子どもを持たない高齢者が増加することになる。その結果、老親の扶養や介護に関して重大な責任をもつ長男(跡取り)およびその嫁と、それ以外の子供たちという構図、あるいは、多くの子供たちが少しずつ分担するという構図がくずれ、今後はほとんどの子どもが(自分の親にせよ、配偶者の親にせよ、)親の問題を我が事として受けとめざるをえなくなるのである。
他方、家族に視線を移すと、第一の少子化の帰結として1990年代に入ると、子どもの少ない高齢者が登場するという大変化がもたらされた。表1は厚生省の出生動向基本調査に基づき、夫婦一組あたりの平均出生児数を夫婦の出生年次別に整理したものである。これによると夫1894〜98年、妻1898〜1902年生まれの夫婦の平均出生児数は4.27、同1911〜15年、1915〜1919年生まれの夫婦で3.60と3を大きく上回っていたのが、1916〜1920年、1920〜24年生まれの夫婦では2.83と急激に減少し、その後も世代が下がるほど減少している。そして、出生力の転換点となった1916〜1920年、1920〜24年生まれの夫婦が高齢人口に参入したのが1990年である。つまり、1990年以前には高齢の親の多くが3〜4人、またはそれ以上の子どもを持っていたのに対して、1990年以降は2人しか子どもを持たない高齢者が増加することになる。その結果、老親の扶養や介護に関して重大な責任をもつ長男(跡取り)およびその嫁と、それ以外の子供たちという構図、あるいは、多くの子供たちが少しずつ分担するという構図がくずれ、今後はほとんどの子どもが(自分の親にせよ、配偶者の親にせよ、)親の問題を我が事として受けとめざるをえなくなるのである。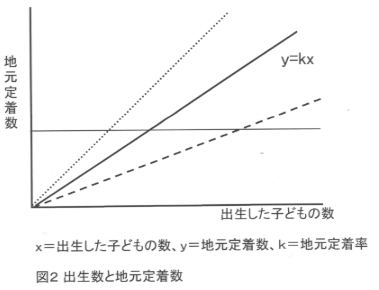 図2は一定の期間に地元で生まれた子どもの数(x)と地元に定着した子どもの数(y)、および子どもの地元定着率(k)との関係を示したものである。たとえば、老夫婦が子どものうち最低1人は地元に残ってもらいたいと考えた場合、子どもの数が4人、5人と多かった時代には定着率が25%、20%でよかったものが、2人っ子が主流となった現在では50%以上でなければならない。さらにいえば、こと介護に関しては、たとえ同居していたとしても独身の子どもは必ずしもあてにできない。就業と介護の両立が難しいからである。したがって、子どもの配偶者まで考えると、実際に要求される定着率はこの2倍の100%となるのである。
図2は一定の期間に地元で生まれた子どもの数(x)と地元に定着した子どもの数(y)、および子どもの地元定着率(k)との関係を示したものである。たとえば、老夫婦が子どものうち最低1人は地元に残ってもらいたいと考えた場合、子どもの数が4人、5人と多かった時代には定着率が25%、20%でよかったものが、2人っ子が主流となった現在では50%以上でなければならない。さらにいえば、こと介護に関しては、たとえ同居していたとしても独身の子どもは必ずしもあてにできない。就業と介護の両立が難しいからである。したがって、子どもの配偶者まで考えると、実際に要求される定着率はこの2倍の100%となるのである。| 今号のトップ | メインメニュー |