少子化と政策的視点について
 |
椋 野 美 智 子 (日本社会事業大学教授) |
| 特 | 集 | 論 | 文 |
|---|
 |
椋 野 美 智 子 (日本社会事業大学教授) |
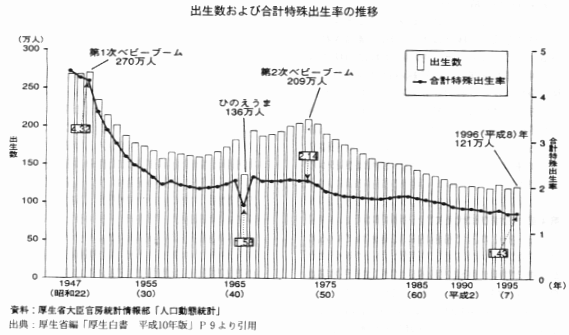
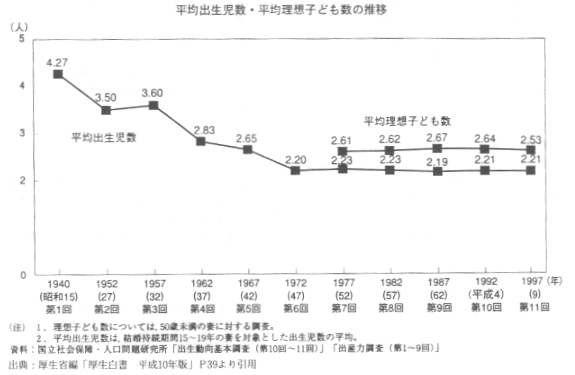
 |
機会費用軽減のためには、次の(1)または(2)が必要。 (1)「継続就業した場合の賃金曲線」(=「年功序列型賃金」など)をもっと緩やかにする。 (2)「再就職した場合の賃金曲線」をもっと上方に移動させる(中途採用の拡大、パートタイム労働者の処遇の改善など)。 なお、経済企画庁「平成9年度国民生活白書」によると短大卒の平均的なケースにおける、出産・子育てによる就職中断・再就職後の賃金格差による金銭的損失は退職金の差額も含め、約6,300万円にのぼると試算されている。 出典:厚生省編「厚生白書 平成10年版」P186より引用
|
| 今号のトップ | メインメニュー |