
少子化と家族
─歴史的パースペクティヴ─宮坂靖子
(奈良女子大学助教授)
| 特 | 集 | 論 | 文 |
|---|
 |
少子化と家族─歴史的パースペクティヴ─宮坂靖子 (奈良女子大学助教授) |
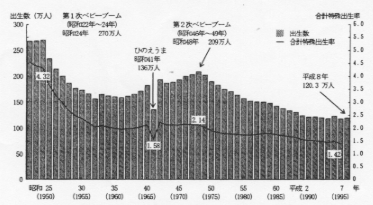 資料:厚生省大臣官房統計情報部「人口動態統計」、厚生省国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」 (注1)平成8年の出生数は推計値 (注2)「合計特殊出生率」とは、15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの平均子供数に相当する。 出典:総務庁編『高齢社会白書 平成9年版』P.31より引用
|
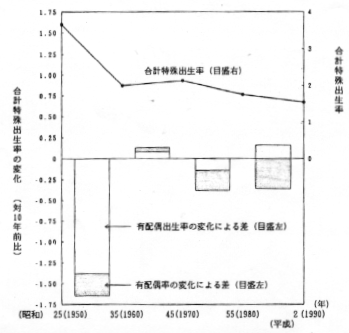 (備考)石川 晃「近年における地域出生変動の原因──有配偶構造の影響」「人間問題研究所」第48号第3巻、1992年10月により作成 出典:『国民生活白書 平成6年版』P.13より引用
|
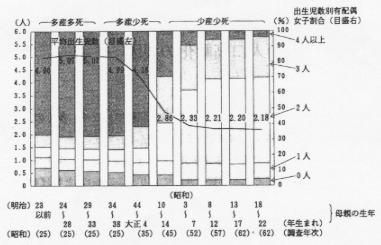 (備考)
(備考)1.数字は各年生まれの有配偶女子が15〜49歳のときまでに出産している子供の数である。 2.古い順に6時点は総務庁「国勢調査」、最近4時点は厚生省「出生動向基本調査(第7次〜第10回)」により作成。 3.母親の生年により子供は3つの世代に分類できる。すなわち、(1)明治30年代以前生まれの母親から生まれた子供(昭和以前生まれ)は、出生率も死亡率も高かったので多産多死型、(2)明治後半から昭和初期生まれの母親から生まれた子供(昭和一桁から20年代半ば生まれ)は、出生率が高く死亡率は低かったので多産少死型、(3)昭和一桁以降生まれの母親から生まれた子供(昭和20年代半ば以降生まれ)は、出生率も死亡率も低かったので少産少死型である。 出典:経済企画庁編『国民生活白書 平成6年版』P.12より引用
|
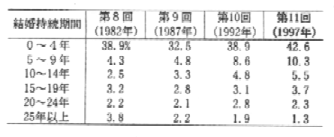 出典:国立社会保障・人口問題研究所『第11回出生動向基本調査、結婚と出産に関する全国調査、夫婦調査の結果概要』P.11より引用 注)最上段の数字は、調査の回数を、( )内の数字は調査の実施年を示している |
| 今号のトップ | メインメニュー |