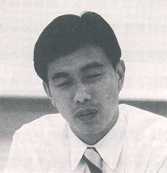岐阜県経済の現状と課題
[出席者]
| 大松 利幸 氏 | (岐阜プラスチック工業株式会社取締役社長) |
 |
| 加藤 典孝 氏 | (ソニー美濃加茂株式会社代表取締役社長) |
| 郷 睦和 氏 | (富士変速機株式会社代表取締役社長) |
| 田代 正美 氏 | (株式会社バロー代表取締役社長) |
| 星野 鉄夫 氏 | (岐阜車体工業株式会社代表取締役社長) |
| 矢橋 達郎 氏 | (関ヶ原石材株式会社代表取締役社長) |
| 原 耕平 氏 | (株式会社大和総研経済調査部理事) |
(司会)高津 定弘 (財団法人岐阜県産業経済研究センター副理事長)
高津(司会) 本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。本日の座談会は、「岐阜県経済の現状と課題」をテーマに、現状、課題、展望という流れで進めていきたいと思います。活発な本音ベースのご議論をお願いしたいと思います。
最近の景気の概況
高津 まず、岐阜県の景況について報告をさせていただきます。当センターが6月29日に公表しました「岐阜県景況調査」によれば、概況は「底打ち期待ハズレ、最低水準に落ち込んだ県内景況感」として、引き続き景気後退局面となっています。特に製造業の落ち込みが相対的にひどく、7〜9月期見通しが好転するとみている方はゼロでした。また、先行きについて主要企業や中小企業といった経営規模による温度差が大きくなっているようです。
売上高についてですが、非製造業の景況感は最悪期を脱したかのような気がします。つまり、非製造業は製造業に比べ、これ以上先行き悪化しないかのようです。断言できませんが、どうも安房トンネル開通効果があるようです。製造業はDI自体は先行き少し改善する傾向を示していますが、非製造業よりは製造業の売上の方が悪化を示しています。
受注高・生産量については、特に建設業の受注が先行き悪化するとしています。16兆円の経済対策があるのですが、企業の方々はそれ程良くならないと判断されているようです。
在庫量については、在庫調整が顕著で、数量の減少に加え、価格も下がっており、売上高が減少しています。この傾向から私どもはデフレが深刻化していると判断しております。
設備投資ですが、年間83兆円(実質ベース、90年価格)程あり、日本全体では高水準ですが、本格的に調整期に入ったようです。調査結果でも設備投資意欲が一層低下しています。
資金繰り・借入難易度についても、資金繰りは一段と悪化し、借入れ難は増すと判断しています。貸し渋りかどうかは分かりませんが、非常に苦しいということです。
雇用については、雇用調整、雇用の過剰感が強まっています。特に今年に入って雇用情勢が厳しい状況のなっております。非製造業においても本年1〜3月期まで不足感があったのですが4〜6月期以降過剰感が強まっています。
実は、5月中旬から6月中旬にかけ、県内企業経営者や市長、総数25名程に景況感の核心部分を知りたいと思い、ヒアリングを行いました。その結果、景況感は当センターの報告とほぼ同様の結果でした。それに加え、何人もの方が先行きの見通しについて、暗さや閉塞感をかなり持っていました。こうした感覚が実態の景況感をより悪くしているといいます。もう一つの特色は業界全体、経済全体が悪化していく中で業績が良いという企業もあるということです。その企業の経営者の理念、考え方、技術、製品、販売戦略に比較優位が見られ、企業規模が大企業や中小企業といった区分ではなく、企業企業の質的な違いが業績の良し悪しを決めている、そんな時代に入ってきたと思います。
6月にアジア諸国を駆け足で見てきましたが、変化、スピードに個々の企業、人々が変化を実践していることが強く印象付けられました。
また、学習院大学の奥村洋彦教授と議論をしました際、日本は500兆経済の経済大国としての自覚を忘れ、「小国の論理」で意思決定などを行い、部分的な利益追求型が色濃く残っていると指摘されました。このことが、様々な政治的、社会的、経済的な混迷の大きな原因となっているとも指摘されています。
アメリカ経済を見ますと、世界中から資金を吸収し、その後、世界各国に再投資することにより、世界経済のリード役を果たしています。しかし、この機能が、異常な株高水準を導いていると考えますと、この状態がいつまで続くのか、日本経済にとっても心配な状況ではないかと思います。その中で、日本経済、岐阜の経済も含め、どう先進的な役割を果たしていくかよく考える必要があると思います。
以上、景気の概要について説明させていただきましたが、経営者の皆様には景気の現状や企業の現状について、率直なお話をお願いしたいと思います。まず最初に大松さんからお願いします。
需給バランスが崩れ、慎重な設備投資

大松 利幸 氏 |
大松 製造業、非製造業にかかわらず、製造業についてはオーバーキャパ、非製造業についてはオーバーストアという現象が起こっています。基本的に需給バランスが崩れ、供給過多という状況です。確かにアジア諸国から安いものが入ってきたこともあり、日本に限らず、世界全体で見ても需給ギャップがあると思います。成長センターと呼ばれる東アジアの国々は、設備投資し輸出して外貨を稼ぐといった状況にあり、輸出によりシフトし、世界的な供給プレッシャーが強まって、需給バランスが崩れていると思います。
資金の流れを見ますと実体経済と通貨量とのバランスが非常に崩れており、恐らく10倍強は違うのではないでしょうか。世界の通貨量は300兆ドル程度ですが、実際は貿易量、輸出輸入量を含めますと8兆ドル程度、世界全体のGDPが50兆ドル程度と、貨幣の量が実体の経済より異常に多すぎると思います。その結果として、世界の利回りの良いところへシフトしていくのだと思います。つまり、東アジアがダメになったからアメリカに流れ、ニューヨークダラーが9000ドルを突破するということを導いたと思います。
この状況を引き起こしている諸要素を点検してみますと、一つ一つが治癒するのに非常に時間がかかり、短期的に景気が回復するかは非常に疑問を感じています。政府の景気刺激策は公共事業の積み増しにより、短期的には回復するかもしれません。しかし、基本的にはお金と実体経済とのバランスがうまくとれるようにならない限り難しいのではないでしょうか。ですから、企業は、これからはあまり設備投資をしないでしょう。特別な商品を除いてはそれ程需要が拡大するとは思いません。当社も出来る限り設備投資は慎重に行いたいと考えています。その結果として、個々の製造メーカーが設備投資を抑えれば、将来、需要にマッチングした形でバランスがとれてくるのではないでしょうか。その間はやはり苦しい時代が続くと覚悟しています。

原 耕平 氏 |
原 日本経済の大きな流れの中で、2回の供給ショックがありました。1回目は70年代初頭の世界的な資源の枯渇による供給ショックがあり、この時は絞られるということで価格が上がりました。2回目は80年代後半に日本がアジアなど海外に投資をし、供給の無制限状態を引きおこし、価格の低下につながりました。
日本経済は92年から製品輸入比率が60%に上がりました。資源国でありながら60%製品輸入が増えているのです。ただし、これは民間企業、特に製造業が自ら選んで行ったことで、この間は国内需要が支えていました。これが昨年の秋口以降、国内需要が支えきれなくなり、設備投資の調整が出てきてしまったのです。ただ、これは短期的なことではなく、中期的な流れの中で国内需要が落ち込んでしまったことが非常に大きい問題なのです。
高津さんのお話にもありましたが、今や日本は500兆経済。海外に依存しているのは10%もありません。96%強が国内需要なのです。これだけ大きな国内需要があるにもかかわらず日本は非常に弱気になっていました。昨年の夏の通貨危機が来るまで、日本人はなぜ自信喪失していたのでしょうか。
残念ながら、今年に入り設備投資の調整が本当に始まってしまいました。私は今後、1年半から2年の間は設備投資は落ちるのであろうと見ています。
高津 民間企業設備投資の推移を見ますと、現状は83.9兆円ですが、足元のところが減少し始めており、設備投資調整が始まっているようですね。
原 そうです。日本が海外展開により供給力を増やしている反面、国内ではそれを支えるものがなくなってしまい、完全に設備投資の供給力が見えてしまいました。つまり、設備投資に対する需要と供給、支える側とそれを生産する側のギャップが非常に大きくなってしまったのです。
もう一つは、今度は残念ながら設備投資のギャップが雇用に結びついてしまいました。資金需要がなくなり、国内投資が落ち、国内に投資する部分がなくなったので海外に行く、という流れになっているのです。規制緩和により貿易に関する資金量や資本取引量を考えますと、実体経済と通貨量とのバランスは短期的には10倍ではすまないでしょう。そのしわ寄せがアジアで起きたのです。
全体的に見ると欧米が非常に顕著な中で、東アジア、アセアンは需要が低下しています。そういった意味で、今後、日本経済は小国ではなく大国的な行動をしないと大変な状況になっていくと思います。
一度、原点に戻ることも・・・

加藤 典孝 氏 |
加藤 これから先、どうなるかは誰も分からないと思います。ただ、今までと随分違うと皆さん感じているのではないでしょうか。ただ、町の中で見かける若者の行動を見ますと、本当に不況なのかなと感じてはいます。
円レートに関しては、95年の円高のころを思い出します。当時、東京大学の伊藤先生とお話する機会を得ました。その時、円安になったらどうしますかと質問されました。95年当時は、円がどんどん強くなり、工場は海外に出ていき、国内では明日の仕事があるかどうか分からない状態になりました。翌96年には当社では作るものがなくなるだろうとも思いました。ただ、ソニー全体での売上は輸出が70%程度を占めており、円安になっても特に問題はないし、そのようなことは起きないだろうと回答をしました。
今、思うと何が起こるか分からない世界になっています。予想は出来ないし思っていることと全く違うことが起きてしまう。このような状況の時は、一度原点に戻るのが良いと思います。もともと日本製品は非常に安く、品質もあまり良くなかった。生産技術もなく、給料も安かったから、安く作れたのでしょう。ところが、ここへ来て賃金が高くなり、生産技術も高くなり、製品も高くなった。やはり、安く作ることが原点ではないかと思います。
ものを作っていながら、個人的には今、何も欲しいものがありません。このような状況下で、どのようにして消費を増やすかは非常に難しいことだと思います。そうはいうものの、性能がいい、社会的にも機能的にもいい、何か工夫を凝らしたおもしろい商品、良い商品が出てくるとよく売れるようです。ただ、必ずしも安いものが売れる時代ではないようですが。
今後の課題としては、テレビもビデオもウォークマンも家庭の中にいっぱい転がっており、エアコンも各部屋についていたり、車は3台あったりと。そのような状況でどうするのか重要な課題だと思います。
最近、当社の場合、国内で作った方が安くできることがわかってきました。どうしたらよいかといえば、一人当たりの生産数を上げればいいのです。当社の場合、5年前の3倍生産しています。
このように製造業の生産性が上がってはいますが、まだ人を減らさないと駄目なんです。半分くらい減らさないと。ただ、それは結構できるということがやっと分かりました。
高津 半分くらいに減らす可能性というのは、あるのですか。
加藤 あると思います。減ったら本当に減らし放しでは駄目で、8割にもっていけばいい。どこか駄目になるところもあるかもしれません、確かに。自分たちの範囲だったら多分できるであろう。
原 長年見ていますと、需要と供給がある程度いくまで、コンセントレーションは続きますよ。本当に来たなという気がします。裏側では、変わったりしてますから、ここを調整せざるを得ないという気がしますね。
加藤 例えば、この時期にアンケートを行っても書くことは同じです。そして本当のことも書かなくなります。まるで偏差値のよう回答が集まります。経済企画庁も同じですが、NHKなどで景気がよくないとあおってはだめだと思います。益々みんなをあおってしまう。
原 その話でいえば、マスコミは危機感のあおるタイトル書け、危機感をあおることしゃべってくれというのです。そうでないと人気がでないと。大変な問題です。研究もまさにマスコミ型です。しかし、日本はもっと自信を持っていいと思います。内需が非常に大きい。このことを認識すべきだと思います。
高津 以前、加藤さんにお話を伺った時に電気製品も生鮮食料品化したとおっしゃていました。そのことが強く印象に残っているのですが、このことは、需要に非常に迅速に反応し、企画、生産、販売へとつなげることを意味していると思いますが、いかがでしょうか。
加藤 なぜ、そう考えたかといいますと、家電商品を買う場合、少し前の型ですと非常に安く売っています。例えば、定価の5割ぐらいで売る商品も結構あると思います。なぜ、このようなことが起きるかといいますと、要するに作り過ぎたのです。どんどん作ったが、売れないから仕方がなく次の新製品を出す。新製品を出すから前の型が売れなくなる。それを売るために無理して安くしてしまう。結局は、作り過ぎるからだと思います。そのためにどうしたらよいのか。やはり、在庫を少なくするしかないでしょう。つまり、出来るだけ分だけ作るのがいいのです。私は出来るだけ少ない在庫で商品を残さずに生産しようと考えています。当社で作っているカメコーダー(カメラとビデオが一体のもの)の場合、1日1万台程生産しているのですが、アッセンブルの部材は約コンマ8日しか持っていません。5年くらい前は15日くらい持っていました。
アンバランスな強さを身に付けよ

郷 睦和 氏 |
郷 景況については私は単純にだめだと思いますが、今、世界でこれだけ恵まれている国は日本だけだと思っています。ただ、我々の次世代や次々世代が日本だけがいいというような世界はもうないとも思っています。
私が入社した時は日曜日は休みでしたが、土曜日も祝日も出勤していました。今は1年365日24時間8760時間で3100時間しか働かないのですから、トータルではだめだということでしょう。ただ100が80になることは間違いないことですが、全員が8掛けになるわけではなく、全体の中の20%が切り捨てられ、80%は従来通りだと思います。
当社は、今日お集まりの企業の中で、恐らく一番ユーザー数が少ないのではないでしょうか。となると当社は自分の所だけよくなればいい、競争にいかに勝つか、このことだけを考えていかなければいけない企業だと思っています。一つ一つの企業が自社の独自性を出していけば、伸びる企業は数は減っても出てくるのです。ただ、落ちる数と無くならなければならない数、そして失業者も多くなるでしょうし、非常に苦しい立場に追い込まれる人も出てくることは覚悟しないといけない。ただ、その時は、みんなも悪いのです。後は個々人がどこまで頑張るかしかないと社内では言っています。
今、社内ではすべての見直しを行っています。自分たちのアンバランスに強いところをどうやって作ろうかと考えています。バランスの悪い部分とバランスのとれた部分があり、全体的として平均点ならば生きてはいけません。どこか飛び抜けて、非常にアンバランスな強さといったものを作っていかないといけないでしょう。当社の場合は技術的なところ、一面だけ肥大化した、よくいえば特徴のある企業を目指していかないといけないと考えています。
高津 それは具体的にはモーターということになるのですか。
郷 ええ。特有の技術をいかに発揮していくかということです。
原 実は、私ども金融業界も何か特徴を持っていないと生き残こっていけないのです。
郷 やはり、負ける覚悟をしないといけないですよ。
原 そういうことですよね。金融界でもデリバティブといったコンピューターを使った物理学の新商品があるのですが、要は技術開発力です。技術開発力を持ってないとやはり生きていけないのではないでしょうか。特に私どもの業界は規制緩和の非常に強いところでしたので、ある程度売れても、それにキャッチアップ出来るか否かで差がついてしまうのです。
高津 これから先の成長率はゼロないし低成長だから極めて一部が伸びると思います。伸びた分の反動により逆に落ち込むところも非常に多くなると思います。結果として全体としては前年同か多少しか成長しない。ゼロサム的な経済が一部ではありうると思います。だから一部の勝者と多数の敗者が、鮮明になってくるかもしれません。
郷 私は、ゼロサムではなく、差し引きしたらマイナスになると思います。
高津 今まで日本、少なくとも戦後においては経済活動の中でそういった体験が無かったと思います。それなりにそこそこ経済活動をして、そこそこ実績を上げ、お互い生きてこられたということが難しい状況になると思います。
生活そのものにも大きな変化

田代 正美 氏 |
田代 今の経済の問題は、それなりに解決していくと思いますが、解決するにはかなりの時間がかかり、解決しない限りは景気は良くならないと思います。ただ、基本的には非常に厳しい状況が続くだろうという認識を持っています。
私ども流通業は大店法により、歪められた形で成長してきました。その矛盾が、今、全部出てきたような感じがします。規制緩和により立地法が成立したのですが、この法律は都市計画と整合した形で店舗を評価していこうというものです。ただ、私は都市計画そのものがあまり上手くいっているとは思いません。つまり、その上手くいっていないものとどのように整合性をとるのか、ここで大きな矛盾が出てくるのです。また、規制緩和といいつつも、違った規制がかかってくる可能性が非常に強いと思います。だから、アメリカのように自由な出店というのは非常に難しいと思っています。特に店舗は土地と切っても切れない関係があります。日本の流通業を見た時、例えばコンビニエンスストアは一面ではアメリカよりも上手くいっています。それは土地の面積が小さくて済んだからです。ですから、歪められた形ではない成長が出来たのです。
ところが、我々スーパーマーケットはかなりの土地が必要となってきます。そうすると土地規制によりいろいろな形で歪められてしまった。それが今、単なるオーバーストアでの競争に置き換えられてしまっているのです。確かに、我々小売業の店舗は完全にオーバーストア状態にあり、一番大きな問題となっています。ただ、全体的に売れないといわれていますが、伸びている商品もかなりあります。例えば、惣菜は非常に伸びています。これは社会生活全体が変わってきているからだと思います。一つの流れとして、ダブルインカムやスリーインカムといった形態に変化してきたことにより、家庭で料理を作るという時間がなくなり、出来上がりのものを買われるという流れです。
ほかの例では、ホームセンターではガーデニングブームによりその関連商品群が非常に大きく伸びています。スポーツクラブは従来の子供のスイミングスクールから熟年を対象としたものに変わってきています。ドラッグストアの場合、当社は調剤薬局も展開していますが、保険料の負担増からお客様が非常に少なくなってきています。しかし、同じ薬局でも化粧品は非常に大きな伸びをしております。
原 実は、私、最近花を作り始めましたのです。花を買いにいったり、レイアウトを考えたりするようになりました。
田代 先日、旅行業者の方とお話をしていましたら、旅行は全般的に良くないといっていましたが、イングリッシュガーデンを見るツアーというのはお客さんが殺到するといいます。
原 専門家を同行させるという企画もありますね。先ほどのお惣菜でいえば、東京のデパートは百貨店ではなくて、食料品と衣料品の二貨店に完全になっています。やはり、お惣菜の売れ行きはよいのですが、逆にいいますと生活は苦しいということでもあります。全国でも岐阜でも同じですが、世帯主の収入は下がっています。ただ、全国では、まだ配偶者ががんばっているのですが、岐阜県は配偶者もだめになっています。ということで、雇用にしわ寄せがきて、所得の目減りが今年出てくるのではないかという気がします。
田代 このように、ただ単に経済全体が悪いからではなく生活自体が大きく変わってきていることも要因としてあげることができると思います。つまり、経済がこのように厳しい状態が続いていくと、社会生活も大きく変わっていき、経済を経済だけとして見ることは出来なくなる、そんな感じがします。
原 それに関して、最近の中高生といった子供たちには、いろいろ問題がありますよね。
田代 先日、学校の先生と話す機会があったのですが、静かに授業を聞けなくて、授業中ふらふらと歩き出す児童がいるそうです。そのほとんどが朝食を食べていないといいます。よくよく調べて見ますと、母親が朝早くから仕事に行っているといった状況が見受けられます。犯罪が多くなればなるほどセキュリティ産業が伸びてくるように、今までとは随分違うようです。
高津 その話の関連ですが、犯罪というのは都市化の負の面で、アメリカで起きていることは、やがて日本に来るということを恐らく暗示していると思います。家庭崩壊の問題、都市社会全体の犯罪の増加、それに対する防御をどうするか。本当に大事な問題です。
田代 本当にそうです。今、万引きがすごく増えていますが、万引きは基本的には罪悪感が無いのです。
高津 万引きは統計的にも増えているのですか。
田代 非常に増えています。しかも、罪悪感がない。この問題は非常に大きな問題です。
高津 それはいつごろからですか。
田代 3年前からぐんと増えてきています。若い人の万引きと同時に痴呆老人の万引きも増えています。この人たちも全く罪悪感がありません。そういう老人がどんどん増えてくるでしょう。
郷 痴呆老人は仕方がないのでは。
田代 ですが、以前は痴呆老人の万引きは少なかったのです。一番多いのは若い子たちですが、最近は痴呆老人も増えてきました。これも高齢化の影響でしょうか。
高津 日本の場合、岐阜も同じですが、戦後、土地利用の規制を誤り、都市構造がスプロールに拡がってしまったと思います。特に首都圏がその典型ですが、都心から60km〜100kmまで拡げてしまった為、社会資本整備をする時、非常にコスト増要因が強いのです。その中で都市計画にポリシーがないのではとのお話がありましたが、私もその通りだと思います。日本の都市計画は失敗したと思います。
そこで、仮に岐阜で流通店舗の整備を核に、本来の都市的な部分はコンパクトに縮小するということが出来れば、郊外の一定の所に計画的に大規模なショッピングセンターを建設し、それ以外は自然的あるいは農業的な利用にもう一回戻した方がよいのではと思っています。このことは、無理でしょうか。極めて失礼ないい方ですが、郊外型のショッピングセンターが都市を破壊したのではと思いますが、それについてどうお考えですか。
田代 ただ単に破壊といっても、どの部分をいうかでしょう。開発自身がほとんど民間にやらせようという傾向が強くなってきています。例えば、ある一定の規模の面積があると、道路を作れ、何々を入れろ、その部分は市町村に寄付しろ、という形でです。そうであればコストに見合う開発をしていかなければならないということになります。また、事業規模ごとにも考えが違ってきます。だから、トータルな開発が日本では出来ないのです。要するに農道などは国や市町村が計画的に作っていきますが、いわゆる商業施設についてはほとんどありません。そして、民間に負担させようという考えですから民間事業者の考え一つで、隣と違う部分が出てきてしまうのも当然です。
原 そうですね。みんなデベロッパーに任せ、負担させる訳ですね。
田代 当然、デベロッパー自体の考えも違いますので、全体の整合性がとれない。そこに大きな矛盾が出て、それを解決する為のコストがかかってくる。このように追いかけっこをやっている部分があると思います。
これからの日本はストック的なもので動くべき

星野 鉄夫 氏 |
星野 この10年、20年前はものが無かった。車でいえば「いつかはクラウン」でした。今は、みんなクラウンを持ってしまい、今度は「いつかはセルシオ」といえるかも知れません。景気のトレンドは、みんなの気持ちや充実感などにより随分違ってくると思います。
では、景気の回復とは一体どうなった時に回復といえるのでしょう。勿論、所得が高い国とそうでない国とでは違うと思います。
車でいえば、岐阜や東海地区は一家に3台は持っていますが、もう1台買ってもらわないといけない。ただ、車は良くなってきており、恐らく故障した経験がない方も多いと思います。そうであれば、我慢すれば長く乗れてしまう。今まで4年で乗り換えていたのが、6年になってしまうのです。
日本人は、特有の国民性と相まってファッションや海外のブランドが流行します。しかし、消費が冷え込み、買えといわれても、ちょっと待てよという感が今はある。
つまり、景気が本当に回復するかというと、今のトレンドがこれからも続くと思います。みんなが、益々生活に対し知恵を持つようになると思います。欧州はそれ程ものを買わないでしょう。机はお婆ちゃんが使っていたもの、花嫁衣装もそう。それが誇りなんです。日本も生活の原点に戻らないといけないと思います。
原 まさに私も同感です。これからの日本はストック的なもので動かなくてはいけないと思います。例えば、住宅。当然に生活のパターンが変わっていいのです。これからは成長率で経済が豊かになるというのはおかしいことです。私は常々いっているのですが、あなたのお子さんを芸術家に出来ますかと。出来るようになれば、日本は本当に豊かです。いかに成長率が高くても芸術家が育たない、あるいは自分の子供を芸術家に出来ないのであれば、豊かではないです。ただ、数字的には人口の伸びと生産性の伸びで全部決まっちゃう訳ですが。
車でいえば、日本はセルシオという車を作りました。ベンツがびっくりしてしまったとんでもない車です。そういった意味では車はまだまだ発展する分野ではないでしょうか。
星野 ただ、日本の中で量で発展するかという話になるとどうでしょう。
原 量では無理ではないでしょうか。
星野 そうですね。ただ、例えばプリウスのように環境に優しい車であるとかターゲットを絞った車は売れると思います。一般的で、安いものを作れば売れるという時代は過ぎたと思います。
原 バブル崩壊後、100万円を切るカローラが販売されましたが、これは失敗でした。これは、安いから売れるという時代ではない、そういった時代に入ってきていることを示していると思います。
星野 郷さんのように、自社の得意分野に特化し、お客さんの欲しいものをキャッチし、自ら駆け回って先手を打ったものは当たると思います。今までにもあったと思いますが、そんな時代だからこそ、日本経済が伸びるとは思わないですね。
原 そうですね。昔のように10%成長というのはもう期待できないですね。車もそうですが、技術力のある企業とそうでない企業が鮮明になってきていますね。
星野 でも、パイ自体は増えないわけですから。
原 しかし、アジアは今はだめですが、やはりアジアにおける需要は相当なものがあると思います。もう国内で車を作っている時代ではなくなったのです。国内の需要もそれほどでもない。もっと違ったところがある。だから500兆経済の世界から一段上の世界に入ったことを日本は認めないといけないのかもしれません。
世界で通用する技術、特徴を出せ
星野 今、トヨタのものの買い方はイギリスでものを買ったらいくらというように、全部コンピュータの中に入力されています。円高になればコンピュータにインプットすれば、今どこで買うのがいいのかすぐわかるようになっています。
高津 世界中から選ぶわけですか。
星野 そうです。今までのように、こういうものを作っているから次も注文がもらえるわけではありません。
トヨタには技術の棚というものがあり、開発した技術をその中に入れるようにしています。設計者がその中からピックアップし設計していくので、グループの中は競争です。国内だけではなく、海外との競争もあります。やはり、自分を守るには技術力と差別化しかありません。
高津 でも、岐阜の中堅中小企業の方々は、もともと他と差別化することでやってこられたのではないですか。
星野 そうですが、通用する技術とそうでないものとがあるのです。
高津 それは、選別が厳しくなるということですか。
星野 厳しい、厳しくないという判断ではなく、使ってもらえるかどうかだけです。それを厳しいというなら厳しいですが。結局はお客様が認めてくれるかどうかだけです。
高津 受注する対象は常にトヨタグループだけではなく、世界中と競争しているのですか。
星野 企業によって違いますが、グループ以外のところにドラスティックに注文してくるところもあります。
原 そういう意味では新しい地場産業と今までの地場産業との棲み分けが昔はあったのですが、今はもう無くなったわけですね。
星野 逆にいえばチャンスだということです。いわゆる国際標準を取得していればどこにでも入っていけますし。結論の結論はそういった技術を持つことです。
高津 ソニーさんも同じ様な企業構造何ですか。
加藤 企業の中の工場は確かに競争です。この3年ぐらいでソニーがつく会社は4つ無くなりました。潰すことは簡単ですが、やはり特徴を出さないと企業の中の工場では生き残れません。
星野 それに関連してですが、トヨタの年間生産400万台のうち200万台をボディメーカー8社でやっていますが、当社は8社のうち一番小さいのです。他のメーカーのように量は作れません。同じコンセプトだったら、存在意義がなくなってしまいます。もともと、私どもはトラックメーカーでしたが、トラックは日野自動車に全部移ってしまうことになりましたので、私どもはワンボックス車をやることになりました。どうせやるなら、徹底した混成ラインを作り、やっていきたいと考えています。量は多くはないが、みんなが欲しい車を、あそこに持っていけば台数は少なくても何でもできるというのが我々のコンセプトです。やはり特徴がないと生き残れない時代です。
原 85年から設備投資は立ち上がっていますが、この時は円高の時です。普通ですと海外投資はしますが、国内投資はしないのです。でもこの時は投資をしてしまったのです。
星野 それで、車産業の場合、金型メーカーをたくさん作ってしまった。その結果、バブルがはじけ、うち3割は潰れてしまった。ところが、今は作るところが無くなってしまい、非常に忙しいという状況です。
今、大松さんのところとある部品を一緒に作っています。当社は樹脂はありませんが、大松さんのところはあります。1+1が3になるようなアウトソーシングも重要だと思います。やはり、どのようにして特徴を出していくかですね。同じことをやっていたらだめです。やはり何かに特化するかしかないでしょう。
郷 ただ、得意先が特定少数の場合は、やはり物理的な特性とコストと納期。この制約の中でいかに良いものを作るかです。ただ、バローさんみたいに最終的なユーザーを相手にしているところはこれからは価値があり精神的に訴えるもの、限定とかこれだけはというものだと思います。
ある人がいっていたのですが、丈夫で長持ちするものなど作るなと。例えば、パンスト。パンストは一方が伝線したら反対側も伝線し、買い換えにつながる。これこそが企業の発明で、こういう発明をしないとだめだといいます。でも、私どもの場合、早く壊れてしまうと使ってもらえないですから。
星野 私どもも命を預かっていますからね。だから、車は益々良くなりますよ。
原 日本の車は確かにそうだと思います。セルシオが世界に度肝を抜かせたくらいですから、そのマーケットは非常に大きいのではないでしょうか。
星野 セルシオを作った時は、凄かった。従来と比べて精度がコンマ1つ違っていましたから。部品屋は泣きました。でも、その泣いたおかげで技術が上がったのです。その技術は全部、他に通用します。しかも、同じコストで。
何にでも対応できるミニマムサイズに再構築
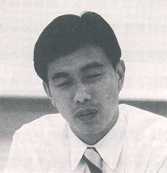
矢橋 達郎 氏 |
矢橋 当社の得意先のほとんどは全国のゼネコンで、建設業の景気とリンクしています。当社は5、6年前に売上も収入もピークにあり、以降減収、減益となっています。実際、景気の回復や需給のバランスは、未だ全く見えていない状況です。新規需要はないし、建物についても新しい主軸、新しいアイデア、個人のアメニティ的なものを付加しながら、新しい需要を喚起していくことは、非常に難しい産業です。ですから、需給のバランスがとれた時に景気が回復といわざるを得ないと思います。
大松社長がおっしゃるように、今は完全にオーバーキャパで、価格が安定しないという状態が続いています。政府のコメントでは緩やかな回復であるとか、回復基調が続いているという話もあったのですが、当業界は全く縁のないところでここまで来ました。今もこの先どうなるかについては全く見えていない状況です。
先ほど申しましたとおり、当社の得意先はエンドユーザーではありません。そうであれば、まず第1にプライスなんです。品質は同業他社に比べて良いし手間もかけている。でも値段は少し高いというのは全く通用しないのです。とにもかくにも、第一関門をこえるには安くなくてはいけないのです。それをクリアーして、やっとどんな品質を提供できるかというプレゼンテーションはさせてもらえるのです。このように今まで当社が行ってきた非常に重厚長大で、装置産業的なメーカーのアイデンティティは完全に揺らいでしまっています。
では、どうすればよいのか。いろいろと考えられるのでしょうが、どんなものに対しても対応できる体質をどのように作っていくかが、今、一生懸命進めている戦略です。
つまり何でも岐阜にある大きな工場に持ってきて作る、その中でのぎりぎりのコスト勝負というのでは限界があるのです。そうするとグローバルスタンダードというか、納期や品質を絡めながら、どこからどういう原材料、半製品、製品を調達して、それにいかに付加価値を付けるかという勝負だと思います。
ただ、生産性を上げ、例えば2人必要としていたのが1人しか必要でなくなった場合、倍売れるような市場があればいいのですが、そうではありません。結局、市場が拡大した時にはパートやアルバイトを使い、あるいは関係会社やアウトソーシングも含めて、伸び縮みできる状態を作りながら、ミニマムサイズの会社へ再構築していくしか成長は見込めないと思います。
その他には今のゼネコン相手の建築市場ではないところにどのように目を向けていくのか、どのような仕掛けはできるのかが新規市場開拓への課題だと思います。

高津 定弘 氏 |
高津 みなさんに明るい展望をお伺いしたいのですが、その前提として、一つだけご報告します。
産業別の就業者数の増減についてですが、就業者でみると製造業が全国と比べ特化しています。岐阜県は31.3%、それに比べ全国は22.5%。これは間違いなくストックベースで見れば、岐阜県は製造業主体の経済構造となっています。ところが、85年以降どの産業が増えているのかといえば、80年代後半までは製造業が就業者のかなりの部分を占めていましたが、90年以降になると第3次産業だけが増えています。製造業は生産性向上などにより人減らしが行われております。90年に入り、近年に至るまでは岐阜県といえどもサービス経済化が進んだということがいえると思います。
95年度の第3次産業における増加就業者の部門別割合を見ますと約半分がサービス業、4分の1が卸・小売業となっています。また卸・小売業の就業者は全国の伸びより遥かに岐阜県の伸びが大きくなっています。これは恐らく、名古屋のベッドタウンの外苑化によりいろいろな店が出来たことや、インフラが整備され、ロードサイドショップが増えたからではないでしょうか。また家事のアウトソーシングが行われてきていることも要因の一つではないでしょうか。
ただ、就業者1人当たり県内総生産をみますと、質が悪いのです。1人当たりの生産性が低いのです。つまり、岐阜県は全体として90年に入り、サービス経済化が進展し始めているのですが、サービス業と卸・小売業の生産性が高くないのです。これが5月末の有効求人倍率0.78にもみられるように、急速な失業率の増大、あるいは有効求人倍率の急速な低下を引き起こしています。これに、卸・小売業が大きく寄与していると思われます。仮に日本の成熟した経済構造が更にこれから進んでいき、アメリカ型になるとすればどうなるのか。アメリカ労働省発表の資料をみますと、2006年には製造業は引き続き雇用者減少、非製造業が増えるとしています。このうち、サービス業が一番増え、その中でも、ビジネスサービス、ヘルスサービスが相当増えると予想しています。特に岐阜の場合、車社会ですから、車を使い、いろいろな雇用の場を得るということが可能ならば、将来的にはサービス経済化に進むのかもしれません。ただ、そうはいっても岐阜はものづくりの県で、中小企業が支え、今後もものづくりが中心なのかもしれません。現に今日みなさまからお話を伺っていましても特色ある製造機能で勝負、発展していこうと考えのようです。
全体の流れとしてはサービス経済化が進展し、ある程度サービス業は増えていくと思いますが、製造業も特色ある製造業という形で発展していくとすれば、明るい展望がこれから岐阜に必要なのかあるいは考えられるのか、お気付きの点をお話下さい。
オリジナルでプラスアルファの魅力を
星野 やはり個々の会社がいかにオリジナリティを作っていくか、魅力ある製品を作っていくかに尽きると思います。つまり、基本的には自己努力しかないと思います。10年前は、コストを安くし、いかに量をこなしていくかだった。良いモノを安くだった。今は良いモノを安くは当たり前で、プラスアルファの魅力をどのように作っていくしかないと思います。
高津 そうすると経営者の先見性がすごく大事になってきますね。
星野 それしかないでしょう。と同時に情報産業により産業が活性化するとは思いません。これらは一つのツールだと思います。ソフトウェアはツールですから、飯は食えないと思っています。
原 そうです、道具だけですから。
星野 やはり、基本が重要です。それが固有技術であり、生産技術であり、開発力だと思います。それを磨くしかないと思っています。それと商品力、つまりアイデアが重要です。そのアイデアが日本人は弱いのです。ただ、日本人はそういう教育を受けていないから仕方がないかもしれません。どちらかといえばそれをリファインするは得手ですが、全く新しいものをクリエイトすることは不得手です。
原 でも、日本人は立派なものを多く作っていますよ。
星野 作っていますが、一般的にはまだまだ弱いのではないでしょうか。ソニーやホンダが素晴らしいのは経営者のコンセプトだと思います。例えば、長崎にあるソニーのエスパー研究所は、価値観、遊び心といった面で大切な部分だと思います。ホンダの場合、トヨタと三菱の社員は自社の車に乗らないといけないのですが、ホンダは他の車に乗れというのです。そして、他車の良いところやホンダの悪いところを報告しろと。つまり情報を従業員から集め、製品化に生かすのです。こういう価値観はなかなか変えられないです。
人間の自然な感情や文化にリンクした商品開発
高津 当センターでは「2020年の岐阜を考える」アンケート調査を実施しました。経営者一人一人の個性、アイデアが大事だと星野さんはおっしゃるいますが、アンケート結果を見てガッカリしました。将来、どのような方向を望みますかという質問に対して、無理をせず背伸びをしない生活、福祉が大事、自然が大事というのが多かったのです。ところが何度もチャレンジする人生、独創性を重視するという回答は少なかったのです。日本人全体がそうだと思いますが、今が非常によく、今が将来にそのまま続くであろうとの錯覚が蔓延していると思います。
星野 だから、それが日本の問題だということです。日本とアメリカの大学生にアンケートを行うと「国家のため」と回答する者がアメリカは70%いますが、日本は5%もいないのです。その違いはやはり文化でしょう。昔は日本もありましたが。
原 車は文化ですよ。その象徴です。でも、今は確かにマニュアル志向になっています。だから、夢がなくなってきているのです。夢がないから今が良いということになるのでしょうか。
星野 女の子がみんな同じ様な服装で、背中からみるとみんな同じ。世界からみたら恐ろしいですよ。でも、それは大きなエネルギーであることには間違いないのですが。
原 ただ、日本人は戻ってきません。ファッションみてもそうです。そういった意味でストック的なものがなかなか育たないという文化であることは間違いないでしょう。
加藤 昔なんか会社に入って給料もらったら、これ買いたいというものがあったのに、今の人はそれすらない。
大松 人間は相対的に比較優位に弱いのです。例えば、数寄屋づくりや大理石の高級な家が建つと、うらやましいといったいろいろな感情が起きると思います。いつかはクラウンという話もありますが、もっと自分の身近に、良いモノがあれば、その商品を持ちたいというのは人間の自然な感情だと思います。だから、商品開発力はあると思います。やはり、牽引力になるような商品が出てくれば、裾野が広がっていくでしょうが、それがなかなか難しいのです。しかし、よくよく考えれば、あると思います。家の場合、面積の制約もありますが、正直なところ仕方なく住んでいる方が多いと思います。やはり、どこまで本物を求めているのかについては、まだまだ十分ではないと思います。
ガーデニングブームですが、これからも続くと思います。昔は家に庭木があったのですが、今は家の前に庭もないところも多い。ガーデニングブームになり、これから良い時代なんだなと感じます。そういった意味ではどんどんグレードアップし、新しい需要を開発するポテンシャリティーはいっぱいあると思います。
原 これからようやく豊かな世界というのはおかしいのですが、できるチャンスになったと思います。そういった意味では土地税制といったいろいろな税制の問題を解決しないといけないと思います。
大松 ただ、今の経営者の心理、働いている人の心理はすごく変わっています。我々も違った切り口の違った商品をつくらなければいけないと思っています。経営者だけでなく社員みんなが思わなければ企業は生き残れない、そういう危機感が醸成されています。確かに町に出れば、若者は不景気なんて関係ないみたいですが、企業内に帰れば、非常に危機感を感じています。やはり会社がつぶれたら大変だとうことで、みんな生き残りゲームをやっています。これからがチャンスだと思っています。
高津 今後、人口自体はトータルで1億3000万人弱くらいから9000万人に減っていきますが、反面土地利用をうまくやればゆったり住むことができる。それは恐らくもっと広いスペースの住宅を日本人は手に入れることが可能になるのです。人口が減るということは、新しい文化が広い住スペースの中で作り出される可能性があるということです。確かに企業は非常に激しい企業間競争により競争力を備えながら発展していくと思いますが、生活の方は非常にゆったりとした空間を手に入れて、それぞれ個々が一つ一つ違うということを認識して豊かな生活を何とか作れないだろうかと思います。
大松 ガーデニングブームに関連して、我々もプラスチックのプランターをいろいろ作っております。ただ、それだけではお客さんは満足しない。もっとカラフルで、いろいろな機能を備えたものを望んできます。バローさんも楽しいガーデニングの売場展開をしていくでしょうし、切り口はいっぱい出てくると思います。生活の文化レベルにきちんとリンクし、同じ様な歩み方をして、商品開発をすればいいと考えています。
ダイナミズムの誕生に期待
郷 日本は今、不景気だといっても贅沢をしていると思います。韓国や中国、東南アジアの国々の人と比べて、どちらが楽な生活、充実した生活をしているかです。日本はハイレベルな生活をしているのですから、これがもっと良くなるというのは虫が良すぎると思います。製造業はこれからよくならないといいますが、当社のギアロータリーをみても、もともと人が大変な仕事をしなくてもすむように機械に置き換えてきました。そうすることにより人を減らしてきましたから、製造業の従業員が減っていくのは当たり前です。その分を一般の人が精神的な満足の得られるサービス業でいかにまかなうかだと思います。
あとは、教育です。今の教育が全部間違っているといっているのではないですが、21世紀を考えるならやはり教育を変えていかないといけない。今のように、点数が非常に取れる人たちも大事ですが、点数が悪くても、何かスポーツが優れていれば、芸術が素晴らしければ、それを生かして大学に行ってもいいと思います。今は極端にいえば、欠点のある人間がだめなんです。そうではなく、欠点はたくさんあるが、一つでも飛び抜けたものを生かしていかないと今後はいけないと思います。結構、大物といわれる人やすごい芸術家は欠点が非常に多いと思います。ただ、その欠点の多さをたった一つの長所が上回るものであれば、それを認める社会を作らないといけないのではないでしょうか。ある意味では超法規的に認めることも必要ではないでしょうか。
高津 今後、困難に直面した場合、ある仕掛けや力が働いて、それなりに日本の社会も柔軟に対応していくような気がします。超法規的といわれましたが、実際にこれからいろいろな世界で次々と起きてくるのではないでしょうか。起きてこないと、ダイナミズムが生まれてこないでしょう。
大松 先日テレビを見ていましたら、京都の中村ソトジさんという大工を取り上げていました。彼を磯崎新さんといった建築家が非常に心酔している方です。最初、磯崎さんはおかしいと思っていたのですが、中村さんのように空間に1本、柱を入れてみると建築がしまったといいます。私は学問の基礎技術を受けてきた人たちとは違う、職人の世界に啓発されています。そのような話が出てくれば、評価する方も変わってくると思います。
高津 岐阜でそういった動きが起きてくるとダイナミックになってくるのではないでしょうか。
原 岐阜はもともと楽市楽座があり、そういう風土は育っていると思います。東京はもともと枠組みが設定され、そこから動くことを嫌うのが江戸ですから、今回の景気の回復は、大阪の方が早いと思います。
魅力ある産業、企業に
田代, 岐阜県で大学生の卒業者6000人のうち、流通を第一志望にしている学生は1%程度しかいません。もっと学生に対し、プレゼンテーション、つまりもっと訴える必要があったと思います。ただ、魅力のある産業が本当に少なくなってきたのではないでしょうか。実際、食べていくために仕方がないから就職する人が多くなってきてるようです。やはり、我々の一番の役割、やらなければいけないことは、自分の所属している産業の魅力をもっと築き上げていかないといけないと思います。もう一度自分たちのやってきた仕事の価値を再検討し、その中から新しいものを見出していかないといけない。そうすればいい人材も自然に入ってくると思います。希望して入ってくる学生が増えてこなければ、あらゆる産業も、日本もだめになってくるのではないでしょうか。
高津 確かに今、学生が志望しているところを見ますと日本の将来がある程度分かるかも知れませんね。
田代 金融機関を第一志望にしている人が多いようです。ただ、金融機関とは何なのかという意味を持っていないのです。単に相対的にこちらよりもこちらがいいという捉え方だけです。金融機関がビックバンになって、今後どのようにやっていくのかを今の金融機関は学生に訴えていないのです。その部分が今の日本を閉塞状態にしてしまっているという感じがすごくしています。
高津 やはり、教育、人材ですか。
田代 基本的な能力は若い人たちにはすごくあると思います。ただ、魅力のある産業や企業がなかなか出来上がっていない。要するに基本的な自分たちのアイデンティティをもう一度作り上げているいくこと、そしてそれを若い人たちい訴えていくことだと思います。
高津 日本はGDPが500兆円という高水準にあるのですが、不幸にして高質なものを作りだし得ない宿命じみたものを持っているのでしょうか。
田代 丁度、今、全体が変わりつつあると思います。ゆらしがかかるまで、今の段階で躊躇しているのではないかと思います。だから、一度ゆらしがかかれば、価値観にしてもかなり変わってくるのではないかと思います。
高津 もう1ランク、質を高めないと、学生が就職する時に、あの企業なら自分のやりたいことができそうだというギャップが狭まってこないような気がしますね。
新しい価値観の創造
矢橋 今の景気の低迷は功罪、両方あると思っています。功の部分としては、学歴で上にいけば、それが豊かな暮らしや物質的満足につながる、お金が価値観のすべてという階級ピラミッドの価値観が崩壊しかけていることがあげられます。そして価値観の多様化というものが、今後、ますます進んでいくのではないかと思います。
今、NHKの朝のドラマで、大工の女の子を主人公にしたものが放送されています。このことは非常にいいことだと思います。学歴社会がいいんじゃないんだよという風潮をもっと盛り上げていっていいと思います。
では、なぜ今、そうなったのか。ものを作っている我々でさえ欲しいものがない。お金もものにも満ち足りてて、何を作ったらいいか分からない。何をしたらいいか分からないというところまで来たからこそ壊すことができるのです。これが10年くらい前だったらどうでしょう。学歴がすべてでないということは一つのデモンストレーションとしか受け取られなかったと思います。今はもう目の当たりに例があり、非常に説得力があるのです。そして、高成長あるいは量による拡大という経済成長は日本経済の成長のすべてではないのではないかと。ただ、その中で経営者としては、どのような価値観を従業員に提供するのか、あるいはそのエネルギーに源として、どう影響を与えられるのか、非常に難しい課題だと思っています。
当社は業績はよいとはいえず、雇用調整もやりました。そして、従業員は必死にやらないと給料が減ったり、やらないと会社は生き残っていけないんだなと実感するようになりました。そのためには、社長や役員だけが考えるのではなく、工場の一人一人が考え、行動するようになったのです。そうしないと給料や雇用調整に跳ね返ってくることを、ここ1、2年で彼らは身を持って体験しました。今も業績はよくありませんが、社内の空気は目の色が変わりエネルギッシュです。それは何にも代え難い財産を得たと思っています。ただ、そのボルテージを落とさないように、今後どうやっていくか。その具体的な内容を私が提供しないといけないと思っています。
これからは女性の時代
田代 経済成長という言葉がありますが、成長というのは男性の論理だと思います。後進国は基本的には男性が上位にくる。ところがある程度成長し成熟すると女性上位になってくる。そして、これからの時代は、成長ではなくて成熟です。成熟すれば、女性の論理でものの論理を考えなくては行けないのです。例えば、当社のスーパーバックがはがれやすいようにチェカーが折っているのも、もとはといえば、女性のチェカーたちが考えたものです。男性ではそういう発想は出てこないのです。これからは、女性の論理で世の中が動いていくと思います。このような女性上位の世界の中で、今後どのような企業をつくり上げていくか。このことが非常に重要になっていくと思っています。
加藤 ただ、心配なのは若い人も年寄りも含め女性はすごく元気なのですが、男性の、特に若い人が異常に元気がありません。学生を面接するとよくわかりますが、女の子はきちんと答えることができるが、男性はまともに答えられない。女性が成熟するのはいいけれど、男性が下がってきている。こちらを何とかしないといけないでしょう。
郷 先日、お昼時だったので、岐阜グランドホテルの展望レストランで昼食に入ったのですが、男は我々だけでした。
矢橋 今はもう、一般消費は女性ですね。女性をいかに掴むかにかかっているのではないでしょうか。
原 以前は、お寿司やはだいだい男がいくところだったのに、今は女性だらけなんです。
矢橋 お金を得た時に、男性はまず車を買いますが、女性はもう少し体験的に自分の身になるようなもの、海外旅行などそうですが、多分、そういう消費行動にでているようです。このあたりが男性の元気のなさの象徴、価値観の硬直化の象徴といえるのではないでしょうか。
高津 聞いておりますと、男の人はどうも壮大な世の中が悪いとか世界が悪いとかといっているのですが、女の人はやはり足元をしっかり見ていて、したたかに一人一人実行している。今日のお話で、企業はプラスアルファや個性が大事。あとは実行できるかどうかが問われています。
今日は皆様から貴重なお話を伺いました。お忙しい中お集まりいただきありがとうございました。
情報誌「岐阜を考える」1998年夏号
岐阜県産業経済研究センター