人民元はきり下がるのか、切り下げるのか?
アジア通貨危機後の中国経済
 |
渡邉真理子 日本貿易振興会アジア経済研究所駐香港研究員 |
| 特 | 集 | 論 | 文 |
 |
渡邉真理子 日本貿易振興会アジア経済研究所駐香港研究員 |
香港の中国への返還の翌日、タイバーツが急落し、アジア通貨危機がはじまった。その後、タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシアおよび韓国の通貨は大きく下落したのと対照的に、香港と中国の通貨は、対米ドル為替レートをほぼ一定に保っている(図1)。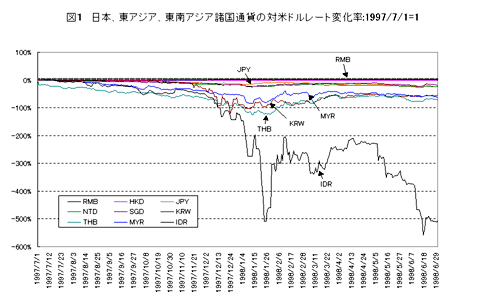
1998年4月に入って日本円もドルに対して下落しはじめ、アジア地域経済の為替の総崩れを懸念する声が強くなった。このため、対米ドルの為替レートを固定続ける香港ドルと人民元の切り下げがあるのでは、という観測が依然根強い。
これに対して、中国の朱鎔基総理は、人民元の切下げを再三否定し、1998年6月末の米国のクリントン大統領の訪中の際にも、この方針があらためて確認された。こうした政治的な保証によって、現在人民元への信任が一応回復した形となっている。しかしながら、人民元のレートは政治的要素のみで決まっているのわけではない。通貨危機後約1年さまざまな観測にもかかわらず、人民元の水準はほぼ一定に保たれてきた。これには、経済的な理由があるはずである。
人民元の引下げを懸念する論拠としては、つぎの二つの要因があると思われる。(1)中国の輸出価格競争力が落ち、輸出も減少する。(2)中国自身の経済成長率が鈍化傾向にあり、第3四半期に入った現在、朱鎔基総理が立てた1998年通年の国内総生産の成長率8%の達成が危ぶまれるようになってきた。以上の理由から、輸出を促進するために通貨を切下げざるを得なくなるだろう、という議論である。しかし、第一の米ドル建ての輸出価格について考えるとき、為替レートの他に、人民元建ての価格水準とその動向も考慮する必要がある。また、第二の点については、為替レートの引下げは輸出回復の有効な対策とはいえず、景気回復効果は薄い。中国政府もより内需拡大を重視したスタンスを取っており、為替レートの切下げが予想される状態にはないのである。この点について、本稿では詳述したい。
改革の途中にある中国経済は、脆弱な体制を抱えているにも関らず、今回の通貨危機が国内のシステムに直接打撃を受けなかった。これは、漸進的な対外開放の進展の結果、いまだに残るさまざまな保護政策が、運良く防波堤として働いたことが幸いしている。具体的には、外資への国内市場開放に関する制限であり、人民元の自由兌換の制限である。こうした要素が影響し合った結果、中国のマクロ経済動向からみて、人民元の切下げの緊急性は低いといえる。
為替レート水準を左右する要因は、①モノやサービスの貿易などを含む経常収支、②金融資産の売買、直接投資などで構成される資本収支とに区別される。人民元の外貨兌換は、現在①の経常収支部分については、自由化されているが、②についてはまだ規制がある。このため、現在の体制では、市場の変動が主に影響を与えるのは経常収支のみである。資本収支部分の自由化と対外開放を進め、外資導入を促進した結果が裏目にでて、通貨危機に陥ったタイ・インドネシア・韓国などとちがい、中国は資本収支部分の規制が対照的に、外資の突発的な逃避をさける直接的な防波堤となった。
(1)経常収支と国際収支現在の体制のもと、人民元の水準に直接的な影響を与えるのは、経常収支である。まず表1に示した1990年代の動向を見てみると、経常収支は1991年から減少し93年にはマイナスに転じていることがわかる。こうした経常収支のアンバランスを受けて、1994年1月に為替の公定・市場レートが一本化され、実質的な切下げを行った。その後、経常収支は急速に回復し、97年も前年の倍近いのびを見せている。
表1 :中国の国際収支| 経常収支 | 資本収支 | 純国際収支 | 外貨準備増減 | 経常収支2 | 為替レート | |
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5) | RMB/US$ | |
| 1991 | 13272 | 220 | 13492 | -14089 | 11601.255 | 5.3227 |
| 1992 | 6402 | -250 | 6152 | 2267 | 4995.5575 | 5.5149 |
| 1993 | -11092 | 23472 | 12380 | -1767 | -11792.98 | 5.7619 |
| 1994 | 7658 | 32644 | 40302 | -30527 | 7357.2581 | 8.6187 |
| 1995 | 1618 | 38674 | 40292 | -22487 | 11957.081 | 8.3507 |
| 1996 | 7242 | 39967 | 47209 | -31651 | 17551.899 | 8.3142 |
| 1997 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 33113.382 | 8.2897 |
また、管理下にある資本収支も大きな赤字となれば、人民元の切下げ圧力となる。しかし、1993年の頳小平の南巡講話を受けた直接投資ブームを反映して、資本収支は黒字基調である。実際、経常収支が赤字となった93年にも、資本収支の黒字が貢献し、国際収支そのものは黒字となっているのである。こうした国際収支部門の黒字は、人民元の切り上げ圧力となる。また、海外からの資金導入はマネーサプライの増加、インフレへの圧力となる。こうした圧力を軽減するため、対外取引全体の黒字を、外貨準備として積み上げ、米国債などの形で海外で運用する構造が続いている。
(2)輸出と強く連動した輸入輸出と輸入の差である経常収支がこれまで安定して黒字を保っている原因として、輸入が輸出に強く連動していることがある。これは、外資の国内販売に対する規制と輸出振興策とが背景にある。現在、中国の輸出の大半を担っているのは外資であり、彼等は生産活動に必要な設備・原材料の大半を輸入し、加工した上で輸出している。こうした設備・原材料輸入を免税というインセンティブが与えられている。この結果、生産活動に関る輸入は、輸出と連動しかつ下回る形で推移してきた。一方、国内産業によって関税障壁で保護することで、国内企業の生産活動と消費のための輸入を抑え、国内の経済の過熱によって、経常収支が悪化するという道筋も押え込んできた。こうした、対外取引に残る規制によって、経済全体の対外取引の安定化を可能にしていた。図2のように、97年から98年にかけて、輸出および経常収支は大きく減退するうごきを見せていない。
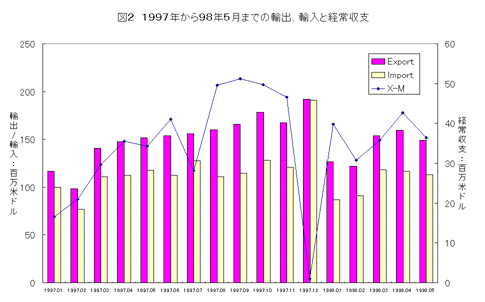
(3)価格競争力
人民元切下げ懸念の最大の論拠が輸出価格競争力の低下である。米ドル建ての輸出価格を左右するのは、対米ドル為替レートとともに人民元建ての価格である。為替レートは97年から98年にかけて、ほとんど変化がない。しかし、物価水準はもともと非常に低く、かつ現在国内の物価上昇率は急速に低下している。たとえば、タイ・バンコクの最低賃金は、日給で162バーツ、深センは、時給で1.92元。これを一日8時間、月20日として月給に換算し、98年6月末のレートで米ドル建てにすると、バンコクは64.8ドル、深センは37.0ドルとなる。中国の労働コストは、まだタイに比べ、3割安の水準なのである。一方、賃金水準に大きく影響を与える消費者物価自体も伸びが鈍化しており、98年の4月にはマイナスに転じている。この低い物価水準と物価上昇率の低下が、この時期の輸出と経常収支の悪化を防ぐ要因のひとつになっていると考えられる(図3)。
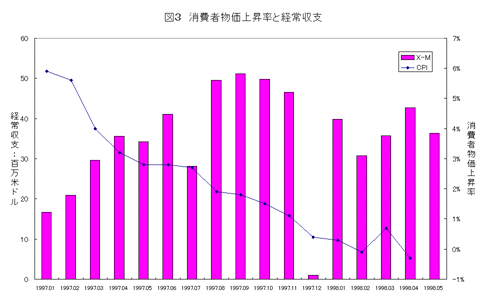
(1)内需の不振
この物価の鎮静化は、対外収支の悪化をたまたま防ぐ格好になっているが、経済全体で見た場合、デフレーションの進行を示すものであり、内需刺激策が急務となっていることを意味している。物価上昇率の低下は、まず実質金利の上昇を意味する。これは、企業の資金コストの上昇という形で投資を抑制し、また債務負担企業の利払い負担を重くする。物価の鎮静化の背景には、テレビやエアコンなどの家電、農産物など特定部門の過剰生産と過剰生産能力が原因といわれる。確かに、こうした商品に対する需要が一巡したことが、内需を不振に陥らせている。これに加え、物価が下がり始めると、消費が仮に購買したい商品の価格の下落を期待し、消費を控えるというメカニズムも働き始める。こうした状況を予防するための措置が、現在より緊急に必要とされている。
発展途上国である中国において、経済全体として生産能力が過剰であるということは考えにくい。農村部や全国を結ぶインフラの整備など、投資が必要とされる部分は大きい。こうしたインフラ整備などに向けた公共投資や優良企業の競争力拡大のための投資などを、デフレの進行が急速化する前に、実施していくことが急務のはずである。
(2)金融政策のうごき
1990年代に入って、中国政府にとってのマクロ経済コントロール政策とは、すなわちインフレの抑制であった。1995年末から内需の減退が始まっていたにも関らず、インフレ抑制のマクロ政策スタンスが変更されなかったことが、現在の物価と需要の急激な低下をもたらした要因のひとつといえる。図4には1995年7月以降の実質金利の推移と金利引下げのタイミングを示した。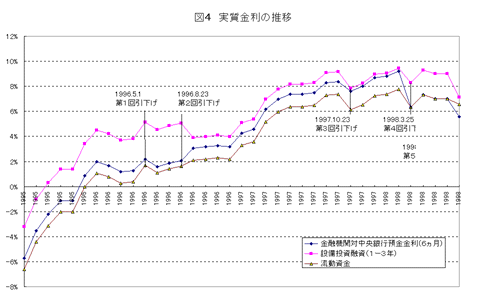
ここで、1995年秋に実質金利がプラスに転じて以降、急速に上昇していることがわかる。96年から97年の間3回の金利引下げを行なっているが、これは改革途中にある国有企業の利子負担の軽減が目的であり、景気刺激は意図していなかった。この様子が、図5に現れている。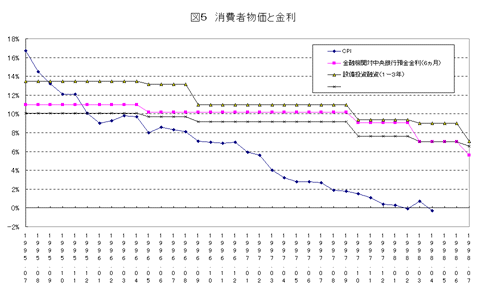
現在の金利体系では、金融機関が利益を得られるのは、非金融部門に対する設備投資向け金利、流動資金向け金利、そして中央銀行預金という3つのうちのいずれかである。図5に示した3つの金利の基準水準のうち、非金融部門の流動資金向け金利と中央銀行預金を比べると、1998年の金利引下げまでは、前者が後者を下回っていた。この大勢のもとでは、金融機関にとって、企業に流動資金を貸出すよりは、中央銀行に預金をした方がより大きな利幅が稼げるようになっていた。こうした措置がとられたのには、政府が銀行貸出の増加による景気の刺激を恐れていたことを示している。
しかし、98年に入り、3月には流動資金向け金利と中央銀行預金向け金利の水準を同レベルに調整し、98年7月には後者が前者を下回った。ここでようやく、中国政府の金融政策は、景気刺激のスタンスをとるようになったといえる。このほか、政策銀行である中国国家開発銀行もインフラ部門への融資を拡大させており、政策銀行を通じた景気の刺激も意図もしている。
このように、98年7月にいたってようやく本格的な内需拡大のスタンスに中国政府は転じた。これによる国内投資の拡大が見込まれる。一方で、現在アジア諸国および日本の景気減退からこうした地域の中国産品への輸入需要が減退していることはあきらかである。こうした需要自体が縮小している状態では、為替による物価調整による輸出刺激の効果は、あまり期待できないことを意味している。つまり、外需の振興のために為替レートという政策変数を調整するよりは、利子率を低くすることで内需を刺激することが、より緊急性が高いのである。すでに中国政府は、内需拡大による8%成長の達成という道筋に向けて、手を打ちはじめている。経済効果が薄く、また経常収支の悪化がみられない現在、緊急性の低い為替引下げを行なう可能性は、非常に少ない。
中国は、輸出競争力の減退に耐えられず、人民元を引下げ、アジア通貨はまた混乱に陥る、というシナリオを恐れる論調がある。これに対し、朱総理を始め中国政府高官は、この一年辛抱づよく否定を繰り返してきた。この中国側の発言を見ると、「人民元は切り下げない(中国語で人民幣不偏値)」というよりも「人民元は切り下がらないだろう(おなじく人民幣不会偏値)」というニュアンスの方が強かった。これは、外需が現在の経済不振の原因ではない、というマクロ経済の状況を認識した上での発言でもある。またアジア通貨危機が起きた当初は人民元の切り上げ圧力があることを強調していた。このように、人民元に対する中国政府の声明は、面子のためだけというより、現状の経済情勢を素直に述べたものと考えるべきであろう。
しかし、中国の人民元は、あくまで政策変数であり、切下げには、制度的なコストはかからず、今後政府の政策スタンスに変更が生じる可能性はある。それは、どういう場合であろうか。
まず第一に、景気が拡大して物価が上昇しはじめ、インフレ傾向になった場合である。北京の専門家の間では、中国において金利の引下げが経済に効果をもたらすまでには、約3ヵ月かかるのが通常である、といわれている。これに従えば、景気が上向きかつインフレ傾向になるのは99年に入ってからと考えるのが妥当であろう。
第二に、輸出および経常収支が急激に鈍化・悪化した場合である。これには、為替によってコントロールできる輸出価格の他、輸出国側の景気動向と、中国側の輸出産品の構成と質という3つの要素が絡んでくる。一番目の輸出価格については、内需の回復が見られるまでは、上述のように人民元建ての物価の激しい上昇は見られず、99年もこの経路の圧力は薄いと考えられる。また、需要についてはアジア、日本、アメリカの景気動向が大きく左右することになるが、全般に急激な拡大が予想されない。世界全体の大幅な景気減退がおきた場合、輸出が大きく減退するのは不可避であろう。しかし、こうしたケースに陥った場合、為替の切下げという手段がどれほど有効かは疑問である。
三番目の要素は、前二者と異なり、中国の産業高度化がどこまで進んでいるか、という構造的な問題である。輸出産品構成の高度化が遅れ輸出不振に陥った、タイやインドネシアと大きく異なり、中国の製造業部門は、関税などの保護を受けながら、生産能力の高度化を進めてきた。例えば、テレビやエアコンといった家電製品は、シェアの上位を国内企業が占め、国外への展開を開始している。国内市場において、低価格の強みを利用したてではあるが、外資との競争に勝つ段階に至っている。また通信部門で、2000人にのぼる研究者と8億元の研究開発費を投入し、電話交換器、GSM(携帯電話の欧州規格)の基地局を自力で生産化し、エリクソン、モトローラと国内市場での競うレベルに達した民営企業もある。こうした例は、最先端の一部分ではあるが、20年の改革開放政策を経て、国際競争に参加するのにもう一歩の企業が存在していることが、中国の強みであるのは間違いない。
以上から、人民元の為替レートは、現在の水準がマクロ経済全体からみて妥当な水準にあると考えるべきで、突発的な切下げがおきる可能性は低いといえよう。景気が上向き、インフレ基調に転じた時が、切り下げ時期となるとかんがえられるが、この局面に至るには、まず内需の振興という課題が解決された後となり、もうしばらく時間がかかると考えるべきであろう。
| 今号のトップ | メインメニュー |