
(学習院大学経済学部教授)
| 特 | 集 | 論 | 文 |
 |
奥 村 洋 彦 (学習院大学経済学部教授) |
|
図表1 民間企業設備投資の推移(実質・1990年基準) | |
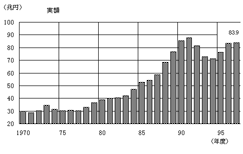 |  |
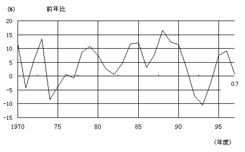 |  |
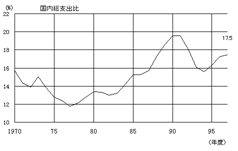 |  |
| 資料:経済企画庁「国民所得統計速報」、「国民経済計算年報」 | |
| 調査時点 | 見通し(注) | 現実の中期成長率 | 現実−見通し | 設備投資 対前年度伸び率 |
| 1986年2月 | 3.4 | 4.6 | 1.2 | 3.2 |
| 87年1月 | 2.7 | 5.1 | 2.4 | 7.9 |
| 88年1月 | 3.2 | 5.3 | 2.1 | 16.5 |
| 89年1月 | 3.7 | 4.4 | 0.7 | 12.3 |
| 90年1月 | 3.8 | 3.0 | -0.8 | 11.3 |
| 91年1月 | 3.5 | 1.3 | -2.2 | 2.7 |
| 92年1月 | 3.4 | 0.5 | -2.9 | -7.2 |
| 93年1月 | 3.0 | 1.3 | -1.7 | -10.4 |
| 94年1月 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | -2.5 |
| 95年2月 | 2.2 | 1.9 | -0.3 | 7.4 |
| 96年1月 | 2.0 | 9.1 | ||
| 97年1月 | 1.8 | 0.7 | ||
| 98年1月 | 1.4 |
| 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | |||||||
| 当初 | 補正後 | 当初 | 補正後 | 当初 | 補正後 | 当初 | 補正後 | 当初 | 補正後 | 当初 | 補正後 | 当初 | |
| 中央政府 | 8.2 | 9.8 | 8.6 | 12.5 | 9.0 | 10.5 | 9.3 | 14.2 | 9.7 | 11.1 | 9.8 | 11.0 | … |
| (対前年度当初比) | - | 25.9 | 4.8 | 52.6 | 4.9 | 22.2 | 4.0 | 55.0 | 4.0 | 18.6 | 1.3 | 13.4 | |
| (対前年度補正比) | - | - | -13.0 | 26.7 | -27.9 | -16.1 | -10.7 | 35.4 | -31.4 | -21.9 | -11.1 | -0.9 | |
| 地方政府 | 19.8 | 23.0 | 21.9 | 28.2 | 22.4 | 23.0 | 25.3 | 29.7 | 25.9 | 26.7 | 26.0 | 26.0 | … |
| (対前年度当初比) | - | 21.4 | 10.5 | 42.2 | 2.0 | 4.9 | 13.0 | 32.9 | 2.6 | 5.5 | 0.3 | 0.3 | |
| (対前年度補正比) | - | - | -4.4 | 23.0 | -20.7 | -18.1 | 9.8 | 29.2 | -12.7 | -10.1 | -2.6 | -2.6 | |
| 財政投融資 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | … |
| (対前年度当初比) | - | 17.6 | 12.4 | 20.0 | -4.3 | -3.6 | -8.6 | -7.0 | -3.0 | -2.0 | 0.2 | 0.2 | |
| (対前年度補正比) | - | - | 5.9 | 13.1 | -10.4 | -9.8 | -9.3 | -7.7 | -4.7 | -3.7 | -0.9 | -0.9 | |
| 公共事業関係予算総計 | 33.2 | 38.4 | 36.4 | 46.7 | 37.0 | 39.1 | 39.8 | 48.9 | 40.6 | 42.8 | 40.8 | 42.0 | 37.0 |
| (対前年度当初比) | - | 19.0 | 9.4 | 40.5 | 1.6 | 7.6 | 7.6 | 32.2 | 2.2 | 7.5 | 0.5 | 3.4 | -9.3 |
| (対前年度補正比) | - | - | -5.3 | 21.6 | -20.9 | -16.3 | 1.6 | 24.9 | -16.9 | -12.5 | -4.7 | -1.9 | -11.9 |
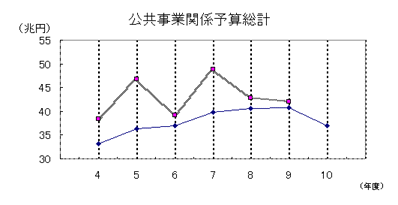
| 項目 | 1991 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 民間消費 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | -0.7 |
| 民間住宅 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 0.7 | -1.1 |
| 民間企業設備 | 0.5 | -1.4 | -1.9 | -0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.1 |
| 公的固定資本形成 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | -0.6 |
| 純輸出 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | -1.0 | -0.4 | 1.5 |
| 輸出等 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| 輸入等 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -1.0 | -1.5 | -1.0 | 0.3 |
| GDP | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 3.2 | -0.7 |
| 項目 | 1996 | 97 | 98 | |||||
| 4〜6 | 7〜9 | 10〜12 | 1〜3 | 4〜6 | 7〜9 | 10〜12 | 1〜3 | |
| 民間消費 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | -3.2 | 1.0 | -0.6 | 0.1 |
| 民間住宅 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | 0.1 |
| 民間企業設備 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.9 |
| 公的固定資本形成 | 0.4 | -1.3 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| 純輸出 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | -0.4 |
| 輸出等 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | -0.5 |
| 輸入等 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| GDP | 0.1 | -0.4 | 1.1 | 2.0 | -2.8 | 0.8 | -0.4 | -1.3 |
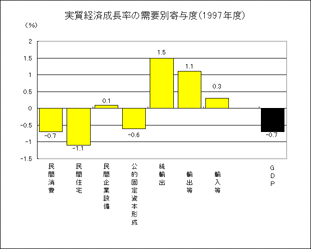
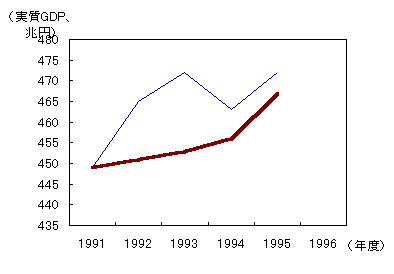
| → | 消失付加価値 約44兆円 | → |
1.契約型貯蓄の積立不足 2.財政の不健全化 3.金融機関の不良資産増大 =企業経営の不健全化 4.潜在失業の増大・就職機会の喪失 5.対外黒字の高水準持続 |
| FY | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| 目標(%) | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 2.8 |
| 実績(%) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 2.8 |
| 差(兆円) | 14.0 | 18.5 | 6.6 | 4.9 |
図表6 米国における産業別雇用者数の増減状況(1986-2006年)
【備考】 サービス業の内訳
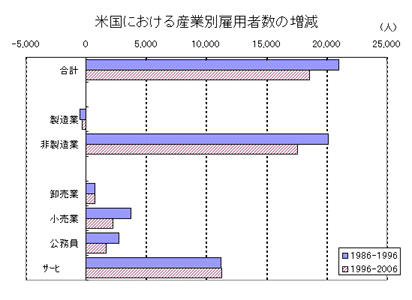
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今号のトップ | メインメニュー |