−岐阜県の景気分析−
 | 三井 栄 (岐阜大学地域科学部) |
| 特 | 集 | 論 | 文 |
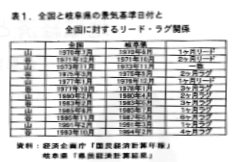 表1は、経済企画庁のマクロレベルの景気基準日付と岐阜県統計調査課が作成した景気基準日付のリード・ラグ関係を比較したものである。1975年の第1次石油危機以降は全国に対し岐阜県の景気は全般的に遅行傾向にある。さらに、景気の山では±1〜2ヶ月のタイミングのずれが生じており、谷に関しては1975年以降はすべて遅行しておりその度合いは年数とともに広がる傾向にある。岐阜県の谷についてはDIの一致指数の動きで景気が上昇する時期よりも景気基準日の付け方自体が遅れる傾向にある。また、1975年以降の経済活動別国内総生産と岐阜県の経済活動別県内総生産の構成比を比較してみると、全国レベルでは製造業の比率は減少し、サービス業の比率が増加しているのに対し、岐阜県では製造業の減少の程度もサービス業の増加の程度も緩慢であることがみられる。景気基準日付は総体的な経済活動から判断されるため、サービス業と製造業が全産業にしめるウエイトの違いが景気基準日付、つまり、全国と岐阜の景況感のタイミングがずれる原因の1つであり、時間の経過とともに経済構成にしめるウエイトに開きが見られるため、ずれの度合いが大きくなっていると考えられる。
表1は、経済企画庁のマクロレベルの景気基準日付と岐阜県統計調査課が作成した景気基準日付のリード・ラグ関係を比較したものである。1975年の第1次石油危機以降は全国に対し岐阜県の景気は全般的に遅行傾向にある。さらに、景気の山では±1〜2ヶ月のタイミングのずれが生じており、谷に関しては1975年以降はすべて遅行しておりその度合いは年数とともに広がる傾向にある。岐阜県の谷についてはDIの一致指数の動きで景気が上昇する時期よりも景気基準日の付け方自体が遅れる傾向にある。また、1975年以降の経済活動別国内総生産と岐阜県の経済活動別県内総生産の構成比を比較してみると、全国レベルでは製造業の比率は減少し、サービス業の比率が増加しているのに対し、岐阜県では製造業の減少の程度もサービス業の増加の程度も緩慢であることがみられる。景気基準日付は総体的な経済活動から判断されるため、サービス業と製造業が全産業にしめるウエイトの違いが景気基準日付、つまり、全国と岐阜の景況感のタイミングがずれる原因の1つであり、時間の経過とともに経済構成にしめるウエイトに開きが見られるため、ずれの度合いが大きくなっていると考えられる。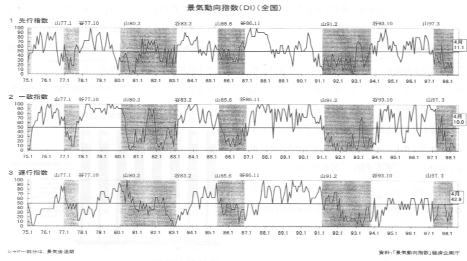
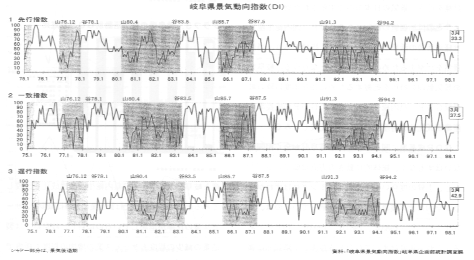
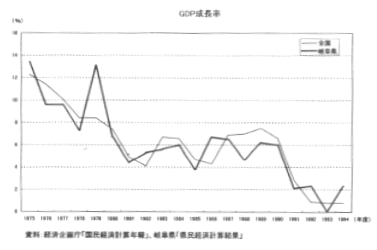 GDP成長率に関して、全国と岐阜県が全く相関がないはずもなく、総体的に動きの方向は似ている。しかし、上昇の度合いや上下のタイミングにはずれもあり、全国に比べ岐阜の成長率が上回っているのは、1976年、1980年、1983年、1987年、1993年、1995年である。これら年度はすべてGDP成長率の下降局面に属し、特に1980年は全国のGDP成長率の動きに反し、岐阜県のGDP成長率は大きく上昇している。ただし、GDP成長率から景気の強弱をみると、基本的に全国レベルの景気水準は高く、1980年を除けば、山は全国レベルの方が高く、谷は岐阜県の方が深い。
GDP成長率に関して、全国と岐阜県が全く相関がないはずもなく、総体的に動きの方向は似ている。しかし、上昇の度合いや上下のタイミングにはずれもあり、全国に比べ岐阜の成長率が上回っているのは、1976年、1980年、1983年、1987年、1993年、1995年である。これら年度はすべてGDP成長率の下降局面に属し、特に1980年は全国のGDP成長率の動きに反し、岐阜県のGDP成長率は大きく上昇している。ただし、GDP成長率から景気の強弱をみると、基本的に全国レベルの景気水準は高く、1980年を除けば、山は全国レベルの方が高く、谷は岐阜県の方が深い。| グラフ2、3で、1975年以降の経済活動別国内総生産と岐阜県の経済活動別県内総生産の構成比を比較してみると、全国レベルでは製造業の比率は減少し、サービス業の比率が増加しているのに対し、岐阜県では製造業の減少の程度もサービス業の増加の程度も緩慢であることがみられる。こういった各産業の構成比の違いが全国レベルと岐阜県の経済成長率と構造自体に変化をもたらし、景気変動の強さとそのタイミングが異なる一因であると考えられる。 |
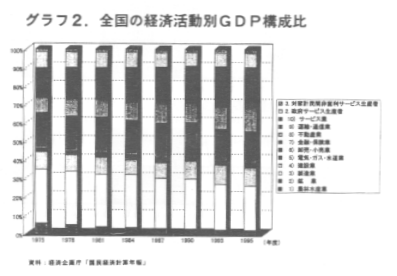 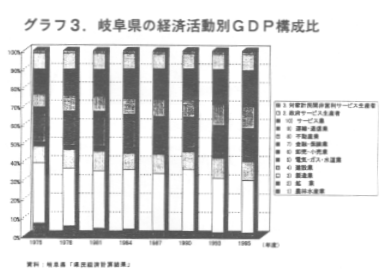
|
| さらに、各産業の成長率の比較を行う。GDP成長率の動きで全国レベルと最も違いが見られた1980年の岐阜県の産業成長率に注目すると、鉱業と不動産業以外はすべて全国の産業成長率を上回っている。そのうち、製造業、電気・ガス・水道業、卸売・小売業は全国レベルの上昇率を上回る形となっている。この3産業で岐阜県GDPの構成比の半分程度を占めるため、岐阜経済に与える影響が大きいことがうかがわれる。すなわち、岐阜県の景気の強さはこれらの産業の上昇や落ち込みの程度に依存する。 |
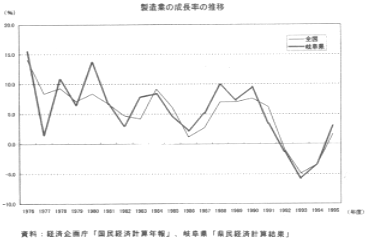 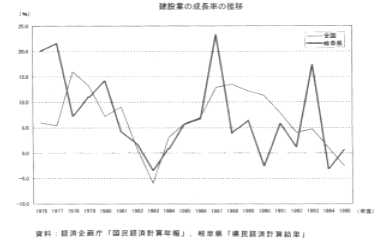 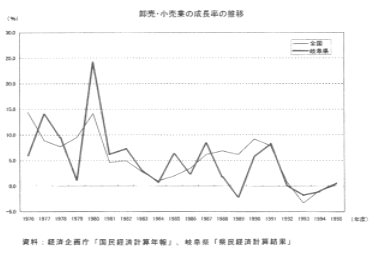 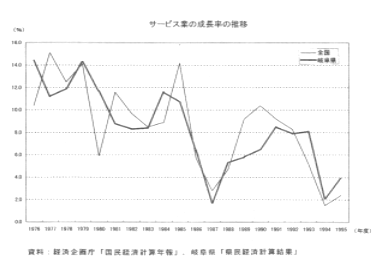
|
|
全体的な構成比の特徴としては、鉱業、製造業、建設業、卸売・小売業の構成比が高く、金融・保険業、サービス業は低いことがあげられるが、こういった産業とDIの変動で対応させた景気動向との関係を比較する。製造業は成長率についても総体的に高いため、その伸びが大きいときは岐阜県の全般的な景気動向は良くなっている。建設業の成長率の動きは、景気後退期における景気動向と似ているが、不況時の景気対策で公共投資などが行われることが影響しており、タイム・ラグを持った形で景気上昇期に突入している。また、こういった政策は全国レベルよりも効果が見られるようだ。卸売・小売業については1980年代は構成比が高いため、その成長率は岐阜県の景気への影響は大きかったが、90年代にはいると構成比の成長率も全国レベルと差がなくなっている。次に、全国レベルでは1977年、1979年、1981年、1985年、1989〜91年といずれも景気上昇局面とサービス業の成長率が高い時期が一致しているが、岐阜県の産業の中でサービス業は構成比が低いため、両者にはずれが生じており、岐阜県の景気動向へのサービス業の成長率の影響は比較的薄いようだ。 一方、各産業全般的に見て、岐阜県は成長率の山と谷の変動が激しく、山の高さと谷の深さの格差が大きいため、集計したGDP成長率に関しての全国レベルよりは多少低い水準で山と谷の変動の回数が多く、悪いときの落ち込みは激しい。 |
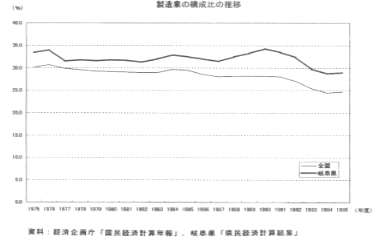 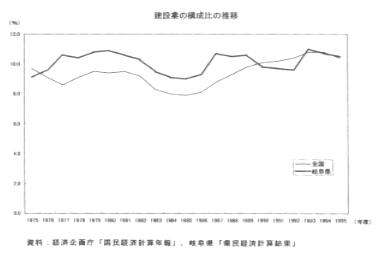 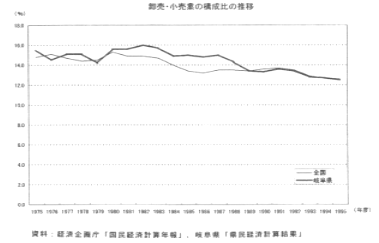 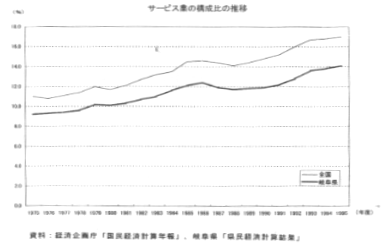 |
| 今号のトップ | メインメニュー |