
岐阜2020委員会に参加して
名執 潔
(名古屋大学工学系研究科助教授)
| 特 | 集 | 論 | 文 |
 |
岐阜2020委員会に参加して名執 潔
(名古屋大学工学系研究科助教授)
|
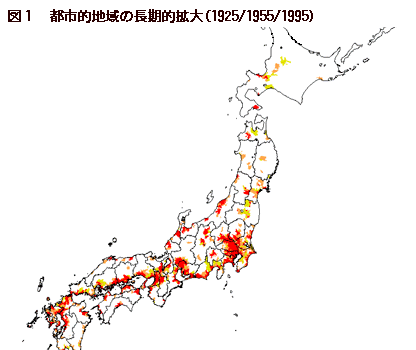 大陸から稲作がもたらされて以来の、我が国における人口集積の動向をみると、ほぼ一貫して九州から東方向へ、東京へと伸びてきたことが知られている。20世紀後半に至り、福岡から大阪・名古屋を経て東京に達する都市的地域の連たんは概ね完成し、さらに東京から東北方向へと急速に伸びつつある(図1)。この前者がいわゆる「第一国土軸」、あるいは「西日本国土軸」であるが、岐阜はこの軸のほぼ中心に位置することになる。
大陸から稲作がもたらされて以来の、我が国における人口集積の動向をみると、ほぼ一貫して九州から東方向へ、東京へと伸びてきたことが知られている。20世紀後半に至り、福岡から大阪・名古屋を経て東京に達する都市的地域の連たんは概ね完成し、さらに東京から東北方向へと急速に伸びつつある(図1)。この前者がいわゆる「第一国土軸」、あるいは「西日本国土軸」であるが、岐阜はこの軸のほぼ中心に位置することになる。 東京への通勤・通学者が10人以上居住する市区町村の分布をみると全国に展開しており(図2)、日本全国すみずみまで「東京」になったとも言えるが、逆に、東京居住者の通勤・通学者も全国に展開しているのであって、いわば岐阜をはじめ全国各地が少しづつ東京を構成するような、相互に影響を与え合う関係が、特にそれが第一国土軸の上で強く、先行的に進行しつつあるものと考えられる。
東京への通勤・通学者が10人以上居住する市区町村の分布をみると全国に展開しており(図2)、日本全国すみずみまで「東京」になったとも言えるが、逆に、東京居住者の通勤・通学者も全国に展開しているのであって、いわば岐阜をはじめ全国各地が少しづつ東京を構成するような、相互に影響を与え合う関係が、特にそれが第一国土軸の上で強く、先行的に進行しつつあるものと考えられる。図3 10代後半の若者の増減(1990→1995)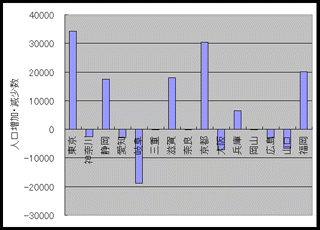 |
| 今号のトップ | メインメニュー |