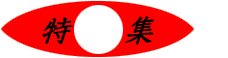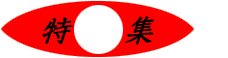
平成7年度調査研究
岐阜県農産品の首都圏市場への販売万策
第1章 首都圏市場における岐阜県産品の現状
1 岐阜県産青果物の現状
岐阜県農産品の県外仕向地は、名古屋、関西方面市場への出荷のウエイトが大きく京浜市場への出荷は、果実類では「カキ」が主力。野菜では「夏ホウレン草」「夏秋トマト」があるがまだ少量でシェアは低い。
- 果実類
日本人の果実消費量は昭和40年代後期をピークに20〜30%減少している。そうしたなかで、「カキ類」の東京中央卸売市場における取扱高は50年代初めに比べ少なくとも20%前後増加している。内訳をみると、昭和50年代の初めには東京市場で取り扱われた「カキ類」のうち65%前後が「富有」であり、天然の甘カキが全体の約8割近くを占めていたが、近年は各種脱渋技術の発達により、「平核無」のシェアが増加しており、ここ数年は
「富有」を抜き40%を超える。
岐阜県産「カキ類」の東京市場への出荷量はここ20年ぐらい4,000〜5,000トンを上下して、傾向的には大きな変化がない。岐阜県産「富有」の最盛期である11月について、価格面での優位性は維持されているものの、「富有」と奈良県や和歌山県産の「平核無」の価格差は以前に比べ随分縮まってきており、年によっては「平核無」の単価が高い場合もある。
- 野菜類
岐阜県産の野菜類は東京市場においては平成6年の統計では、数量1,330トン、卸売金額6億4,300万円余であり、産地別では数量で42位、金額で41位、シェアでは数量・金額とも全体の0.1%を占める小産地である。平成5年との対比では数量、金額とも35%もの成長をしており、品目により特徴的な伸長傾向が見られる。
例えば、平成6年の猛暑で関東地区でも需要が逼迫した際に、入荷が増加したことが、京浜市場での岐阜産ホウレン草の認識を高めた。また、トマトは入荷シェアでは0.7%ながら、県別の平均単価ではトップの産地となっている。
2 岐阜県産和牛の現状
子牛成績は、岐阜県内市場で、「安福」産子を中心に高価格で取り引ききれており、出荷価格で全国平均を大きく上回る。枝肉成績では、枝肉重量は全国平均の420kgに比較すると398kgと小さいが、脂肪交雑7.4(全国平均5.5)、肉質等級4.3(同3.6)とも全国平均を大きく上回っている。
平成6年の東京市場での牛取引頭数は134,775頭で、前年より1,636頭(1.2%)増加した。
産地別の出荷状況を見るとメスでは宮城県が4,921頭(17.1%)とトップで岐阜県からの出荷はない。去勢では栃木県が7、921頭(19.5%)でトップ。岐阜県からは4頭。
第2章 首都圏市場における岐阜県産品評価
1 京浜地区の卸売市場における評価
「価格を基準に出荷している」、「相場によって細かな分荷をしすぎる」点を指摘する声が強い。京浜市場への出荷量が少なく、安定出荷が確保できないという意味で
「客が固定しない」とみられている。
「富有柿」については大玉がギフト用に回り、市場入荷が少ないとの指摘が青果卸売会社からあった。近年人気の「平核無」への転換が進んでいないのは、岐阜県では総合的判断で「甘柿振興」を打ち出しているからだということはあまり知られていないようだ。
2 京浜地区の小売店、業務需要における評価
- 野菜類・果実類
スーパー(10社)、生協(3組織)、青果店(3店)、カット業者(2社)、外食企業(3社)へのアンケート調査結果
- 岐阜県産野菜・果実に関するイメージ
全体を通して「首都圏の流通量が少なく印象が薄い。」と言ったコメントが多く、イメージが浮かばないようだ。
- 岐阜県野菜・果実の取扱い状況
トマト、シメジ、官有柿などの評価はわるくないが、”まずまずの品質にはまずまずの価格”ということで「レギュラーの扱いではなくスポット扱い」である。
- 岐阜県産野菜・果実品目に対する要望
全ての業態で、「どうしても岐阜産でなければならない商材ではないので、とくに希望はない」という状態。
- 岐阜県産野菜、果実を首都圏でアピールするための方策
「市場での流通量を増やすことが第一」(スーパー)、 「安全性(無農薬、低農薬)をアピールすること」(生協)、 「岐阜県でなければできないものを使用した料理メニューの提供」(外食企業)など。
- 地方特産品に関する意見等
「最近これと言った地方特産品がなく、全国的に生産物が均一化しているので、当該産地しかない品質の野菜、果実を市場で流通させることが必要」
- 岐阜県産和牛
京浜地区の主要なデパート、スーパーの精肉担当者からの飛騨牛の認知度をヒアリングを行ったところ、ほとんどの人が「名前だけは知っている」程度である(今回の調査対象の中では、東急ストア1店だけが販売を手がけていた)。扱っている銘柄牛は、松阪牛のみ(デパート2店)、松阪牛と米沢牛、十勝牛(デバート1店)、神戸牛と上州牛(デバート1店)、神戸牛と山形牛(デパート1店)、近江牛と仙台牛(デパート1店)、地方銘柄牛単独は、山形牛、越後牛、宮崎牛(スーパー各1店づつ)であった。
「飛騨牛」は三大銘柄牛(松阪、神戸、近江)には代替しないが、それに組み合わせる地方銘柄牛は特別な理由があって採用されているわけではないため、代替できる可能性がある。
第3章 岐阜県農産品の生産・流通・販売振興対策
1 岐阜県の園芸特産振興方針と首都圏対策
- 基本目標
- 銘柄産地・産品づくり→作り上手のリード
「コストは低く、品質は高く、儲けは大きい」
- 流通づくり→売り上手のリード
「より良い物、より値打ちに、いつでも」
- 産消交流、環境、安全づくり→消費者、需要者と環境と共生のリード
「美しい、温かい、面日い」
- 首都圏における岐阜県産農産物の販売促進対策
- 流通
- 情報活動の強化
- 有利販売の促進
- 多元販売の促進(新流通ルートへの対応)
- 低温流通システムの促進
- 県内卸売市場の活性化と域内消費体制づくりの促進
- 消費対策
- 消費宣伝の強化、消費者対策
- 指定店舗販売強化による販路拡大
- 食品産業との連携
- クリーン農業の推進
2 今後の農産物振興に向けての提言
- 野菜類や牛肉などでの「岐阜らしい食べ方」の提案を行うための方策・外部専門家等による「岐阜料理」レシピー開発
- 「岐阜料理」の開発と提供を行っている外食業者や食品メーカーに対する支援
- 「岐阜料理」新レシピーの強力な広報活動の実施・学校給食に対する県産品利用推進のための方策
- 岐阜県産品の差別性のアピール
- 県内生産者、県内流通業者と首都圏の市場、流通業者との差別化検討会等の設置
- 専門家による差別化を具体化するための調査研究の実施
- 首都圏におけるテイストテストの実施
- その結果の強力な広報活動の実施
- 仕向け先別(消費地別)の適正需要量の測定
- 卸売市場において常に有利な販売を行うための適正量の掌握
- 需要別、用途別の需要を測定する(一般消費用、ギフト用、業務用、加工用等)
- 岐阜県産農産物のニーズを探り適正なチャンネルを開発する。とくに量販店、生協などとの契約、提携の可能性とその条件を検証する。
- 岐阜県産農産物の消費拡大対策の樹立
- 地場牛産の振興とそれに連動する地場消費のためのシステムや制度の樹立
- とくに果実類に対し、地場並びに首都圏の若年層の消費を誘導するための方策の検討、実施
- 岐阜県産農産物の販売システムの改善
- JAの共販事業の方法が見直しの時期となっているため、拠点重点市場の設定など、卸売市場の「育成」をするよう、日々頻繁な出荷コントロールを見直すための対策
- JA系統販売事業に、「系統直販」部門を設置するための対策
- 宅配などダイレクトマーケティングの過度な振興の抑制
3 岐阜県産和牛の首都圏対策
- 東京食肉卸売市場の価格形成において指導的立場にある仲卸業者など関係者に、岐阜県の和牛生産、製品枝肉をみてもらう。
- 販売促進のための企画や催し物を投入して、小売店が”売りやすい”状況を作ってあげる。
- 岐阜県和牛がどんな料理に向くのか、すなわち、すき焼き、しゃぶしゃぶあるいはたたき用なのか、ステーキ用なのかを産地側から明確に提案する。
- スーパーなり料理店、あるいはそれらに納める問屋のニーズに合わせて、安定した品質のものを、望ましくは消費者の近づき易い価格で、安定供給していく。
第4章 岐阜県産和牛(飛騨牛)のPR戦略に関する提言
1 飛騨牛に関する認知度調査結果
「飛騨牛の認知度」、「食事経験の有無」、「食べた感想」等についての日本リサーチセンターによるアンケート調査結果。
- 牛肉銘柄へのこだわり
”こだわり派”(「こだわる方」、「まあこだわる方」)が3.1%、”非こだわり派”(「あまりこだわらない」「こだわらない」)が76.4%と非こだわり派が圧倒的に多い。
- 飛騨牛の認知度
全体では約4割の人たちが知っていると答えている。地域別では、中部・北陸地方の「知っている」の73.7%は当然であるが、関東、近畿地方で約6割、北海道・東北、中国・四国・九州では8割の人たちが「知らない」。年齢別では10代、20代で「知らない」が約7割を超える。
- 飛騨牛の食事経験
飛騨牛を知っている約半数弱(44.8%−調査サンプル全体では18.3%に相当)が飛騨牛を食べた経験がある。年齢別では、五〇代を除く各年齢層ごとに、約6割前後の人たちが「食べたことがない」と答えている。
- 飛騨牛を食べての感想
すべての属性で「おいしかった」、「まあおいしかった」と感じた人たちは9割を超える。その中で、「18.19歳」の層での「あまりおいしくなかった」とする答え(25.0%)が目を引く。
2 飛騨牛のPR戦略に関する提言
- 著名料理家による新しい飛騨牛料理の開発及びレシピーブックの製作・配布
- 広報メディア(雑誌・テレビ)を活用したPR活動
- FHJ(全国高等学校家庭クラブ連盟)を中核とした飛騨牛購買予備軍(10代男女)を対象としたPR活動
飛騨牛に対する認知度が低く、飛騨牛の食事経験が少ない、将来の購買予備軍ともいえる10代の男女を対象としたPR活動
- 機関誌FHJ誌別冊付録の作成
- 「高校生飛騨牛コンテスト」の実施
情報誌「岐阜を考える」 1998年冬・春合併号
岐阜県産業経済研究センター