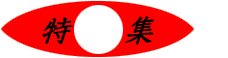
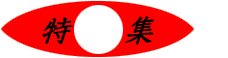
 |
企業間協力による ロジスティックスシステム高度化の方向 忍田和良(朝日大学経営学部教授) |
ロジスティックス活動の基本目標は産業の高度化と国民生活の豊かさを支援することにある。流通の川下化動向を前提とし、豊かな品揃え、生産から消費に至るサイクルタイムの短縮、トータル在庫の削減等が基本課題となっている。加えて、これらへの対策を低コストでしかも生活環境を保全しながら効率的に実現することが求められている。
1.ロジスティクシステム構築・改善の課題
ロジスティックス活動は高度で多様な需要に応えなくてはならない。この課題間にはトレイドオフ(二律背反)関係にあることが多く、その対応はロジスティクス部門に止まらず生産・販売も含めた全社、そして他社間協力へと拡大している。従ってこの解決は決して容易でないことが多い。反面、これらへの挑戦によってシステムを高度化してきたともいえる。
輸送費と保全費等を総合したトータルロジスティクス費用の削減、トータルロジスティクス費用と納品サーヴィス水準の調和を考慮したロジスティクスシステム全体の効率化、ロジスティクスシステム全体の効率化と企業全体の効率が追及されてきた。さらに、全社効率と社会的課題への対応によって企業の長期的な安定を図ること、これが今後の課題である。これらトレイドオフ関連にある課題それぞれに基本的な事例がある。
1.1 輸送費と保全費等を総合したトータ ルロジスティクス費用の削減
ロジスティクス拠点の集約によって、在庫の圧縮、小分・値付け等の流通加工が効率化される。反面、配送距離は延長しコストは増大する。これらを総合して拠点数・立地が決定されることとなる。なお、多品種・少量化が進展するほど一般的にこの集約効果が高まるため、流通各段階での拠点の集約・高度化が進展している。
1.2 トータルロジスティクス費用と納品 サーヴィス水準の調和を考慮したロジステ ィクスシステム全体の効率化
この効率化には次段階の効果を考慮した対策が欠かせない。例えば、流通センターにおける検品の自動化によって、自動化のシステム費用は増加するものの納品精度の高度化と配送車の回転効率が向上する。検品効率を高めるにはやはり取扱量の増加が必須であり、拠点の集約、企業間協力が効果的である。
1.3 ロジスティクスシステム全体の効率 化と企業全体の効率の追及
衣料品のハンガー輸送化が大型小売店で推進されている。これによって配送センターでのピッキングや店頭陳列の効率は劇的に向上する反面、配送効率は二分の一に低下する。ロジスティクスシステム全体の効率は低下しても販売促進は向上し、トータルとしては効果を挙げることになる。
また、卸売企業等が推進している取引先の小売店活性化支援(リテイルサポート)がある。小売店での品揃え、店頭陳列や発注情報処理、納品効率の向上等を支援するものである。さらに、納品業者のセンターから小売店へ店の棚順序に品揃えして出荷し、陳列効率の向上を図る製造業者と小売り業者の戦略同盟も展開している。
1.4 全社効率と社会的課題への対応によ る企業の長期的な安定
ロジスティクス活動に関する社会的課題には輸送に伴う排気ガスや包装資材等の回収・再生等がある。排気ガス対策としては輸送の企業間共同化によるロジスティクス交通量の削減が最も実効的である。この方策によって輸送費用の削減にも通ずるからである。
このような多様なトレイドオフ関連課題に対する共通的な基本方策としては、高度化を重ねている情報機能のフル活用とともに企業間協力が決め手となる。
2.企業間協力のパターン
一企業の枠を越えた企業間の協力には次の四つの類型がある。その一つは取引企業間の垂直統合であり、その二はこの統合が高度に発展した製造業者と流通業者との同盟によるサプライチェーンの形成である。その三は製造業者・中堅の卸売業者における同業間の水平統合であり、さらに階層的に配置されたノード・リンクを多主体によって広域的に展開されるネットワークの構築がある(表1)。
表1 企業間協力のパターン
| 類 型 | 事 例 | 推進主体 | 優れている点 | 問 題 点 | 行 政 |
|---|---|---|---|---|---|
| 垂直統合 | カンバン納品 | 製造業 | 迅速な実現 | 購入優位濫用 | 公取委 |
| ベンダー納品 | 小売業 | ||||
| 供給連鎖 | 製販同盟 | 製造・小売業 | 資源有効活用 | 品揃えの偏り | |
| 配販同盟 | 卸・小売業 | 他社排除 | |||
| 水平統合 | 小売店支援 | 卸売業 | 効率性大 効率性大 |
対象の拡大 情報漏洩防止 |
資金援助 |
| 返路活用 | 製造業 | 迅速な実現 | 統一・標準化 | ||
| 網状統合 | パレットプール | 第3セクター | 参加自由 | 全体的な統一 | 設立援助 |
| 動・静脈一体化 | 第3セクター | 災害対策 | 弾力的対応 |
2.1 垂直統合
売買の取引関係にある企業間で、購入者がその調達分野、すなわち製品・商品の荷受けの効率化を基本目的として構築するシステムである。この事例は、自動車組み立て工場への協力工場からのJIT納品、チェーン店に対するベンダー・センター納品に伺える。
バイイングパワーを利用した購入者が主導するためにその迅速な実現性に優れている反面、優越的地位の濫用によって購入者が販売者に過度な負担を強いることがあり、公正な競争が損なわれる恐れがある。新設されるセンターフィー(料金)の負担をめぐって公正取引委員会の指導等が発動され兼ねない。
2.2 サプライチェーン
垂直統合を高度化したサプライチェーンでは、製造業者と流通業者が協力して、製品や商品の生産から消費にいたる流れを円滑する。これによって、そのサイクルタイムの短縮、在庫の圧縮、鮮度の維持、最終需要動向の把握、そして費用の削減等が可能となる。
このチェーンの構築はロジスティクス力に優れた製造業者と流通業者とが、品揃え・情報・ロジスティクス等を包含した幅広い分野での連携によって実現される。製造業者と大型小売業・チェーンストアーによる製版同盟、卸売業者と小売業者による配販同盟がその事例である。これによって消費者が発信する最終需要情報やその他の両者の経営資源の共有化が行われ、相乗効果を追及する。
2.3 水平統合
大型小売業やチェーンストアーが垂直統合や戦略同盟によって流通・ロジスティクス支配を進めるのに対し、川中に位置する卸売企業を中心に同業界にある他社、時には競争相手との協力化によって、規模のメリット追及によるロジスティクスの効率化を図っている。とくに中堅企業はその命運をこの協力化に賭けているところが少なくない。
この統合は荷姿等を同じくする商品輸送の共同化であり、経済的にも社会課題への対応においても最も効率が高い。とくに、納品先を同じくする納品業者による共同輸・配送は極めて効率的である。卸売業界での加工食品・日用雑貨・菓子等の卸売企業が連携して小売店を支援するサポートシステムもこの典型的な例である。
最も効率の良いシステムである反面、参画企業を拡大し取扱量を増大することがこの効果を実現するための必須条件である。そのためには、取引内容に関する情報漏洩の防止を始め、力のある推進企業の存在、受発注等の情報処理や納品方式の統一化・標準化等解決すべき多くの課題がある。
また製造業においても製品輸送車の返路を同業他社の製品輸送に活用することにより費用の大幅な削減を図っている。トヨタと日産による完成車輸送に対するキャリアーカーの共同利用がその典型例である。そのほか大手ビルメーカーと洗剤メーカーとのパレット輸送、リフトローラー車による相互の返路利用もある。製品輸送に適した専用車の実車率を向上するためには、競争相手との協力も厭わない。
なお、この水平統合においては、ロジスティクス力を同じくする企業の連携が効果的である。また、「ロジスティクスは共同で、競争は商品や店頭で」の提言を行って、この水平統合を全国各地で展開している大手洗剤メーカーも健在である。
2.4 ロジスティクスネットワーク
複数企業による輸送の共同化はロジスティクス量を減少せず、ロジスティクス交通量を削減するものである。本方策は輸送コストの低減にも通じるものであり、実現性に優れた対策である。この最も発展したシステムの一つがロジスティクスネットワークである。
通信販売の宅配や、クラブ財であるパレットやコンテナのプールシステム等がロジスティクスネットワークの対象となる。このプールシステムの推進は、複数企業、時には行政も参加した第三セクターによって担われる。利用者にとってはオープンであり、参加・脱退の自由が担保され、地域・ピーク時に応じたシステムの使い分けも可能となる。反面、ネットワークが拡大するほど不採算地域が増大し、全体効率を低下させる。規模の経済が最も機能するシステムであるだけに、多くの参加が容易となるよう、利用のための簡素化、統一化、標準化、モジュール化等が必須となる。
大手外食チェーン店からの紙類回収に対して、納品車の返路やこの廃棄物の一時保管に納品センターを一時利用する等の事例がある。このように動脈におけるリンク・ノードや情報システム、すなわち製品・商品の輸送・保管システムを静脈である廃棄物処理に活用し、循環型ロジスティクスシステムを構築することが期待される。これによって、その効率化と社会的課題への対応が同時に可能となるが、その拡大はこれからの課題である。とくに全国に点在する公共ロジスティクス拠点での複数企業による共同化の推進が効果的であり、地方自治体等による支援機能が必須であり、地方自治体等による支援機能が必須であることを力説したい。
また、これら公共拠点間の連携を情報機能の支援によって高め、ネットワーク化を推進することは大災害等への弾力的対応(リダンダンシイ)も可能とする。
以上の企業連携について次のように要約し、補完しておこう。
企業連携の推進にはチャネルリーダーが担うことが多く、自動車業界に於ける組み立て製造業主導、家電・カメラ分野における製造業と小売業のバッテング、加工食品・日用雑貨品分野に於ける小売業主導等がその典型的な例である(図1)。
図1
製品別のチャネルリーダー
日通総合研究所が(社)流通問題研究協会資料より作成したもの
日通総研レポート [90年代の物流]から引用
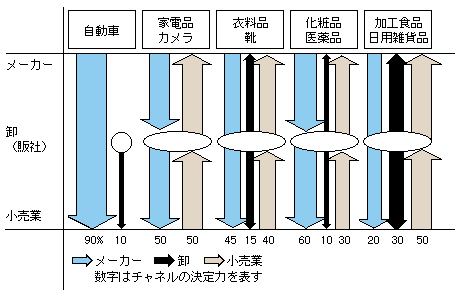
このような連携を軸にロジスティクスセクター(需要・供給者に加え関連する企業・公共主体を包括)に大きな変化が生じている。その一つは、大手製造業を中心として構築された物流子会社の活躍である。親会社の製品・商品を基盤に、加えて生産や販売活動との一体化に関して積み重ねた経験を広い分野で活用している。さらに、他の荷主に対して総合システムの設計・管理とその提案に挑戦し、既存の物流専業者の存在を脅かしつつある。また、海外からの物流も含め関連する需要者、供給者を統合し、さらに情報システム業者も包含した保冷等のネットワーク構築を図る商社の動向を見逃せない。新しいシステム間競争が形成され、ロジスティク活動の高度化を加速させている。