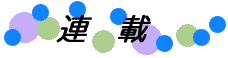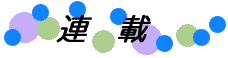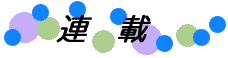
「売れて儲かる商品作り」の為に何をなすべきか(第二回)
松 久 庸 安
VEAM法とは
1 VEAM法とは、商品創造の時代に、顧客ニーズの中でもとりわけ潜在ニーズに焦点を当て、予測から顧客ニーズを発想し、従来技法にない方法で商品企画までの手順をシステム化するという考え方で創造された新しいテーマ探索法であり、VE
Analyzing system about Mask-ed need の頭文字を綴り合わせたものである。
2 VEAM法の特徴
- 今まで未検討であった潜在ニーズを顕在化することに的を絞っている。
- VE的分析法をその基礎にしており、機能(モノの働き)を重視する。
- 潜在ニーズの仮定から新商品開発企画書作成までの全体をシステム化している。
- 具体的な手順、豊富なチェックリストやワークシート
を準備し、同時にシミュレーション例によって使いやすくしている。
3 第1図にVEAM法のスケルトンを示す。VEAM法は、大きく三つのステップによって構成されており、三つのステップは「イメージ」→「仮説」→「商品コンセプト」と呼ばれる概念で繋がり、最終 出力は「新商品開発企画書」である。
第1図 VEAM法のスケルトン

4 各ステップの手法名と内容
- 顧客ニーズ発想
「よみかき法」
顧客になり代わって顧客ニーズを発想するために、三〇〇項目以上の‘発想’のためのチェックリストと‘絞り込み評価基準’により顧客ニーズの「仮説」をアウトプットする。
メンバー五人×約二時間で五〇〇〜一〇〇〇ヶの発想が出、これが約六時間で一〜三ヶの有望な仮説に絞り込まれる。
- 顧客ニーズ確認
「機能絞込み法」
多様化した顧客の欲求を正しく確認するために、その「仮説」を‘ふくらませ具体的な商品イメージとする’ためのワークシートや、顧客の容認度を調査・算出するワークシートにより「新製品コンセプト」をアウトプットする。
- 顧客ニーズ実現
「とりあわせ法」
新製品コンセプトに対する制約条件としての自社要因の
評価・対策、最適の開発手段を選択するためのワークシートなどから構成され、「新製品開発企画書」をアウトプットする。
5 商品説明及びアンケートの事例
「商品説明及びアンケートのシミュレーション事例」(第2図参照)
6 筆者意見
- VEAM法は、三〇〇項目以上のチェックリスト・一五枚のワークシート・一組調査用紙よりなる一連の新商品探索手法であり、その全貌をこの短い紙面で説明することは難しくその要点を記したにとめたため、読者には非常にお解りづらいと思われる。
一方で、手法というモノは本等をいくら読んでも分かりづらいが、実際にやってみると比較的簡単に出来、使ってみることで自然に覚えられる事が多い。
- VEAM法はまさにその典型的な例である。目標とする分野と商品イメージを決め、三〜五人のメンバーが動員できれば、馴れない内は四泊五日、馴れてくると二泊三日程度の日数で新商品コンセプト決定の為の「新製品説明及びアンケートシート」が作成できる。
- ご興味のある方は、日本VE協会又は筆者にお尋ね下さい。
<問い合わせ先>
(社)日本VE協会
東京都世田谷区等々力6−39−15
TEL 03−3704−1111
松久庸安
岐阜市長良若葉町1−5
若杉荘302号室
TEL 058−297−4440
まつひさ・つねやす
中小企業診断士(鉱工業)、岐阜県技術アドバイザー
昭和三二年東京工業大学理工学部卒業。同年富士写真フィルム株式会社入社。吉田南工場生産技術部長代理、東京本社企画部部長代理を経て、昭和六一年、生産システムセンター長に就任。富士写真フィルムグループへのVE、IE、QC等の管理技術の開発・導入を推進した。この時に使い捨てカメラ‘写ルンです’の開発も手掛ける。平成六年、富士フィルム株式会社を定年退職し、その後二年勤務後、平成八年退社。同年、コンサルタント活動を開始する。 |