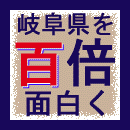
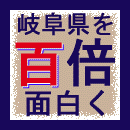 |
ちょっと派手なタイトルである。しかし東の「江戸八百町」や西の「大阪八百八橋」にくらべれば、真ん中の岐阜県を「100倍」とはささやかなものである。心配なのはむしろ話が看板倒れにならないか、ということである。 |
岐阜県の県民性には特徴がない という話
匠 照人・文
日頃から梶原岐阜県知事さんは、「岐阜県のアイデンティティ(独自性)は、日本のまん真ん中にあるということである」と言っておられるが、私にはその本当の意味が、もうひとつはっきりと呑み込めていなかった。
話はそれるが、今からおよそ520年ほど前、戦国時代に著されたとみられる、当時の日本の諸国の人々の性格を記した著者不詳の『人国記』という一書があって、これを下敷に江戸期に関祖衡という人物が、『新人国記』を著している。そして、この二つの著書が浅野建二氏の校注による『人国記・新人国記』が、岩波文庫から刊行(1985年)されている。この著書によると、岐阜県南部の美濃国は、「当国の風俗は、人の意地奇麗にして水晶の如し。されども水晶も磨がかざれば光沢なし」、つまり「美濃人は根性が良いので、垢を早くけずり落とせば、さらに良い」ということ。一方、北部飛騨国の人々は、「健直にして愚かなり。日本広しといえども、我が国に如くことなし・・・生得 は石鉄の性なり」と、簡単に言えば、「他国人には見られないほど義理がたく、バカ正直だが、根は大変な頑固者」であろう。飛騨人の私には、ずい分バカにしたものだと思うが、うなずける節もある。
ところが、そういう日本の60余州の国が、明治維新後2〜3か国を合わせて府県制になって以来、かつての諸国人の性格が少しカスンでしまったと言われている。それでも東京オリンピック以前までは、それなりの特徴のある県民性がみられたが、岐阜県では明治以後、際立った県民性がみられなくなったというのが、識者の意見なのである。
例えば、岐阜県の県民性について、昭和38年(1963)に県が調査を行っている。その結果、「伝統的とか慣習的に一般にみとめられたさまざまの社会的行動様式のなかに、保守性を基盤として、着実で勤勉で協調性をもっている」と、難しい表現でまとめているが、要するに、「保守的で人づき合いが良くて勤勉だ」ということであろう。だが、考えてみると、こうした県民性は日本の東西のどの県にでもあてはまりそうな気がする。
昭和四6年(1972)に祖父江孝男氏が調査した結果を、『県民性』(中公新書)と題して発表し、その中で、「岐阜の県民性ということになると、どうもその姿がはっきりしない。私自身も、この県内のいくつかの村や町をあちらこちら訪ねたりしているが、まだ答えが得られないでいる状態だ」と述べている。つまり「特徴がないので、困った」ということであろう。同じような意見が、もう一つ、『改訂郷土史事典−岐阜県』(昌平社・船戸政一編)に記されている。それは昭和53年(1978)にNHKが「全国県民意識調査」を行い、その結果、岐阜人の意識の特徴は、「勤倹貯蓄型の金銭観のあることと、東海道や山陽道沿いの各県と同じように郷土意識が薄い傾向にあること」、言いかえれば、「きわだったことのない県民性」だと評していることである。また、岐阜県の郷土史家の吉岡 勲氏(故人)も『岐阜県人』(新人物往来社)の中で、「岐阜県に住んでいる人びとは、自分を平均的な日本人だと思っている。・・・そうした姿勢が岐阜県の県民性である」とし、その原因を、「日本を東西に分けたとき、岐阜県がちょうど、平均台の支点にあたる位置だったことも、この性格を決定的にしてきたのである」という。つまり、岐阜県が日本列島の「まん真ん中」に位置していることに原因があるというわけである。
実は、こうした意見を証明するようなデータの一つがある。さきの船戸政一氏(現関市教育長)は、日本の仏教を浄土系・禅系・日蓮系・真言系・天台系・その他に分けて、『全国寺院名鑑』(1978年)で調査したところ、図にみられるように関東は禅系、関西は浄土系が圧倒的に多い。そこで日本のまん真ん中の岐阜県は、どうかとみると、東・中美濃は禅系、岐阜・西美濃は浄土宗に半々になっているのである。つまり日本をそのまま縮小したのが岐阜県だということである。
このように、岐阜県の県民性は日本の中央にあるゆえに東西の社会・経済・文化の影響に押し込まれて、「きわだったことない県民性」だとして、自他ともに是認してきたのではないだろうか。つまり、日本のまん真ん中にあることが、「どうにもならない負の存在」としてあきらめてきたのではないだろうか。
ところが、梶原知事は、この「負の存在」を逆手にとって、「正の存在」に置きかえた。すなわち、岐阜県が日本のまん真ん中にあるという事実を、消極的な視点からでなく、積極的な視点からみることによって、他の県にはない岐阜県の「アイデンテイティー」として、日本における岐阜県の存在性を高める武器にされたのではないだろうか、という考えに及んだとき、やっと私なりの理解ができたと思ったのである。
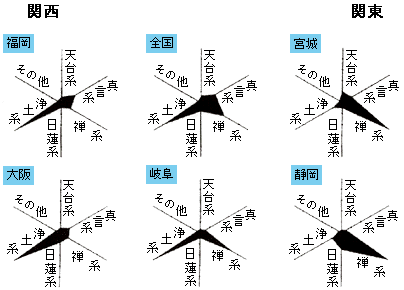
日本の宗教の地域的特色(船戸政一氏調)
『続幻の美濃・飛騨王朝を追う』(濃飛伝承懇話会)から