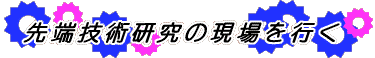
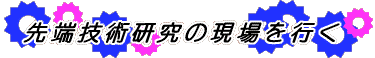
岐阜大学バーチャルシステム・ラボラトリー
■ 世界に羽ばたくVRの拠点を目指して
| 岐阜大学バーチャルシステム・ラボラトリー(以下「VSL」とする)は、平成七年度に文部省のベンチャービジネス・ラボラトリーを設置する二一大学の一つとして選ばれ、平成八年一一月末に完成した。 VSLの施設長である川崎晴久工学部教授と研究の中心的存在である小鹿丈夫工学部教授に、VRの現状とその課題及び今後の見通しなどについて聞いた。 |
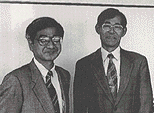 川崎教授(左)・小鹿教授 |
ベンチャー志向の教育を目指す
──まず、VSLの概況について説明をお願いしたい。
| 川崎 | VSLは新産業創出につながる研究を行うのと同時に、ベンチャービジネスを起こせるマインドを持った専門的職業人を養成することを目的としている。従来の学部教育とは違った、ベンチャー志向の大学院レベルの教育・研究を目指している。 では、なぜ岐阜大学でVRなのかというと、もともと岐阜大学にはVRの素地があった。小鹿教授が科学技術庁からVRに関する受託研究を行っているし、大学としてもVRとマルチメディアに関する国際会議VSMMを平成七年から開催してきた実績がある。岐阜大学として、地域に貢献する、貢献されることが期待される分野で、かつ実績のある分野、それがVRだった。なお、このVSLは最新のVR機器を有しており、我が国における最先端のVRに関する研究・開発拠点となっていることを知って欲しい。 |
──それはVRの研究を通じて可能な限りベンチャー企業を起していきたいという考えか。
| 小鹿 | そうだ。実務型の高度な研究を通じてベンチャービジネスをやれる若者を育てていきたい。今までの大学は、どちらかといえば研究者を育てることを志向してきたが、これからは大学院レベルの高度な技術を生かした起業家も育てていかなくてはいけない。 |
──現実には、企業を起こす学生より企業に就職する学生が大半だろう。その場合でも、岐阜に就職する学生は少ないのではないか。
| 川崎 | そのとおりだ。しかし、個人的には地元は岐阜だけとは思っていない。岐阜大学の学生の六割から七割は愛知県出身であり、地元を中部地区としてとらえるならば、名古屋やその周辺の大企業もこれからはVR技術を生産などに取り入れて行くだろうから、それらのに対して優秀な人材を岐阜から供給することも重要なことだ。 |
VRは五感を体感できる総合技術
──基本的なことだが、VRとCGとの違いは何か。
| 小鹿 | CGは視覚情報だけだが、VRは五感で体感・体験できるようにする技術である。そもそも、VRとは、現実には存在しない物体や環境(仮想環境)等をコンピュータ、センサー、ある種のシミュレータ等により構成し、あたかも現実の環境(実環境)のような感覚を持って、その中で主体的に行動し、五感で体験・体感でき、さらには評価できることを可能とすることを目的とした技術である。 |
| 川崎 | VRは、人間とコンピュータとのインターフェイスが視覚だけではなく、触覚、嗅覚などを総合的に駆使して、コンピュータとコミュニケーションをとることができ、CGとは違う。 |
| 小鹿 | VRは統合技術ともいわれている。したがって、技術のみんならず、色々な理論や法則、人間に関する知識(人間学)、さらにはアート的なセンスも要求される。 |
| 川崎 | このため、VSLでは工学はもちろん、医学、農学、教育など様々な分野の先生や学生も参画して、専門の枠を超えた総合的・学際的な研究を進めている。 |
地元企業、興味はあるが…
──岐阜は中小企業がたくさん集積しているが、VRのような新しい分野に対し地元中小企業経営者の反応はどうか。
| 川崎 | 岐阜にはVRテクノジャパン振興会というVRに関する調査研究するグループ(一五〇社加盟)がある。このことから、かなりの企業がVRについて興味津々である。が、多少なりとも人材や開発資金を投入して実際にやっている企業は非常に少ないのが現実だ。 |
| 小鹿 | VSLに常時出入りはしていないが、共同研究という形で具体的に研究している企業が県内には数社ある。まだまだ、VRはゲームの世界だけのことと思っている人が多いようであるが、VRは新製品の開発と評価等には非常に有効であり、あらゆる産業分野に導入することが可能である。地元企業には、もっともっと関心を持って欲しいと思っている。 |
──「地元企業は一定レベルにまで達していないので、高度な研究とはつながらない」という議論があるが、高い水準を低い水準にあわせるか、それともVRも一〇年もたてば当たり前になるかも知れないので、長い目でみるのか。
| 小鹿 | 岐阜県としては、最先端の研究にも、また現場での実用的な応用にも対応できるようにすべきであると思っている。岐阜大学のVSLにはVSMM国際学会の事務局があるし、国際会議を平成七年から開催するなどして、最先端のVRの技術情報を容易に得られる状況にある。ただ、それだけでは地域企業から遊離してしまう。そこで、これを埋めるのがそれぞれの分野ごとにある県の試験場や大学、高専など。これらが最先端の技術を消化し、地元企業に伝えて実用化することを図ることが重要である。また、その実践の場として、大垣市に完成しているソフトピアジャパンがあり、今正に各務原市に建設中のVRテクノジャパンがある。アメリカを初め、ヨーロッパ、特にイギリス、スイス、ドイツ、また、韓国、シンガポール等の中小企業でも、真剣にVRに関する研究開発とその実用化に取り組んでいることを認識しておく必要がある。 |
──最後にこれから力を入れていきたい分野は何か。
| 小鹿 | 今年はスイスのジュネーブでVSMMを開催し、この国際会議のオープニングに際しては、岐阜県の森元副知事が招かれて招待講演を行ったことからも分かるように、岐阜は国際的にもかなり認知されつつある。これを受けて、来年の国際会議VSMM’98は岐阜で開催する予定である。そこで、来年の国際会議を是非成功させたい。また、研究面では、工学分野のみならず、現在、岐阜大学医学部とタイアップしながら、医学分野への応用研究も積極的に行っている。一方、VR技術の実用化面では、アパレル、木工業、プラスチック業、窯業、機械・金属業等の地場産業に普及を図っていきたい。また、医療・福祉、教育、スポーツ科学等の分野での実用化を検討していきたいと思っている。 いずれにしても、岐阜県はVR関連の環境には非常に恵まれており、地場産業の理解と奮起を大いに期待したい。 |
| 川崎 | 工学部と医学部がある大学は全国的にはそれ程多くない。これを生かし、お互いに協力し合って、新しい研究分野を開拓していきたいと考えている。 |