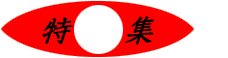
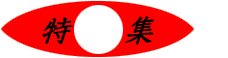
産業を変えるEC・インターネット
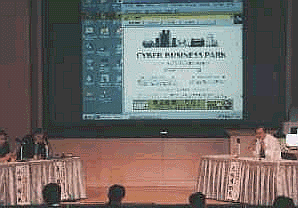 |
コーディネーター 大嶋 秀則 ((株)野村総合研究所コンサルティング本部事業 企画室長・主席コンサルタント) |
| パネリスト 原 俊雄 ((株)荏原製作所情報通信事業本部 システム開発室部長) |
|
| 小谷 昭 (日本アイ・ビー・エム(株)ネットワーク事業部 ネットワークサービス事業推進担当) |
| ECを地場産業へどう活かすか? |
| 大嶋 | 岐阜は繊維、陶磁遝A刃物など地場産業が発達しているが、この地場産業にECをどのように活用していけばよいか。 EC(※1)は文明の利器で、特にその文化的側面はかなり智恵の出せる部分がある。単に商取引の手段として、地場産業がECを行うと特徴のないものとして潰されてしまう。しかし、クリエイティブなものを作り、そこに独自の文化、例えば、非常にユニークなものが出来た時にECを行えば、自分たちの文化の成果を広く発信することができる。ただ、結局は独創的なものが出来るかどうかが問題で、ECを行うかどうかということは最後に考えればよい。 |
| 原 | 私もそう思うが、皆が本当に特徴のあるモノを作っている訳ではない。また、EDI(※2)で見積もりが出せない、契約が出来ないということであれば、世界の土俵も変わってくる。ECの世界ではマーケットは一つとなり、いわばビジネスオリンピックである。しかし、そのビジネスオリンピックは誰でも参加できるのではなく、実際自分も取引が出来、自分のためになる相手としか組まない。ECをうまく使う手もあるが、それは3年後、5年後を考えた方が良い。その時にはこのような仕組みを取らないと、商売が出来ない、土俵に上がれないということになるのではないか。 |
| 大嶋 | 実はEDIは、日本ではグループ企業内部というレベルにとどまっているが、シンガポール、マレーシア、香港、そして中国の一部を中心に取引のEDI化が業界レベルで導入しようとする動きがある。この世界はもしかするとアジア、ASEANでアジア・スタンダードが出来ていく可能性が十分にあり、むしろ日本はASEANの動きに刺激されて業界などの対応が始まるのではないか。 |
| 企業がECに参加してくる背景は何か? |
| 大嶋 | 次に、企業がECに参加してくる背景として何を求めているのか。 |
| 原 | 答えになるかどうかわからないが、一つ例を出したい。 ミスミという200人弱の部品商社がある。この会社に機械部品を買いたいと依頼すると、グローバルネットワークで物流を持っているため、世界から最も安い部品を買ってきてくれたり、加工したりしてくれる。約1千社の加工業者とアライアンス(同盟)を組んでおり、オファーすると即、電子カタログ化される。 例えば、今までは五冊くらいの本を設計部門に送っていたが、インターネットにデータを乗せれば、いつでもデータを取りに行くことができる。つまり、この延長線上に何があるかと言えば、電子カタログにエンジニアリングデータを乗せると、自分のパソコンに取り入れ、自分で設計できるのである。 それで、このミスミが行っていることは、1つは部品を集めてきて供給する購買代理店の役割と電子カタログ情報をネットワークに乗せ、お客さんが最も満足するような形をグローバルなインターネット上で展開しようということなのである。 |
| 大嶋 | 電子商店街に各社が参加してきているのは、新しい技術や新しい形態等がダメでも、そのどこがダメなのかを確認したいからである。そして、もう1つは参加コストが安いからである。参加コストに1億円も2億円もかかるのなら出来ないが、せいぜい数百万円ならとりあえず参加しようということである。ただ、チケッティングやパソコンといった、どこで買っても品質が保証されているブランドと型番を言えば保証されているような企業は本気で考えているだろう。例えば、旅行代理店のようにコミッションが非常に少なくて、チケッティングがうまく出来れば、ECという媒体は非常に可能性を秘めていると言える。 一方、紳士服で電子商店街に参加している人がいるが、どう考えてもコンピュータでスーツを選ぶとは思えない。写真がいくらきれいに何枚も出ていても、蛍光灯や日の光で見るとスーツの色は全く違う。たぶん、ダメでもともとと思いながらも参加しているのではないか。だから、商品によって求めているレベルはかなり差があるような気がする。 |
| 小谷 | 今はどちらかというと、参加してみようか、まずやってみようかという方が多いと思う。それで、成功した事例として、リーバイスのジーンズを紹介したい。ジーンズは普通我々が店に行き、自分に合うものを買う。ところが、リーバイスジーンズは何をしたか。自分自身で腰回りや脚の太さ、長さなど体のサイズを提出すれば、後日、宅配であなただけのジーンズを送ってくるのである。リーバイスジーンズはジーンズはジーンズショップで買うものという概念と全く違うことをし売上を伸ばした。我々にとって重要なことは、リーバイスジーンズは小売店が販売しているため、ユーザーの顔が見えない。そこで、リーバイスジーンズはオンラインでインターネットを経由し、エンドユーザーから直接注文が入るようにした。これでユーザーの顔がかなり見えるようになったことである。 だから、すべてうまくいくかどうかはわからないが、知恵とアイデアと、少しひねったものがあるとうまく当たると思う。それが何なのかということは、非常に多くの方が悩んでいる、考えているのである。ただ、インターネットに参加することは非常にコストが安いのである。今の状況はまずやってみようかという状況ではないか。 |
| インターネットのビジネスへの活用策 |
| 大嶋 | 今、皆が一番興味を持っているインターネットについて、どのようなビジネスに活用できるのか。また、成功要因は何なのか。 |
| 小谷 | 成功事例は少しずつ出て来ている。やはり重要なのは、既存のシステムとどのようにつないでいくかである。既存のシステムは、今まで営々と築かれた財産だから、それを活かしきることである。このことが非常に重要なことなのである。 そして、もう1つはアイデアである。先程のリーバイスジーンズの場合もそうだが、これもやはりベースは今まで営々と築いてきた財産、つまり、既存のシステムである。これをどう活かしきるかをもう一度見直すべきである。 |
| 原 | インターネットは、企業間において、EDIで使えるのではないか。セキュリティや信頼性は確かに大問題だが、それを除いた情報交換もたくさんある。例えば、FAXと併用すれば今すぐにでも出来るものがある。また、セキュアドネット(※3)のような形のを使い分ければ、EDIのような商取引において使い道があると思う。 |
| 大嶋 | インターネットビジネスは大きく分けて3つある。 1つがインフラビジネス。2つ目がコンテンツビジネス。3つ目がインテグレーションビジネスである。 1つ目のインフラビジネスは、当たれば儲けは非常に大きい。この代表例はソフトバンクである。衛星を買い取り、いろいろな画像、データを流すための基盤を提供する。ただ、これは非常にたくさんのお金がかかる。資本集約的であり、これに参加しているのは大手企業、商社などそれほど多くない。これはなかなか普通の会社では手が出しにくい領域である。 2つ目のコンテンツビジネスは非常に幅が広い。余りお金をかけずに作る方法もあるが、長期に渡ると意外に資本集約的である。インターネット専用にコンテンツを作ったら、しばらくの間は儲からない。今一番うまく使っているのは新聞社である。そのほか、今後出てくるのは、アニメとか教育ではないか。教育については昔からビデオがあったが、例えば、試験を行い、その間違い方を分析して、その人用に編集された映像を見せるなど、そのコンテンツの作り方の幅が非常に広がった。中小企業にも参入の余地はある。 3つ目のインテグレーションビジネスは、例えばマイクロソフトのIISを使ってイントラネットを作るとか、システム開発をしてプラットフォームやアプリケーションを作るビジネスである。ただ、このビジネスは止めた方が良い。なぜかと言えば、ほとんど儲からないからある。やはり、インターネットが非常に普及しているのは、ベースソフトであるOSやTCP/IP(※4)などが非常によく出来ていて、作る手間がかからないようになったためである。今までのシステム開発は手間がかかるため、何とか儲かってきたのであり、インターネット周辺のソフトウェアのインテグレーションはびっくりするほど儲からないと思った方が良い。 アメリカでインターネットビジネスをやっている知り合いが話していたのだが、アメリカでも金持ちの人は、インターネットを余りやっていない。金持ちの人はインフラの買収といった方向に行く。インターネットビジネスで儲かるのは月120万円程度であり、それ以上は絶対儲からないという。いくら賢くやってもなかなか儲からない。インターネットは参入障壁がほとんどないビジネスであるためである。自分で素晴らしいものをやったと思っても、次の日にはそれをまねて誰かがもっと素晴らしいものをやる可能性がある。このように参入障壁がないため、どうしても値段は下がっていく。だからこそ、インターネットは安くて、オープンで、普及する。大手企業などの既存組織より、人のつながりをベースにした小規模組織の方が成功の可能性は大きいとも言える。 |
| (注) | |
| ※1 | EC=電子商取引 |
| ※2 | EDI=電子データ交換 |
| ※3 | セキュアドネット=秘密保持の機能がついたネットワーク |
| ※4 | TCP/IP=Transmission Control Protocol/Internet Protocolの頭字語、LANやインターネットなどで使われる通信制御手段の1つ |
| (このパネルディスカッションはさる、平成9年2月12日にソフトピアジャパンセンター・セミナーホールで開催された「岐阜県産業情報化フォーラム」のパネルディスカッションの内容をまとめたものです。) |
| はら としお 株式会社荏原製作所情報通信事業本部システム開発室部長 1945年生まれ。70年荏原製作所入社。化学ポンプ設計、風力機械設計、CIM開発推進室長を経て現職。現在、通産省エレクトロニクス・コマース/PLANT CALS実証研究を推進 |
| こたに あきら 日本アイ・ビー・エム株式会社ネットワークサービス事業部ネットワークサービス事業推進担当 1948年生まれ。71年日本アイ・ビー・エム入社。VAN営業課長、インダストリアルソリューション営業課長を経て現職。現在、インターネット、イントラネット等のネットワークサービス事業を推進 |
| おおしま ひでのり 株式会社野村総合研究所コンサルティング本部事業企画室長、主席コンサルタント 1946年生まれ。71年野村総合研究所入社。米国ザ・ランド・コーポレーション派遣。社会システム研究部研究員、戦略情報システムコンサルティング部長を経て現職。専門は、経営戦略及びシステムコンサルティング、社会情報論 |