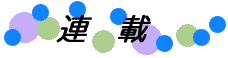
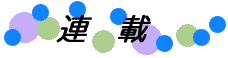
「売れて儲かる商品作り」の為に何をなすべきか ①
松 久 庸 安
バブル崩壊後、売上の減少・価格の大幅な下落による景気の悪化が起こり、その対策が叫ばれ色々な不況対策も行われて久しいが、はかばかしい効果を上げ得ないでいる。
巷には不況対策を求める声が高いが、筆者はむしろこの様な状態が今後は普通の状態であり、戦後の復興期からバブル期までのような誰もが容易に成長できる高度成長期は再び来ることはないと考えて経営を進めるべき時代に入ったと考えている。事実、この様な時期にも好調に売上や利益を伸ばしている企業は存在している。
これらの企業は(1)顧客が本当に欲しがっているものは何かを見抜き、(2)それらの商品やサービスを顧客が支払っても良いと考える価格で、(3)タイムリーに供給している企業である。
この様なことは色々な人が以前からよく言い、又書物にもよく書かれており、これを熟知している企業やその実現に努力している企業は多くある。しかし、これを実施して成果を上げている企業は非常に少ない。これはなぜか?成功するためのポイントは何かについて私見を述べてみたい。
新製品の開発のプロセスと各段階に於ける課題や問題点を簡単に整理してみると図1のようになる。課題の中で「(2)如何に良い品を安く早く作るか」や「(3)如何にして出来るだけ高い値段で、且つ少ない経費で売るか」に付いては既に色々な手法が開発されており、又企業でも多くの経験から独自の方法を所有しており、困難な課題ではあるがそれなりに対応出来ていると考えられる。
しかし、「(1)誰に何を売るのか」に関してはこのモノ溢れの世の中でも顧客が飛びついて買ってくれる商品をどの様にして市場調査し商品として企画すればよいかに関しては、既存の手法にも企業のノウハウにも有効なモノは極めて少なく、この点が「売れて儲かる商品作り」の最大の困難点であると共に成功のポイントであると考えられる。
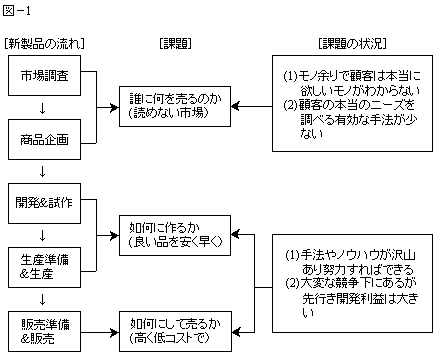
筆者は富士フイルムに勤務時代この問題に長年携わり、色々な手法を調査・開発したり活用したが、日本VE(バリューエンジニアリング)協会で研究課題として開発したVEAM法がこの目的に有効であり且つ使い易いのでご紹介したい。因みに「写ルンです」等の新商品はこの方法を活用して企画したモノである。
「顧客ニーズ把握〜商品企画の進め方」に関しては、1950年代にP.コトラーが市場細分化戦略という考え方を提唱し大変なブームを巻き起こした。これは市場を性別、年齢別、職業別、所得別、所帯構成別、地域別、学歴別と言った基準によっていくつかのセグメントに区分し、その中の特定市場を市場標的とし、その標的に向けて製品計画(市場調査〜商品企画)をはじめとするマーケティングミックスを集中的に展開することによって、部分的独占市場の創造を目的とした戦略であり、それまでのマスプロ・マスセール戦略とは大いに異なるものであった。これに刺激されて色々な市場調査〜商品企画手法が提案され、盛んに使われるようになって来た。
一方世の中は、(1)戦後の復興期から高度成長期にかけてのようにモノ不足の時代であり、モノが有れば売れる〜良いモノを安くすれば売れる時代から、(2)石油ショック以後のようにモノ余りの時代となり、顧客ニーズ(顕在ニーズ+潜在ニーズ)に応えるモノしかよく売れない時代を経て、(3)バブル崩壊後以降になるとモノ溢れの時代に入り、一層多様化された顧客ニーズ(潜在ニーズの比重一層アップ)に応えながらコストパフォーマンスが高いモノしか売れず、しかもその商品寿命は短くなってきた。
この傾向に対応する為、世界の有力企業はこぞって市場調査や商品企画・販売戦略に大きな力を入れるようになり、これに学者やコンサルタントも同調して世の中はまさに市場調査〜商品企画ブームの状態にある。しかし、その実体を調べてみると大部分の企業では図2のような市場調査〜商品企画方法を行っており、そこで対象とされている顧客ニーズ情報は顧客のクレームや流通業者のニーズが殆どで顧客ニーズが含まれる場合でも顕在顧客ニーズ程度のケースが多く、最も大切な潜在顧客ニーズが含まれ主対象となっているケースは少ない。この様な情報を基にして商品を企画・開発し、市場に出しても一時しのぎの間に合わせ品に過ぎず、到底新しい大きな市場を創造することは出来ず、余り売れる訳がない事は自明のことである。(潜在ニーズを的確に捉え、これに応える商品企画がなされた新商品は殆どヒットしている。例:ウォークマン、アサヒスーパードライ、布団乾燥機、写ルンです、携帯電話等)
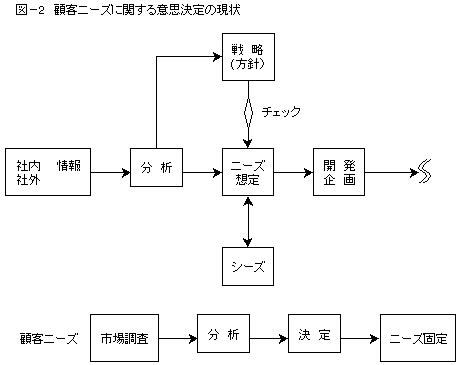
なぜこの様に大切な潜在ニーズを織り込んだ新製品が少ないのであろうか?それは(1)顧客の中にある潜在ニーズを顕在化し、(2)それを基に新しいニーズを創造する為の、(3)誰でもが容易に使える手法がないからである。
確かに世の中には調査・分析・予測・評価に関する技法は数多くあるが、潜在ニーズの顕在化のために使うのは非常に困難であった。又、国内外の商品開発力優秀企業ではその会社独自の潜在ニーズ把握方法を持ち、これを自社の新商品開発に活用している例は多々ある。しかし、この様な会社は長い間の体験に基づくノウハウやそれに適したシステムを作り上げているケースが多く、他社が簡単に真似出来ないことが多い。
又、国内有数のコンサルタント会社や学者の御指導も数多く受けたが、上手くいくケースは少なく、上手く行かない場合大抵は商品企画担当者として(1)感性不足、(2)経験不足、(3)努力不足を指摘されるか、(4)こんな難しいテーマは直ぐ出来る訳はないという云訳をされることが多かった。
VEAM法では、顧客の心の底にあるニーズ(潜在ニーズ)の把握を重視する。潜在ニーズは直接顧客に聞いても分からないので、特別の手法を活用して把握する。そして図3の様に顕在ニーズと潜在ニーズを合わせた総合ニーズに基づいて商品を企画しようと言うのがVEAM法である。
VEAM法には(1)進め方のステップ、(2)種々のワークシート類、(3)種々の補助資料類が整備されていて非常に使い易くできている。紙面の都合でその内容の説明は次回に、又「写ルンです」等での実施例は次次回に譲るが、是非一度使用されることをお奨めする。
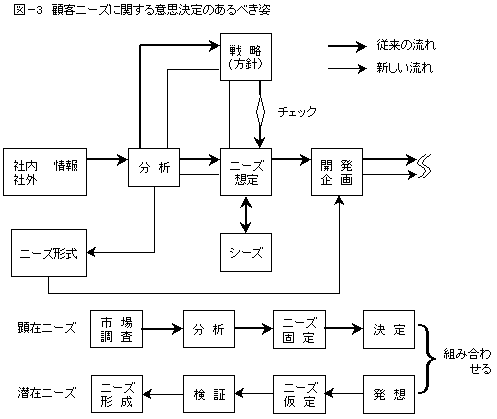
| まつひさ・つねやす 中小企業診断士(鉱工業)、岐阜県技術アドバイザー |