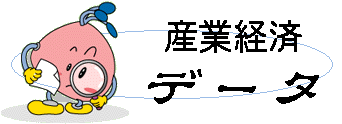
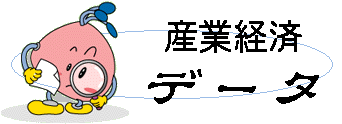
- 産業構造から "岐阜を考える" -
産業構造の変化、この言葉に何を思い浮かべますか。サービス化、国際化、ベンチャー企業の隆盛等々、色々なものが考えられます。産業経済データのコーナーでは、岐阜県の産業について、データをもとにしたいくつかの考察を加えてみたいと思います。今日はその最初、難しく考えずに肩の力を抜いて読んでみて下さい。
1.岐阜県の産業構造
岐阜県の産業経済を引っ張ってきた製造業、サービス業等へバトンタッチか!?
岐阜県はものづくりの盛んな地域だと言われています。平成6年における県内総生産約6.9兆円の内、約28.6%が製造業です。雇用者も約34万人と第2位のサービス業(公務等は除く)の1.7倍となっています。現在もなお、製造業は岐阜県の産業を支える重要な業種です。しかしながら、その位置は低下しつつあります。昭和59年から平成6年までの10年間で、多少の増減はありますが製造業はそのシェア(県内総生産ベース)を4.3ポイント落としました。逆にサービス業が1.9ポイント、不動産業が3.4%シェアを伸ばしました。いわゆる産業のサービス化の現象がデータの上からも見られます。特に平成3年頃までは、県内総生産の伸びと製造業の伸びはほとんど一致していましたが、その後は製造業の減少にも係わらず総生産自体は伸びています。この製造業の減少を補ったのが、サービス業などの製造業以外の業種だと言えそうです。さしずめ、4番打者がスランプに陥ったのを3番、5番が頑張ったといった所でしょうか。4番打者(製造業)の引退ではなく、3番(サービス業)の成長を願いたいところです。
一方、同じ期間の雇用者の増減をみると製造業はほとんど変化が横ばいです。県民総生産のシェアの落ち込みほどではなく、雇用の面からはまだまだ頑張っていると言ってもよいかも知れません。むしろ、農林水産業が減少し、サービス業、建設業の増加が見られます。"田畑をあきらめて、建設現場や街の仕事へ"というのが今の岐阜県の産業構造の変化を示す姿なのでしょうか。(表-1)
表ー1 総生産額シェア、雇用者数の推移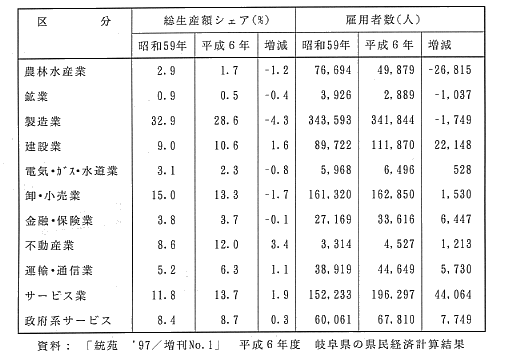
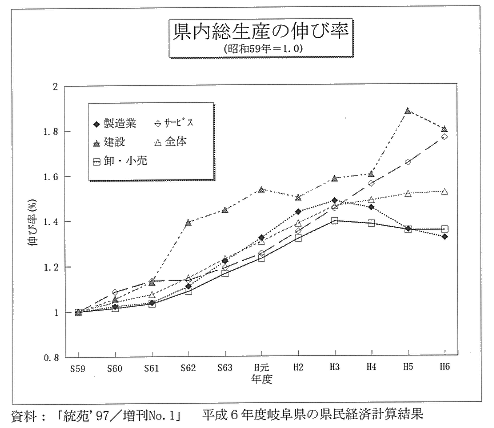
2.産業構造をめぐるいくつかの考察
(1)作り上手の売り下手は本当か? -データから推測される1つの仮説-
岐阜県を代表する産業として地場産業があります。もともとものづくりの盛んな地域であり、その質の高さは一定の評価を得ていると言われています。ただし、その実力ほど商品としての評価は高くない、高く買ってくれない、といったいわゆる"作り上手の売り下手"というもどかしさが地元関係者の間で聞かれます。
その構造をデータの上から概観したいと思います。表-2は岐阜県の地場産業の一つである家具・装備品の製造品出荷額等、卸売業商品販売額を示したものです(なお、ここでの数値は異なる統計調査を用いており、流通の流れの中で重複などの影響を排除したものではありません。従って、産業の輪郭を掴み1つの仮説を立てるための概略的な分析であることに注意して下さい。)。
まず、生産(製造品出荷額等)と流通(卸売業販売額)の数値の比較をしてみました。福岡県の家具は生産よりも流通の方が数値が大きくなっています。おおざっぱな構造を類推すると、福岡県ではものづくり面の産地を形成しているだけでなく、流通面の集積地、いわゆる産地卸を形成しているものと考えられます。一方、岐阜県の家具では生産に比べて流通で扱う量が少なく、生産したものの多くを県外へ販売しているものと考えられます。このような産地卸の存在が売り上手になるために必要かどうかは議論の分かれるところですが、産地全体の力を結集するような役割をもつ小売とメーカーの中間的な存在がいない可能性は指摘できると思います。それは、岐阜県を1つの単位として考えた場合に、全体として川下(小売側、消費者側)への影響力が小さい構造(つまり流通構造から見て"売り下手"とならざるを得ない構造)とも言えるのではないでしょうか。高山のある家具メーカーの方はこう言っています。「製造メーカーだから作る所だけやっていれば良いというのではなく、自分たちが製品の材料を購入する所から消費者へ届けるまで、一貫した思想で貫かれている状況を作り出すことが大切だと思っている。」(岐阜県地場産業の製品とデザイン開発-イタリア企業との比較- 平成9年3月 岐阜県より)。いずれにせよ、岐阜県産の製品のイメージを守り、ブランドを大切に売ってくれるパートナーの確保あるいは販売組織のようなものを整備し、独自の販路を確保することが必要なのかもしれません。
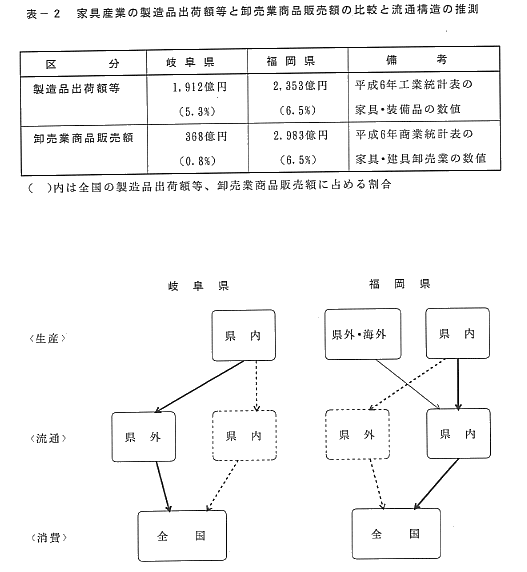
(2)データが語る3つの興味ある"一致"
分析の作業を進める際に、時折、統計データが見せる興味ある一致。これらは、現象や構造を示す証拠なのか、それとも偶然の一致なのか。読者の皆さんはどう考えますか?
数字のトリックだと眉をひそめられるのか、ウンウンと頷いていただけるのか?筆者の気になるところではありますが、この記事が岐阜県の産業を考えるきっかけとなるならば、この稚拙な分析も生きてくるものと信じています。
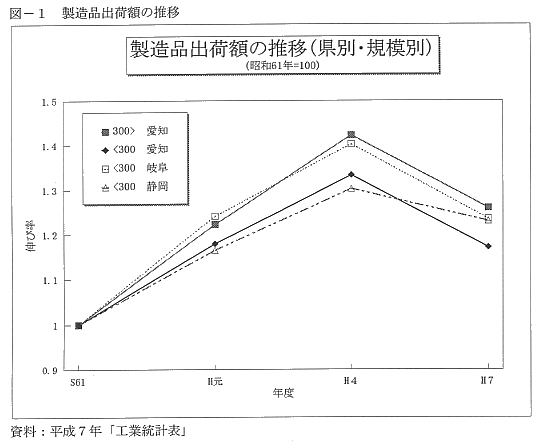
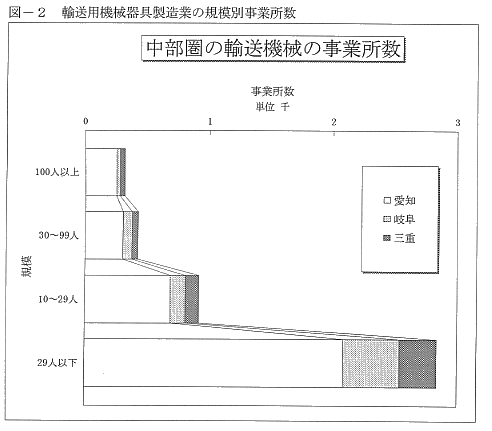
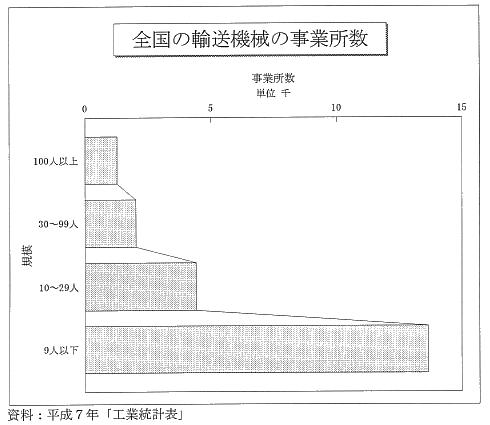
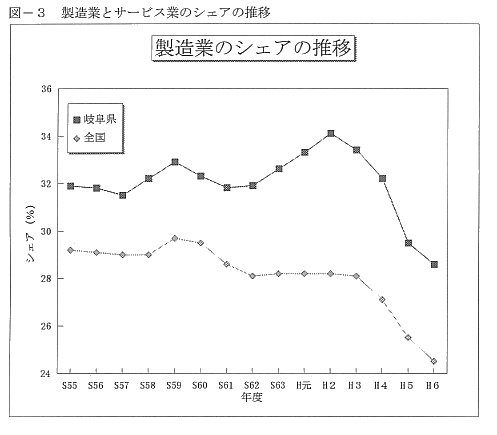
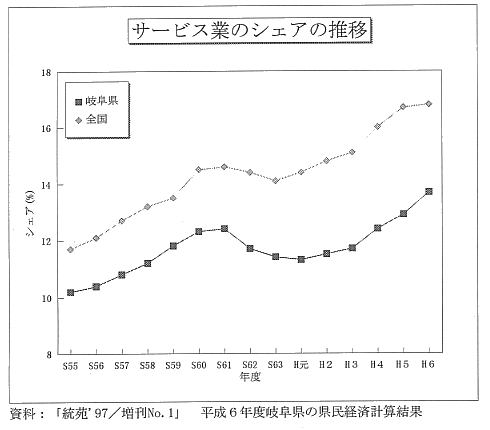
(研究部 主任研究員 新田啓之)