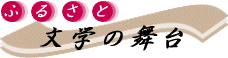
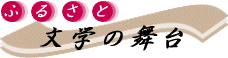
| 文・道下 淳 岐阜女子大学地域文化研究所 エッセイスト |
作家・長谷川伸の短篇小説やシナリオ・随筆などに、本県を舞台にしたものがある。そんな意味でも、親しみの持てる作家のひとりである。今回取り上げた短篇小説『夜もすがら検校』も、そのひとつである。
長谷川が作家を志したころ、山野芋作・長谷川芋生をはじめ、いろんなペンネームで作品を発表していた。しかし芽が出ず、悩み続けていた。そんなとき、作家菊池寛の紹介で雑誌『新小説』に発表した『夜もすがら検校』が認められ、出世作となった。大正13年のことである。このとき使ったペンネームが長谷川伸で、本名長谷川伸二郎から「二郎」を省いたものであった。
* * * * * * * * * *
小説のストーリーは、次のようである。
都に玄城という平家琵琶の名手がいた。目が不自由だったが、まだ40歳前と若く、夜どおし聴いていても飽きないため、人びとから“夜もすがら検校”と呼ばれていた。ある年、江戸の大名家から招かれ、内弟子の友六を連れて下向した。長滞在になったため、友六の世話で、りよと呼ぶ年増の女が身回りの世話をした。
秋の半ば、検校は都へ帰ることになった。同行者のなかに、りよの姿もあった。運の悪いことに彼女が病気になり、福島宿でしばらく泊った。その間、木曽路は冬になり、降雪を見るようになった。
病気が治った彼女を伴い、検校一行は木曽路を急いだ。ところが山中で検校はこともあろうに、友六らに財布を奪われ、置き去りにされた。降りしきる雪のなかで、検校は死を覚悟した。この世の名残りにと、日ごろ愛誦していた琵琶の『女院住生』を口ずさんだ。寂光院の鐘の声、今日もくれぬと打ち知られ、夕陽西に傾けば、還御ならせ給いけり。女院はいつしか昔や思 しめされ給いけむ。忍びあえぬ御涙に、袖のしがらみ塞きあえさせ給わず、御後を遙かに・・・・
やがて、気を失った。
気がつくと山家のいろり端に寝かされており、若者が心配そうにのぞき込んでいた。聞けば男は夜逃げの途中、凍死寸前の検校を見つけ、わが家へ連れ戻ったという。若者はたったひとつ残った財産の仏壇を壊していろりにくべ、部屋を暖かくしてくれた。
それから3年、都へ戻っていた検校を訪ねて若者がやってきた。検校は木曽路でのお礼にと大歓待をしたが、喜ばなかった。最後に一番大切な琵琶を打ち割り、いろりにくべた。このせいいっぱいの礼心が、若者に伝わり感激させた。
* * * * * * * * * *
この小説は、なんとなく謡曲『鉢木』に似ている。謡曲では諸国を旅する僧(北条時頼)が、雪道に迷い、貧しい武士佐野源左衛門の家に泊まる。佐野は愛蔵の梅・松・桜の鉢の木をいろりにくべ、旅僧をもてなす。やがて鎌倉幕府から佐野に対し、思賞が下される────といった内容である。
このことと、小説の舞台が美濃と信濃の国境で、場所が特定されていないのに、筆者は気になった。ただ『故郷美濃へ立帰りますじや』と、小説の最後で若者に言わせている。すると中津川市落合の十曲峠付近かと、思っていた。
昭和30年ごろ上京した筆者は、偶然にも長谷川氏とお会いする機会に恵まれた。お聞きしたいことが、たくさんあった。飛騨のこと、岐阜のこと、赤報隊のこと、そして『夜もすがら検校』のこと。約束の15分はすぐ済み、30分余り話し込んだ。『夜もすがら検校』のヒントは『鉢木』ではなく、『信盛記』と題する江戸時代末期の記録(写本)であった。美濃紙4〜5枚をとじたもので、作者は不明である。「表題は、どう読むのか分からない。私は『しんせいき』としているが、『しんじょうき』かもしれない」と、長谷川氏は述べられた。
作品の舞台となった信濃国境の木曽路であるが、長谷川氏は次のように語る。
「私が作家活動を始めたころ、木曽川をせき止めて発電所を設ける大井ダム計画があった。あの急流をどのようにせき止めるか、関心を持っていた。小説のタネになるかも知れないから・・・。それに続いて上流の落合ダム建設が計画された。私はあの辺りの地図などを広げ、場所を確認しながら興味深く見守った。そんなとき『信盛記』を読み、小説に書こうとした。思い出したのが、落合付近の地図で、それを頭に描きながら“検校”を書いた。だから具体的な地名は入れることが出来なかった。」
中山道の難所木曽路の西入り口が、現在中津川市の中心部になっている中津川宿である。その東に落合宿があり、十曲峠を越えると長野県側の馬籠宿。島崎藤村の故郷でもある。古い地図を見ると、中央線(JR)落合川駅から大久手経由馬籠へ通ずる脇道がある。途中で分かれ十曲峠に出るルートもある。この脇道は馬籠宿の人びとが落合川駅から鉄道を利用する際、通った道である。藤村の作品にも登場する。
長谷川氏は具体的なことは言われなかったが、筆者はこの脇道のどこかに検校を助けた若者の家があったのではないかと、思っている。そんなわけで一度、馬籠から新茶屋・大久手経由、落合川駅まで歩きたいものである。