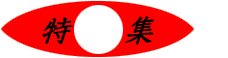
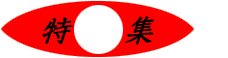
パネルディスカッション
「自動車産業の将来はどうなるか」
| コーディネーター
香川 勉((社)日本自動車工業会常務理事) |
|||
| パネリスト | |||
 |
 |
 |
 |
| 岩月伸郎 トヨタ自動車(株) 海外企画部長 |
伊東忠彦 パジェロ製造(株) 代表取締役社長 |
今川順夫 丸順精器工業(株) 代表取締役社長 |
土屋勉男 (株)三菱総合研究所経営 市場戦略研究センター長 |
| 成長するアジアなどの世界市場 |
| 香川 | 日本の自動車産業は今後、グローバリゼーションの中での海外展開と資源・エネルギー制約下での環境・安全問題という二つをキーワードとして展開する。その時、国内ではどのような体制をとるべきでしょうか。 まず、世界の自動車市場の構造変化と国内メーカーの海外戦略について、議論をお願いします。 |
|---|---|
| 土屋 | 私どもの三菱総合研究所で、最近、世界の自動車市場の展望について予測しました。結果をみると世界的には成長市場であるといえるが、こと国内をみると、国内生産はピーク時(一九九〇年)の一三五〇万台から一〇〇〇万台程度に減少してきておりますし、将来的にもあまり伸びない。自動車産業は今後、厳しい産業であるといえる。 世界の自動車市場は、九四年で四九五六万台、二〇〇五年には六一五六万台程度と予測される。つまり約一〇〇〇万台強増加する。日本の生産規模と同じくらい市場が増えるということなのです。この予測から国内、世界のどちらに目を向けるかによって戦略が変わってくる。世界のどこが特に成長性が高いのか。これはアジア市場が非常に成長性が高く、九四年の四七一万台から二〇〇五年には一〇一二万台と五〇〇万台強の増と予測されます。日本での生産は九〇年の一三五〇万台をピークに落ちてきているが、アジア周辺を取り込んでいけばそれ以上に伸びていくという構図ができる。 なぜアジアが成長するのか。アジア市場はまず人口が集中し、世界人口の約六〇%を占めています。今まではあくまでも潜在市場だったが、今、アジアは貿易投資が活発化してきている。アジアの成長をみる場合、重要な視点はやはりアジアは非常に貯蓄に熱心なことで、国内の蓄積が投資に向かい、投資不足の部分は海外からの直接投資がカバーしている。 またアジアの成長性にとって非常に重要なのは、社会主義国のインテグレーション(統合)に成功したこと。世界市場が九〇年代にグローバル競争の時代に入り、コスト競争力が厳しくなってきましたが、これを欧州やアメリカ地域よりも上手く取り込めたのです。このことがグローバル競争にとってコスト競争上重要であるとともに、潜在力の高い地域を統合できたということをベースに今のアジアの成長がある。今後、アジアをうまく活かすことが、日本の自動車産業にとって生き残る道ではないでしょうか。 |
| 日本メーカーの海外進出 |
| 香川 | アメリカのメーカーもヨーロッパのメーカーもアジアに注目し進出してきていますが、日本のメーカーはどのような戦略で進出していかないといけないでしょうか。 |
| 伊東 | パジェロ製造は三菱自動車から完成車の組立てを委託されている会社であり、日本にしがみついていないといけない会社です。 講演の中で、トヨタ自動車の岩月さんから市場のある所に工場を出すという話をお聞きしましたが、実際問題として輸出基地という発想で海外に進出するという会社もあると思います。この点トヨタ自動車のように市場のある所に工場を建設するということに徹してもらえれば当社のような国内のアッセンブル企業は助かる。 |
| 今川 | 当社はタイに部品と金型の工場を持っています。タイはまだ発展途上の国ですが、これからかなり伸びると予想しています。また、インドなどでは、「日本の自動車部品の造り方を勉強したい」また「金型の技術も教えて欲しい」と、私共の進出を希望されている企業もあり、これらを踏まえてこれからのアジア地域を見直していく必要があると思っています。 |
| 岩月 | 現在トヨタ自動車が計画しているのは、販売増加分を全て海外生産で賄うということ。従って、日本からの輸出台数は、基本的には増えもしないけど減りもしないという構造で考えています。車とは多くの種類をお客様に提供し、初めて満足していただけるもの。その種類からすると現地で全部造れるはずはなく、日本がその基地として非常に重要になってくるのです。トヨタの現地工場で造る車について為替を一〇〇円位でみると、決して日本で造る車より安くないのです。ただ、当該市場に参入するためには現地で生産せざるを得ず、生産したものはその市場だけで売る。このような形でしか競争力を持ち得ないのです。グローバルな競争力を持った海外事業を海外でしっかり持つということは、もう少しの時間と努力がいると考えています。 そのために現在いろいろな形で努力していますが、世界市場の中で、例えば南米からアジアに向けてトヨタブランドの車を供給するとか、アジアからヨーロッパに向けて供給するとか、そんな時代はまだ二一世紀初頭では難しいのではないでしょうか。やはり二〇〇五年あるいは二〇一〇年といった頃に起こり得る姿ではないでしょうか。以上のようなことを踏まえ、うまく企画し、展開すれば日本に付加価値が残る、あるいは現在よりも相対的に拡大すると考えています。 |
| アジアへの展開と国際競争力 |
| 香川 | 海外展開というのは世界経済への貢献と海外投資に対するコストの回収という二面がありますが、このうち、付加価値を維持したり行動化が進む中で海外展開により発生するコストはどのようにして回収したらよいのでしょうか。 |
| 土屋 | アジアについてみると、現地化に対応して輸出をKD生産していた時点では日本が圧倒的に強かったし、欧米メーカーも注目していなかった。日本は少なくともASEANにおいては独占的な地位を築いていた。例えば、タイの場合は八〇%〜九〇%、マレーシアでも同様のシェアを占めてきたが、最近アジアが成長性が高いということで、各国とも現地参入を強化してきており激戦となっています。 日本がアジアに参入し、アジアの自動車産業を育ててきた側面もありますが、国際競争力のある車造りが本当に出来ているかといえば、これは国産化規制もあり出来ていないのではないでしょうか。逆にいえば、日本に対して、国際競争力のある車造りが出来る拠点を早く造ってほしいという要請が出てきている。アジアは非常に成長性もあるし、これから有望な拠点です。が、従来と同じように参入していてもアジアで生き残れるかどうかは厳しい。今、アジアに参入し始めているのは欧米メーカーであり、欧米メーカーはかなり戦略的に大規模投資を行っています。更に最近は韓国も日本のシェアを脅かしつつあるという状況になってきている。 |
| 岩月 | 実はアジアと一口にいいますが、国によってその状況は随分違う。例えば、タイは大発展をしていると言いますが、自動車の市場規模としてはせいぜい年間五五万台とか六〇万台という規模です。また、「ASEANは一体だ」といいながらも国別に国産化政策などが異なっている。自動車は規模の経済といわれますが、個別国産化政策といった枠組みがあるがゆえに国際競争力を持ち得ない構造が存在するのです。 従来、ASEAN加盟国は「BBC(Brand to Brand Complementation、地域内部品補完協定)」というのを持っていました。これは各国間で部品を相互に融通しようという計画で、それが今、「AICO(ASEAN Industrial Cooperation)」という仕組みに変わり、これを二〇〇三年には「CEPT(Common Effective Preferential Tariff)」という仕組みに変えていこうとしています。この「CEPT」という段階になると、ASEAN加盟国の中で自由に完成車も行き来させるという段階となり、いわばこの時点でやっとASEAN市場が一つの市場として、そして生産戦略も一つの対象として考えられるようになるのです。しかし、その時点でも、各国別の貿易収支などはやはり問題になるだろうとし、ある国から一方的にある国へ車が流れた場合はやはり閉ざそうとする動きが出てくるでしょう。従って、「CEPT」という制度により、二〇〇三年からアジア域内の自由化が抜本的に進むだろうが、事実としてそうなるのは二〇〇七、八年辺りと考えています。例えば、ピックアップ車をタイで造ってアジア全域に輸出する。TUVというバンタイプの車をインドネシアで造ってアジア全域に輸出する。そうなるとある程度対象市場が大きくなり規模の経済が働いて、国際競争力を持ちうる原価の車ができると考えています。 |
| どう保つ? 海外と国内のバランス |
| 香川 | 海外戦略を行う場合、長期的な視点やグローバルな視点のみならず、国ごとの実態や現地の企業の要望などを含め、かなり戦略的、政策的な選択が必要となってきます。 このようにして行ったとしても、当然国内はどうなるか、海外と国内とのバランスはどうなるか、特に下請け企業はどうなるかという問題もでてくると思います。こうした点について、どう考えていますか。 |
| 今川 | 当社のタイ工場では、ホンダ車用のガソリンタンク、オイルパン、汎用エンジンのタンク等を製造しています。従業員の給料は、日本と比較して約一〇分の一位です。このメリットを活かす方法はたくさんあります。日本では生産性が悪く使い物にならない機械をタイへ持っていき、人間トランサーのような形態で人海戦術で製品を造り、かなりの効果を上げています。将来、技術的にもう少し成長してくると、小物部品はタイで造り、日本の自動車メーカーに納入できるようになると思っています。また、ある自動車メーカーでは精密小物部品はかさばらないので、日本から全部送っているが、オイルパンやシリンダーなどエンジンの中でも比較的かさばるものは現地化を図り、現地の従業者によってコンベアではなく台車に乗せながら組立をしていると聞きます。それでもエンジンの性能についてはあまり問題なく、少量生産であれば安くつくということもあって、アジア地区にかなり供給されているそうです。 |
| 伊東 | 先程アッセンブリーは日本でといいましたが、組み込むパーツはどこからでも調達したい、と考えています。 アッセンブリー会社も外国へ出ていかなくてもいいのかという点に関しては、幸いなことに自動車のアッセンブリーというのは品質を作り込む必要性の高い作業であります。だから、品質を作り込めるような優秀な人材が多い日本に残しておける余地があると考えております。 |
| 海外展開に伴う国内生産体制 |
| 香川 | 海外展開に伴って国内生産体制がどのようになるのかですが、国内の生産といっても販売の問題もありますし、様々な課題があると思いますが、どう考えていますか。 |
| 土屋 | 海外展開に伴う国内の体制ですが、まず日本の競争力がどの程度あるか予測しますと、九〇年は基本的にはCBU(製品輸出)及びKD生産を中心にしながら海外展開を進めてきました。しかし、これから二〇〇〇年にかけては急速に海外生産が増えていき、我々の予測では二〇〇五年には国内生産よりも海外生産が上回るという予測が出ております。国内生産は今は約一〇〇〇万台だが、中期的には一〇〇〇万台プラスマイナスアルファー、若しくは若干減っていく可能性がありますし、海外生産は二〇〇五年で一〇〇〇万台強になるだろうと予測しております。 そこで、国内生産よりも海外生産が上回っていくということはその部品をどのような形でどのように供給していくかが今後非常に重要になってくる。 組み立ては基本的にはやはり現地で行うことがベースとなりますので、部品をどこでどのような形で供給していくのか。その際、国内の供給構造が空洞化するのか、それともしないのか、あるいは国内の部品メーカーにとって何がマイナス影響が大きいのか。それを判定するためのベースとして、通常、KD生産と海外生産の分かれ目を付加価値ベースで〇・四を境に判断しています。その中で部品を供給するための世界的な体制をどのように作るかが恐らく組み立てメーカーにとってはポイントとなってくるでしょう。 一方、海外展開に伴う国内生産体制をみると、基本的には国内はいずれにしても付加価値が減っていき空洞化していく可能性がある。トヨタが全体で上手くバランスが取れるのはトヨタであるからであって、他の日本のメーカー全部が取れるかは疑問である。国内にとっては非常に厳しい状況を想定した方がよいのではないでしょうか。 |
| 岩月 | ご指摘の通りだと思います。私はかなりバラ色の話をしましたが、それを実際にバラ色にするには大変な努力や調整が必要なのです。事実、海外に進出しても三割程度は国内に残るが、全く残らない業種も出てくるのです。例えば、非常にかさばる大きなものや高度な技術が必要でないものは、どんどん海外生産に変わっていく。その一方で海外生産が拡大しても、日本から輸出せざるを得ない部品もある。このようなミスマッチが現実にたくさん起こっていくのです。 だから、そのミスマッチを摩擦はあっても積極的に補正をしていかなくてはいけない。従来のような企業系列内ではミスマッチをとても吸収できない状況になってきています。従って、なるべく大きな土俵の中でミスマッチを解消していくということが必要となり、そうしないと全体がバラ色にならないということなのです。そのため、必然的に企業系列を随分緩やかなものとして、そのミスマッチを解消していく過程に入ってきております。今後もそれを進行させていかなけれないけないでしょう。 |
| 国内生産と雇用の将来的見通し |
| 香川 | 次のテーマに進んで、国内市場の動向と生産、雇用の見通しについて、土屋さんからお願いします。 |
| 土屋 | 一昨年、非常に円高に進み、空洞化が話題になりました。そこで今後雇用はどうなるのかについて自動車総連から依頼があり、為替レートが一〇〇円、八五円、七〇円など、かなり厳しい状況を想定しました。現時点ではかなりギャップがあるかも知れませんが、二〇〇〇年に九〇円とか九五円位になるという見方をした場合、雇用者数は現在(九四年)の八四万九〇〇〇人から減少し、八二万五〇〇〇人と六八万五〇〇〇人の中間くらいになる可能性があり、今後減少基調で推移します。 雇用問題を考える場合、トヨタの雇用、あるいは自動車メーカーの雇用という軸で考えれば基本的には問題ないとみています。これはグローバル調整や成長機会を海外に求め、国内から海外へうまく雇用が移転できれば生産自体は増えていくため、グローバル生産が増えるという意味で問題はないのです。ただし、日本自動車工業会や日本部品工業会、日本政府という立場になると、少し見方が変わってくるのです。いずれにしても国内の生産が仮に横ばいなり若干減るという状況下で国際競争に勝ち抜くためには、雇用は将来的には国内では減り、生産性は上がるという雇用節約的な技術革新のもとで競争力の回復が生じる可能性があり、造船や繊維産業で実際に起こったように雇用問題にとっては間違いなくマイナス影響が出てくるに違いない。国内の空洞化という意味はそういうことではないでしょうか。また、部品工業にとっても同じような可能性はあるのです。 |
| 香川 | 聞き方によっては非常に厳しい話です。繊維や造船もそうでしたが、一〇年間位産出量としては変わらないが、雇用は半分になることもありうるわけです。この場合、雇用の調整が上手く何の摩擦もなく行われれば問題はない。そういう意味でしょうか。 |
| 土屋 | その通りです。例えば、東レや三菱重工は基本的に本業部門が半減していますが、かといって非常に厳しい雇用調整をしたかというと対外的にはあまり明確には出ていません。ではなぜ出ていないかというと、これはまさに日本的なリストラなり構造調整を実施したのです。要するに長期雇用をベースに時間をかけて調整していくことがまず一つ。東レの場合、本業を中心にグローバル、特にアジア展開を、三菱重工の場合、多角化展開を実施したのです。ただし、ベースは長期間かけて調整するということなので、やはり将来に対し明確なビジョンがなければいけない。不況になり厳しくなれば短期で調整したいと思うが、それでは経営の活力、従業員の意欲を破壊するおそれがあります。時間をかけて中期で調整するためには、やはりトヨタのように、二〇〇〇年におけるトヨタ像という将来像が間違わないということとその将来像を持っていることが前提になってくるのではないでしょうか。 |
| 香川 | 部品メーカーの方で雇用の問題、生産と雇用についてどうお考えですか。 |
| 今川 | アジア地区の自動車市場をみますと、一九九五年には五八〇万台の規模であったものが、二〇〇〇年に一〇〇〇万台、二〇〇五年には一五〇〇万台位の市場になると予想されています。こうなると世界の自動車メーカーは先を争って、アジア各国で生産を始めようとする。現に今、日本の各自動車メーカーもタイに集中投資をしています。これからは発展途上国でも自動車生産業は自国の重要な産業となり、先進国だけの基幹産業ではなくなってくるわけです。また、日本だけが品質が良いということで輸出をすることは、相手国の経済を著しく脅かすことになる。さらに為替が円高になれば輸出も出来なくなり、逆に日本は、完成車の輸入などの増大につながる。これからの日本は、自動車生産をはじめ部品生産についても、落ち込んでいくことはあっても生産増になることはあまり期待が出来ないのかと思います。 九六年度の実績で日本の自動車部品産業の動向調査をみますと、九〇年のピーク時を一〇〇とした場合、九六年実績では生産数で二四%の減となり、また生産額ベースでは一七%の減という数字が出ています。自動車産業は裾野の広い産業ですので、今後もさらに空洞化問題が深刻な問題になっていくのではないかと予想されます。事実、当社もバブルが崩壊した九一年以後、四年間で売上を五〇億円程落としました。このような状況の下、思い切ったリストラや新規取引先の開拓あるいは新商品の開拓などで、厳しい環境をようやく乗り越え、今年前期はやや減収ながら増益という決算を出すことができました。しかし、現実に何か手を打たなければ自動車部品メーカーとしては厳しい環境になっていますので、雇用問題も大きくクローズアップされていくのではないでしょうか。 |
| 伊東 | 当社が製造しているパジェロは、発展途上国にはオフロードという特性で、先進国にはユニークなRVというイメージで対応している車です。このようなイメージを持ったパジェロを製造しているお陰で、日本国内需要への対応と発展途上国におけるオフロード、先進国におけるユニークなRVという切り分けで幅広い諸外国への輸出も対応出来ると考えており、今後も頑張りたいと思います。 これから先を考えるとやはりボリュームが変動するだろうし、直接作業している人の数はそれに応じて増減はあるだろうと思います。 また、当社はアッセンブリーをしている一方で、設計者や生産技術者を一五〇名程抱えており、これらの人達にはこれからたくさんの需要があると感じています。親会社からもグループの一員として頑張ってほしいといわれていますし、生産効率を上げながら適正な人員を配置していきたい。 |
| 香川 | 話が段々厳しくなってきてあまり歓迎すべきことではないのですが、岩月さん、コメントはありますか。 |
| 岩月 | 工場でモノの製造に直接的に携わる部分は、やはり雇用という観点からみますと今後も減っていくだろうと思います。先程申し上げたように台数は必ずしも減らなくても、当然生産性を上げていかなくては競争に負けるわけですので、結果として雇用は減っていくでしょう。ただし、自動車産業の中にも、開発とか生産準備あるいは管理に携わる部分はグローバル化によって新しい雇用が多く生まれてくると思います。加えて、一八歳になり仕事場に出てくる人口はこれから激減していきます。そういう意味では、従来から製造現場にいる人達の能力をかなり高めていき、新しい分野にどんどん若い人達を回さないといけない。今後、若い人達を低付加価値分野に置いておくことが国としても当然出来ないという状況が出てくると思います。雇用の問題というのはやはり職種というか、取り組む仕事の中身により、大きな変化が出てくるだろうと思っています。 八五年から九五年までの海外生産はまさに空洞化をさせる海外生産でした。これからの海外生産は、海外市場の伸びに沿って拡大をしていくべきであり、その付加価値が周り回って日本に少しずつ落ちていくという海外生産だろうと、そのような認識を持っています。 |
| 香川 | このテーマの結論のようなお話をいただき少し安心しておりますが、私も同意見で、空洞化というと非常に暗いイメージですが、これからはむしろ前向きに雇用なども調整していく、対応すべきではないかと思っております。国内生産が増えないような時代になってきたのですから、その中でどう生き残っていくかを考えれば空洞化、空洞化と騒いでいても仕方がない、今後の対応を考えていかなくてはいけない、そんな時代になったと思います。 本日は長時間のパネルディスカッションありがとうございました。 |
● プロフィール
| かがわ つとむ
(社)日本自動車工業会常務理事 昭和10年生まれ。昭和33年農林水産省入省。その後経済企画庁 計画官、国民生活調査課長、環境庁国際課長などを歴任後、昭和58年(社)日本自動車工業会企画調査部長に。平成5年より現職。 |
| いまがわ よりお 丸順精器工業(株)代表取締役社長 大正12年生まれ。昭和27年丸順精器工業創業。昭和35年丸順 精器工業(株)設立、代表取締役社長に就任。 |
| いとう ただひこ パジェロ製造(株)代表取締役社長 昭和11年生まれ。昭和34年新三菱重工業(株)入社。三菱自動車工業(株)、東洋工機代表取締役副社長を経て、平成8年より現職。 |
| つちや やすお (株)三菱総合研究所経営・市場戦略研究センター長 昭和21年生まれ。昭和47年(株)三菱総合研究所入社。平成7年より現職。 |