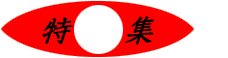
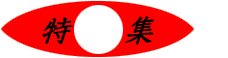
 |
トヨタの海外戦略
|
はじめに(世界の自動車市場規模)
1995年には、全世界で約5000万台の車が売れている。市場として最も大きいのが北米市場の約1600万台、次に欧州市場が1400万台で続き、日本は約700万台の市場である。85年から95年までの10年間の推移をみると、米国を中心に北米市場は完全に成熟した循環型市場であり、景気の変動などにより増減を繰り返しているのがわかる。欧州市場も北米市場とほぼ同様である。日本市場は、90年をピークにやや低下傾向を示しており、成熟段階に入ったと言えよう。経済発展の著しいアジアは、その規模こそ日米欧に及ばないものの、非常に速いスピードで成長している。
1 これまでのトヨタの販売と生産
国内30%、世界10%のシェアを持つトヨタ
トヨタの全世界向販売の記録が90年の約500万台である。以降1、2年は減少したものの、93年からは緩やかな拡大傾向にある。その内訳をみると、日本では、90年のバブルの絶頂期以降減少。その一方で、海外での販売は緩やかではあるが拡大を続けている。
トヨタの95年の販売実績は、多少数字を丸めて申し上げれば、国内で約205万台、海外で約245万台、合計約450万台であった。国内の除軽市場でのシェアは約40%である。しかし、「軽」を分けて考えるというのは日本独特の考え方なので、「軽」を含めた市場シェアをみた場合、そのシェアはほぼ30%強となる。一方、海外市場は日本を除いても4000万台を超える規模があり、その中でのトヨタの95年販売、約245万台は、シェア、約6%に相当する。この数字をみる限り、まだまだ海外でシェアを伸ばせる余地があると考えるべきであろう。
国内と海外とを合わせた、いわゆるグローバルシェアについては、トヨタは世界市場の中で10%のシェア、すなわち「グローバルテン」を目標に頑張ってきたのだが、実は90年前後に既に実現している。現在は少し下がり、9%強のグローバルシェアである。これはトヨタの世界における活動が鈍ったのではなく、トヨタが日本市場で高いシェアを持っており、世界市場における日本市場の相対的規模が小さくなると、結果トヨタの世界市場シェアは低下するという構造になっているためである。世界市場の構造変化がトヨタの事業、あるいはグローバルシェアに大きく反映をしているのである。
生産実績の推移
販売から生産に目を転じると、95年実績は、国内で生産し国内向けに出荷した車が約200万台、国内で生産し海外に輸出した車が約100万台、海外で生産した車が約150万台という構成になっている。この10年間の推移をみると国内生産は減少し続け、海外生産は順調かつ急速に拡大している。特に90年から95年にかけて、海外向けの完成車輸出が減り海外生産が増えるという傾向が強く出てきている。この時期は、国内向けの出荷も同様に減少しており、日本生産の完成車減に拍車をかけたかっこうになっている。
トヨタの海外生産−三つのステップ
海外生産が順調かつ急速に伸びてきているが、どのように伸びてきたか。 これまでのトヨタの海外生産への取組みを、その背景から大きく三段階に分けて考えてみたい。
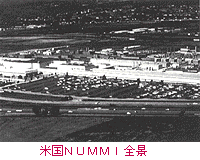 次の段階は85年から95年にかけて起こった。これはいわゆる通商摩擦を回避するために、やむなく海外生産へ移行した時期である。通商摩擦が欧米諸国との間に起こり、具体的には「欧米輸出自主規制」というかたちを採った。米国については81年から93年までこの規制が続き、EUについてはモニタリングという表現をしているが、八六年から何らかの形でEUへの完成車の輸出をコントロールしているという状況にある。
次の段階は85年から95年にかけて起こった。これはいわゆる通商摩擦を回避するために、やむなく海外生産へ移行した時期である。通商摩擦が欧米諸国との間に起こり、具体的には「欧米輸出自主規制」というかたちを採った。米国については81年から93年までこの規制が続き、EUについてはモニタリングという表現をしているが、八六年から何らかの形でEUへの完成車の輸出をコントロールしているという状況にある。
2 トヨタの海外戦略
21世紀初頭のトヨタの販売・生産イメージ
21世紀初頭に向けてトヨタでは今、何を考えているか。
トヨタは九五年に、世界で約450万台の車を販売した。これを21世紀初頭には600万台まで拡大したいと考えている。日本はかなり成熟した段階に入ってきており、市場が拡大したとしても250万台程度と考えられるので、従って、海外で350万台を販売することになる。これは現在より約100万台の増販である。供給面では95年実績の日本生産300万台、海外生産150万台に対し、日本生産350万台、海外生産250万台とすることになる。海外販売向けの供給ということでは250万台の海外生産と100万台の日本からの輸出で対応するという構造にするのである。
21世紀初頭のトヨタの海外生産は、販売が増えた分だけ現地生産を増加していくというイメージになろう。特にこれから市場が急速に成長していくと予想される中国、インド、ブラジル、あるいは東南アジアといった所では販売の増加に対応して海外生産を大幅に増加させていくことになる。
市場別に見た海外戦略
今述べた21世紀初頭のイメージを具現化するにあたり、地域別にどのように取組んでいくべきかを次に考えたい。
まず市場を成熟市場と成長市場とに大別し、さらにトヨタの参入度合いから既参入市場、実質未参入市場と分けてみる。成熟市場の代表的なものとしては米国、欧州、日本市場があげられようし、成長既参入市場ではASEANが代表的である。今後急速な成長が見込まれるものの、トヨタが実質未参入の市場としては、中国やインドがあるだろう。
それぞれの市場に対して、それぞれ違った戦略を持たなくてはいけないのは言うまでもない。
GM、FORDのグローバル展開との比較
ここでやや視点を変えて、トヨタとGM、FORDとのグローバル展開を比較してみたい。
トヨタの海外販売は250万台であるので、すでにFORDの海外販売とほぼ並んでいる。しかし、トヨタは日本をベースにした企業であり、国内市場で30%のシェアを持っているが、日本市場が米国市場に比べて小さいがゆえに200万強しか売れない。FORDの国内シェアはトヨタよりむしろ低いが、1500万台の米国市場では実に四〇〇万台の国内販売が実現できる。従って、世界市場でみる場合、トヨタはなかなか10%のシェアが取れず、FORDは13%を越えるシェアを持っているのである。
21世紀初頭にトヨタはどのような企業となりたいのか。前述のとおり海外では350万台売りたい。そうなれば仮に95年のレベルと比較してみると実にFORDの海外販売を遥かに抜き去り、GMのそれに並びかけることになる。しかし、現実には本国の市場の大きさの違いで世界全体としてはFORDのレベルに追いつかないということになる。従って、仮にGM、FORDと互していくためには、350万台からそれ以上へと順次海外販売台数を増やしていかなくてはならないだろう。
3 グローバル展開による変化と課題
21世紀初頭に向けて、グローバル展開によりどのような変化が起こり、どのような課題があるのか。
海外生産拡大でも日本に多く残る製造付加価値
まず、日本におけるモノづくりの付加価値についてみてみたい。
日本で車を作っていればこれは1台分としてカウントされる。しかし、海外で生産した場合、それはゼロになってしまうかというとそうではない。例えば、日本からトランスミッションやエンジンの一部など各種部品が輸出される。現地調達率を7割位と想定すれば3割程度は日本に残るという計算になる。このように日本側の仕事量をみると、バブル以前は完成車換算で約363万台分の仕事をしていた。これがバブルの絶頂期には約436万台分まで拡大したが、海外生産の進展や国内市場の大きな減速により345万台分まで減少した。この過程で明らかに製造面での仕事量は減少しているが、それでもバブル以前とそれほど変わらない仕事量はあったのである。
では、今後はどうかといえば、正直なところ厳密に仕事量は断定できないものの、海外生産が拡大することにより、日本に残る製造付加価値はまだかなりあるのではないかと思う。トヨタとしては、先程申し上げた計算前提でいけば、全体量が増加することにより21世紀初頭には425万台分程度にまでなる、あるいはそうしなければいけないと考えている。結果90年の、あの非常に忙しかった時代とほぼ同程度の製造付加価値が日本に残ることになるだろう。
海外展開上の課題−商品開発、生産技術、管理・販売
それでは、以上のことに伴い商品開発面ではどのようなことが起こるのか。
欧米先進国では次々と新しい商品を出していかなくてはいけないし、成長市場にはその市場に合った専用の車を作っていかなくてはいけない。現在、トヨタでは海外に約50のシルエットで約250万台販売している。シルエットとは、例えば同じカローラという車種でも4ドアセダン、クーペ、ワゴンといったものがあるが、それぞれを一つと数えたのがシルエットである。国内で販売しているものを、そのまま海外で販売しているのが約40、海外専用が約10という構成であるが、これを21世紀初頭には、約65シルエットで350万台を販売したい。しかしその構成をみると、日本、海外共通のシルエットも若干増えるだろうが、海外専用のそれは実に倍増するであろう。しかし、これにはそれ相応の開発を進めていく必要があり、これを進めるためには技術員を今よりも大幅に増やすことが必要になってくるのである。
また、生産技術面はどのようなことが起こるのか。様々な捉え方があるが、その中の代表的なものとして海外工場の新設という視点でみると、過去5年間、トヨタは海外の新工場により約20万台分の能力増強を図った。さらに今後5年間で建設を予定している新工場の能力が、合計約35万台である。もちろん生産台数を95年実績から約100万台増やそうとしているので、現有工場の能力も増強していく必要がある。これらの能力増強に伴う生産技術工数は、開発と同様大幅に増加することになるが、この付加価値の増加は、当面日本で発生することになろう。
以上のように海外展開に伴い、大規模なリソーセスが必要となる。リソーセスの三大要素は「人材・設備・資金」であるが、その中でも特に「人材」が非常に重要で、しかもより高度な人的リソーセスが要求されてくるのである。グローバル化のステップを考えると、いわゆる製造、管理、販売といった基礎的なオペレーションは短期間にグローバル化、つまり現地化の対応が要求されるし、またそれが可能である。しかし、商品開発や生産技術、あるいはトップマネージメントの現地化は非常に難しく、長期的に対応するというよりは長期的にしか対応できない、なかなかすぐには力がつかない部分なのである。従って、この長期的に対応をせざるを得ない部分は、逆にいえば短期的にはその大半を日本で対応せざるをえないということなのである。
海外発展上の課題
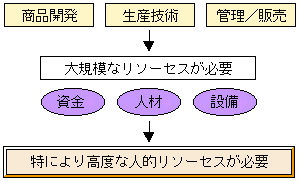
付加価値の高度化と人材育成・再配置
自動車産業がグローバル化を進めていく際、どのような変化が起こり、どのような課題があるのか。
グローバル化が進行しても日本では、製造面の付加価値はこれからも若干増える、少なくとも減りはしないだろう。また商品開発や生産技術といった面は、むしろ日本側の付加価値が大幅に増大していく。逆にいえば、人や金や設備が必要となってくるのである。その上、その日本側の付加価値は急速に内容が高度化していくのである。それは単なる製造ではなく、商品開発や生産技術といった面が非常に膨らんでくるからである。こうなると、やはり人の問題が一番重要になってくる。人材をどう育成し再配置し活用するかということになるわけだが、まず第一には自社内で人材を育成していくことになろう。次にグループ内で人材を育成し、再配置するのである。しかし、それでもミスマッチは生じるだろう。例えば、グローバル展開を行っても製造の仕事の三割位は日本に残るだろうが、それは平均的に残るわけではない。無くなる所は全部無くなってしまい、残る所は全部残るというミスマッチが起こる可能性がある。結果人材にもミスマッチが起こり、これを再配置する必要が生じるのである。そして、さらにはグローバルな人材活用が課題になってこよう。
トヨタの人材育成・人材活用のイメージ
トヨタのケースで人材育成のイメージを語るとすれば、例えば工場で作業をしている人、特に工長や組長といった経験豊富で力を持った人に、まずは新車の生産準備であるとか、工場の設備改善など、そのような方面に積極的に移行してもらうということになろう。そして、従来それらの仕事にたずさわっていた工場技術員には生産技術の開発や設備の開発にたずさわってもらい、最終的には現地会社のマネージメントをまかせていくというようなかたちで、人材を育成していくべきであると考えている。
人材再配置については、国際分業の進展により必要となってくる人材を他社からも得る必要がある。しかし、その前提として、やはり人材の流動化を促進する制度が必要となってこよう。特に日本はその方面で大変遅れており、人材を固定するのが得意な社会である。やはり年齢や経歴にこだわらず、キャリアをきちんと次の企業で引き継げる制度、あるいは評価の尺度の公平性、透明性といった改革が大変重要になってくる。
またグローバルな人材活用ということでは、例えばトヨタのアメリカの現地工場採用の中国系社員が、トヨタの中国プロジェクトに参画し、中国で仕事をする。あるいはインドのプロジェクトであれば、旧宗主国である英国採用のインド人またはイギリス人にマネジメントとして参画してもらうというようなことが必要になろう。GMの場合、中国の上海汽車と提携して上海で車を造ることにしているようであるが、このプロジェクトのために700人いる中国人事務技術員のうち150人位は中国へ派遣できる準備があるという。トヨタでは現状、そこまでできないが、将来的には行わなければいけないと思っている。
おわりに
日本の自動車産業はここ数年空洞化に苦しみ、将来について大変暗い見通しもあったが、グローバル化の進展を一層進めることにより、将来に渡って継続的な発展が可能であるし、またそうしなければいけないと考える。そのためには当然優れた企画力とその企画を実行していく展開力が必要となろう。トヨタ自動車は今、これらを念頭に積極的にグローバル化に取り組んでいる。
| ● プロフィール いわつき しんろう |