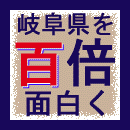
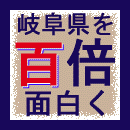 |
ちょっと派手なタイトルである。しかし東の「江戸八百町」や西の「大阪八百八橋」にくらべれば、まん真ん中の岐阜県を「百倍」とはささやかなものである。心配なのはむしろ話が看板倒れにならないか、ということである。 |
東濃への遷都は還都だ、という話
匠 照人・文
2月の岐阜県知事選に新首都誘致問題が争点になった。
岐阜県は、既に「岐阜東濃地域」で手をあげ、その理由の一つに「優れた歴史と文化」を主張している。
『日本書紀』の12代景行天皇条に、4年の春、美濃国の「泳宮」(現岐阜県可児市久々利)に行幸し、そこで八坂入彦命の娘・八坂入姫を妃に迎えて、後の13代成務天皇をもうけている。
その八坂入彦は、10代崇神天皇と濃尾平野の雄族・尾張氏の大海姫との間に生まれた皇子である。この泳宮のすぐ近くに皇子のご陵があって、宮内庁が管理している。また、この地から南の土岐市泉町には、八坂入姫の妹・弟姫を葬ったと伝える「乙塚古墳」がある。それから泳宮のすぐ近くの番場の地から大型のすばらしい銅鐸が出土し、その地から関市寄りの加茂郡富加町羽生の地は、日本最古の戸籍「大宝2年(702)の御野国加毛郡半布里戸籍」(正倉院蔵)のゆかりの里である。そして、戸籍が記された紙が、現存最古の「美濃紙」なのである。
ところで、この泳宮の位置は、古代には信濃国(長野県)から流れ下る「木曽川」と、飛騨国(岐阜県飛騨地方)から流れ下る「飛騨川」の合流地域を扼するとともに東国に対する重要拠点だったと推測されるのである。したがって、泳宮は、『日本書紀』に記されているようなロマンの宮ではなく、軍事的拠点性を帯びた宮だったのではないだろうか。だとすれば、一体、景行天皇はどんな目的でこの泳宮に行幸したのであろうか。古代における結婚は、平和的戦略の手段として盛んに用いられている。八坂入姫との結婚は、そうだったのであろうか。いな、私はそれだけではなく、もっと大きな目的、つまり大和朝廷の東国進出への拠点づくりのための東海王国の支配化の徹底にあったのではないだろうか。
これも『日本書紀』によるのだが、尾張氏は神々の住む高天の原から日向(九州)の高千穂の峰に降臨したニニギノ命の兄・火明命が始祖だとされている。この尾張氏が、学会では「欠史の時代」といわれている5代孝昭、6代孝安、7代孝霊、8代孝元、すなわち「孝」の字のつく天皇たちと血脈で結ばれている「フシ」があるとともに、9代開化、10代崇神の両天皇も濃尾平野の豪族たちと深いかかわりを持ち、景行もまた、皇子・日本武尊が尾張氏の宮ズ姫と、その兄・大碓命は美濃国の大根王の姉妹と結ばれている。さらに26代継体天皇も尾張氏の目子姫を入れて、安閑・宜化の両天皇をもうけているのである。
それで、尾張氏のこうした流れを追ってゆくと、欠史の時代といわれる「孝」の字のつく天皇たちの時代に、大和朝廷に先行して、尾張氏をバックとした東海王朝ともいうべき東海王国が存在していたのではないかと推測されるのである。ところが、最近、この濃尾平野に弥生末期に独自の文化をもった強大な「クニ」が存在していた。いわゆる「狗奴国尾張・美濃国説」が、考古学や歴史学の分野から主張されている。私はこれが当然のことだと思っている。
なぜかといえば、木曽、長良、揖斐いわゆる木曽三川によって造形された広大で肥沃な濃尾平野の存在である。ご存知のように、世界の文明社会の発祥は、チグリス・ユーフラテス両河川流域平野に開花したメソポタミア文明をはじめエジプト、インダス、中国などのように、すべて河川流域平野においてであった。このことは、日本の古代における「クニ」、ヤマタイ国、吉備、出雲、越、毛野の諸王国についても同様である。にもかかわらず、濃尾平野に「クニ」が存在していたということを聞かないのは、なぜか。このことは日本古代史上の大きな謎であった。そこへこの謎に応えるかたちで、「狗奴国尾張・美濃国説」が主張され、その延長線上に、私は「大和王朝に先行した東海王朝」をみるのである。
そして、さきの「泳宮」を中心とする地域には天皇氏に「聖水」をもって仕えた鴨県主氏や身毛津君氏らが、後の天皇即位式すなわち「大嘗祭」に深くかかわってゆくのである。
つまり、泳宮は、今日ではその存在すら伝説化されつつあるが、私はこうした推測から泳宮は、かつての東海王朝の王都の東辺を支配した皇族将軍・八坂入彦の宮所であったとみている。
その意味から、首都機能移転先に手をあげた東濃への「遷都」は、かつての東海王朝への「還都」だといった方がいいのかもしれない。
(次回はひだ・みのは超古代が花盛りだ、という話)