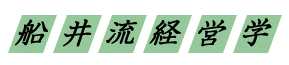
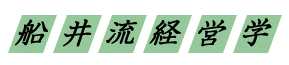
 |
|
健全なるスクラップ・健全なる赤字
ミネアポリスにMall of Americaという、450店のスペシャリティストア(専門特化店)を有する全米最大規模のショッピングセンターがあります。このMall of Americaに視察セミナーとして行ってまいりました。まず目についたのが閉鎖店舗の多さです。約30件ぐらいのベニヤを貼った店があったと思います。普通のショッピングセンターの場合、これは空店舗の多さを意味するのですが、このMall of Americaはかなりの好業績を上げています。約400億の目標に対して150%の600億を達成していたはずです。変化は常に起こっています。当然、時流にあっている企業とそうでない企業が生まれます。ディベロッパー側としては、時流に合った企業をどんどん誘致して、時流に遅れた企業には出ていってもらったほうが好都合です。Mall of Americaではこの作業を常に進めているのです。これが閉鎖店舗の多いひとつの理由です。そして、ディベロッパー側のもうひとつの狙いとして、「店揃えの整理」があります。ベビー用品を例にとると、このMail of Americaの入り口付近に一店、そして全く違うフロアーの端にもう一店の合計2店のベビー用品がありますが、これではベビー用品を見に来たお客様はとてつもなく広大なショッピングセンターの中を、へたをすれば数キロメートルも歩かされることになります。こうなったのには致し方ない理由もあります。オープン前には450もあるテナントを何とか「埋める」という作業が発生し、このために同業種の店舗が全く違った位置にレイアウトされるという結果を生んでしまったのです。また好業績のショッピングセンターには、オープン後は逆にテナント入居希望者が殺到します。そこでMall of Americaではこの際に、同じカテゴリーの商品を扱う店を1箇所に極力集中させるという「店揃え」の作業を実施しているのです。私はこの光景を見て、「健全なるスクラップ」の必要性を強く認識しました。
これだけ時流の変化が早いと、売れる商品と売れない商品がはっきりと分かれてきます。私が担当している宝石業界では2億円以下の宝石店は非常に厳しい状態で、昨年対比売り上げは60%〜70%という店も少なくないはずです。せめて1億円ぐらいの利益が出ている会社なら、売れないデッドストックを2000〜3000万円の赤字をはたいて処分しても持ちこたえられるでしょうが、そうでない会社が同じ事をすると決算書は全くの赤字となってしまいます。とはいっても、特にこのような店は銀行との付き合い上の問題もありますので、実際には半分ぐらいの値打ちしかない不良在庫商品を仕入れ当時の薄価のまま、とりあえず棚卸在庫として計上し今期は利益が出たという形にしておく。このようなことを繰り返しているうちに、不良在庫はますます積み上がり在庫商品の評価価値はますます低下するという悪循環に入り込んでしまいます。さらに資金繰りもだんだんうまく行かなくなり、身動きがとれないという状況に追い込まれる企業も少なくないはずです。ですから、もし本当に活性化を望むなら、そのようなデッドストックは赤字を覚悟で早期にはたいて現金に換え、いまの時流に合った商品を仕入れ直すべきなのです。銀行や外部への体裁にこだわるあまり、表向きには利益が出ているように見せ、水面下で不良債権を抱え込むということをしている企業は少なくありません。「来年、あるいは近い将来に徐々に償却すればいい」と会社側は考えがちですが、「頑張って利益を出しても結局は不良債権の償却に充当されるんだ」ということで従業員のモラールは低下してしまいます。結局これも「従業員のモラール低下→売上の低下→デッドストックの増加→不良債権の増加」という悪循環サイクルに入り込んでしまうきっかけとなります。
「健全なる赤字」は企業が潰れない程度に出して下さい。但し、「不健全な赤字」を正当化するためにこの文章を利用しないようにしてください。
のれんは自分で守るしかない
自社ののれんを守るのは自分たちであって、問屋やメーカーではありません。つまり、お客様から不良品の返品やクレームを受けてから問屋やメーカーにケチをつけているようでは、その店は二流店だと言わざるを得ません。私はこのことを仲庭総本店という百年の歴史を誇る宝石貴金属店の指導に行ったときに特に強く思い知らされました。当時この店の宝石の売上が16億円、時計部門の売上が5000万円でした。私は時計部門の活性化策として「ロレックスの並行輸入モノの取扱」を提案しました。この提案に対し先方はのれんに傷がつくかもしれないという理由であまり乗り気でない様子でしたが、何件かの信用できる問屋を紹介するなどして何とかこの提案を呑んでいただくところにまでこぎ着けました。すると5000万円だった時計部門の売上が翌年には数倍にまで跳ね上がりました。ところが仲庭さんから問屋への返品の多さに驚きました。私の最も信用できる問屋でも、納めた商品の30%近くが返品されているというのです。実は仲庭総本店さんは自分のなかに、のれんを守るための独自のルールを作っていたのです。まずは重さです。正規の代理店モノと比較してプラスマイナス0.2グラム以上重さが異なっていると、明らかに本物であっても返品。また、文字盤のコマ数が正規代理店を通して入ってくるものは12コマ+10コマの合計22コマとなっています。インドネシアやシンガポールからの並行輸入モノは14コマ+8コマで合計22コマとなっています。見た目には本当に分かりにくいわずかな違いですが、これを全てチェックして返品していました。これが「のれんを守る」ということなのです。他の私の指導先でここまでやったところは1軒もありませんでした。「信用できる問屋」と先ほど言いましたが、問屋は信用できてもメーカーや一次卸問屋がどこかでごまかしていることが往々にしてあります。自社で絶対基準を設け、徹底した検品を行なうことによってしか、自社ののれんは守ることができないのです。
他社がやっているから・・・では駄目
今まで皆さんは競合企業が行なっているサービスは自分たちもしなければならないと考えていたのではないでしょうか?時計の電池交換、ズボンのすそ上げ、配達など、「人がやっているから仕方なくやる」というのは包み込みの発想ではこれで正しいと言えます。しかし、サービスの本質を本当に捉えていると言えるでしょうか?今までの「これぐらいはやっておかねば」という考え方に基づいたサービスを、もう一度考え直す必要があるのではないでしょうか?
小売業マーケティングの概念は大きく四つに分かれます。ひとつは「市場のマクロな状態を知ること」です。マーケットサイズの推移であるとかパーソナルユース化がどれだけ進んだかがこれにあたります。
二つ目は「皆さんの店が立地している商圏の特性を知ること」です。これをエリアマーケティングといいます。例えば松江・金沢・姫路には餅菓子屋が沢山あります。これらの街は城下町として栄えたところで、人間関係を特に重視する風土がありますので、贈答・進物需要が大きく餅菓子屋が栄えることになります。伊達正宗の城下町・仙台には”萩の月”などで年商80億を超える企業もある程です。これがエリアの特性です。
三つ目は「皆さんのお店の中でのフィールドマーケティング」です。レジ客数・客単価の動き、部門別の推移、お客様の好みの変化などを知ることです。ここまでくるとお気づきになる方もおいででしょう。つまりマーケティングとはお客様一人一人の平均値なのです。
マーケットとはお客様一人一人のことなのです。ですから小売業に限らずマーケティングで最も大切なのは、「お客様一人一人の声を直接聴くこと」なのです。これが四つ目にあたります。
皆さんはクレーム以外のことで、皆さんのお客様や取引先からの要望や希望・意見などを一対一でお聞きする機会を持ったことがあるでしょうか?アメリカのステューレオナードという食品スーパーでは一週間に一回、レジで清算を済ませたお客様5〜10人に30分程度時間をとってもらい、応接にてクレーム・要望・意見を直にお聞きする機会を設けています。そしてこの内容は翌日までにまとめられ、全部長職に配布されます。さらにこの内容について月に一度会議を開き、良いと思われる意見に関しては翌月から即実行に移されます。これが「お客様の要望に真剣に耳を傾ける」というマーケティングの本質から生まれた「フォーカスクラブ」という同店独自のサービスなのです。皆さんの会社でもスナックや旅行などでお客様を接待する際、お客様の要望や意見を聴いているでしょうか?それだけでも接待はかなり有意義なものになります。
レター法「素直に実行することの大切さ」
当社の創業者である船井幸雄会長は、私が入社して間もない頃、私にこう言いました。「小山くん、1日10通手紙を書けば3年も経つと人生変わるよ。」その時の私には会長の言葉の意味がよくわかりませんでしたので素直には実行できませんでした。とはいえ、会長のいうことなのでできるだけ書くようには心がけていましたが、やはり1日10通は無理でした。しかし、この後でこのことを後悔させられる事件が起こります。
私はある日講演を頼まれて新宮の商工会に行く事になりました。その日は白浜空港から飛行機に乗って帰ることになっていたので、空港まで送ってもらったのですが、予想外に空港に早く着いてしまいかなりの時間をもて余すことになってしまいました。そこで私はその時間を利用して、その講演会を手配してくれた担当者に礼状を出すことにしました。それでもまだ時間が余っていたので、担当者以外の、その日に名刺交換をした方々にも「ついでに」礼状を書くことにしました。すると後日こんな内容の返事をそのお付きの人達からいただきました。「先日はお手紙本当に有難うございました。小山先生のようなお方が私の様な者にまでわざわざお手紙をくださるとは、夢にも思っていませんでしたので、とても感激しています。これからは自分の行く先々で小山先生と船井総研のことを宣伝して回りたいと思います。」私はこの文面を読んだ瞬間「しまった」と思いました。なぜなら今までずっとこのように手紙を出し続けてきたなら、このように私や船井総研のファンになってくださる方々がもっと沢山できていたと思ったからです。船井会長の言う通り1日10通として1年で3650人、12年で4万人近い私と船井総研のファンが全国にできていたかも知れないと考えたからです。
私の指導先の経営者で、このレター法を全く素直に実践された方がおります。私は毎年、「小山VIPツアー」と称するアメリカ視察ツアーを主催していますが、この方はこのツアーに皆勤で毎年欠かさず参加してくれています。このかたは毎回スーツケースを2個持参され、ひとつにはご自分の衣類等が詰まっています。そしてもうひとつのスーツケースには何と日本から持ってきた絵ハガキが5000通も入っているのです。前もって買っておいた絵ハガキに、宛名とメッセージを店のみんなで手分けして書いたものをわざわざアメリカからエアメールで発送するために社長自らが運んでくるのだそうです。エアーメールでアメリカから送られてきた手紙を読まない人はいないし、中には大切に保管する人もいるはずです。さらにこれを受け取ったお客様は、まさかアメリカから、それも社長自らが5000通も発送しているとは思わないでしょうから、自分が特別扱いされたと感じてとてもいい気分になるはずです。きっとこれによってこの店の熱烈なファンになってしまったお客様も多いことでしょう。私もさすがにここまで徹底されている社長さんを他に見たことがありませんが、素直であるということの大切さをあらためて痛感させられました。この社長さんが経営される会社は10年間で売上規模が10倍になりました。このような地道な努力をコツコツと積み重ねてこられた結果だと私は考えています。
独自固有のサービスで生き残り
 サウスコーストプラザというアメリカのロサンゼルスの南のオレンジカウンティにあるショッピングセンターの中にFAOシュワルツという70坪程度の玩具店があります。数年前、道を挟んで反対側に1500坪の売り場を擁するトイザらスが進出してきました。トイザらスには7メートルもある天上の5メートル近くまで商品が大量に積まれており、全て30%〜50%オフで販売されています。一方、FAOシュワルツは天上はせいぜい4メートル、商品は1.5メートル程度までしか積まれていません。値引き販売もなく、どう考えてもトイザらスの圧倒優位が目に見えている様でしたが、驚くべきことにこのFAOシュワルツはここ3年間110%〜118%ほど売上をを伸ばしているということでした。ここから導き出されることは、小さい店は小さい店なりに、大きな店ができないことを自分の長所として持つことができれば生き残ることができるということです。これを私は「独自固有の長所」と言っています。私は5年前、「日本にパワーセンターができたら私の指導先にもたいへんな影響がでる」と考え、そのパワーセンターやカテゴリーキラーの研究をするためにアメリカに折りを見て足を運んでいました。しかし、1500坪のトイザらスの横で立派に営業を続けるこの店を見た時に大きなショックを受け、「なぜこの店は潰れないのか?」その理由を探った方が日本の中小小売業の活性化に役立つと思い、研究を始めました。
サウスコーストプラザというアメリカのロサンゼルスの南のオレンジカウンティにあるショッピングセンターの中にFAOシュワルツという70坪程度の玩具店があります。数年前、道を挟んで反対側に1500坪の売り場を擁するトイザらスが進出してきました。トイザらスには7メートルもある天上の5メートル近くまで商品が大量に積まれており、全て30%〜50%オフで販売されています。一方、FAOシュワルツは天上はせいぜい4メートル、商品は1.5メートル程度までしか積まれていません。値引き販売もなく、どう考えてもトイザらスの圧倒優位が目に見えている様でしたが、驚くべきことにこのFAOシュワルツはここ3年間110%〜118%ほど売上をを伸ばしているということでした。ここから導き出されることは、小さい店は小さい店なりに、大きな店ができないことを自分の長所として持つことができれば生き残ることができるということです。これを私は「独自固有の長所」と言っています。私は5年前、「日本にパワーセンターができたら私の指導先にもたいへんな影響がでる」と考え、そのパワーセンターやカテゴリーキラーの研究をするためにアメリカに折りを見て足を運んでいました。しかし、1500坪のトイザらスの横で立派に営業を続けるこの店を見た時に大きなショックを受け、「なぜこの店は潰れないのか?」その理由を探った方が日本の中小小売業の活性化に役立つと思い、研究を始めました。
 まず、FAOシュワルツは全てのオモチャに触らせます。店員は子供と一緒になって遊んでくれたり、時には遊び方のコーチまでしてくれるという楽しいお店です。ところが一方のトイザらスは袋はやぶいてはいけない、箱には開けられないようにセロテープが張ってある、ファミコンソフトは現物でなく商品番号札を持ってレジで清算するなど、全く商品に触れることができないようになっています。これは少ない人員で大きな店舗を運用するためのノウハウなのでしょうが、大型店の弱点ともいえます。ここで私は「使用時体験の提供」の大切さにあらためて気付きました。オモチャ以外の商品に置き換えると食品の試食・靴の試着は「使用時体験の提供」だと思っていましたが、じつはこれだけでは不十分なのです。靴は試着してサイズが合うかどうかを測るだけで、それは使用時の感覚を体験することにはなりません。その靴を履いて歩いたり走ったりしなければ本当に自分の足にあっているかどうかはわかりません。アメリカのSneaker
StadiumやJust for Feetというスニーカー専門店ではこのことが実践されています。この店では鉄柵で囲んだストリートバスケット専用のコートが店内に設けられており、そこで気に入った靴を履いてバスケットボールをプレイしてもらうことにより、実際に靴を履いて運動した感覚をつかんでもらうことができるようになっています。お客様がその靴を買うか買わないかはそれから決めてもいいのです。これこそが使用時体験の提供なのです。日本の食品スーパーの試食は、店側が勝手にキャンペーンをしている商品だけに限られています。つまり売らんかなの試食しかありません。しかし、アメリカのステューレオナードでは店内全ての商品に関して試食ができます。私がソーダ水を買いに行ったとき、そこにいた店員さんに「これはソーダ水ですか?」と念のために尋ねただけなのに、その店員はそのソーダ水の瓶の栓を抜いてコップに入れて私に飲ませてくれたのです。これには本当に驚かされました。以来私はこの出来事を「ステューレオナードのソーダ水事件」として、皆さんに話して回っています。
まず、FAOシュワルツは全てのオモチャに触らせます。店員は子供と一緒になって遊んでくれたり、時には遊び方のコーチまでしてくれるという楽しいお店です。ところが一方のトイザらスは袋はやぶいてはいけない、箱には開けられないようにセロテープが張ってある、ファミコンソフトは現物でなく商品番号札を持ってレジで清算するなど、全く商品に触れることができないようになっています。これは少ない人員で大きな店舗を運用するためのノウハウなのでしょうが、大型店の弱点ともいえます。ここで私は「使用時体験の提供」の大切さにあらためて気付きました。オモチャ以外の商品に置き換えると食品の試食・靴の試着は「使用時体験の提供」だと思っていましたが、じつはこれだけでは不十分なのです。靴は試着してサイズが合うかどうかを測るだけで、それは使用時の感覚を体験することにはなりません。その靴を履いて歩いたり走ったりしなければ本当に自分の足にあっているかどうかはわかりません。アメリカのSneaker
StadiumやJust for Feetというスニーカー専門店ではこのことが実践されています。この店では鉄柵で囲んだストリートバスケット専用のコートが店内に設けられており、そこで気に入った靴を履いてバスケットボールをプレイしてもらうことにより、実際に靴を履いて運動した感覚をつかんでもらうことができるようになっています。お客様がその靴を買うか買わないかはそれから決めてもいいのです。これこそが使用時体験の提供なのです。日本の食品スーパーの試食は、店側が勝手にキャンペーンをしている商品だけに限られています。つまり売らんかなの試食しかありません。しかし、アメリカのステューレオナードでは店内全ての商品に関して試食ができます。私がソーダ水を買いに行ったとき、そこにいた店員さんに「これはソーダ水ですか?」と念のために尋ねただけなのに、その店員はそのソーダ水の瓶の栓を抜いてコップに入れて私に飲ませてくれたのです。これには本当に驚かされました。以来私はこの出来事を「ステューレオナードのソーダ水事件」として、皆さんに話して回っています。
このマクネアの環の図にあるような米国流通業界の流れの中で、現在百貨店は青色吐息、量販店はシアーズ以外なくなってしまいました。しかし、スペシャリティストア(専門店)だけは、小さい店ながらもいまだに生き残っています。この本質的な理由はこれまで述べてきたようなことにあると思われます。そしてこのようなスペシャリティストア(専門店)が沢山集合してできたショッピングセンターは、これからとてつもない力を持つようになると私は考えています。他社にできない自社だけのサービス、しかもお客様が本当に喜んでくれるサービス。これを提供できる企業はこれから先もしぶとく生き残っていくことでしょう。(完)
マクネアの環の理論
1957年、アメリカ・ピッツバーグ大学で開催されたシンポジウムの席上で、マルコム・P・マクネア教授は「小売の環の理論」を発表しました。
これまでのアメリカの流通、小売業は「良い品を安く」というマスマケーティングの風土の中で、経費節減による合理化、省力化をすすめてきました。それにより粗利益率を下げ、価格訴求を原動力に新しい業態と経営システムを生み出しながら発展してきたのです。事実、1830年頃に登場したスペシャリティストア(専門店。ただし日本とはやや異なる)以後、1988年頃に登場したカテゴリーキラー、メンバーシップホールセールクラブ(ウェアハウスクラブともいう)に至るまでの新業態は、常により低利益で広域商圏を制覇しながら成長を続けてきたといってよいでしょう。
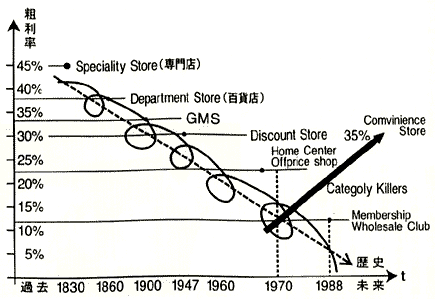
| こやま
まさひろ 昭和22年生まれ。早稲田大学理工学部数学科卒業。 ディスカウントストアの店長を経て昭和59年株式会社日本マーケティングセンター(現 船井総研)入社。 現在同社の専務取締役・ライン統括本部長。入社以来船井幸雄の右腕として活躍し、これまで数多くの地域一番店を育て上げ、”経営指導成功率100%のコンサルタント”の名を欲しいままにしてきた。著書は『船井流マーケティングの極意』『船井流肩書きがついたら読む本』『船井流リーダーの条件』『船井幸雄に学ぶ成功の黄金律』など多数あり。 |