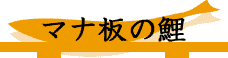
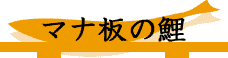
| ビール文化創造の 拠点として、 岐阜観光名所としても 育てていきたい |
マナ板の鯉 |
| 國井正英 クニロクビアファクトリー(株)代表取締役 國井孝洋 クニロクビアファクトリー(株)取締役統括部長 |
|
| 料理人 | |
| 藤掛庄市 岐阜大学教育学部教授 |
「岐阜を考える」のこの欄は、各分野の第一線で活躍していらっしゃる方に登場していただき、その話題が社業繁栄の一助になればということで設けています。
今回は、床材製造から地ビール製造に進出された「長良地ビール」の國井正英、孝洋両氏を岐阜大学の藤掛教授に料理していただきます。
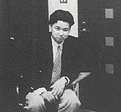 |
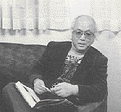 |
 |
| 國井統括部長 | 藤掛教授 | 國井社長 |
長良川の伏流水がうまいビールになった
| 藤掛 | さっそくお邪魔して『長良地ビール』をいただきましたが、いいですね。ドイツで飲んだビールのあのうまさとレンガ造りの建物、木をふんだんに使った様子からパブのあたたかい雰囲気を思い出しましたよ。 |
| 國井 (社長) |
ありがとうございます。地ビールは手作りが基本なんです。で、私どもは、岐阜の人に愛されて女性にも受け入れられる飲みやすさを求めて試行錯誤を重ねた結果、イメージに合ううまさが実現できました。雰囲気も味わいを左右しますから気を遣いました。 |
| 藤掛 | ”親しみやすさ”は地ビールの生命ですからね。 |
| 國井 (部長) |
そうなんです。そこで、親しまれるうまさを求めて、岐阜の水に注目しました。岐阜は水の街。岐阜の人が毎日飲んでいる素晴らしい水に恵まれている訳です。環境庁の「名水百選」に選ばれた清流・長良川の伏流水を利用するために、通常の倍以上の深さまで井戸を掘り下げました。 |
| 藤掛 | さらにいい水脈が生まれる『長良地ビール』というわけですか、うまいはずだ。 ところで、地ビールは大きく分けると”パブブルワリー”という自分の所で醸造し、自分のレストランで提供するものと、自分のレストランを持たず、特定のレストランだけに卸す”マイクロブルワリー”があるんです。ここは”パブブルワリー”にということになりますね。 ビールの種類はどんなものが揃っているんですか。季節によって好まれる味も異なると思うのですが。 |
| 國井 (部長) |
ピルスナー、デュンケル、ヴァイツェン、ブラウンエール、そして、スタウト。これは冬のビールですね。真っ黒でアルコール度数が若干高いタイプです。 |
グラス片手に花咲く、ビール談議
| 藤掛 | メーカーのビールに近いのは、ピルスナーですね。種類を聞いただけでうまさの違いがわかるまでになれたらいいのですが、みんなが味について談義しながら飲むようになると、まさにビール文化といえますね。 |
| 國井 (部長) |
そうなると作る方もつくりがいがあります。最近は、ブラック麦芽を使用して、ほのかな香りと甘みが特徴のデュンケルがよく出ます。 |
| 藤掛 | ピルスナーとデュンケルは下面醗酵で他は上面醗酵ですね。 |
| 國井 (部長) |
下面は低温で、上面は高温で醗酵させるわけですが、アルコールと炭酸ガスをつくりだす酵母そのものが違うんです。 |
| 藤掛 | 余談ですが、ラガービールのラガーという意味は下面に置く、ためておくという意味なんです。下面醗酵ですからね。 |
| 國井 (社長) |
そうなんですか。 |
| 藤掛 | それと「地ビール」はすべて酵母入りだということも特徴ですよね。この点がメーカーのビールとは違う。酵母は生きていて健康にいい働きをしますから。日本では発売当初、明治時代のことですが、ビールは薬屋でも売られていたんです。 |
| 國井 (社長) |
健康と美容にもいい。団体のお客様には酵母入りの良さを説明したりもしているんですよ。 |
| 國井 (部長) |
メーカーのビールで酵母入りは考えられません。飲む量に合わせて醸造する地ビールだからできるわけで、飲むまでに日数がかかるメーカーのビールでは酵母の醗酵によって味が変化しますからね。だから、出荷の際にろ過して酵母を取り除いているんです。 |
岐阜を盛り上げたい その願いから地ビールへ進出
| 藤掛 | さすがに日本では昼食時にビールを飲む週間はありませんね。 |
| 國井 (社長) |
ないですねぇ。 |
| 藤掛 | ランチと一緒にゆっくりとビールを飲む国もありますけどね。 |
| 國井 (社長) |
その違いがビール文化の差でしょうか。 |
| 藤掛 | 私の研究室の冷蔵庫にはいつもビールが冷えているんです。文化に貢献しているとでも申しましょうか。そういう意味では『長良地ビール』は文化に大いに貢献する余裕があるわけで・・・ |
| 國井 (社長) |
文化もさる事ながら、私どもは地ビールを作るということ自体考えてもいなかったんです。 現在、地ビールは全国に65位あると思います。そうしたなか、地ビールを作っているのは大体がレストラン経営とか、ハム製造業、牧場経営など、食べることに何等かの関連のある会社がほとんどですよね。私どもはまったく違う業種です。床材製造業から地ビール業への進出ですから。この分野に踏み込むことにあたっては正直なところ、迷いに迷ったのです。 |
| 藤掛 | そのきっかけは何だったんですか。 |
| 國井 (社長) |
親会社である國六工業では工場の跡地利用について何年も前から考えていたんです。マンションを建てる話やスーパーといった提案もありました。そうすれば家賃が入って楽なんですが、楽に収入を得ようということはしたくなかったんです。 私のこだわりにはもうひとつありました。それは、岐阜にはこれといって自慢できる文化がない。何でもいいから岐阜を盛り上げて、観光的にも何か役に立ちたいと以前から思っていたんです。そこに、たまたま息子が、統括部長ですが、勤めていた会社を辞めて帰ってきたんです。そして、岐阜に地ビールを、という話もあって、私は異業種から参入してうまくやっていく自信がなかったのですが、息子が「やりたい」というものですからね。 岐阜市も特色あるビールで新しい観光名所として売り出すためのPRに協力していくという力添えもあったものですから、踏み切った次第です。 |
| 藤掛 | 確かに話題を集める拠点になっていますね。どこか参考になっている先発の地ビールなどあったのですか。 |
| 國井 (社長) |
当時目新しさで話題になっていた地ビール第1号の『エチゴビール』をとにかく見に行ってみようということで新潟県巻町へ出かけました。そこは山奥なんですよ、バスも通っていない。昼前11時に先方に着いたのですが、すでにお客様が集まっているんですよ。女性同士も多い。ビールがこんなに人を集めるのかと感心しました。 |
| 藤掛 | ただビールを飲みに来ているのではなく、新鮮なコミュニケーションの場としての魅力もあるのでしょうね。 |
時間とこだわりを醸造。そこに熟すビール文化。
| 藤掛 | ドイツでビールといえば地ビールのことで、パブブルワリーにはさまざまな人々が集い、多くの情報が行き交う。そして、ビールの種類に合わせてグラスも異なるし、コースターにも特徴をもたせるなど徹底して暮らしに結びついたというか、そのパブならではの文化が息づいているわけで・・・・ 『長良地ビール』も岐阜の土地に根づいてビール文化の発信地として醗酵していくといいですね。 |
| 一口データ ■クニロクビアファクトリー株式会社 |