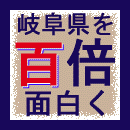
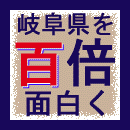 |
ちょっと派手なタイトルである。しかし東の「江戸八百町」や西の「大阪八百八橋」にくらべれば、真ん中の岐阜県を「100倍」とはささやかなものである。心配なのはむしろ話が看板倒れにならないか、ということである。 |
天武天皇は美濃で育ったのではないか、というお話
匠 照人・文
ご存知のように、古代における最大かつ重要な内乱だったといわれている「壬申の乱」は、今から1320年ほど前、天智天皇の子・大友皇子(乱のときは、天皇だった可能性が高い)と天智天皇の弟・大海人皇子が戦い、大海人皇子が勝利して天武天皇になった事件である。その時が672年で、壬申の年にあたっていたので「壬申の乱」と呼ばれるようになった。
ところで、歴史上では、現政権に反抗した、筑紫の磐井君、関東の平将門、関西の藤原純友などのように、大抵の場合、反抗者が破れているのだが、壬申の乱では勝利しているのである。これにはいろいろな意見があるばかりでなく、大海人皇子その人についても、天智天皇の弟でなく、兄だったとする説や、いや全く別人だとする説などさまざまであるのも、実は『日本書紀』は不思議なことに天武天皇の出生について、何も語っていないのである。だから謎が生まれるのである。
この謎について、私は次に述べる4つの理由から、天武天皇の出生と養育には、美濃・尾張の2国がかかわっていたのではないかと、我田引水的な憶測をしているのである。
その第一の理由は、天武の葬儀に際して、天武を養育したという人物、大海宿弥あら蒲が最初に壬生のこと、すなわち天武の出生・養育について、霊前で誅って(述べること)いることである。だが、このあら蒲自体の出自(経歴)も不明である。ただ『続日本紀』に大宝元年(701)に追大 (位)になり、冶金のために陸奥に派遣されたとある。
私は、この大海宿弥あら蒲の「大海」と尾張国の尾張氏の崇神天皇の妃になった大海姫の「大海」とは血縁的なかかわりがあると推測している。その大海姫は八坂入彦皇子(可児市久々利に宮内庁が管理しているご陵がある)を生み、皇子の娘・八坂入姫は景行天皇と結婚して成務天皇を生んでいるのである。
それに、私は大海人皇子を養育した地は、『和名抄』に記されている「美濃国池田郡壬生郷」現在の揖斐郡池田町辺りではないかとみているのだが、、それは次の第二の理由によってである。
『日本書紀』に、天武天皇の皇子時代の経済基盤としての所領として、美濃国の「味蜂間評の湯沐邑」が記されている。それは、現在の大垣市、安八郡、揖斐郡南部、それに不破郡の一部も入っていたかもしれないが、現在の西美濃の大半の地域を占める広大な地域であるばかりでなく、この地域は美濃国の穀倉地帯であり、織物・紙・鉄器具などの生産地帯でもあり、美濃国の人々もこの地域に集中していたと考えられる。つまり、天武は経済的にきわめて豊かだったとみることができるのである。それに、この所領の管理者「湯沐令」は、「多臣品治」なる人物である。天智天皇が皇太子のとき、百済の王子豊璋に多臣こも敷の妹を妃に与えた。多臣品治はこも敷の子とされ、『記・紀』の編さんに携わった太安万侶は、品治の子とみられている。一体に、多(太)は意富につながり、尾張氏の系譜には「意富那昆」、「意富阿麻(大海)比売」、「凡連の妹、目子姫」などのように「意富」と呼ばれる人物が多い。また奈良県の田原本町に太安万侶を祀った小杜神社があるか、一宮市於保にも太神社があるのも興味深く、天武も大海宿弥も多氏も尾張氏を中心に結ばれているように思われるのである。
第3の理由は、この乱で活躍した皇子の舎人、今日でいう秘書である。その舎人に、美濃の豪族の子弟である村国雄依、身毛君広、和珥部臣君手、それに美濃出身とみられる朴井連雄君(物部連雄君ともいう)らがいたことである。
『日本書紀』によれば、乱の発端は朴井連雄君が所用で美濃へ行ったところ、近江側に不穏な動きがあると、皇子に報告したというが、ひょっとすると、この人物こそ、密命を帯びた乱の火付け役だったかも・・・・。皇子はこの報告を受けるやいなや、さきの3人の舎人に、直ちに味蜂間評の湯沐邑に急行し、多臣品治と戦略をたてるとともに兵を集めて不破道を塞ぐよう命令し、皇子自身もあとを追って吉野を脱出し、美濃に向かうことを約しており、この乱における美濃とのかかわりの深さを物語っている。
そのうえ、注目すべきことは、近江側の動きに対して、皇子が終始、実に的確かつ迅速に行動していることである。これが第4の理由である。すなわち、671年10月19日天智からの天皇即位の打診を断り、その場で出家して、吉野の離宮に隠棲した。その年の12月3日に天智が没し、『日本書紀』は記していないが、大友皇子が天皇(後に弘文天皇と称される)に即位したと思われる。
朴井連雄君が近江側の美濃での不穏な動きを知らせたのは、明らかでないが、6月21日頃であろう。22日に、皇子は村国雄依ら3人に湯沐邑の多臣品治のもとへ急行し、戦略をたてるとともに、兵を集めて不破道を塞ぐよう命令した。その2日後、24日には皇子一行は吉野を脱出し、昼夜兼行で鈴鹿峠を越え、26日には伊賀の迹太川(三重県三重郡の朝明川)に到着。翌27日には一気に美濃の不破郡野上郷(岐阜県関ヶ原町上の地)の行宮に到着している。その頃には、既に不破道は3千の兵によって塞がれていた。そして、この地に皇子をはじめ長子の高市皇子らの首脳陣が集結し、皇子の進撃命令を待った。7月2日命令が下り、皇子軍は三方面に分かれて、大津京に向かって進撃を開始した。以来各地で激戦がおこなわれること21日間、ついに大友皇子は山前という地において自縊して、乱は終った。それは大海人皇子が吉野を脱出してからほぼ1か月のことであった。
大海人皇子が朴井連雄君の情報を聞いたとき、「・・・・・己むこと獲ずして、禍を承けむ。何ぞ黙して身を亡さむや」といって、反抗を決意したと、『日本書紀』は記しているけれども、それにしては以後の皇子の判断と行動が的確かつスピーディだったのはなぜだろうか。この謎の答えこそ、この乱の真相である。
私は、皇子はこのときをあるを期して、さきに述べた4つの理由のとおり、美濃の経済力を中心に、すぐれた兵力や武器、さらに豊かな食料などの調達について、長い間、綿密に計画し、、着実に実行していたのではないか。そして、その根底には皇子が美濃で育ったという絆があったからだと思っている。
(次回は東美濃への遷都は還都だ、という話)