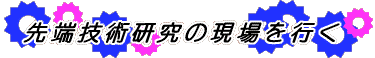
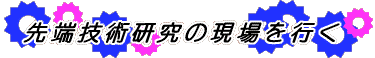
岐阜薬科大学生物薬学研究所
■ 新薬開発に活かすバイオ細胞の働き
 葛谷教務 |
時代の先端を行くものは華やかであり、人々の注目を集める。宇宙ロケットしかり、ニューメディアしかり。ところが、全体としてのロケットは科学者一人ひとりの地道な基礎研究の結晶であることを認識できるなら、その基礎研究こそまさに先端的なものとして位置づけられる。 |  井上教授 |
* * * * *
岐阜薬科大学生物薬学研究所の基礎研究も未知なる人間の生命科学に関わるものだけに日々の先端を行くところといえる。が、しかしその研究はあまりにも地道なために、宇宙ロケットのようにスポットを浴びる機会は皆無である。実は、何事においても、いかなる企業においてもこの基礎分野にこそ大いなる意義があるのだが。
医療の世界において、医学や薬学の進歩で多くの疾病が治癒するようになった。しかし、なお老人性痴呆やガン、エイズなどの疾病が人々の健康的な生活を脅かしている。こうした疾病に効果を発揮する新薬の開発に挑むことも生物薬学研究所の大きな役割のひとつである。
井上教授は、細胞を使い生薬がもっている薬効成分を大量に作り出す研究に取り組んでいる。生薬とは、植物を乾燥させたり人の手を加えることによって薬にする、いわば漢方薬の前の段階を指す。植物のほかに動物、鉱物もあるが、ここでは植物が研究対象となる。
まず、どの様な植物にどの様な薬効成分があるのかを探求する。次に、その薬効成分は他の植物には含まれていないかどうかを求める。あるいは、特定の薬効成分をバイオ細胞によって殖やすことはできないのか、細胞研究室での闘いは静かに繰り広げられる。平板にいうなら、植物がもつ薬効成分は微量であり、それを薬として用いるにはあまりにも少ない。それなら、植物自体が作り出すのを待つのではなく、バイオ細胞に作らせてしまおうということである。この薬用資源の開発法が先端的である。が、やはり地道すぎる。
確かに現実、生命科学の著しい進歩やコンピュータシステムの導入によって、新薬開発においても分子生物学的な新しい手法が取り入れられている。
個々の化合物の有効性をスクリーニングし、その中から薬になる微候の成分をみつけだすという方法がこれまでのやり方であった。しかし、現在では遺伝子組み替えや細胞融合などの最新のバイオテクノロジーを導入することにより生体成分からより有効的な新薬の開発が可能になっている。
ここ生物薬学研究所ではこのようにライフサイエンス=生命科学の先駆的研究が推進されているわけだが、加えて葛谷教授は”水”の研究も研究所のテーマになりうるのではという提案を私案としてもっている。
岐阜は、水に恵まれた風土にある。人間の体の60%は水分であり、地球上のすべての生き物は水に支配されている。単にH2Oだけでは解明できないほど奥深いものであるそうだ。
* * * * *
人類がこれまで経験したことのないものをビックリ箱を開くように見せてくれる、それが先端であると思いがちだが、そこには縁の下の力もち的な科学者の混沌とした研究が基礎にある。基礎の積み重ねによって人類は月面への一歩をしるした。生物薬学研究所の研究が老人性痴呆やガン、エイズ、O157などを克服する日も大いに期待できる。華やかではないが、注目していきたいところであることは間違いない。
生物薬学研究所/概要
|
||||||||||||||||
生物薬学研究所/主な役割
|
||||||||||||
生物薬学研究所/研究分野
|