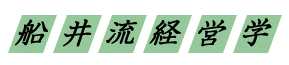
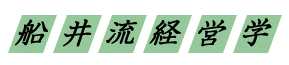
 |
|
チャンスは不況にある
マクロな時流について、私は村山節先生の文明法則史学をベースに考えています。ここで、ミクロな好景気・不景気というものを中心に戦後の歴史を振り返ってみたいと思います。昭和38年ぐらいの東京オリンピックの特需景気が終った頃からやや不景気に入り、次は昭和47年ぐらいから、第一次石油ショックに入ります。そして昭和57年の第二次石油ショックから不景気に入り、昭和で言うと66年にあたる平成3〜4年にバブルがはじけるといった流れになっています。それぞれの不景気ごとに9年前後の間隔が空いていますので、好景気と不景気が9年ぐらいで一周期を持っていることが分かると思います。もし我々が80歳まで生きるとすれば9×9=81ですので、死ぬまでに約9回の好景気と不景気を経験するということになります。
戦後創業した企業で年商1兆円を超えているのはソニー・ダイエー・ホンダですが、これらの企業は皆不況期に創業しています。また、私の指導先でもあるオートバックスの1号店も昭和49年開店ですから、ちょうど石油ショックの2年後に創業したことになります。このように不況期に創業した企業は、不景気型の経費支出スタイルで企業経営がスタートしますので、次の好況期で利益が出やすい体質を兼ね備えています。逆に好況期に創業した企業は好景気型の経費支出スタイルでスタートしますので、次の不況期には利益が出にくいという一定の法則があります。つまりこの法則から導き出されるキーワードは「新規事業に参入するには不況期・本業を強化すべきは好況期」という”逆転の発想”とも言えるルール化なのです。
バブルのころ景気が良かったからといって子会社をつくった企業は、この不景気では赤字のところが多いでしょう。不況期には不況期の過ごし方、また、不景気の利用の仕方というものがあります。好況期には下克上はありません。旧来の勢力もそこそこは業績も良いはずです。下克上は不況期に一気に起こります。こういったタイミングをうまく利用された方々が時代の寵児となっていることは皆さんもおわかりいただけることでしょう。こういった意味からも、好景気と不景気の波をもう一度よくご理解いただきたいのです。
”本物”というものについての定義
「オレンジ100%」という表記のジュースがあります。「オレンジ100%・天然水使用・濃縮還元」と銘打った缶ジュースを私はある日見かけました。でも皆さん、おかしいと思いませんか?なぜ「オレンジ100%」なのに「天然水使用」なのでしょうか?ここには2つの問題点があります。まず1つは、このジュースは濃縮還元ですからもともとは100%のオレンジジュースを一旦濃縮して、また天然水でもとの含水率に戻してあるということなのでしょうが、こんなものは本物ではありません。100%というのはオレンジからしぼった一滴一滴がジュースそのものでなければならないのです。そしてもうひとつの問題点、「天然水使用」という唄い文句です。ふと考えると「じゃあ今までどんな水を使ってたの?」と考えてしまいます。ここから言えることは「本物志向という概念は騙されやすい」ということです。「ロサンゼルスやハワイに行って飲んだ100%生ジュースは本当においしかった」という経験をお持ちの方がおいでのことでしょう。これは、「アメリカの果物がおいしいから」というよりもむしろ、「搾りたての本物」だからおいしいのです。このように、一度本物の搾りたての生ジュースを飲んだことのある人は、濃縮還元との味の違いに気付きます。私も搾りたてのジュースを毎日飲みたいと思って自分でスクィーザー(果物を搾ってジュースを作る機械)を買ってきて一度に10個のグレープフルーツを搾ってピッチャー満杯に生ジュースを入れて冷蔵庫に冷やしておきました。冷えればおいしいだろうと思って3時間後に飲むと味が全く変わっているのがわかりました。グレープフルーツが酸化してしまったのでしょう。
このように消費者が舌に味についてのモノサシを持つようになります。私の舌のモノサシでは「濃縮還元」「搾りたて」「3時間経過後の搾りたて」という3つのグレードを区別するようになり、低いグレードのものは飲まなくなりました。ユーザーがヘビーユーザー化していくという過程をご説明するためにジュースの例を挙げましたが、これからはほとんどの商品に関してユーザーがこのような尺度を持つようになり「より本物」を志向するようになります。今後はさらに進化します。前号でもご紹介しましたが、お客様の購買基準は「店 → メーカー → DCブランド」というように移行してきました。昨今では「モノサシ上の本物」がひとつの基準となっていると先程ご説明しましたが、これからは、「お客様自身」が購買基準になると私は考えています。過去の経験の積み上げに基づき、お客様は「より本物」を選ぶようになってきました。これに対応して既存の商品に「より本物性を付加する」というかたちで商品は進化してきました。ということは次の時代に何が売れるかを予測するには「本物性をどれだけ付加すれば良いか?」と考えるのが普通です。しかし私の予想は全く逆で「お客様が自らの尺度で良いと思うもの」が売れるようになると思います。客からすればあまり必要ない付加価値や機能が商品に付け加えられ過ぎたからです。
[客思考の変化]
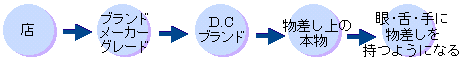
ヒット商品もブーム前は「変なモノ」
ではどのようにして次の時代に売れる商品を見つけるのか?まずは革新的消費者、つまり世間一般でいう「変な奴」の動きを察知することです。またわかりやすいように例を挙げましょう。私は6〜7年前から黒のナイキエアーをビジネスに履いています。ビジネスシューズをナイキに換えてから全く腰痛がなくなりました。今でこそナイキがブームとなっていますが、当時は田舎の指導先に行くと「先生、仕事に運動靴を履いているのですか?」とよく言われたものです。いまではそう言っていた人達も「先生は早かったですね」などと言っています。何が言いたいのかといいますと、革新的消費者はいつも初めのうちは「変な奴」扱いされますが、後にそれがブームとなってから認められる。歴史が変わるときには必ずブームが起こっています。このブームを巻き起こすのは一部の変な奴です。前にもいった通り「砂糖に群がる蟻」では儲かりません。ブームになった後にその商品を扱ったのでは競争が激しくなっていて利益率は激減してしまいます。また、「変な商品」からも次のヒットのベクトルをつかむことができます。例えば大規模商圏においてニッチ商品を販売する東急ハンズという店がありますが、まだ一般的に普及していない新しいタイプの商品ばかりを扱っています。なかには「何だこれ?」といった様な「変な商品」も混じっていますが、先程の「ブーム前は変な奴」といった観点からこれらの商品を見れば、次の変化のベクトルが少しは見えるのではないでしょうか?
「知ったつもり」が一番危ない
「育ちがいい」という言葉があります。私も部下に「もっとマナーを勉強しろ」という意味で「君たち育ちが悪いよ」と言ってしまうことがあります。しかしこう言われた部下は「小山さんは自分が育ちがいいと思っているから俺たちにそんなことを言うのだ」と勘違いしてしまう様です。しかし私は自分が育ちがいいなどと一度も思ったことはありません。私の父は高等小学校を出てすぐに家具屋を始め、一度はその家具屋を倒産させ、その後ディスカウントストアを始めました。その息子である私が育ちが良いはずなどありません。ただ、自分でマナーというものを全く知らないから、だからこそマナーというものを覚えたいと心から思っただけのことです。例えば、茶道では飲む前に茶碗を回すのが作法とされています。でも、「なぜ回さなければならないのか?」私はこのような原則的なことを知りたくなります。そうしているうちにマナーの本当の意味は「周囲の人達を不愉快にさせなければそれがマナーである」という私なりのルール化にまで最近は到達しました。
私は毎年仕事でアメリカに行きますが、その度に新しい発見をします。それを何十枚ものレポートにその場でまとめるのですが、この新しい発見があること自体、それまで私がそのことを全く知らなかったということを意味しています。だから私は「自分はまだ何も知らない」といつも思っていて、まだ自分の知らない物事をどこからでも必死に探し出そうと努力します。例えば私があるテーマについて研究を始めたら、毎年数十ページにもわたるレポートが出来上がります。前の年にレポートをまとめた時点では発見できなかったこと、見抜けなかったことが新しく際限なく付加されるのです。同じコンサルタントで2〜3枚のレポートにまとめたくらいでわかったつもりになって有頂天になっている人もいるようですが、これが一番危険です。
つい最近、船井総研の若い社員と仕事に出かけた時、喉が渇いたので自動販売機でジュースを買うことにしました。私が選んだのは安室奈美恵がCMをやっている Mistio という清涼飲料水だったのですが、その若い社員に「小山さん、安室のMistioなんて飲むんですか?」と冷やかされてしまいました。でも「自分はもういい年なんだから」といっていつも同じものばかり飲んでいては何の発見もありません。私は単に自分の知らない物事を知りたかっただけなのです。新しいものがあったら一度は試してみてそれが自分に合わないということがわかったなら次から買わなければいいのです。(無論、これは110円の缶ジュースだから気楽にできることですが・・・)。
ここで私がお伝えしたかったのは、人間はどこまでいっても「知っている」ことより「知らない」ことのほうが多いという意識で自分たちのレベルを再認識した方が良いのではないかということです。
資本主義社会での成功法
現在の社会システムは資本主義をベースとして動いています。資本主義とは資本を持っている者がその資本をどうやって増殖させるかという動機に従って動かされる仕組であると言えます。では資本のない人がその仕組の中で成功を収めるためにはどうすればいいのか?答えは簡単です。「メチャクチャ働くしかない」のです。人より多く働いて小さな資本を作る、この間に得た信用によってお金を借りる、このお金を増殖させるためにまた働く。この観点からすれば、資本のない人が人並みしか働かないで資本主義社会で成功するわけがないということがおわかりいただけるでしょう。
人並みしか働かないで、やれ「週休二日」だの、やれ「賃上げ」だの言っている人は資本主義社会の底辺を支えていく人達です。世の中には「トップ」になる一部の人達と「底辺」を支える多数の人達がいます。このどちらに属するかはその人自身の「心」が決めることです。だから自分が意図して底辺に属することを選択した人はそれでいいのですが、そのままでは底辺に属してしまうことに気付くチャンスすら与えられなかった人は本当に気の毒だと思います。とにかくこのことに気付いて「トップ」に属したいと思ったら今すぐに行動に移すことです。私の父は42歳で会社を倒産させ、44歳からたった60万円の資本で再び事業を興し、現在に至るまで約20年で50億円の資産を築きました。「20年もあれば人間は凄いことができるんだな」というのが私の実感です。とにかく「思い立ったらすぐやること」。これが全ての始まりです。
やると決めたら3年は粘ること
私はもともと本を読むのが嫌いでした。しかし船井幸雄会長に言われて、とにかく毎月20冊前後の本を読むという努力を3年間続けてみました。そうするといつの間にか読書が好きになっていました。もちろん初めのうちは苦痛で仕方ありませんでした。人間は新しい環境や行動に自分を合わせるのに時間がかかる生き物なのです。ある会社に入ってたった1年で「この仕事は自分に合わない」といってやめていく人がいますが、これは仕事が自分に合わないのではなく、自分が仕事に合わせようとする努力をしなかっただけのことです。新しい環境に飛び込んで行ったのだから、しばらくは合わないのが当然です。私も船井総研に入って3年目ぐらいが精神的にも肉体的にも一番キツイ時期でした。入社13年経った今、稼ぎも仕事量も当時の数倍にはなっていますが、体調はすこぶる好調です。それだけ自分が仕事に適合してしまっただけのことです。「3日・3月・3年」とはうまく言ったもので、仕事で言うと、まず会社のことを知るのに3日、周囲の人のことを知るのに3月、自分に仕事が合っているかどうかを知るのに3年ということになります。「5年で2回、10年で3回以上会社を移っている人は絶対に雇ってはいけない」という採用時のルールが船井総研にあります。何をやるにも3年以上、つらい中でも努力することができなければ何事も開花しないということです。
弱者の論理
|
| 7つの経営資源 経営に必要なのは7つの経営資源だと私は捉えています。ヒト・モノ・カネと一般的には言われていますが、その他に、時間・情報・技術・数字の管理力がなければ経営はできません。会社の力の差というのはこの7つの経営資源の調達力と運用力の差と言っても良いと思います。皆さんはこの本でいろんな情報を調達されることと思います。是非それらを仕事で生活で運用してください。運用しなければその情報は、一銭の価値もありません。余談ですが、”豊かさ”とは「金持ち」「人持ち」「時持ち」の三条件が揃うことだと言われています。確かに「金持ち」だけでは豊かとは言えません。本当に豊かな人はお金の他にも「時間」と「人材=人間関係」に恵まれています。私は今忙しすぎて「時貧乏」です。人材に関しては今でこそ素晴らしい部下たちに恵まれていますが、彼等が育つまでにたいへんな時間と労力がかかりました。こう考えると「豊かさ」への第一歩として、「金持ち」は最も容易に達成可能な条件なのではないでしょうか? |
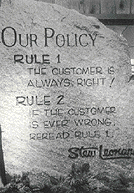 |
ステューレオナード(米国・食品スーパー)の店頭に置かれたオブジェ。
|
情熱は世界を動かす
 昨年の世界の資産家の長者番付は、西武グループの堤清二氏をぬいてジム・ウォルトン氏が第1位でした。彼はウォルマートの創業者サム・ウォルトンの息子です。そのサム・ウォルトンが
Wolton's Five and Dime
という小さな店をオープンさせたのが1946年でした。しかし、この店はいろんないきさつがあって閉店せざるを得なくなります。一旦は夜逃げまでしたことのある彼が、ロジャーズという田舎町にウォルマートの1号店を出したのが1962年でした。その後彼の店はディスカウントストアという新業態を確立し急成長し、現在では57万人の従業員を抱え、売上9兆5000億円・経営利益4500億円という世界最大の小売業になりました。まさに裸一貫から商売を始めた彼の情熱が世界を動かしたのです。後に彼がまとめた『SAM'S
RULE』の中でも情熱の大切さを説いています。ここにその一部を掲載しますので、皆さんの企業でも実践できそうなところは是非取り入れてみてください。
昨年の世界の資産家の長者番付は、西武グループの堤清二氏をぬいてジム・ウォルトン氏が第1位でした。彼はウォルマートの創業者サム・ウォルトンの息子です。そのサム・ウォルトンが
Wolton's Five and Dime
という小さな店をオープンさせたのが1946年でした。しかし、この店はいろんないきさつがあって閉店せざるを得なくなります。一旦は夜逃げまでしたことのある彼が、ロジャーズという田舎町にウォルマートの1号店を出したのが1962年でした。その後彼の店はディスカウントストアという新業態を確立し急成長し、現在では57万人の従業員を抱え、売上9兆5000億円・経営利益4500億円という世界最大の小売業になりました。まさに裸一貫から商売を始めた彼の情熱が世界を動かしたのです。後に彼がまとめた『SAM'S
RULE』の中でも情熱の大切さを説いています。ここにその一部を掲載しますので、皆さんの企業でも実践できそうなところは是非取り入れてみてください。
| SAM'S
RULES ルール1:COMMIT ルール6:CELEBRATE ルール10:SWIM |
| こやま
まさひろ 昭和22年生まれ。早稲田大学理工学部数学科卒業。 ディスカウントストアの店長を経て昭和59年株式会社日本マーケティングセンター(現 船井総研)入社。 現在同社の専務取締役・ライン統括本部長。入社以来船井幸雄の右腕として活躍し、これまで数多くの地域一番店を育て上げ、”経営指導成功率100%のコンサルタント”の名を欲しいままにしてきた。著書は『船井流マーケティングの極意』『船井流肩書きがついたら読む本』『船井流リーダーの条件』『船井幸雄に学ぶ成功の黄金律』など多数あり。 |