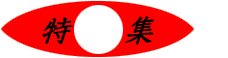
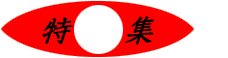
 |
新世紀への胎動と創造的企業への途 福 川 伸 次(ふくかわ しんじ) 電通総研社長兼研究所長 1932年生まれ。通商産業省産業政策局長、事務次官、その後、神戸製鋼所副社長、副会長等を経て、1994年より現職。 また、21世紀万博基本問題懇談会委員や行政情報公開部会委員、経済同友会欧州委員長等も努めている。 主な著書に「21世紀・日本の選択」、「美感遊創・プラスサムへの途」など。 |
はじめに−魅力のない日本
日本は一時ジャパン・アズ・ナンバーワンといわれていたが、最近では世界の日本に対する関心が下がっている。いってみれば日本に対する魅力が劣化していると考えられる。なぜそうなったか。その背景には三つ程理由があるようだ。
一つは日本経済の成長力が落ちていることである。最近ようやく景気が良くなり、全体としては緩やかな回復傾向だが、ここに至るまでの約四年間はゼロ成長に近かったのである。短期の問題であればそれ程心配したことではないが、長期で見ると果たして日本の経済成長力は弱くなってきたと感じる。このことはやはり真剣に受け止めなければいけない。
世界全体を眺めてみると、1985年頃からアメリカを中心に情報技術革新がとうとうと進み、息の長い景気拡大に入ったようである。80年代に、アメリカはレーガン大統領が規制緩和を徹底的に進め減税を行うことにより、ベンチャービジネスが活躍するようになっていった。アメリカの実業家に聞くと、もう日本の産業は怖くない、特に情報技術分野についてはアメリカは遥か先を行っているという。
これから日本は2010年になると高齢化が非常に進み、65歳以上の人達が今の14%から20%になる。2020年になると65歳以上の人達が25%になる。また2020年まで今の傾向が続くとすると、人口が減少し始める。今の日本は一人の女性が生む子供の数は1.43で、この傾向が続くとすれば、ある厚生省の友人が出してくれたデータによると、500年経つと日本人の数が約5000万人になり、1000年経つと40万人になる。1500年経つと2人になってしまうという。人口が減ってくるというのは実は大きな問題であり、経済の成長力に関係してくるのである。
二つ目は日本が保守的、硬直的であるということである。これまでも「前川レポート」や「平岩レポート」で、構造改革を進めなければいけないと提言しているが、欧米人の目から見ると、日本の市場は依然として閉鎖的であると映る。いくら通商交渉をしても、日本は変わって行きそうにもないという印象が定着している。
三つ目は日本が技術、文化の発信力がないことである。日本から新しいモノがなかなか出てこない。日本人は欧米で確立した技術を導入、改良し、安くて良いモノを作るというのには長けているが、本当のアイデアというのは日本から出てこないという評価が定着をしている。例えば、ノーベル賞の自然科学分野で日本人でノーベル賞を受賞したのは5人、アメリカでは170人くらい受賞している。どうも日本は自然科学の分野でもあまり貢献しないようだ。ソフト開発でいえば、ゲームソフト等は日本は大変進んでいるし、最近では日本の漫画が海外で評価をされており、欧米人の若者が日本の漫画を大変好んで読んでいる。しかし、基本的なソフトだとか、システム・デザインのベーシックの分野などでは日本からなかなか発信されない。これからは文化、技術、科学の分野から発信するということは非常に重要なことであり、日本はこの点で魅力がないと外国から思われている。
従って、日本の魅力をどのように高めるかを真剣に考え、新しい文化の香りがする活動とは何かを考えていく必要がある。
第三の産業革命−キーワードは”情報化”
今後日本の魅力を高めるためのキーワードの一つは、情報化ではないか。この情報化の能力を高めれば、恐らく経済の成長力も回復させることが出来るだろう。つまり、情報化を進めるには、規制緩和も進めなければならないし、社会の柔軟性も高まってくる。情報発信力についても同様である。また情報技術が進むということは文化性を高めることにもつながり、日本の魅力を回復させることにもなる。
情報化という言葉がいわれだしてもう3、40年経つが、最近、歴史的に非常に発展してきており、革命と名のつくような状況に入ってきた。情報化の第一段階は1960年代までで、コンピューターを導入し給与計算や在庫管理を行った時代であった。第二段階の1970年代には、大型化したコンピュータ、即ちスーパーコンピュータが登場し、企業の内と外を結ぶ情報システムが登場した。1980年代に第三段階に入り、半導体の技術が急速に進歩し高集積の半導体の出現により、ワークステーションやパソコンが登場し、ダウンサイジング化と低コスト化が非常に進んでいった。それに光通信に代表されるネットワークの技術が出てきて、ダウンサイジング化と低コスト化でネットワーク化が始まった段階である。そして1990年代、デジタル技術やそれを基礎として情報技術と通信技術が融合発展し、マルチメディアが出現をするという時代になっている。
1990年にジョージ・ギルダーが「テレビが消える日」という本を出版し、1995年にはビル・ゲイツが「未来を語る」という本を出版し、インターネット以降の生活のあり方、社会の変革を問うており、今日、第四段階に入っていると考えられる。このマルチメディアの出現で象徴される技術革新は革命というに相応しい。このマルチメディアというのはいろいろな特色がある。双方向インタラクティブなコミュニケーションのネットワークであり、画像、文字、音声等を統合的に伝達でき、大量の情報処理が可能になったのである。ジョン・ネスビッツという未来学者がいるが、彼はこの情報化が非常に進展した背景として能力の進歩とダウンサイジング化、低コスト化があると述べている。またコンピュータの能力を換算したコストはこの30年間で8000分の1になったという。もしコンピューターメーカーが行った努力を自動車メーカーで行っていれば、レクサス(トヨタ自動車)は二ドルになっているべきであるという。そのくらい情報化が進んだのである。
情報が加速する国際化
この情報技術がどのような変革をもたらすか。一つはボーダレス化を加速する。情報化が進むと、時間と距離と場所を超越し、企業は瞬時にして情報を地球上すべての場所に送ることができる。今のところ通信料金は遠距離逓増型であり、国際的な情報伝達となるとコストが高いが、現在開発が進められているイリジウムやインマルサットというサービスが始まれば地球の裏側に情報を送っても、名古屋に送っても料金は同じというサービスが提供される、もしそういうことになれば、時間と距離と場所を真に超越することが可能になる。
東西の冷戦が終わり、市場経済システムと民主主義が世界共通の価値観となった。このため、企業は利益を目指し商品、資本、技術、情報を自由に世界中に移動させることができるだけでなく、地球上で最も有利な場所に立地することも可能となった。このような状況になると、企業がどこに立地するかは、むしろ企業が選ぶ段階になったのである。フランス革命以来、ナショナルエコノミー(国民経済)が議論され、政治的なネーションステイトという領域の中でいかに経済の効率を高めるかというような議論がなされたが、今はネーションステイトのボーダーがなくなっている、少なくとも低くなっており、企業はどこに立地するか、どこが一番有利かを自分で選ぶ状況になっている。日本企業も海外で活躍するようになり、海外生産比率も9%程度まで上がってきた。85年が3%だったから大変な進展である。このまま行けば、今世紀末には14〜15%になると予測されている。アメリカ企業の海外生産比率が23%、ドイツが18%といわれているが、アメリカほどではないにしてもやがてドイツに近い水準になってくる。そのような状態になれば当然大競争の状態に入るわけである。そうなると、市場ルールの国際化や共通化が進んでくる。それは、知的所有権の保護であるとか標準化だとかだが、こうしたルールの国際化だけではなく、企業行動の国際化も進んでくる。このことは国際社会が同じ共通の場で競争するという条件となり、競争は激しくなるが、マーケットは大きくなり、ビジネスチャンスが拡大するのである。企業のルールも共通化されるので、まさに創造性が勝負という状態に入ってくるのである。
情報技術革命は技術革新を加速する
マルチメディアを中心とした情報技術革命は、技術革新を加速する。
まず、シミュレーション技術が非常に進んでくる。色々な発明、発見、あるいは見つけ出した原理を論証する場合、このシミュレーション技術というのが有効に働く。いろいろな条件の下での実験がコンピュータ上で可能になってくるのである。それから技術のデータベースも豊富になる。従って、これから様々な技術を開発する場合や違った分野の技術を融合しようとする場合、このデータベースを利用できる。しかもそのデータベースは国境を越えた地球レベルのデータベースであり、技術に関する情報を非常に多く蓄積をすることができる。今まででも異分野の技術融合は行われてきた。電子と機械とか、科学と生物とか、新素材と電子とか、農業とバイオとか様々な形で組み合わせが成されてきた。実はそのような技術融合は、それぞれ固有の分野の技術開発と同時に情報技術、情報処理技術の進歩に起因しているということが大きな特色になっているのである。
21世紀になって期待が持たれる分野は、一つはデジタル技術、もう一つは生物系の技術だといわれている。特に生物系の技術が非常に進歩するということは、それがバイオ技術を進歩させ、人間の能力についての科学的解析を進めることになり、これらが特に伸びて行くであろう。相互に技術情報を交換し合い、あるいは技術の発明、発見と融合し合うということは技術革新を非常に進めるのである。21世紀は地球環境に関する技術ニーズが非常に高まってくる。これを解決していくためには、デジタル技術と生物系の技術がかなり重要な要素となる。
最近、食料不足や食糧危機が起こるのではないかと心配されている。シカゴの穀物相場はこの1年間に約2倍になった。穀物、トウモロコシ、小麦の国際的な在庫はピーク時のおよそ3分の1に下がっており、将来の食糧不足が問題となっている。しかも中国やインド等の人口が増え、やがて相当量を輸入する等国際市場に頼らざるを得ない状況になるという。中国は最大の小麦や穀物の生産国であるが、2000万トン程の穀物を輸入すると発表するとシカゴの穀物相場は上がる。しかし、問題は長期的に見た場合で、人口が増加し、発展途上国、特にアジアの国々が工業生産で発展をしてくると生活水準が上がってくる。生活水準が上がると肉食が増えてくる。いろいろな計算方法があるが、例えば牛肉の場合、穀物の消費は8倍〜10倍、豚肉の場合、4倍〜5倍、鳥肉の場合でも2倍〜4倍の穀物が必要となり、大変な穀物需要が出きてしまう。この食糧の問題は相当重要な問題になるのである。
特にアジアの工業化が進むと、エネルギー需要が増える。そうすると当然に環境汚染も進み、チッソ化合物あるいは硫黄化合物により酸性雨が降る。化石燃料を多く使うと二酸化炭素が増え、地球の温暖化が進む。当然食糧生産は落ちてくる。この問題を解決するには、農業技術の進歩が必要であるし、農業投資を増やすということも必要である。しかし、特に問題なのは農業技術についてである。環境破壊や環境汚染が進むと、食糧減産の一つの原因になっている。
環境破壊というのはPATにかかっているといわれている。PというのはPopulation(人口)、AというのはAffluence(豊かさ)、TというのはTechnology(技術)のことである。従って、人口が増えれば生活水準が同じでも環境汚染は進むし、人口が同じでも生活水準が高くなれば環境破壊は進むということになる。いずれにしても人口は必ず増えるし、豊かさも世界が成長していけば環境は破壊される。だから問題の解決はこのT(技術)に頼るしかないということである。この地球環境をどう守るか、あるいは農業技術をどう開発するかというのは実は非常に重要な課題である。
このように、技術開発をどう進めるかは重要な問題である。これからいろいろな分野の技術開発が進むだろうが、もう一つ非常に期待されているのが人工臓器、人工骨等人間に関する分野である。高齢化が進めば特に重要になってくる。人工臓器等はどのように技術開発するかは非常に重要になってくるし、脳神経等の機能の解明を、産業技術に結び付けていくということが重要である。このようにこれからは、生物系の技術やデジタル系の技術の活躍の場が非常に大きくなるに違いない。
情報技術革命は価値観を変える
情報技術革命の第三の変化は、価値観を変えるということである。マルチメディアが日本人の間で本当に定着するかどうか疑問の声もあるが、マルチメディアが普及するということは、消費者や生活者が自分のニーズを自分で判断をするという価値観が非常に高くなるということである。日本人は流行に左右されやすいとか、他人からどう見られるかという「恥の文化」あるいは「横並びの文化」というものがある。しかし、情報が非常に豊富になり、情報が欲しい時にインターネットでアクセスする時には、自分が何を求め、どのような情報が必要かということが分からないとアクセス出来ないため、消費者や生活者は自分の価値観や判断を明確にするようになる。従って、日本の市場も従来と違い、低価格志向と高価値志向に変わっていくであろう。
消費者や生活者は、価格に対し非常に敏感になってくる。最近、消費が盛り返してくるかどうか議論の対象となっているが、消費者は非常に正確に判断をしている。つまり、安くしているものの需要は非常に根強く、また何か工夫したものは売れているということである。どのようなニーズがあるかは実は消費者がよく知っているのである。
それからもう一つが高価値志向である。消費者や生活者の特徴としては、文化価値と時間価値が高まってくるということである。
まず、文化価値についてであるが、自分がどのようなモノが欲しいか明確になってくるため、価格だけでは決定しない。文化的な情報が豊かになれば、本来人間は高次元の精神活動に憧れているため、情報を通じる文化性が非常に高まってくる。しかもデジタル技術でモノを作ったりサービスしたりする技術は非常に進んでいるため、情報技術と文化の関わりは様々な所で深くなっている。例えば、良いデザインの商品を求めるということである。もちろんその中には美しさが商品の中に求められる。
そして文化の伝達手段を非常に高度化をする必要がある。例えば、文字情報を瞬時に送る場合、ファックスでもEメールでもすぐに送ることができる。また文字情報を送ることができる。そして文化的な表現手段も非常に高度化する。電子音楽はその一つの例であり、その表現手段も非常に多様化する、
もう一つが時間価値であるが、現代は一人電話一台時代といわれており、携帯電話も非常に流行っている。確かに携帯電話から出る電磁波が人間に多大な影響を与えるといわれているし、今アメリカで問題になっている、コンピュータメーカーやソフトの開発をしている人達の子供に女の子が多く生まれるという現象について、その対応策を考えなければいけないが、いずれにしてもこの時間価値を高めることは社会に大きな影響を与えることには間違いない。これからはホームオートメーションも非常に進むだろうし、電子医療情報システムにより病院に行かなくても、家であるデータを入力すれば必要な診察をしてくれる。これも時間価値を高めているのである。このような価値が高まってくると、情報のニーズがより明確になりニューズ・オン・ディマンドとかビデオ・オン・ディマンドというものも出てくるだろう。このことは当然のことながら社会を変えるし、今までアクセスできなかった情報も入ってくるので、いろいろなコミュニティー活動も活発になってくるだろう。
産業システムの構造変化
情報技術革命は、産業システムをどう変えるか。20世紀型の産業システムとは大量生産、大量消費により、モノをいかに安く作るかというシステムで、設備の大型化、規模の標準化、職場の分業という形で効率を上げていった。しかし、情報技術革命が進展すると多品種少量生産も可能となる。消費者の価値観も多様化し、自分の欲しいモノが明確化されるため、モノを作る場合、例えば、自動車なら、このタイプの自動車を大量に作って宣伝し、消費者に買わせるということだったが、これからはどういうニーズがあるか把握した上で自動車を作る必要がある。ただ、ニーズを把握することは非常に難しいが、情報システムが進んでいくとそれは可能となる。これをフレキシブル・マニュファクチャリング・システムというが、非常に多様な商品を効率よく作る技術ができるのである。このようになれば、情報通信産業自体も多様化してくる。通産省や経済企画庁の予測でも情報通信産業の分野は、2010年までに今のマーケットの3倍になり、雇用は今の2倍になると予想している。通信産業においてもメディアは非常に変わっていくといわれている。テレビの多チャンネル化やインターネット等による情報サービスも増えてくる。そうなると、その情報提供に情報を乗せる産業も増えてくる。例えば、ハリウッドは映画産業で非常に有名だが、最近インドと提携する状況が伺える。インドのボンベイではいろいろな映画を作っているが、ハリウッドと衛星回線でつないで、画面をグラフィックスで作らせハリウッドで編集するというようにソフトやコンテンツの作り方が変わってきている。旅行代理店も取り次ぎ業務は次第にインターネットに取って代わるであろう。今でも飛行機の予約はインターネットでできるし、どのようなルートで行けば一番安く行けるかもコンピュータで全部でき、直接飛行場に行けば良いのである。恐らく旅行代理店は、旅行コンサルタントとか文化コンサルタントの業務に変わっていかなければいけなくなる。このように知らず知らずのうちに情報化というのはいろいろ産業を変えていくのである。
マニファクチャリング・オン・ディマンドというのがこの頃よく話題になっている。原理をいえば、例えばセーターを注文する場合、自分の絵を送り、どの色のどのパターンが良い等、いろいろ条件を付けて送信する。そうすると自分の送った画像に注文したセーターをのせてくれ、良ければ注文する。それを編み上げて送ってきてくれるから、同じセーターを着ている人に会うことはない。繊維メーカーにとって非常に困るのは返品で、売れ残りが返品されてくる。しかし、一品生産だと返品が無くなり合理化する。ただ、全てがそうなるかといえばそうではない。ギルダーの「テレビが消える日」という本が有名になったが、テレビは消えないだろう。それから、バーチャルショッピングだとかショッピング・オン・ディマンドがはやされているが、今の流通過程が全くなくなり、皆コンピュータで注文するかといえば、きっとそうではない。ただそういう変化の兆しがあるということであり、恐らくバーチャルショッピングでモノを買いたいという人もいるが、やはり自分で手に取って鮮度を見たいというお客は必ずいる。高価なモノはやはり自分の目で確かめたいという人もいる。従って、マス・セールのようなものも大規模店舗も専門店もなくなるわけではない。ただ、選択の手段が非常に多様化し、競争が激しくなるということである。そして、消費者の選択手段の多様化が、ビジネスチャンスにもつながるのである。
日本型企業経営の限界
最近日本型企業経営が反省されている。この日本型企業経営では、これからの情報化時代は生きていけないという声が非常に多く出ているのである。
日本型企業経営とは何であるか。これは1940年代の統制経済に端を発しているという見方もあるが、いわゆる労使の安定、長期雇用、年功序列賃金体系、そして企業内組合といったもので、やはり戦後日本企業経営の大きな特色であった。労使関係をいかに安定させ、所得水準が低い時代にどのように生活を保証するのかという点で、長期雇用の保証がなされ、また、生活給的な発想を原点に年功序列賃金体系が出来上がったのである。
しかし、問題はこの日本型企業経営が、最近いわゆる「老化現象」を起こしてきているということである。1973年と79年ににオイルショックがあったが、日本はこれを見事に乗り越え、当時は日本型企業経営について世界から賛美された。しかし、バブルの辺りから日本型企業経営は陰が薄くなってしまった。実際、企業経営を見ると、なんとなく現在の雇用を維持し、年功序列については、余程企業経営が悪化しない限り雇用調整が出来にくいという情勢が生まれている。そしてこの制度は形式化して、いわゆる終身雇用という制度だけが残ってしまい、能力の育成や内部の競争があまり進まなくなってしまった。また経営が惰性化すると、前例主義になってしまい、節度ある経営とかけ離れてしまったのである。従って、日本型企業経営というものについて、問題や批判が起こり、創造的な経営が必要なこれからの時代に、今の日本の雇用システムがうまく機能しないのではないかという反省が起こるのである。
しかし、日本型企業経営が全部悪くて、創造的な競争には太刀打ちできないということになるのかといえばそうではなく、日本型企業経営の良いところは良いとして残していく必要がある。実際、何が良くて何が足りないのかということをよく考え、日本型企業経営のあり方を考えてみる必要がある。例えば、アメリカ型企業経営を真似るだけでは、差別性ある競争ができるのではなく、違いがあるから強い所があると考えなければいけない。一番いけないのが「大企業病」である。ベンチャービジネスに代表されるチャレンジングな経営が必要な時代に、日本の、特に大企業は臆病な企業経営をしており、前例主義をどのように脱却していくかが大きなカギとなる。
企業独自のコンセプトと企業文化の確立
こうした状況の中で、企業は、これからどのように対処すべきであろうか。これからの企業で重要なのは、事業目標、ターゲットをどのように設定するかということである。情報システムを活用し、他社より有効なものは何か、我が社の経営資源がどういう所にあるか等を十分に評価した上で、何を目指すかという事業目的をハッキリさせることである。
よくアメリカで比較されるのが「デック社」と「ヒューレットパッカード社」という二社で、これらがよく議論の対象となる。
「デック社」というのはコンピュータのメーカーであるが、何でも自分で作るオールラウンドプレイヤーである。従って、一社で総合的にモノを作るという戦略を採っている。「ヒューレットパッカード社」というのは逆にネットワークを利用してモノを作るメーカーである。ネットワークの中心的な分野は自社でやるけれども、その他は有利な相手とネットワークを組んで事業を行っている会社である。現在、この二社が非常に特徴的な二つの事例だといわれており、業績は「デック社」は悪化し、「ヒューレットパッカード社」は好転している。
この二社にはそれぞれに様々な要因があったと考えられるが、今企業として何をすべきかといえば情報技術を活用していくことである。場合によっては戦略提携を行うべきである。技術条件が非常に複雑化してくると、異分野の技術融合が新しい発明、発見につながっていく。自社だけの技術的資源ではできないモノがでてくるため、当然に優秀で技術的能力の高い他社と提携することが重要になってくる。また、外部の優秀な能力を活用するということも必要になってくる。
日本型企業経営は全部が悪いわけではないし、非常に良い面もある。特にこれからは価値観が多様化してくるため、企業経営者は人を大切にし、長期的経営を睨んでいなければいけない。これから日本企業もシェア重視より収益重視に変わっていくだろうが、長期的戦略に合わせた人材の養成をし、人を大事にすべきである。結局は「企業は人なり」なのである。また、企業の文化をどのように育てるかも重要であるが、チャレンジングな新しいモノを作っていくという企業の文化を育てるべきである。
企業倫理と企業創知
企業として知識創造の重要性がいわれるが、一つの例として、ある学者が、知識というものには「暗黙知」と「形式知」があると指摘した。「暗黙知」というのは、「消費者はこう考えそうだ」とか「こういうものが当たりそうだ」という長年の経験と情報からくる勘のことである。そして、実際に事業化していく時には「形式知」がいる。
これは「情報システムに乗せる」とか、「事業予測をする」とか、いわゆる形式でハッキリさせることである。この「暗黙知」と「形式知」がスパイラル的に上昇していくことが大事だと考えられ、「形式知」が高くなれば「暗黙知」を考える場合の情報データが大きくなり、それに自分の別の経験を加味していけば、またそこに「暗黙知」が高まり「形式知」も高まるということである。このような企業文化を作っていくと、いわゆるスパイラル的に知識が高まっていくムードができるのである。
最近よく企業倫理の問題がいわれるが、企業倫理を間違うと企業は大変窮地に落ち込む。例えば、日本系銀行のニューヨーク支店での事件やロンドンの商品取引所で失敗した事件等はその例で、企業倫理は最低限必要な要件で、その上で企業の知識創造ということを考えていく必要がある。
変化に感応する情報システムと企業のコアの確立
次に変化に感応する情報システムを構築すべきである。市場や技術の条件は変化が激しい。社会ニーズは非常に多様化している。また、変化が非常に激しいためリスク管理や迅速な意志決定も重要になってくる。迅速な意志決定をするには変化に感応する情報システムが重要になってくる。
また、競争力のある企業のコア(核)を作っておくことも必要である。コアというのは決して一人の力でできるのではなく、企業の知的能力のある集団が技術開発をしていくことによりできるのである。企業の技術革新を担うコアや競争力あるコアというものは、企業として大事にしなければいけない。これからはデジタル技術と地球環境関連技術が非常に重要になってくる。人々の価値観も激しく変化し、多様化する。このような中で何をするか考えた場合、経営者一人ではなかなか判断できない。やはりグループによるコアが重要だということになってくるのである。
経営資源の回転率を速く!
経営資源の回転率を速くしなければいけない。例えば賃金や労働、資本の回転率、技術の回転率、情報の回転率等、これらの回転率を速く、高くすることが収益を高める一つの源泉となる。今までの日本の企業、特に大企業は全部自社の中に様々な機能を持っていた。1960年代〜70年代は「重厚長大」の時代といわれ、その次に「軽薄短小」の時代がきて、その後マーケットは「美感遊創」の時代がきた。日本の大企業は重厚長大であるため、非常に回転率が低くなっている。このため、企業は固定費をできる限り減らしておく、いい換えれば軽装備にしておく必要がある。景気がよくなり、忙しくなった時は、人材派遣の人を使うということを考えたり、季節的な仕事は、外部に出すという形で、企業を軽装備にしていくことが重要なのである。つまり、変化に機敏に対応するようなコアになるものは持ち、それ以外はある程度外部との連携を図って対応することも重要なのである。
価値創造へのエンパワメントと人材重視
これから企業として社会に求める価値にどう答えていくべきか。社会の求める価値をいかに創造していくかが重要なカギになってくる。このために必要なエンパワメント、いわゆる力付け、動機付けが非常に重要になってくる。そうすると当然のことながら人材という問題が重要になってくる。日本型企業経営のうち、年功序列賃金体系とか終身雇用制というのは崩れかけている。しかし、コアになるものは残っていくだろう。
あるベンチャービジネスの方と話をした時、非常に優秀で創造力のある人は採用しないという。なぜ採用しないかといえば、日本企業の組織に入れてしまうと、結局足を引っ張られて、能力を殺してしまうからである。もし、日本の企業の中で非常に良い成績を出した場合、その人にたくさんボーナスを払おうとすると他の人から妬まれるということになる。まだ日本ではベンチャー的風土が企業の中に育っていないため、今のところは社外にいてもらい、契約ペースで、成功したら成功払いでドンと払うというようなことを考えているわけである。
最近ベンチャーの中で、ストックオプション制度ができた。一生懸命働き、安い値段で契約した株が市場で高く売れた場合、大変なボーナスが入るという制度で、これもエンパワメントの一つの方法だと考えるが、今後いろいろな形の人材養成が必要になってくる。当然人材は非常に必要となってくるわけだが、最近よくいわれるのが、ミドルマネジメントである。企業の意志決定の時にトップダウンとボトムアップの方法があるが、日本は主としてボトムアップの意思決定で、この方法はモノづくりには非常によいということがいわれているが、これからの変化の激しい時代にはトップダウンでなければいけないという人が多い。また、ホワイトカラーの役割がこれからは非常に変わるだろう。特にホワイトカラーのミドルクラスの能力を決して軽視すべきではない。人によってはミドルアップ、ミドルダウンということをいう人もいるが、いくら経営者が多角的な能力、多彩な能力のある経営者であったとしても、一人ではできないし、情報システムを開発するにしても、経営者が自分で全部やるというわけにもいかない。また情報システムをどう作るか、情報をどう取るか、その情報をどのように経営戦略に結び付けるかという点は、このミドルクラスの役割が重要であり、戦略を考えるミドルクラスが欠かせない。そのような人材をいかに養成していくかが今後の重要な問題になってくる。
企業経営はアートだ!
最後に、これからの経営で、ヒューマニズムの経営というのが実は非常に重要になってくる。つまり人間を大事にするということである。企業経営とは一つのアートではないか考える。経営というものを演劇に例えると、経営方針、経営戦略というシナリオがあり、演出家に相当する経営者が俳優に当たる社員の能力を発揮させる。そしてそのパフォーマンスを通じて人々に満足と感動を与える、つまり消費者あるいはお客様に満足する価値のある物を提供するということである。時代が変わり、価値観が変わり、表現技術が進歩すると、それに応じてまた新しいシナリオを書き、演出方法も変え、社員たる俳優の育成方法も変えていくということである。
21世紀の企業経営というのは、アートと同じように人間的であり、人々に感動を与えるという革新性が必要である。情報技術革命はとうとうと進んでいるが、それはまさに企業経営に新しいシナリオ、新しい戦略、魅力ある演出、いわゆる人々を感動させる経営というものが期待されているのである。21世紀の情報技術革命後の企業経営というのは、非常に人間的であり芸術に近い。しかも革新的なものである。
(去る8月30日に岐阜グランドホテルで開催された「21世紀型企業人と匠の村交流会」の記念講演をまとめたものです。)