

1岐阜提灯と美濃傘
元岐阜県博物館館長 廣田照夫
岐阜提灯、美濃傘、それに岐阜団扇は、県内で生産されていた「紙と竹」を原材料として、発展してきた特産品である。うち岐阜提灯と美濃傘は、戦後全国一のシェアを誇った時期もあったが、打ち寄せる産業革新の荒波に飲み込まれて衰微していった。それでも岐阜提灯は新製品の開発による販路の確保に努めて、今日に至っている。しかし美濃傘は洋傘に押されて、特殊な傘を中心に生産されているに過ぎず、岐阜団扇も同様の状況である。
岐阜提灯
 提灯とは、ろうそく用の灯火具で、球形・同筒形・棗型などの形がある。いずれも細い竹ひごをらせん状に巻いて骨とし、上下に口と底をつけて紙を張り、折りたたみできるようになっている。
提灯とは、ろうそく用の灯火具で、球形・同筒形・棗型などの形がある。いずれも細い竹ひごをらせん状に巻いて骨とし、上下に口と底をつけて紙を張り、折りたたみできるようになっている。
室町時代(1336年から240年ほど)の禅家によって用いられて広まったとされ、折たたみ提灯になったのは文禄年間(1592年−95年)で、江戸時代になると在来の行灯にかわって流行し、各種の提灯がつくられるようになった。
岐阜提灯は、慶長年間(1596−1614年)、宮中より徳川尾張公に下賜された提灯を模して、今の美濃市で生産された薄くて丈夫な典具帖という紙と本巣郡や揖斐郡に産する良質の竹ひごによって、作られたのがはじまりとされ、「御所形提灯」と呼ばれていた。明治維新後、一時衰退したが、明治9年(1876)以来、火袋や絵模様などに工夫を重ね、岐阜提灯のブランドで全国に知られるようになったのは明治20年(1887年)頃からだといわれ、当時の生産者勅使河原直次郎の努力に負うところが大きかったと伝えている。その頃であろうか。今の四ツ屋町裏の大桑町から若松町にかけて「明屋敷」と呼ばれたところがあり、「御所形岐阜提灯」の発祥の地といわれているが、定かでない。
岐阜提灯は、戦前の昭和15、6年(1940)頃、盛んに生産されていたが、終戦直後(1945年)は、戦災と原料不足で生産が停滞した。昭和20年代後半から30年代初頭(1950−56、7年)にかけて好況が続き、昭和34年頃にはピークに達し、以後不振になったが、その原因は労働力不足にあったという。『岐阜市史』によれば、昭和38年での雇用者をもつ事業所数は12企業のみで、あとは家内労働世帯(市内および近郊合わせて253世帯)への外注委託生産だった。また、昭和55年(1980)の岐阜県の提灯生産額は55億円で、日本一。2位福岡県(八女提灯)が30億円、3位愛知県(名古屋提灯)14億円であった。
なお、岐阜提灯は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭49)」によって、平成7年4月5日に、岐阜提灯の原材料および生産技術について、「伝統工芸品」に指定された。
美濃傘
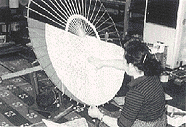 傘は「笠」と区別して、「さしがさ」あるいは「からかさ」と呼ばれ、古代には絹綾を四角に張り、長柄をつけて貴人の頭上にかざす「蓋」だったが、鎌倉・室町時代(1185−1573年)には、紙をはった朱塗りのものが使われるようになった。江戸時代の元禄年間(1688−1703年)頃から庶民の間に柄の短い傘が広く用いられるようになった。傘は、はじめ京・大阪、ついで江戸や岐阜で生産され、やがて全国各地で生産されるようになったという。
傘は「笠」と区別して、「さしがさ」あるいは「からかさ」と呼ばれ、古代には絹綾を四角に張り、長柄をつけて貴人の頭上にかざす「蓋」だったが、鎌倉・室町時代(1185−1573年)には、紙をはった朱塗りのものが使われるようになった。江戸時代の元禄年間(1688−1703年)頃から庶民の間に柄の短い傘が広く用いられるようになった。傘は、はじめ京・大阪、ついで江戸や岐阜で生産され、やがて全国各地で生産されるようになったという。
美濃傘は、伝えによれば、寛永年間(1624−43年)加納城主松平丹波守光重のとき、藩士幡某という武士が内職でつくったのがはじまりとされている。以後、加納藩では下級武士たちの間で傘づくりの内職が広まり明治維新後、加納町民の職業として定着した。大正4年(1915)の加納町時代の傘製作戸数は1400余戸で、367万本の生産をあげ、南洋やインド辺りまで輸出されていた。また、美濃傘の生産は武士の内職からはじまったように、家内工業に適していたため、加納町民の90%が生産にかかわっていたとされている。
岐阜県の美濃傘生産額は、大正4年には、123万円で、全国のトップを占め、次が三重県の35万円、広島県の28万円、和歌山県の25万円の順であった。それが、戦後の昭和24、5年(1949、50)頃には1200万本を生産していたが、その後洋傘の進出に押されて急速に減少し、昭和32、3年(1957、8)頃には最需要期の4〜6月でも月産10万本という減少ぶりであった。
1995年版「岐阜県の商工業」(岐阜県)は、岐阜提灯、美濃傘の現在における問題点と今後の方向について、「和がさ、ちょうちんともに熟練した従事者の高齢化が目立ち人材の確保、育成及び技術・技法の保存が迫られており、今後は『伝産法』等の活用や各種振興事業の充実を図る必要がある」と、述べている。
ところで、岐阜提灯や美濃傘にちなんで、やはり美濃紙と竹ひごにまつわる話題を二つ。
岐阜公園そばに金鳳山正法寺がある。この寺の三層建て大仏殿に、奈良や鎌倉の大仏と肩をならべる大仏さまが安置されている。
ご承知のように、奈良や鎌倉の大仏は鋳造仏だが、この寺の大仏は、竹かごに粘土を塗り、その上に美濃紙に書かれた経文を貼った「竹かご大仏」で、この種の大仏では、日本最古、最大なのである。
この寺は、京都・宇治市の黄檗山万福寺の末寺で、今から310年余年前、天和3年(1683)に開かれた。11代惟中和尚のとき、地震や飢きんで亡くなった人びとを供養するため、経文を貼った大仏建造を発願し、京をはじめ信濃、北陸方面まで浄財や経文の喜捨(寄付)を募り、12代肯宗和尚の2代38年間の努力の末、天保3年(1832)金色の慈光に満ちた「竹かご大仏」が完成し、その開眼供養の盛大さは、信長居城時以来の賑わいだったと伝えている。なお、大仏の胎内には木造の薬師さまが安置されている。
現在の揖斐郡池田町出身の坪井伊助は、天保14年(1843)に生まれた。彼はわずか12歳で、村の庄屋役見習になり、以後、庄屋役、村会議員、県会議員などの公職を勤めた。こうした公務を通して、洪水による堤防改修用の竹の需要が多いことを知った彼は、竹の植栽を思い立ち、以来日本の竹の研究に打ち込んだのである。
彼は、池田町の池野に「竹類標本園」を設け、わが国の竹類の殆どを植栽するとともに国内は勿論のこと台湾、朝鮮なども踏破して、竹の研究に没頭した。そうした研究の集大成として、大正2年(1913)に『竹林造成法』、『竹類図譜』の名著を著わし、世に”竹林王”と称賛された。大正5年(1916)に藍授褒賞を受賞し、大正14年(1925)、享年83歳で死去した。
(次回は、②春慶塗漆器と一位一刀彫・一位細工)