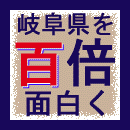
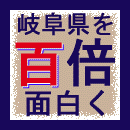 |
ちょっと派手なタイトルである。しかし東の「江戸八百町」や西の「大阪八百八橋」にくらべれば、真ん中の岐阜県を「100倍」とはささやかなものである。心配なのはむしろ話が看板倒れにならないか、ということである。今号は「ムゲツ氏は鉄や紙をつくっていたか、という話」です。 |
ムゲツ氏は鉄や紙をつくっていたか、という話
匠 照人・文
岐阜県の地場産業に「関の刃物」と「美濃紙」がある。刃物は関市で、紙は美濃市でそれぞれ古くから生産され、発展してきた。だが、これらの産業がどうして生まれ育ってきたかということになると、よく分からないのである。
私は、岐阜県の古代史の謎の一つに、「ムゲツ氏」をあげたいのである。「ムゲツ」は、「身毛」「身毛津」「牟義都」「牟宜都」といろいろ表記されているが、いずれも「ムゲツ」と読む。ムゲツ氏といえば、例の壬甲の乱(672年)で、大海人皇子(後の天武天皇)の舎人(側近)として、活躍したムゲツノ君・広がよく知られている。
ムゲツ氏は、『古事記』や『日本書紀』にみえるように、景行天皇の大碓皇子(日本武尊の兄)と美濃の豪族神大根王(開化天皇の皇子彦坐王の子)の娘との間に生まれた押黒之弟日子王を始祖とし、現在の関市・美濃市辺りを本拠地に、その周辺を支配していたと考えられている。その後、雄略天皇紀にみえる「身毛君大夫」は、おそらく天皇直属の武人として活躍していたのであろう。また、ムゲツ君広の後、『続日本紀』にみえる「立春の暁の醴泉」を汲み天皇に献進する役目を、後のムゲツ首がおこなっている。そうすると、ムゲツ氏は、押黒之弟日子王からムゲツ首の間までに、おおよそ670年の歳月が連綿と続いていたことになるのである。
さきの壬申の乱のとき、ムゲツ君広は、現在の各務原市一帯を支配していた村国氏の男依らとともに舎人として活躍して勝利をもたらし、大海人皇子は即位して天武天皇となった。そして村国男依らは中央官人の道を歩いたが、ムゲツ君広は美濃に帰郷して地方豪族となったのである。その後、ムゲツ首の頃には、現在の郡上郡・武儀郡さらに可児市や美濃加茂市辺りまで支配権を広めていたものと思われるのである。だが、このような広大な地域を支配していたと思われるムゲツ氏であるにもかかわらず、ムゲツ氏の実像は今日なお掴めず、わずかに氏寺とみられる関市池尻の弥勒寺跡(国史跡)が、かつての栄光の面影を見せているに過ぎない。
ところが、平成4年(1992)、この氏寺から指呼の地にある美濃市横越の観音寺山山頂から古墳が発見され、中国製の「方格規短鏡」や勾玉などが出土し、ムゲツ氏の墳墓の一つであると推定された。それから3年目の平成7年に、こんどは弥勒寺跡の東隣りから、郡衙(郡役所)跡とみられる大規模な倉庫群跡と役所で使用されていたとみられる「円面硯」なども出土した。こうした相次ぐ発見によって、ようやくムゲツ氏の実像らしい姿が現れてきたのである。
さて、こうして歴史を遡ってゆくと、冒頭にあげた「関の刃物」も「美濃紙」も、ムゲツ氏の支配地に育った産業なのである。
関市は、刀匠「関の孫六」らを輩出した「刃物の町」である。そのはじまりは、鎌倉末期からの南北朝時代(1333−92年)にかけて、越前国から刀匠金重が、大和国から刀匠兼光らが関の地に移住してきてより、全国各地の刀匠たちが集住しつつあった。ちょうどその頃、応仁の乱(1467−77年)がおこり、戦国動乱の世になって、実用本位の斬れ味と堅牢さを追求していた「美濃刀」への需要が急速に高まり、全国一の刀剣鍛冶集団が出現し、今日の「刃物の町」へと発展してきたのである。だが、不思議なことに、この関の地には刀剣生産に必要な立地条件というものが、何一つ見当たらないのである。
それで、関市は、この疑問を解くべく調査研究をし、昨年3月『関鍛冶の起源をさぐる』をまとめた。その中で、鉄とムゲツ氏とのかかわりが追求されている。私も、この謎を解く「カギ」は、ムゲツ氏を抜きにしては考えられないと思っている。
それは、関市の周辺には鉄にからんだ地名や神社、遺跡などが点在しており、今ではすっかり忘れ去られてしまっている古代に、この地に鉄生産の条件の何かがあったものと推測されるからである。
奈良・正倉院に、大宝2年(702)に紙に書かれた最古の戸籍が保存されていて、うち「美濃国戸籍」が7通あり、この紙が最古の美濃紙である。史料上分かっているのは、平安時代(794−1185年)に美濃国の国衙(今の県庁にあたる)の近く、現在の垂井町辺りに美濃国の国営「紙屋」が置かれ、この紙屋を中心に紙の一大生産地が形成されていたとみられている。だが、律令体制の崩壊とともに、この地の紙生産は衰退し、その後、何時の間にか、現在の美濃市牧谷地域を中心に紙生産が行われていたのである。そして応仁の乱の頃には、美濃市大矢田に「紙の六斉市(市場)」がたつほどに盛んになり、美濃紙生産発展への基礎をつくったのである。なぜ牧谷地域に紙の生産が起こったのか。この謎に答える史料を、私はみていない。とすれば、これにもムゲツ氏がひと役買っていたというより、積極的に努力していたのではあるまいか。
よく考えてみると、ムゲツ君広は官人の道を歩まず、帰郷して地方豪族として、支配地域の富国強兵のために、鉄(武器)と紙の殖産事業に徹した、ひょっとしたら須恵器(陶器)の生産にも手を出していたのかもしれない。いずれにしても、ムゲツ氏の実像が明らかになるほど、岐阜県の古代はいっそう面白くなってくるに違いない。
(次回は、天武天皇は美濃で育ったのではないか、という話)