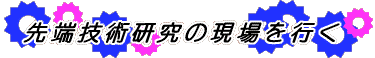
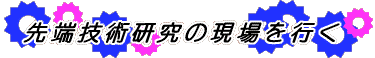
三洋電機ハイパーメディア研究所(安八郡安八町)
■ マルチメディア基盤技術の研究開発を推進
 三洋電機の21世紀に向けた最大のテーマは「地球にやさしいクリーンエネルギー」と「人にやさしいマルチメディア」。
三洋電機の21世紀に向けた最大のテーマは「地球にやさしいクリーンエネルギー」と「人にやさしいマルチメディア」。
このテーマは技術戦略であり、現在、同社の中枢機関といえる研究開発本部が「地球にやさしいソフトエナジー」「快適空間を創るクリーン冷熱」「心に豊かさを与えるニューAVC」「夢のある商品を生むオプト&半導体」という4つの技術分野に取り組んでいる。
研究開発本部は本部室(大阪府枚方市)・筑波研究所(茨城県つくば市)・ニューマテリアル研究所(枚方市)・メカトロニクス研究所(大阪府守口市)・ハイパーメディア研究所(岐阜県安八郡安八町)・マイクロエレクトロニクス研究所(同)から成るが、今回紹介するのはハイパーメディア研究所である。
同研究所は「人にやさしいマルチメディア」をキーワードにニューAVC関連部門の事業を支援しメディア・ソフト、コンピュータ制御、通信・放送の各分野の新技術、さらにこれらを融合したマルチメディア基盤技術の研究開発を推し進めている。
ハイパーメディア研究所の前身は1970年に発足した開発研究所。3年前に技術分野の再編に伴い現在の名称となった。
同研究所の研究内容は三つに分けられる。
その一つが、次世代メディア・ソフトの技術。中でも、現行のCDに比べ、約7倍の記録容量をもった光ディスクの基盤技術は、家庭用DVDやパソコンメモリ携帯情報端末など、AV、情報機器への幅広い応用が期待されている。さらに、立体映像・直視型立体・投与型立体の各ディスプレイはすべてメガネなしで、現在世界に先駆けて実用化を進めている。
二つ目は次世代通信・放送技術現行のFM放送にデジタル信号を多重して放送する「FM多重放送」技術や、放送伝送路のデジタル化により、高画質、多チャンネル、インタラクティブといった新しい放送サービスが可能となる「デジタルTV」技術、音声・データ・画像通信を融合する「マルチメディアネットワーク」技術と多彩。
さらに、同研究所での技術開発の中で重要な位置付けとなっているPHS(パーソナル・ハンディフォン・システム)はすでに基地局や端末ができあがり、通話料も割安で利用できるメドがたっている。
また、FAX機能付携帯情報端末もマルチメディア通信技術が結集された一つの成果でもある。音声・データ・画像など数Kbpsから数Gbpsの情報を高速かつ高能率に伝送する情報圧縮・通信制御などの研究が活かされ、同研究所の最新デジタル技術が応用されている。
三つ目の研究内容は次世代コンピュータ制御技術。コアMCU、コアDSP、OS、言語処理、機械通訳、音声情報処理、手書き情報処理、ドキュメント情報処理など人とコンピュータのよりよいインターフェースを追求している。その一例として同研究所では英語で書かれたWWWホームページをレイアウトそのままで日本語に翻訳する機能を研究。ネットワーク新時代に大きな可能性を秘めたインターネット応用技術の研究開発に拍車がかかっている。
日進月歩の研究開発競争の渦中にあって、他社との競合関係も厳しく、その競争力は製品開発から市場投入までをいかに短期化するかにかかっている。これはどこのメーカーでも共通する話題ではある。
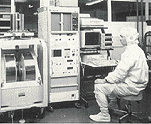 |
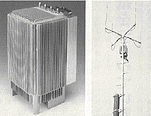 |
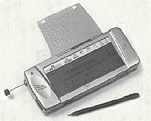 |
| 記録再生実験 | PHS基地局 | FAX機能付携帯端末 |
ハイパーメディア研究所では現在、研究開発プロジェクトと共同研究の二つの制度がある。研究員の平均年齢は34、5歳。グローバルな視野で研究開発が進められ、研究員の海外派遣を行ったり、逆にアメリカ、カナダなど海外からの受け入れにも力をいれている。
研究テーマはいかにつくられていくのか。同研究所の場合は、世界・国・学会・業界などの動きやマーケッティングドライブ、事業部との連携がものをいうマーケッティングインを重要視している。
ハイパーメディア研究所の所長について5カ月という鈴木治所長は「私たちの考え方はアグレッシブに研究しよう、ビッグターゲットをもって研究しよう、コンストラクティブに仕事をしよう、この三つを大切にしていますね。確かに私たちの仕事は競争を抜きにして語れませんが、技術力の蓄積が花開くケースもあります。例えばPHS基地局の技術開発にはプロジェクトチームをつくり3年間を要していますし、機械翻訳には10年間かけています。技術研究の成果はやはり蓄積にあると思いますね」という。