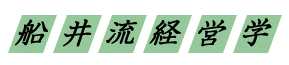
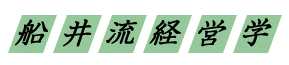
 |
|
売上の壁を超えるには
次の表は戦略・戦闘・戦術とそれに応じたヒト・モノ・カネの管理の仕方のレベルを簡単に表にしたものです。
戦略・戦闘・戦術をどのように分けたらいいのか一般的な区分があるようですが、私なりには次のように解釈しています。
戦略とは3〜5年後のために今何をすべきかであり、戦術とは半年から3ヶ月後のために今何をすべきかであり、戦闘とは今日から一週間後のためになにをすべきかを考えること、であると捉えています。例えば我々の指導という観点から捉えますと、店をリニューアルするとか、チラシの指導をするというのはほとんど3ヶ月先のことへの指導であり、まさに戦術面での指導といえます。戦闘に関しては、私自身が船井総研に入社する以前、実家のディスカウントストアの経営を任されていましたので特に気になる部分でもあるのですが、ポップがあるべき位置に無いだとか、商品密度が薄いから店頭在庫をこれだけ追加しなさいなどといった現場ですぐできる指導にあたります。戦略については、競合店との比較において、店舗面積がどうしても不足しているから店舗の裏地に土地を買って増床しようとか、立地が悪いから3年〜5年のうちに店をスタラップアンドビルトしてもう少し良い立地に店を移転しようとかいう指導をいいます。
これを店のオペレーションの面から考えますと、ヒト・モノ・カネの各経営資源ごとに戦略・戦術・戦闘のレベルがあり、このすべてのレベルを一人の人間がコントロールしている段階を”生業”といい、また、これを二人で分担するのを”家業”といいます。そして、戦略・戦術・戦闘をはっきりと3つのレベルとして分けている会社を”企業”といいます。私はある業界だけをとっても96社の指導先を持っていますが、このなかでも”企業”と呼べるのはたった2社しかありません。十数年間お付き合いさせていただいている指導先も20社以上ありますが、やはり小売業にとっては30億というのがひとつの大きな壁にあたるようです。どんなに素晴らしい商品力や販促力をもってしてもこの壁はなかなか越えられないのです。私は、6年程前にサダマツという会社の専務に出会い、初めてこの理由に気がつきました。私はこの会社にも顧問として指導を行っておりましたが、他の指導先が軒並み20億まで売上を伸ばしたところで頭打ちとなる中で、このサダマツだけはバブル崩壊以降の最近3年間で一気に売上を7〜8倍にまで伸ばし、私が困難と考えていた30億円の売上を軽くクリアしてしまったのです。しかも、他の指導先ほどキャリアの長い社員やベテランのバイヤーに恵まれていないにも関わらず、ここまでやってのけたのです。この理由はたったひとつ簡単なことだったのです。このサダマツの専務は、家業的な現社長の考え方に大手メガネチェーンの行っているチェーンオペレーションを導入したのです。つまり30億を越えたければ、前の表にもありますが、戦略・戦術・戦闘の各レベルに応じた権限や責任だけを、そのレベルに応じた担当者に委譲すべきだということです。これができなければ他のほとんどの指導先のように、たとえオーナーにそれなりのやる気があったとしても30億の壁は越えられません。同じサダマツでのことですがこれにまつわる話をしましょう。新しくオープンするダイエーにこのサダマツが出店することになり、その新店の店長の募集をかけました。気骨のありそうな元スナックのマネージャーを店長として採用しましたが、彼が採用後間もなく店長としてはトップクラスの成績を上げ始めます。しかしながら、サダマツ以外の宝石店ではこの店長は全く使いものにならなかったと私は考えています。なぜなら彼は宝石のことを全く知らなかったからです。店長は戦闘レベルのことだけに専念できる仕組づくりがサダマツでは完成されていたからこそ、他業界からの店長でもしっかりとやれたのです。生業店の多くは、店長レベルでは本来的確に判断できない戦術レベルの意思決定まで店長に委譲しているケースが多く、それがひいては多量のデッドストックを出す店長や、お金をごまかす店長を産み出す原因となり、いくら素晴らしい商品力や販促力をもってしても売上が頭打ちとなってしまうのです。
もちろんリスクマネジメントが大きな要素となりますが、この戦略・戦術の棲み分けが明確になされている組織、またそのような人材を登用することが生業から家業、家業から企業への脱皮につながるというのが私の結論です。こう申し上げると「そんな人材は滅多にいない」と言われる方がおられますが、いないのであればなおさら戦略・戦術・戦闘の区別をはっきりさせなければならないのです。
さて船井総研は創業以来20数年間国内外の流通業の指導に携わってきた会社です。今回はその最も得意とする流通業のマーケティングについて解説してまいりたいと思います。
| 戦略戦術戦闘 |
| ヒ ト | モ ノ | カ ネ | |
|---|---|---|---|
| 戦 略 | 主任以上の人事権 (組織決定) |
レイアウト、MD 決定 |
資金調達 |
| 戦 術 | 組織運用 パート他の人のやりくり |
MD、POPの管理 運用 |
資金運用 |
| 戦 闘 | 一体化 勤怠状況のチェック 楽しい職場づくり |
タリンリネス 欠品のチェック V、MDの管理 万引き等のチェック |
売上金の管理 |
| 人事・人材 | 商品 | 資金・売上 |
消費者の購買基準の変遷
お客様がモノを買う基準は図のように変化します。
今から30〜40年前までは、お客様はあの店ならば安心だろうということで「お店」というものを尺度に買い物をしていました。これをストアロイヤリティといいます。昭和40年代になると、日本ではメーカーブランドが確立されます。次のページの図にあるように電化製品ではソニー・ナショナル、時計ではセイコー・ロレックスという企業が一流メーカーとして大躍進をとげました。ちょうど昭和45年頃、ディスカウントストアという言葉が登場した頃です。私の実家はそれ以前からディスカウントストアの経営をしていましたが、この頃商品を購買されるお客様の心理は次の様だったと思います。「コヤマというディスカウント店は信用していないが、ナショナルというメーカーを信用しているからナショナル製品が安いのならコヤマで買おう」。これと同じ動機でダイエー・ニチイ・ヨーカドー等の量販店に客が足を運ぶようになり、量販店が台頭・成長することになります。この昭和52年頃からDCブランドが注目を集めます。この頃はフェンディ・グッチ・セリーヌ・ルイヴィトンなどが流行していました。そしてバブル景気のころにはプラダ・MCM・プリマクラッセなどのブランドが人気を博しました。そしてやがて不況が訪れ、いわゆる「百匹目の猿現象」が起こります。いよいよこれからは本物時代の到来です。お客様は自分の眼・舌・触感に絶対的尺度を持つようになります。寿司屋の例を挙げましょう。回転寿司にしか行ったことがない人が”お好み”で握ってくれる寿司屋に行ったとしましょう。「いくらですか?」と聞いたら「2万5000円」ですという答えが返ってきたとき、その人は高いとか安いとか果たしてわかるのでしょうか?その人の感想はたぶんこうでしょう。「ああ、ああいう寿司屋はこれぐらいとられるんだ」。でも20回も30回も寿司屋に行き慣れた人がある寿司屋に行き、「今日は2万5000円ぐらいかな」と思っていたのに勘定をしてみたら「1万7000円です」と言われたら、たとえ味は同じでも「この店は旨い」、逆に「3万5000円です」と言われたら「この店はまずい」と感じるはずです。これは寿司屋に行き慣れている人の舌が「2万5000円」という尺度を持っているからこう感じたわけです。つまりお客様の満足度は「価値/価格(価格分の価値)」という尺度によって左右されるのです。テレビなどの出始めのころを思い出してみてもそうでしょう。テレビの絶対的な価値がわからないから「テレビって高いもんね」とか言いながら初任給の9倍もするテレビを買っていたものです。しかし今では、各自のTPOに応じてだいたいどれぐらいの価値があるのか、消費者が自分自身で尺度を持てるようになっているのです。お客様が商品やサービスの価値を自身の尺度で見抜くようになったということです。わかりやすいように紳士服の例でご説明しましょう。郊外型の紳士服店では1万8000円〜4万円の価格帯のスーツを売っていました。百貨店の平場では4万8000円〜7万8000円、普通のブランド品だと9万8000円〜17万8000円の価格帯でした。そしてバブルがはじけた時、郊外型の紳士服店は百貨店で7万円前後の価格帯で売っているスーツを2万9800円で売っていると大々的に宣伝していました。しかし、お客様は経験を積むとそんなことは嘘であるということにすぐ気付き始めます。私自身は日経新聞の決算報告を見て気付いたのですが、ある郊外型紳士服チェーンは粗利率52.3%、経常利益率24%という数字を公表していました。どう考えても百貨店で7万円で売っているスーツを2万9800円で売っている会社が50%以上の粗利率を維持できる訳がないのです。ということはもとから2万9800円の値打ちのモノを2万9800円で売っていたのでしょう。消費者が経験を積み自分で尺度を持つようになると決算数字など見なくても、すぐにこのぐらいのことには気付いてしまいます。私は毎年アメリカには仕事で何回も行きますので、身体が大きいこともあってスーツは全てアメリカで買います。アメリカのアウトレットでは本当にいいものを安く売っています。最近日本の郊外店が扱っている安いスーツはほとんどが中国製です。一時期これに消費者が飛びついたこともありましたが、これを着ると肩が凝って仕方がありません。一度でも並み以上のスーツを着たことがある人は、二度と買わないはずです。このようなことが図の第5段階で起こります。「客自身が自分の眼・舌・触感に絶対的モノサシを持つようになる」のです。商売の世界では嘘つきやニセモノは10年以内に必ず淘汰されます。
購買基準(物差)の変化
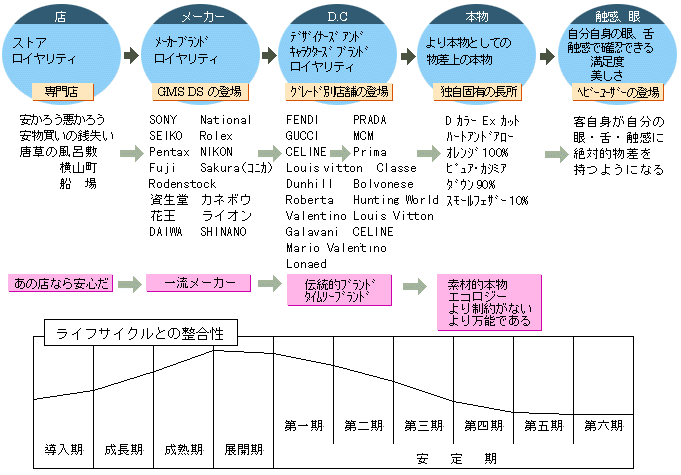
4つの「P」から6つの「C」へ
また、これに伴って接客の方法も変ってきます。かつては店に来るお客様は商品知識をあまり持たずに買い物に来ていました。しかし今では、雑誌や情報誌などで自分の欲しい商品をあらかじめ決めておいて、店には現物を自分の眼で確認し納得するために足を運びます。このように顧客の来店動機や商品知識が多様化するという現象が起こっています。昨年のSPECS'95というセミナーでアンソニーラッセル&アソシエイツという会社の会長であるアンソニー・ストカンはこう言っています。「かつては価格(price)・商品(product)・販促(promotion)・立地(place)がマーケティングの主要素であったが、もはやそれだけでは競合に勝ち、消費者をつなぎとめておくには充分ではない」。そして、この4つの「P」以外にも小売業は6つの「C」に注意を払わねばならないと言っています。この6つの「C」を列挙するとともに私なりの解釈を以下に述べさせていただきます。
顧客をつなぎとめる6つの”C”
| Care: サービスに代わって重要となった。小売業はお客様との接し方について心からの気遣いをしなければならない。CAREとは Customers Are Really Everything の頭文字でもある。前回もご説明した「自分自身を大切にするのと同じくらいお客様を大切にする」という親身法と全く同じことである。 Communication: Coaching&Cheerleading Community: Challenge: Choice: |
最後のChoiceは品揃えに関する提言です。かつて船井総研は品揃えについては総合化の方向性を志向していましたが、徐々に狭くても構わないから深い品揃えをするという方向性に変ってきました。これまで広い分野の商品を取り扱っていたのを、ツイている商品だけを扱ってツイていない商品は扱わないというツキの原理を実践してきた結果、狭い属性で深い品揃えをするというスペシャリティストアづくりの指導を行うようになりました。この狭く深い品揃えのスペシャリティストアを20〜30店ほど”店揃え”すればとてつもない力を持った商業集積ができるというのが私の結論です。この発想から生まれたのがパワフルリテイラーという新業態ですが、この業態について述べさせていただきます。
小売新業態・パワフルリテイラーの開発コンセプト
その前にまず、船井総研のコンサルティング手法の変換から見ていただきましょう。
1量・数・幅
船井総研では創業期から「量・数・幅で包み込む」という考え方を提唱してまいりました。「量」というのは商品量、「数」はアイテム数、「幅」は価格幅を意味しますが、これらの尺度で競合店を包み込むという「包み込み理論」を展開してきました。
2単品一番化
やがて単品一番という手法が一世を風靡する時代になります。商品群ごとに一番化するという手法で、例えばカセットテープならカセットテープ売場だけはどこの店にも負けないように徹底的に強化するといったものです。
3予算帯別価格一番化
しかし、消費者が購買経験を積みヘビーユーザー化するに従い、この一番化手法もやがて予算帯別一番化手法へと徐々に移行していきます。この予算帯別一番化手法というのは一体どういうものなのかまた別の例を挙げてご説明しましょう。先程の寿司屋の話のように消費者は商品やお店に対して自分自身の中に独自の尺度を持つようになります。例えば39万円ぐらいする高価なオーディオを、皆さんはどこで買われるでしょうか?恐らくほとんどの方がディスカウンターではなくオーディオ専門店で買われることでしょう。逆に2万円程度のラジカセならばディスカウンターを利用される方が多いはずです。これはつまり2万円と39万円の間のどこかに「それぐらいの値段のモノならホームセンターで買ってもいいが、それ以上するモノは専門店で買いたい」という価格の分岐点があるということを意味しています。オーディオの場合は私の統計上10万円前後が分岐点ですから、9万8000円ぐらいの値段までだったらディスカウンターでも売れるが、それ以上は専門店でないと売れないということになります。であればディスカウンターがとるべき手法は、9万8000円以下の予算帯の商品を売れ筋として強化・一番化を図るという「予算帯別価格一番化」となる訳です。
4属性(独自固有の長所)
 そしてさらに属性(=独自固有の長所)という切り口が登場します。先程のオーディオの場合で言うと、その中のCDチェンジャーだけで一番になるといった様に、各商品群の細かい属性のところで一番化するという手法ですが、ここで流通業にとっては歴史的と言っても過言ではない程の変化が起こることになります。独自固有の長所を強化することで起こるのは、非競争という考え方です。今までは相手の強いところを見つけてきて、それを徹底して叩くという競争論理でしたが、独自固有の長所というのは自分の店のツイている商品(部門)を伸ばすのであって、相手の強い所はそのままにしておくという共存の論理に基づく手法なのです。余程の時間と資金を投入しない限り、二番店が一番店の強い部分を叩くなどということは到底できません。しかも商品のロス率が上がりますので、一時的には赤字を出すことになります。一方、独自固有の長所を伸ばすことは、これとは逆に商品の回転率を上げ、非効率な商品をなくし、利益を上げることにつながります。
そしてさらに属性(=独自固有の長所)という切り口が登場します。先程のオーディオの場合で言うと、その中のCDチェンジャーだけで一番になるといった様に、各商品群の細かい属性のところで一番化するという手法ですが、ここで流通業にとっては歴史的と言っても過言ではない程の変化が起こることになります。独自固有の長所を強化することで起こるのは、非競争という考え方です。今までは相手の強いところを見つけてきて、それを徹底して叩くという競争論理でしたが、独自固有の長所というのは自分の店のツイている商品(部門)を伸ばすのであって、相手の強い所はそのままにしておくという共存の論理に基づく手法なのです。余程の時間と資金を投入しない限り、二番店が一番店の強い部分を叩くなどということは到底できません。しかも商品のロス率が上がりますので、一時的には赤字を出すことになります。一方、独自固有の長所を伸ばすことは、これとは逆に商品の回転率を上げ、非効率な商品をなくし、利益を上げることにつながります。
そしてこの独自固有の長所を伸ばすという手法が、後に私が「パワフルリテイラー」という新しい小売業態を確立するのに大きなきっかけを与えてくれることになったのです。このパワフルリテイラーという新業態は、既に広島のある宝石店をはじめとして30店舗で展開されており、4年ほど前29坪で6億円だった同店の売り上げがこの新業態に転換後、今では20坪で11億円にまで伸びていることから見ても、この新業態の威力をご理解いただけることと思います。この新業態の開発コンセプトをここで少しだけご説明しましょう。
★パワフルリテイラー開発コンセプト★
|
 これがパワフルリテイラーの開発コンセプトを簡単にまとめたものです。こういった紙面は私にとって皆さんに情報を提供させていただく場でもあります。逆に言うと皆さんにとっては情報収集の場であります。しかし情報を収集しただけでは売上は一銭も上がりません。収集した情報をどのように運用するかが重要なのです。このことによってしか売上は上がりません。皆さんの会社の現場でも、できそうなところから実践してみてください。
これがパワフルリテイラーの開発コンセプトを簡単にまとめたものです。こういった紙面は私にとって皆さんに情報を提供させていただく場でもあります。逆に言うと皆さんにとっては情報収集の場であります。しかし情報を収集しただけでは売上は一銭も上がりません。収集した情報をどのように運用するかが重要なのです。このことによってしか売上は上がりません。皆さんの会社の現場でも、できそうなところから実践してみてください。
砂糖に群がる蟻では儲からない
時流は常に流れています。今、売れ筋で爆発的に売れている商品があったとしましょう。これは半年から1年前に30%の革新的消費者によって認知された商品に、追随的消費者がまるで砂糖に蟻が群がるように集中し一時的なブームとなっているのです。しかし、革新的消費者はもう次の新しい商品に興味を移しています。ここの商品を扱うことが利益につながります。ブームとなってから商品を扱うと競合が激化していますから、利益率が下がるのは当然です。つまり激流のように動く時流の方向を察知し、これに適応した企業だけが利益をあげ業績を伸ばすことができるのです。
| こやま
まさひろ 昭和22年生まれ。早稲田大学理工学部数学科卒業。 ディスカウントストアの店長を経て昭和59年株式会社日本マーケティングセンター(現 船井総研)入社。 現在同社の専務取締役・ライン統括本部長。入社以来船井幸雄の右腕として活躍し、これまで数多くの地域一番店を育て上げ、”経営指導成功率100%のコンサルタント”の名を欲しいままにしてきた。著書は『船井流マーケティングの極意』『船井流肩書きがついたら読む本』『船井流リーダーの条件』『船井幸雄に学ぶ成功の黄金律』など多数あり。 |