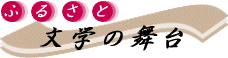
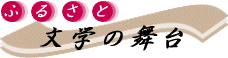
「飛騨越日記」の道
文・道下 淳
岐阜女子大学講師
緑や紅葉などが美しい「せせらぎ街道」辺りを、90余年前に歩いた作家遅塚麗水の『飛騨越日記』を紹介しよう。今でこそ快適な道路となったが、当時は実に悪い道だったことが、この紀行文から分かる。
麗水は明治の中ごろ活躍した作家。紀行文を書かせては田山花袋・幸田露伴らとともに、当時Aクラスの存在であった。この人が岐阜から坂本峠経由で飛騨を通っている。その時の紀行が『飛騨越日記』で、発表されたのは明治39年、彼が飛騨を歩いたのはその前年らしい。
彼は飛騨から富山へ抜けるつもりだったが、どの街道を通るか考えていなかった。岐阜駅前の旅館で聞いたところ、関・金山経由が一般的だが回り道だ。上有知(美濃市)・八幡経由は険しいが近道である ─ と、教えられた。足に自信があったので八幡経由を選んだ。上有知・畑佐(郡上郡明宝村)と泊まりを重ね9月3日、美濃飛騨国境の坂本峠を越した。
現在ではトンネルが設けられ、自動車だと知らぬ間に通過するが、当時は大変な難路であった。
『まことに恥ずかしくは候へど、ヘトヘトになって相疲れ、一字の賛辞をも山霊水伯に呈して、その大観を頌することもなく候。終には肩に掛けたる小鞄・風呂敷包を挙げて、道に棄て去らんとまで幾たびか思い候』
道ばたで一休みしていると、牛を連れた山男のような青年がやってきた。話してみると好人物なので荷物をふもとの里まで送るよう頼んだ。大原(大野郡清見村)の集落を過ぎた辺りで、先の青年と出会った。この青年に聞いたのか、麗水は付近の地名を「長谷」としている。ところが陸地測量部の5万分の1の地図や『岐阜県の地名』(平凡社)にもない。大原で聞いたが分からなかった。小字名らしいが、どの辺にあるのだろうか。
彼は青年を道案内に雇い、坂本峠以上の難路竜ヶ峰(標高1112メートル)にさしかかった。現在高山へ出る「せせらぎ街道」は、そのはるか西の馬瀬川・川上川の上流沿いに走る平たんな道である。白カバ林が点在、民宿もある。だが当時の道は竜ヶ峰が険しいため、お助け小屋が設けられていた。小屋を守る老人に、年8円の手当が出ていると、彼は記している。
江戸時代のころ竜ヶ峰は、信州へ出る野麦峠とともに、2大難所に数えられていた。『竜ヶ峰にはとんとこまり、諸人往来致すごとに禁じ申す道筋なり』と、当時の記録にある。彼が通ったのは秋の盛りのころで『紅紫錦を織るがごとく繚乱いたし、万斛の露香風に従って征客の袂を吹き申し候』と、難しい言葉を並べて花の見事さをたたえている。よほど気にいったらしく、ここで見て草木の名前もメモしている。漢字なのでカタカナにして一部をお目にかける。オミナエシ・ハギ・ユウガオ・ススキ・タマアジサイ・ムクゲ・ネム・イワキキョウなど。
やがて道案内の青年が葉の付いた木の枝を2本切り、1本を彼に持たせた。枝でアブを払うのだという。林の中を行くと、アブの大群が襲ってきた。二人は木の枝で打ち払いながら、突っ走った。ウソのような話ではあるが、実際に体験したことであろう。また、梅雨のころには、ヤマヒルが通行人を襲う。ヒルが落ちてきても体に吸い付かないよう、大きな笠をかむって通るという青年の話を、感心しながら聞いた。
3日の夜は三日町(大野郡清見村)泊まり。高山から巡査と郡役所の書記が来ていた。なんでも付近一帯に赤痢が広がり、検疫のための出張と聞いてびっくり。翌日午前7時に出発、同9時には高山へ入っている。
宿は谷田屋旅館。これまで利用した宿ではノミ・シラミに悩まされ、ヒエ飯を食べさせられた。それに比べこの宿は『まことに月とスッポンとの相違にてご座候。(中略)客室の高敞と器皿の雅潔とは申すまでもこれなく』と、客室の広いことや調度・食器類の優雅で清潔なことに満足している。特に前々夜、畑佐で泊まったときは不潔な食器や汚れた寝具が出されいやな気になった。それだけに、谷田屋のもてなしがうれしかった。
夜は盆踊り見物をした。踊り場になった町内では両側の家の軒へ綱を菱形に張り、その中央に鉄線を渡し、花笠で飾ったランプをたくさんつるす。一方、道の両側には各家庭から持ち寄ったいろいろな型の燭台を数多く並べ、ろうそくを立てる。この町にはガス灯や電灯がないので、これが精いっぱいの照明であると述べている。
踊り子たちはそれぞれ仮装したり、そろいのユカタで登場する。なかには布で顔を隠している女性もいる。踊りの中央には涼み台を並べ、大太鼓1、三味線3−4ちょう、歌い手6−7人が半開きのセンスを口に当てて歌う。歌うというより叫ぶという調子である。踊り手も、手足を左右に動かすだけで『振りも態もこれ無』きありさま。歌詞もエロチックなものが多く、記すことを控えると、麗水は書く。この見聞記のおかげで、明治末の高山盆踊りの風景が再現できた。
翌朝、富山へ向けて出発した。宮川沿いの渓谷美をたたえ『家に老親なくまた妻子なくんば、草をこの渓辺に結んで庵となし』長く住みたいと、同日記を終わっている。この辺りの風景が、よほど気に入ったらしい。