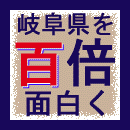
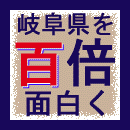 |
ちょっと、派手なタイトルである。しかし東の「江戸八百八町」や西の「大阪八百八橋」にくらべれば、まん真ん中の岐阜県を「百倍」とは、・・・ |
遙かな古代に東海王朝があったか、という話
匠 照人・文
 |
 |
| 9代開化天皇の皇子彦坐王を祀った伊波乃西神社(岐阜市岩田) | 10代崇神天皇の皇子八坂入彦の御陵(可児市久々利) |
日本地図を広げて、緑の平野部を見る、北海道を別にして、一番広いところが関東平野で、その次ということになると、平野面積のデータが見あたらないので、確かなことは分からないが、濃尾平野、新潟の越後平野であろう。その次に広い平野となると、筑紫・熊本・岡山・讃岐・大阪などであろうか。
そこで思い出されるのが、世界における文明社会の発祥の地のことである。チグリス・ユーフラテス両河川流域におけるメソポタミア文明、ナイル河流域におけるエジプト文明、インダス河流域におけるインダス文明、さらに黄河流域での中国文明のように、世界の文明発祥の地は、すべて河川流域平野においてであった。
すなわち河川によって造成された肥沃な平野は、人類の集住を可能にさせ、そこに社会ができ、文明が開花するとともに「クニ」が誕生したのである。このことは、日本の古代についても同じである。「クニ」の成立年代を問わずに挙げれば、九州では遠賀川・那加川・球磨川などの流域平野に奴国やヤマタイ国(九州説)や狗奴国などが、中国では山陽側の高梁川・足守川・旭川・吉井川の流域平野に吉備王国が、山陰側の斐伊川・飯梨川の流域には出雲王国が形成されている。さらに四国では讃岐の河川流域平野に巨大な越王国が存在したとされ、近畿では大和川や淀川などの流域平野にヤマタイ国(近畿説)が、関東地方では利根川上流域平野にも毛野王国が存在していたといわれている。
にもかかわらず、日本列島の中央部で、木曽・長良・揖斐の三大河川によって形成された関東平野に次ぐ広大な濃尾平野に、遙かな古代において、「尾張王国」とか「美濃王国」というような、あるいは両者を合わせたような、つまり「東海王国」ともいうべき「クニ」が存在していたということを、私は聞いていないのである。このことは大げさのようだが、さきの日本の古代諸王国の状況からみれば、これは日本古代史上の大きな疑問であり、謎である。
ところで、『古事記』『日本書紀』に記されている初代神武天皇から、緩靖・安寧・懿徳・孝昭・孝安・孝霊・孝元と続いて、9代開化天皇に至る九天皇は今日の学会では存在していなかった。すなわち「欠史の時代」だといわれている。しかし両書をシサイにみると、私たちの住むこの濃尾平野にかかわりがあると思われる天皇が浮かぶのである。それは5代孝昭天皇で、孝昭の皇后は尾張連の祖奥津余曽の妹・世襲足姫で、6代孝安天皇を生んでいる。さらに、その孝安の皇后・押姫は天皇の姪ともいわれているから7代孝霊も尾張氏の血が流れていることになり、どうも「孝」の字で結ばれた天皇たちは尾張氏一族ではないか、と推測せざるを得ないのであり、そこに天皇の系譜とはかかわりなく古代の早い時期に広大で肥沃な濃尾平野で活躍していた強大な勢力の存在、ひいては強大なクニが存在していたのではないかという大胆な憶測すら芽ばえるのである。
ところが、平成時代に入って、愛知県埋蔵文化センターの加藤安信氏や赤塚次郎氏によって、「狗奴国尾張説」が唱えられ、さらに最近では「狗奴国尾張美濃説」へと進展しつつある。
加藤氏と赤塚氏が主張している内容はそれぞれに異なっているが、1.弥生時代後期頃、2.濃尾平野北部に、3.巨大な弥生集落が存在し、4.強力な戦闘力を持ち、5.同時に他の地にみられない独特のパレス・スタイル土器(宮廷式土器)やS字状口縁台付かめが作られていたことなどから、「尾張に強力な王がいて、独立した政治、文化圏を形成していた。」そして、その時期がちょうど、『魏志−倭人伝』に記されている当時の日本の政治状況から推して、狗奴国ではないか。とすると、狗奴国と戦ったヒミコのヤマタイ国は、大和(近畿説)ということになるのである。
この加藤・赤塚両氏の「狗奴国尾張−美濃説」について、白石太一郎氏は新聞紙上で、「ヤマタイ国を、3世紀中頃の畿内の国と考えると、その東で対等に戦える勢力は、濃尾平野しか考えられない。狗奴国は、ここを中心とする勢力だった可能性は大きい」と、語っている。
また、橿原考古学研究所の菅谷文則氏は、新聞紙上で「これまでのような北九州と畿内という二元論ではなく、東国も入れた三極構造に立って、日本の古代史を考えるべきだ」という。私は、この東国こそ、三極構造の一極として木曽三川流域に広がる濃尾平野に遙かな古代に築かれていたと推測する「東海王国」でなければならないと期待しているし、最近発掘された養老町の象鼻山1号墳が3世紀後半に築造された日本最古級との報道は、一そう意を強くさせてくれる。
(次回はムゲツ氏が鉄や紙をつくっていたか、という話)