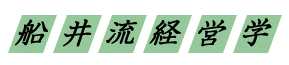
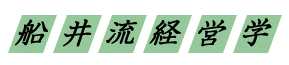
 |
小山政彦(こやま・まさひこ) 昭和22年生まれ。早稲田大学理工学部数学科卒業。ディスカウントストアの店長を経て昭和59年株式会社日本マーケティングセンター(現船井総研)入社。現在同社の専務取締役・ライン統括本部長。入社以来船井幸雄の右腕として活躍し、これまで数多くの地域一番店を育て上げ’経営指導成功率100%のコンサルタント’の名を欲しいままにしてきた。著書は「船井流マーケティングの極意」「船井流肩書きがついたら読む本」「船井流リーダーの条件」「船井幸雄に学ぶ成功の黄金律」など多数あり。 |
3年ぐらい前まで、船井会長の言っていることと、我々がコンサルティング現場で実際に行っていることが多少離れているような気がする、というのが実のところ私の本音でした。だから船井会長の著書が何万冊売れようと、正直なところ我々現場のコンサルタントの仕事にはほとんど影響のないことだ、と正直を言えば考えていました。しかし昨年の春ごろから、船井会長がセミナーで話したり著書の中で書かれていることを指導現場に生かしたほうが、明らかにコンサルティングがやりやすくなってきました。言い替えると現場が船井会長に近づいたのでしょう。そのコンセプトを生かしたほうが指導がやりやすいし、実績が上がるという実感を私自身も持ち始めました。
今回は私がまとめた船井会長の講演録をもとに、私が指導先で経験していることを実例として織りまぜながら述べさせていただきたいと思います。
革命的変化に乗り遅れてはいないか
最近は革命的変化の時代がきているというような気がします。スポーツの世界で起きている現象を例に話をさせてもらいます。野球のバッターの円熟期は何歳ぐらいかといえば、やはり王や長島、野村や落合などの三冠王を例にとってみても一般的には30〜35歳ぐらいでしょう。競馬の世界でも昔の安田さんなどが頭に浮かびます。しかし、昨今のナンバーワン打者といえば誰が考えても22歳のイチローですし、競馬界では20台半ばの武豊がトップ騎手であることは競馬ファンでなくても周知のことでしょう。スポーツ界では彼等のような20〜28歳の団塊ジュニア達が、明らかにそれぞれの種目を支配し始めているのです。その道を極めるまでに十数年かかっていた競技を20歳そこそこの若者が制覇しはじめているのです。このことはもしかすると我々団塊の世代に重大な警告を投げかけているものと思われます。将棋では羽生名人という若い天才棋士がいますが、将棋のように年の差に関係なく勝ち負けのはっきりする勝負ごとでは、たとえ年上の棋士でも負ければ自分より年の若い新人より格下となってしまいます。皆さんは野球の打率や将棋の勝ち負けの様に、皆さん自身と優秀な部下とを比較する基準をお持ちでしょうか?もし、皆さんが時流に遅れてしまっているにも拘わらず、羽生名人やイチローのような優秀な若い部下の提案を「どうせ若僧の言うことだ」と頭ごなしに潰してしまっていることはないでしょうか?もしこのようなことが続いていたとしたら、皆さんの会社が時流からどんどん遅れていき、倒産への道を歩んでいくかもしれない−。私はこのような懸念を持っています。
百匹目の猿
ここで「百匹目の猿」の話をご紹介しましょう。宮崎県の幸島というところにいる天然記念物の猿の群れの中の一匹が餌のイモについていた泥を水で洗って食べ始めました。その2年後には幸島のほとんどの猿が同じことをするようになりました。ところがその時、最後まで泥を水で洗おうとしなかったのが12歳以上(人間でいうと48歳のおじさんにあたるそうです)のオス猿であったという話です。皆さんもこの12歳のオス猿と同じような状況に陥ってはいませんでしょうか?私が20代後半の部下と話をするとき、私の言葉で普通に話していてもなかなか話が通じないことがあります。彼等は東京オリンピックも知らなければ、佐藤総理大臣も知らない世代なのですから。ここでよく考えていただきたいと思います。もし自分の世代の言葉や伝え方だけで年下の部下がすぐに理解を示してくれたなら、その部下は皆さんよりはるかに優秀ということになります。なぜなら、部下は若い世代の言葉や表現だけでなく、自分たちとは異なる年上の世代の表現をも理解していることになるからです。皆さんが若者の表現を理解できずにおじさんの表現だけで意思疎通しようとしている一方で、若者は両方の表現で意思疎通しようとしているのです。少し極論ですが、このことを船井会長の言葉でさらに掘り下げて言うと次のようになります。「人類が生成発展し修行をするためにこの世に生まれてきたのであれば、若い優秀な人間が我々よりもレベルが高いことは当然」なのです。だからこそ、世の中は改善され良くなっていくのでしょう。ですから、若い人を動かすにはきちんと納得させないといけません。
| 生成発展・・・世の中は浮き沈みを繰り返しながらも、マクロには常に改善の方向に向かってスパイラル状の弧を描きながら進んでいるという概念を説明する際によく用いられる言葉。 |
具体的な事例を挙げてお話ししましょう。福島県いわき市に内山という宝石店があります。このいわき市は、平市と小名浜市が合併してできた日本最大の面積の都市ですが、内山にとってはほぼ無競合の商圏で売上をこれまで順調に伸ばしてきました。ところがサティ、ダイエー、長崎屋が2万平方メートルの面積で相次いでオープンし、この内山にも売上減少の気配が漂い始めました。そんな折、社長が31歳になる長男に社長職を譲ると突然言い出します。これを耳にした古参の幹部を中心に社内は騒然とします。このことを受け、周囲に自分の実力をアピールするためにも一刻も早く実績を挙げねばと焦った長男は、宝石店の接客専門のコンサルタント(船井総研ではない)の指導を売り場に導入しました。これまでと全く異なる販売手法を導入しようとしたそのコンサルタントと一部の従業員の間に衝突が起こり、数日後最も販売成績の良かった女性社員と売場主任から辞表が提出されてきました。さてこのケースでは、このような事態を招いてしまった原因は何なのでしょうか?社長も長男も、先程の「納得」のプロセスを省いてしまったのが大きな原因です。古参の幹部社員には「息子を頼む」と社長が頭を下げて根回しを行い、長男は売り場の担当者に「接客専門のコンサルを入れようと思うが・・・」と一言相談し、事前に「納得」してもらえればそれで済んだのです。若い人に限らずやる気のある人間は特に納得させてから動かすことが非常に大切だと私が感じた体験でした。
一体化が始まった
船井会長は一体化について次のように述べています。
右記の通販の話を少し詳しく述べましょう。「通販では押入商品がよく売れる」というのがセオリーです。つまり人に見せたくないものは通販の方が買いやすいということです。もう一つ通販が好まれる要因があるといわれています。それは「小売店の強烈な接客力のシッペ返し」です。つい販売員にノセられて予算よりも高い商品を買わされてしまったといった経験は皆さんもお持ちのことでしょう。通販ならばカタログを見ながら自分のペースでゆっくりと商品を選ぶことができます。だから通販は小売店の接客に懲りた客層を取り込んで伸びているとも言われています。「小売店と通販業は敵対関係にあり、通販が伸びれば小売業は潰れる」とまで有名百貨店の社長は言っています。
一体化は包み込み
しかし、私はこれとは全く違った意見を持っています。有店舗販売にとって無店舗販売は敵対する競合社ではなく売上を驚異的に伸ばすひとつの武器であると私は考えています。つまり「有店舗販売者が無店舗販売に参入すればこれだけメリットがある」という観点で捉えています。例えば、同じカー用品を通販カタログで購入しようとする場合、カー用品が数アイテムしか載せられていないサンケイディノスの総合カタログの他に、数千アイテムのカー用品が掲載されたオートバックスのカタログが手元にあった場合、どちらのカタログで買い物をするお客様が多いでしょうか?また、遠隔地や離島に住んでいる人については、近隣の都市の一等地にしっかりと店舗を構えている専門店のカタログとそうでない通販会社のカタログではどちらが安心して買い物をしやすいでしょうか?ほとんどの方が「オートバックス(専門店)のカタログ」とお答えになるでしょう。しかも商圏が限定される有店舗販売と異なり、通販では店舗の無い離島や遠隔地までもが対象商圏となります。日本の人口の約二割が離島・遠隔地に分布していると仮定して宝石のマーケットでシミュレートしてみましょう。1億3000万人(日本の人口)×20%×1万2000円(宝石のマーケットサイズ)=3120億円ですから、この中でたった15%しかシェアがとれなくても468億円の売上となります。通販マーケットの裾野が拡大するにつれ、品揃えも「狭い間口で深い属性」といった専門化の方向に進化していくことでしょう。こうなれば益々有店舗販売の専門店が無店舗販売事業を一体化したほうが効果が上がると予想されます。有店舗販売が無店舗販売事業を包み込むと大変な威力を発揮する、と私は考えています。
不況時は大商圏商法と小商圏商法を一体化させなければならない
小商圏化と客単価ダウンが不況の大きな原因だとすればこれを四つの方向に分けて考えます。例えば小商圏化に対しては、「大商圏商法による抵抗」と「小商圏商法の確立」という二つの方向で考えます。大商圏商法とはさらに商圏が縮小するのを防ぐために商品政策やチラシ等によってより遠くからお客様が来るようにすることです。しかし、小商圏化が進行しているのならば、小商圏商法を確立しなければならないともいえます。小商圏商法とはつまり口コミです。お店の顧客名簿を整理し年間の買上高や来店頻度の高い上位20%のお客様に対して徹底的な固定客催事を仕掛けそのお客様の年間購買高を増やす。これが小商圏商法の決め手となります。
これからは大商圏対応のチラシを少しずつ減らし、その分を固定客へのアプローチに回していくといったように、大商圏商法と小商圏商法を一体化して考えねばなりません。
敵と味方を一体化すれば敵が味方になる
ミムラという私の指導先があります。ここでは息子さんが現場のマネジメントをすべて担当していましたが、10店舗ある店のすべてを到底1人では管理できないので一部を古い従業員のKさんに任せていました。Kさんは少数の固定客にしっかりと売り込むという昔ながらの販売スタイルを持っていました。先ほどご説明した小商圏商法です。私はこのミムラさんに対して主に大商圏商法、つまり商品力強化とチラシ訴求の指導を行い、店の売り上げを相当伸ばしていました。当然Kさんがこのことを面白く思うわけがなく、私に随分反目してきました。そこで私はKさんにこういう話をしました。「私が指導している大商圏商法も間違っていないと理解してほしいけれども、このような不況期にはKさんがやっているような小商圏商法がなければ会社を維持できない。小商圏商法と大商圏商法の両方を一体化しなければ会社としては利益を出せなくなる」こういうとKさんの目が一瞬耀き、そしてこう言ったのです。「先生よくわかりました。一緒に頑張りましょう。」
私が船井会長の言葉「敵と味方を一体化すると敵が味方に変わる」ということを目のあたりにした瞬間でした。
客数アップと客単価アップを一体化させなければならない
「客単価のダウンにはどのように対処すればよいのでしょうか?」最近こういう相談を受けることが多々あります。これには、商品力の強化と販売促進によってお客様にとにかく来店してもらうという、客数のアップで対処します。これが今までのやり方でした。しかしやはり客単価が減少しているのですから、客単価を上げる方策も考えねばなりません。総合店であればワンストップ性の追求です。ですからアメリカでは食品スーパーとドラッグストアが一体化して開発されているケースが最近多いのです。一方、宝石などの専門店がとるべき客単価アップの方策は、店内滞留時間の延長です。アメリカのバーンズ&ノーブルズという書店では、立ち読みどころかソファーセットまで用意して座り読みを勧めています。この「座り読みOK」戦略により滞留時間を延長し、本の売り上げを伸ばしているのです。日本でも岐阜のカルコスという書店でこの「座り読み」は実践されています。年商5億円ペースで順調に売上を伸ばしており、いずれ岐阜ナンバーワンの書店になると言われています。つまり、お客様の滞留時間を延ばすには、「売る目的以外の売り場の充実」がポイントであると言えます。ソファーセットやテーブルなどを置いてお客様にゆっくりと買い物をしていただき、購買単価を向上させるという手法は客数アップにもいずれ繋がります。このように客数アップと客単価アップを一体化させる手法をこれからは考えなければなりません。
不況時の対策
不況が小商圏化と客単価のダウンによってもたらされたのであれば、これまでの大商圏化のための販売促進やMD、または客数アップのための頻度品の強化の他に、
などが不況対策になるということがこれまでの話でご理解いただけたと思います。
ローコスト経営とハイコスト経営を一体化しなさい
 ローコスト経営をしようと思ったときに決算書の各項目を見て、全ての支出項目を削れるだけ削ってローコスト化しようとする経営者は会社を倒産に追いやるのみでしょう。私はこのことをウォルマートから学びました。ウォルマートではお客様の目につかないバックヤードや本社事務所や倉庫等ではハイテクを使って徹底的にローコスト化を行い、その浮いたコストの何%かをお客様から見える売場部分に投資し、他店と差別化を図るのです。例えばウォルマートでは、来店者に笑顔で挨拶をするためだけに入り口にピープルグリーターを置いたり、返品を無制限に受け付ける返品カウンターにスタッフが2人も張り付いていたりします。徹底したバックヤードの機械化により浮かせたマンパワーを主にお客様と接点のある場所に投入しているのです。こうしてウォルマートはお客様から圧倒的なロイヤリティを勝ち取っているのです。企業経営とはハイコストとローコストの分配業であるといっても過言ではないと思います。ローコストとハイコストを一体化させなければ繁盛企業はつくれないということです。
ローコスト経営をしようと思ったときに決算書の各項目を見て、全ての支出項目を削れるだけ削ってローコスト化しようとする経営者は会社を倒産に追いやるのみでしょう。私はこのことをウォルマートから学びました。ウォルマートではお客様の目につかないバックヤードや本社事務所や倉庫等ではハイテクを使って徹底的にローコスト化を行い、その浮いたコストの何%かをお客様から見える売場部分に投資し、他店と差別化を図るのです。例えばウォルマートでは、来店者に笑顔で挨拶をするためだけに入り口にピープルグリーターを置いたり、返品を無制限に受け付ける返品カウンターにスタッフが2人も張り付いていたりします。徹底したバックヤードの機械化により浮かせたマンパワーを主にお客様と接点のある場所に投入しているのです。こうしてウォルマートはお客様から圧倒的なロイヤリティを勝ち取っているのです。企業経営とはハイコストとローコストの分配業であるといっても過言ではないと思います。ローコストとハイコストを一体化させなければ繁盛企業はつくれないということです。
究極の一体化とは
有店舗販売と無店舗販売を一体化せよ、大商圏商法と小商圏商法を一体化せよ、客単価アップと客数アップを一体化せよ、ローコスト経営とハイコスト経営を一体化せよ、顧客満足と社員満足を一体化せよ−等々一体化しなければならないものがこれまで沢山出てきました。結論としては、「自分自身と他人を一体化しなさい」ということだと私は思います。結局、顧客満足だとか会社の一体化というのは、皆さんが自分を大切にするのと同じくらい顧客を大切にすればそれで済むわけですし、自分を大切にするのと同じくらい部下や上司を大切にすればそれでいいということだと思います。これを船井会長は「親身法」と言っています。これこそが究極の一体化ではないかと私は考えています。そしてまた、この「親身法」というコンセプト自体がコンサルティングの現場でとてつもない威力を発揮する時代が来たと最近つくづく感じています。一体化こそ今最も重要な経営のコツだと私は考えています。
以下では一体化の他にも数え切れない程存在する、示唆に富んだ船井会長の教えを、私の観点から皆様にお伝えしたいと思います。
| 親身法・・・子に対する親のような気持ちになってすべてに対処すること。相手の立場にたってなにがその人のためになるか親身に考えてあげること。 |
素直とは
他者からAという情報に接した時、Aと頭の中に再現される状態(定義1)、あるいは、人類の科学も最終到達点には程遠いし、その中の百分の一の情報も理解していない自分が、この事態を判断することは難しいと考え、一度理解してみようと取り組んでみること(定義2)、大きく分けてこの二つを素直と言います。人の言うことを鵜呑みにすること、つまり「盲信」を素直だと勘違いしている人もいますが、これは違います。逆に自分が判らないことを頭から「そんなことある筈がない」と否定するのを「盲疑」と言います。
「盲疑」でも「盲信」でも正しい情報は入って来ません。結局「盲疑」も「盲信」も素直な人より騙され易いということになります。素直とは加工される前の情報を原形のまま受信する能力のことなのです。全ての情報を一旦は受け入れて論理的体系的に理解しようとしなければならないということです。もしそれで理解できなければ吐き出せば良いのです。このプロセスを経ずに何でも信じるのが「盲信」、何でも疑うのが「盲疑」です。素直とは能力であり、性格ではありません。成功する人はこの能力を兼ね備えているのです。
| 素直・・・プラス発想・勉強好きとならんで船井流の思考の根幹をなす要素のひとつ。人や企業が成長するための必須条件であるとされている。 |
納得とビー・ギブン
船井会長がギブアンドギブということをよく言っています。20代はテイクアンドテイクでいいけれども、30・40代はギブアンドテイク、50代はギブアンドギブでいこうというものです。しかし人間なかなかギブアンドギブは実践できないものです。そこで私はギブアンドビーギブンという表現を使っています。「与えたり奪ったり(give&take)」ではなく、せめて「与えたり与えられたり(give&be given)」でいこうという考えです。これを「互恵」と船井会長は言っています。ですから融合の時代は相手を納得させ、ビー・ギブン(be given)という考え方を主体に人付き合いをしようという結論に達しました。日常の仕事の中では立場の違い、世代の違い、性別の違いなど様々な「違い」の要素があります。この「違い」のためになかなかうまくいかないことも多いことでしょう。しかし、生まれも育ちも年齢も違うのですから、うまく行かないのが当たり前なのです。そのとき相手の心がONになっているか、納得してくれているか、理解してくれているか、また、こちらも相手の本音を理解しているか−等が大切なポイントです。
願望と意思
願望とは「したいなあ」というもので、「する」といった意思とはかなり異なります。願望は大きく四つに分かれます。一つは「夢想的願望」といって、意識でなんとなく望んではいるが、少しも具体的に目指してはいない状態です。例えば、ただぼんやりと金が欲しいと思っているだけの人は一生金持ちにはなりません。自分の置かれている現状を把握し金持ちになるには一体何をしなければならないかを具体的に詰めて初めて金持ちになれる可能性が生まれるのです。これは明らかに意思とは違います。
二つ目は「求待敵願望」といって他人が何か自分のためにしてくれるのを待っている状態のことを言います。こういう人達は「会社は自分のことを分かってくれない」などと愚痴をいつもこぼしています。何もしようとしない自分のことなど会社が分かってくれる訳などないのです。分かって欲しいという意思さえあれば愚痴をこぼす前に何か行動を起しているはずです。
三つ目は「話題としての願望」です。本当は特に望んでもいないのに、話題を持たせるためについ口をついて出てくる意思のない願望のことを言います。上司はこれをまともに受けないように気をつけなければなりません。
四つ目は「自己誤認的願望」といって自信過剰の状態を言います。できもしないのに今日から毎日3時間勉強すると宣言して、三日坊主に終わってしまうタイプです。
結論として申し上げたいのは、強い意志が一つの方向に向いた願望でないと決して実現されないということです。「こちらに行きたい」ではなく、「必ず行くんだ」という強い意思がなければ物事は実現しないのです。
「答える」と「応える」の違い
旅館であった話をしましょう。ある宿泊客が若い仲居さんにこう尋ねました「あの自動販売機は千円札使えるの?」すると仲居さんはこう答えました「申し訳ありません。あの販売機は千円札使えないんです。」さて、この返答は正しいのでしょうか?確かにお客様の質問の言葉には「答えて」いますが、お客様の気持ちには全く「応えて」いません。お客様は煙草を吸いたいのです。旅館業の従事者なら本当は最低でもこう応えるべきでしょう。「もしよろしかったら両替してまいりましょうか?」あるいは「私が買ってまいりますのでどの銘柄をお吸いですか?」こうしてお客様の言葉自体よりもむしろ気持ちに「応えて」あげるのです。ただ、お客様が無理な要求をしてくる場合もあります。このような場合でもすぐに「できません」と答えてはなりません。「お待ちください。何とかしてもらえないか聞いて参ります」と言って、こちらとしても手を尽くした姿勢を見せてお客様に納得してもらうことが大切です。キーワードはNothing Noです。とにかく第一声で「できない」と言ってはいけません。このことは旅館業でなくても全ての業種に当てはまることだと思うのですが如何でしょうか?
1+1=2にするために
普通の仕事ではなかなか1+1=2になってくれません。少し方向がずれたりすると1に1をプラスしても1にしかならないケースも有ります。皆さんが従業員を使うのは、皆さんの欠点を補ってもらうためでもあるのです。ただ気が合うという理由で皆さんと同じ能力を持った従業員だけを雇っていれば、この企業のポテンシャルは向上しません。部下や社員のそれぞれ異なる長所・短所を見抜き、その長所をうまく組織の中で活用する方法を見つけてこそ1+1=2となるのです。
役割の違いを認識するという意味では、コンサルタントも同じです。自店や地域のことばかり考えている社長と、全国を股にかけたドサ回りのコンサルタントではその役割が違うからこそうまく噛み合うのかも知れません。
また小売店の競合対策も同様で、
(1)競合店と全く違った商品が置いてある
(2)全く違う品揃えがなされている
(3)競合店より魅力的な売場演出がなされている
(4)競合店より接客・サービス・企画が優れている
等の要素がなければお客様が自店に足を運ぶことはまずないでしょう。
息抜きと思考回路
私の指導先にある製造卸の企業があります。仮にA社としておきましょう。その後しばらくしてからここのオーナーに新たに数社クライアントをご紹介いただき何社かと指導の契約を結ぶことになりました。ここまではよくあることなのですが、その後不思議なことが起こります。後からご紹介いただいた企業の方が先に業績が伸び始め、A社の業績だけが一向に改善されないのです。後になって理由がわかったのですが、オーナーが無類のマージャン好きだったのです。土曜日などは朝の10時から翌日の午後までマージャンをやるそうです。30時間近くもマージャンをやっているというのです。これでは完全にこのオーナーの思考回路はマージャンに支配されてしまいます。月曜日に仕事に復帰したとしても、頭の思考回路はすぐには切り替わりませんので、企業経営者としての直感に溢れた冷静な判断はできません。頭というのはそんなに簡単に切り替わるものではありません。長い時間仕事のことを真剣に考えれば考えるほど、熟達した思考回路が形成されます。息抜きは5時間以内に抑えること。10時間以上一つのことに没頭するとその思考回路が頭の中に定着してしまい、それを変えるのに非常に時間がかかります。このことを裏返せば次のようにも言えます。3年間ひとつのことに集中して考えをめぐらせれば、必ず驚異的な思考回路が形成され、解決策が見つかるということです。3年間頭脳と身体をひとつのことに集中して使い切ればその分野で超専門家になれると船井幸雄も言っています。仕事の思考回路の上に余分なものをできるだけ載せないようにしたほうがよいでしょう。息抜きは構いませんが、それもある一定の時間を超えると息抜きではなくなってしまいます。
善苦悪快観念とは
エデンの園で罪を犯したから人間に罰として労働を与えたという教えがキリスト教にありますが、この考え方はおかしいと私は思います。だから欧米人は休日には一切仕事をしようとしません。仕事が苦しいものだと思い込まされているのではないでしょうか?私は仕事は楽しいと思います。起きている時間のほとんどあるいは人生のほとんどを仕事をして過ごすわけですから、仕事が楽しくなければ楽しい人生を送ることは不可能です。
人間は頭を使うのが楽しい地球上で唯一の生き物なのです。修学旅行などでお金を賭けるわけでもないのに、ずっとトランプやオセロをやっていたことを皆さんも覚えているでしょう。
では何故勉強嫌いな人が多いのでしょうか?これは親や学校の教育法にも問題があるのだと思いますが、とにかく苦手を克服させるために欠点ばかりを修正しようとするからです。「勉強しろ=欠点を直せ」という意味合いで口うるさく言われるものだから余計に勉強したくなくなるのです。このようにして「良い(勉強する)ことは辛い、悪い(さぼる)ことは楽しい」という善苦悪快観念というのが形成されていきます。仕事も同じことで、欠点修正の社員教育をしていると、「仕事は辛い、仕事をさぼることは楽しい」という観念が従業員にも定着してしまいます。では子供はどうすれば楽しく勉強をするのか。従業員はどうすれば積極的に働いてくれるのか。それは勉強の好きな子供を見ればすぐにわかります。良い成績をとって褒められたい一心で、始めは好きでもない勉強を一生懸命やります。そして良い成績をとって周りから褒められれば、だんだん勉強を好きになってきます。仕事も同じことが言えます。一生懸命に仕事をすると仕事が楽しくなり収入も増え、会社内での地位が上がり、それに伴い社会的地位も向上し、さらに仕事が楽しくなるのです。
私の人生訓
ある会社の講演会で「小山先生の人生訓について話してください」といわれたことがあります。その時に私なりにまとめたものを以下に列挙したいと思います。もしよろしければ参考にしてください。
意地を張って得をしたことがありますか?絶対にない筈です。私は3年前にやっとこれが実践できるようになりました。
明らかに判っている相手との考え方の違いを指摘して相手との関係が改善されたことがありますか?例えば自分の妻に「お前と俺とはこういうところが合わなかったな」といっても溝が深まるばかりでしょう。ですから、明らかに判っている部下の欠点を決して口に出して言ってはなりません。私は今の秘書に対してこのことを100%実践しているつもりです。
自分の立場の正しさを主張して、相手が納得したことがあったでしょうか?特に上司が部下を納得させる場合、気をつけなければならないのは、部下は組織図上の位置付けで強引に納得させられているのかもしれないということです。上司に本当のリーダーシップがなければ部下は心を開いて納得しようとはしません。リーダーであるからこそ誤りは素直に認めたほうが良いのです。
「創造性開発講座」開催のご案内 ”21世紀に向けての創造性開発の実践”をテーマに「創造性開発講座」を開催します。
詳しくは(財)岐阜県産業経済研究センターまでご連絡下さい。 |