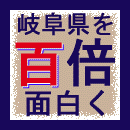
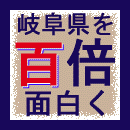 |
ちょっと、派手なタイトルである。しかし東の「江戸八百八町」や西の「大阪八百八橋」にくらべれば、まん真ん中の岐阜県を「百倍」とは、ささやかなものである。心配なのはむしろ話が看板倒れにならないか、ということである。2回目に続いて3回目の今号も「古代天皇と岐阜県は深いおつき合いがあったという話」です。 |
古代天皇と岐阜県は深いおつき合いがあったという話(下)
匠 照人・文
 |
 |
| 根尾の薄墨桜 | 養老の滝 |
さて、今年も本巣郡根尾村の薄墨桜は見事だった。幹回り9.1メートル、樹齢およそ1500年だが、この老樹は、開花時の花は淡白色だが、やがて薄墨色に変わるところから「薄墨」の名があるといわれている。また一説に、この桜を植えて詠ったという継体天皇の ”身の代と遺す桜は薄住よ 千代にその名を 栄盛へ止むる”という和歌の「薄住」からとった名ともいうが、「薄墨」にはロマンチックな陽気さが感じられ、「薄住」には何か悲しみがこもっているようである。
もとは尾張国一宮・真清田神社(一宮市)ゆかりの土田家から見つかった古記録『真清探当證』によれば、安康天皇の皇位継承をめぐって、弘計王(後の顕宗天皇)の幼い皇子男大亦王は雄略天皇の迫害を恐れて、ある夫婦に守られて、尾張の国から美濃の国の根尾谷(本巣郡根尾村神所)に逃れ住んでいた。やがて王が18歳になられたとき、皇子がないままに没した武烈天皇のあとの天皇にと、朝廷の重臣たちに迎えられたとき、王は18年間住みなれた根尾谷の生活を惜しみ、一株の桜を植え、さきほどの和歌を添えられたという。その後樟葉宮(大阪府枚方市)で即位し、26代継体天応になられたというのである。
それから、およそ140年後、中大兄皇子(後の天智天皇)は、蘇我入鹿を倒して天皇親政による大化改新を断行した。
その後、皇子が天智天皇になったとき、天皇の弟・大海人皇子を皇太子にしたが、わが子の大友皇子が成長するにつれて、天皇にしようと思うようになり、天皇が死期に近づいたある日、大海人皇子を呼んで、天皇になるよう進めたが、彼は天皇の真意を見抜き、即座に皇太子を辞して吉野山に遁世し、大友皇子は政治の実権を握った。
671年12月。天智天皇が没すると、大海人・大友両皇子の間は険悪になり、ついに大海人皇子は、翌年六月東国、すなわち美濃国への脱出と不破道の閉鎖に成功し、約1ヶ月の戦いの末、大海人皇子が勝利して天武天皇になった。壬申の乱である。
天武の発意による『日本書紀』には、大海人皇子が天智や大友によって苦境に追われたため、止むなく戦ったと記してあるが、近頃では、私は、壬申の乱は、むしろ大海人皇子によって仕組まれた天下取りのプランだったのではないか、と思うようになった。
その理由は三つ。一つは大海人皇子の経済的所領湯沐邑・美濃国「安八磨郡」は、現在の大垣市・安八郡・不破郡・揖斐郡南部に及ぶ広大な地域といわれ、その当時において最も人口が集中し、生産性に恵まれていた地域と推定され、かつこの所領民は何時でも直属の武力団化ができ、そこに皇子の腹臣多臣品治が支配人として配されていたことである。二つめは、この地域は関ヶ原の山峡によって、東西交通の要所、つまり朝廷からみると、この地を抑えられると東国の武力を得られなくなることである。三つめは、皇子は、近従者に美濃の豪族たちの子弟、村国雄依・身毛君広・和珥部臣君手・朴井連雄君らを積極的に採用し、美濃国の豪族たちとの親交を図っていたと思われる。
つまり、私は皇子の壬申の乱の勝利のカギは、美濃国にあったと思うし、むしろ皇子は将来このことのあるのを予期して、周到に計算し、計画されたシナリオだったのではないか。だからこそ、美濃国は天武以後の歴代天皇とのかかわりが一層深くなったと思っている。
天武天皇の皇后が、持統天皇になるや、わが子・草壁皇子を次の天皇にと、大津皇子を謀反の罪で自害させ、側近の礪杵道作(美濃国出身)を伊豆に流し、新羅僧行人を飛騨の寺院に流したが、病弱だった草壁皇子は死去した。上皇になってから、美濃など5ヶ国の行幸の旅に出て、信濃に通じる官道「木曽道」の開通を視察し、また壬申の乱の功労者をねぎらわれたが、都にかえって、間もなく亡った。
元明天皇(女帝)は、天武の意志であったわが国の史書編さんを、さきの多臣品治の子で美濃出身とみられている太安万侶に命じて、『古事記』を撰上させた。
次の女帝元正天皇は、即位すると直ちに美濃国多度山(養老山)に行幸して、この地の美泉を賞賛し、717年に元号を「養老」と改元して、美濃国の人々に位や贈物・減税をおこなった。
聖武天皇は、天平12年(740)10月に伊勢へ行幸。11月に美濃国多度山の美泉をご覧になり、不破郡の宮処寺・曳常泉・美濃国府・不破関をご巡幸。「飛騨楽」を鑑賞するなど約1ヶ月滞在されている。
ところで、『岐阜県史』によれば、文武・孝謙・称徳・淳和・陽成の五天皇の即位式すなわち天嘗祭に、美濃国は悠紀国あるいは主基国に選ばれて奉仕しているが、その頃では最も多く選ばれているという。悠紀・主紀とは簡単にいえば、天嘗祭に用いる新穀や酒を造って献進する役目のようである。
美濃国は、この天嘗祭にもう一つかかわっている。それは美濃国など7ヶ国の「語り部」が、祭儀で古くから伝わる大和朝廷を称える「古詞」を奏上するというセレモニーだが、美濃国は最も多く8人が奉仕する例になっている。「養老」の元号にみられるように、古代の美濃国は「水」を介して、歴代天皇と深いかかわりを保ってきたが、その役目をつとめたのが、関・美濃両市を中心に奥美濃の勢力をもっていた豪族・身毛氏であった。
(次回は、安吾氏の「日本は飛騨から始まった」という話です)