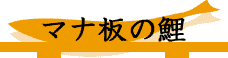
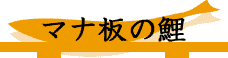
| 市橋に来る人に夢と希望と錯覚を与えたい | マナ板の鯉 |
| 浅野 のぶなが 有限会社伸愛 代表取締役 |
|
| 料理人 | |
| 藤掛庄市 岐阜大学教育学部教授 後藤 一俊 株式会社中広代表取締役 |
−「岐阜を考える」この欄は様々な分野で活躍していらしゃる方に登場していただき、社業繁栄の一助になればということで設けております。今回、マナ板の上に乗っていただく鯉役は、建設関係のマネージメントをはじめ、岐阜市の市橋地区を拠点に、ユニークな店舗展開を進める浅野のぶなが社長。料理人は前回も登場願った岐阜大学の藤掛教授と”辛口経済人”の一人、中広の後藤社長です。
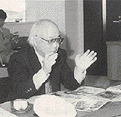 藤掛庄市教授 |
 後藤一俊社長 |
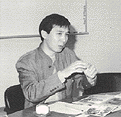 浅野のぶなが社長 |
| 浅野 | うちは伸愛という会社でして、子供からとった名前です。表向きは伸吾(shingo) と愛ということでして、S&Aといいまして都市建築研究所という名で自然を交えた建築を目指しています。コニカさんと提携して「写真亭のぶなが」をやり、シキシマパンとも一緒に文化事業ということで「のぶながじゅパン」をやっています。写真も音楽もパンもすべて、文化だという観点が動いています。織田信長ではありませんが、自らが動いて文化を作っていこうと考えます。 |
| 後藤 | 浅野さんが市橋地区のこだわる理由が知りたいですね。 |
| 浅野 | いま行政側のやっている街づくりをみましても、例えば施設なら有名な建築家のバラバラなポリシーでバラバラなものを造っている傾向にあると思いますね。せめて市橋地区だけは自分たちのものを創っていきたい。自然の生態系を保護して一体化した街づくりをしていこうと。この辺りは昔、県庁が来る前は小川のせせらぎがあり、ドジョウやウナギ、ナマズが棲んでいたところなんです。いま梶原知事が世界文化村をつくるということで、私たちもそれにふさわしい文化ゾーンをつくるために、ハワイからヤシの木を持ってきて電信柱のかわりに10本位植えましたね。とにかくここに夢と希望と錯覚を与えたいと。民間でもここまでできるってことを証明したかったんです。 |
| 藤掛 | 錯覚ってのが面白いですね。どう錯覚するんでしょうかね。ヨーロッパ風とか、ディーズニーランドとか、異次元にきた錯覚とか・・・・・・いろいろありますよね。 |
| 浅野 | 郷土愛という意味でスイスのような街並みにしたい。新近代建築で自然資材を多様化して自然の花を植え、イメージとしてスイス風にしていきたい。 |
| 後藤 | 浅野さんが次に目指す事業とはなんですか。 |
| 浅野 | 新本屋をやりたいんです。いわゆるベストセラーを置くのではなくて”ドベ”セラー(笑い)を置きたい。図書館にも置いていないような変わり種の、皆さんが買わないような本をね。 |
| 藤掛 | 例えば美術書は日本では高いから誰も買わないですよね。ところがイギリスやアメリカから輸入すれば100ドルするのはないんですよ。日本円で1万円するものは絶対にない。そんな本があればみんな買いますよ。 |
| 浅野 | 「国破れて山河あり」といわれましたが「経済破れて山河なし」ということで、自然がない。原点に戻るには歴史を勉強してほしいと思いますね。それもコトバじゃなくて絵で見て勉強してほしい。 |
| 藤掛 | インターネットを利用して、電子ブックで見るだけじゃなく、音を聴くとかしてね。そういったものを売るだけじゃなく作ったらどうですか。英語盤を作って外国へ売ればいいんですよ。信長を岐阜だけにしておくのはもったいない。(笑い) |
| 後藤 | さきほど浅野さんは文化といわれましたね。実は私は文化というコトバにあまり興味がないんです。文化は豊かさが共有されないと絶対文化は生まれてこない。そう思っているんです。日本でも貴族とか豪族がいた京都など富が集中したところには食文化を育っていますが、それ以外にはあまりありませんね。浅野さん流の文化とはなんですか。 |
| 浅野 | かつて開高健さんがいったコトバに「文化とは移動できないもので、文明は移動できる」 とね。私の思う文化とは好きか嫌いか。文明とは損得で物事をみる。私がやっているパンでも音楽でも写真でも好き嫌いで決めますよね。だから文化なんですよ。私はね、市橋発信、岐阜発信のスターを出したいんです。市橋で音楽を聴き、パンを食べ、岐阜の自然のなかで育ち、岐阜の経済人とか知識人とかの人たちに感化された大スターを出したい。例えばアイルトン・セナのように |
| 藤掛 | 話が戻るかもしれませんが、ぼくは文化は嫌いだけどカルチャーは好きなんです。日本人の持っている文化というコトバの意味と、カルチャーとは全然違う。文化とは中国からもってきていて、文に化するという。文化が嫌いなのは文化人が嫌いということでね。語源からすれば、「カルチベイト」で、耕やすというところからきているんです。浅野さんの言ってらっしゃる文化はカルチャーの方ですよね。 |
| 後藤 | CDショップ、パン、写真そして本屋で4点セットになるわけだけれど、その一つひとつが何で結びついているのか。浅野さんは文化だとおしゃるけれど、まだ私には見えてこない。それぞれの店づくりの特徴というか、コンセプトをはっきりしていく必要があると思うんです。CDショップなら「育てる」部分、パンなら「作る」ところ、写真なら「スタジオ」がセットになっているほうがいいわけです。CDなら若い人が作れます。CDそのものを作るのではなく、音を自分で創造する人のために、CDを作る。そういうようなCDショップなら面白いかもしれません。パンはね、暇な主婦が夕食でもいいし朝食でもいい。ここで作っていきなさいよ、と。若い女性だったら材料も揃っているし、彼氏のために。そして、パンづくりの匠、パンづくりの芸術家といいますか、本業は他にある。それが主婦であり、OLだったり。私はパンづくりの匠として自負できるんです、という人をつくっていくと面白い。写真にしても、いろんなバリエーションのなかで腕を磨いて、一皮むくと、いわゆる信長が発信した写真の匠であると。写真家ではないが、そういうものを作っていくと、文化と人を創造していくことになると思いますね。 |
| 浅野 | ぼくは10年前からドイツのワイン協会、日仏協会の人々とともにソムリエというコトバを広めたんですね。ところがパンにはソムリエに匹敵するマイヤーという職人のコトバががあるのに、それほど広まっていない。日本でいうと匠にあたります。ところが、このマイヤーも時給がアルバイトの人と一緒では馬鹿らしくてやらないわけです。ぼくはマイヤーは人に喜びを与える職業だと思うし、人間国宝になれる職業だと。オーナーがそれだけの給料を払って維持していかないと、その職人さんたちは他の高級職なんかになって散ってしまう。 |
| 藤掛 | ワインの話がでましたが、ワインというのはまさにカルチャーなんです。土地を耕して手作りのワインを産みだす。パンにしてもそうだし、日本なら手打ちそばがありますよね。 |
| 後藤 | 話は変わりますが、浅野さんに新しい型のロード店をつくってほしい。市橋発のものをね。そのとき肝心なのは、目的の整理と目標の設定ですね。事業として考えると、数字の設定。この二つが設定されるとスタッフは育っていくと思いますね。あとは文化、感性を言いつづければいい。 |
| 浅野 | 岐阜もあと10年経てば人口は30万を割るといわれています。若者にとって魅力ある都市ではなくなってしまうわけです。それまでになんとか商業区域の見直しなどをして、いい街作りをしておきたい。 |
| 後藤 | 確かに岐阜市の将来性を考えれば、明るいイメージではないけれど、浅野のぶながグループが地域とともにどう育っていくのか、私は非常に興味がありますね。ただ、すでに岐阜の市橋から発信したこの感性文化事業は浅野さんのポリシーを持ってスタートしているわけですから、ぜひ成功してほしい。 |
| 藤掛 | 市橋発、世界へ。浅野さんの事業にはどうしてもマルチメディアが係ってくるでしょうし、インターネットを契約して、自分たちでホームページをつくって市橋−岐阜の情報を世界に発信する可能性が出てくると思いますね。その時に大切なのはやはり感性と知性だと思います。それを大事にして大いにがんばってほしいですね。 |
| 一口データ ■有限会社 伸愛
■関連会社
|