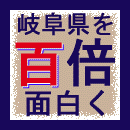
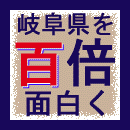 |
ちょっと派手なタイトルである。しかし東の「江戸八百町」や西の「大阪八百八橋」にくらべれば、真ん中の岐阜県を「百倍」とはささやかなものである。心配なのはむしろ話が看板倒れにならないか、ということである。1回目の前号では「日本のまん真ん中こそ、わが岐阜県の本質(アイデンティティー)であること」、2回目の今号では、「古代天皇と岐阜県は深いおつき合いがあったという話(上)」です。 |
古代天皇と岐阜県は深いおつき合いがあったという話(上)
匠 照人・文
わが国の最初の史書『古事記』や『日本書紀』を開いてみると、古代天皇と美濃・飛騨両国、つまり岐阜県は意外に深いおつき合いがあったことに驚くのである。
まあ、歴史家は両書は古代へ遡るほど史実と異なるところが多いといわれるが、ここでは、そのあたりのことは、100パーセント鵜呑みにして話を進めよう・
さて、神代を経て初代神武天皇から数えて9代目が開化天皇である。岐阜市岩田に「伊波乃西神社」が鎮座している。古代神社のランクづけで有名な『延喜式神名帳』(延長5年・927)にあげられている神社で、祭神は開化天皇の皇子・彦坐王である。神社の近くに彦坐王を葬ったという墓があって、御陵として宮内庁が管理している。この王が、隣国近江の豪族息長氏 −後に仲哀天皇の皇后・神功皇后を出した氏族 −の水依姫をめとって、生まれたのが神大根王(神骨・八瓜入日子王)である。
この王は本巣国造や長幡部連の祖といわれ、美濃国の中央部(今の岐阜市・本巣郡あたり)を支配していたとされている。つまり、現在の岐阜県の心臓部が天皇ゆかりの豪族によって治められていたというわけである。
それから2代あとが、12代景行天皇である。天皇は皇子・日本武尊(小碓命)とともに東奔西走して、皇威を大いに広めたが、艶福家でもあった。ある年の春、天皇は美濃の国の「泳宮」(可児市久々利)に行幸したとき、この地方の豪族、祟神天皇の皇子・八坂入彦の子の姉妹が美しいと聞いて、泳宮の池に見事な鯉をたくさん放ち、その鯉をオトリに姉妹をおびき寄せて、天皇の妃になるよう説得した。が、弟姫は断り、姉の八坂入姫が妃になり、生まれたのが次の13代成務天皇である。この久々利の地にも八坂入彦皇子の墓があり、やはり御陵として宮内庁が管理している。真偽のほどは別として、彦坐・八坂入彦両皇子の御陵が美濃にあるということは、美濃の国と天皇一族が深い関係にあったことをうかがわせるのである。
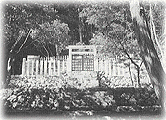 彦坐王のご陵(岐阜市岩田) |
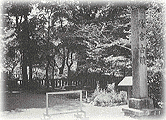 くくりの宮跡(可児市久々利) |
さて、さきほどの日本武尊すなわち小碓命には兄の大碓命がいて、二人は双子だったという説がある。もともと弟の小碓命は剛胆で武勇に優れていたが、兄の大碓命は軟弱であった。あるとき、景行天皇は前述の美濃の豪族・神大根王の子の姉妹を妃に迎えたいと思い、大碓命にその使いを命じたところ、彼は使いにいったがその姉妹が大変美しかったので、天皇に内緒で二人とも自分の妃にし、かわりの姉妹をたてて知らん顔をしていたが、間もなくそのことがバレてしまった。それにあれこれと事情が重なったため、天皇は怒って大碓命を美濃の国に追放した。つまり、天皇一族から勘当されて、美濃の豪族になったというわけである。それで、大碓命と姉・兄遠子の間に生まれたのが、「押黒之兄日子王」といい、美濃の国の「宇泥須和気」の祖になり、妹・弟遠子との間に生まれたのが「押黒之弟日子王」といい、身毛津君や守君の祖になったという。
また、日本武尊が東征のとき、美濃の国の善く弓を射る弟彦公が召されて参加しているが、その人物は「押黒之兄日子王」ではという説もある。しかし、この辺りの記録には、『古事記』『日本書紀』両書に違いがあって、よく分からない。いずれにしても、景行天皇とその息子たちは、美濃・尾張・伊勢すなわち美濃平野の国々と深くかかわっていたことは確かである。
16代仁徳天皇65年のことである。当時、飛騨の国に、身一つに両面があり、四手四足で超人的な能力を持つ「両面宿儺」と呼ばれる異形人が住んでいて、住民を苦しめ、天皇に反抗していたので、天皇は和珥氏の祖・難波根子武振熊なる人物を派遣して討ち取ったという出来事があった。この話については地元の飛騨の国ばかりでなく、美濃の国にも伝説が残っていて、両面宿儺に対して史書は鬼賊といっているが、地元の伝説はすべて王者か聖者として崇敬している点が大きい違いであり謎である。さらに伝説では両面宿儺は服従のしるしとして、位山のイチイの木で作った笏を天皇の即位式に献上したと伝えられ、事実、近いところでは、明治・大正・昭和・今上の各天皇の即位式にイチイの笏が献上されている。ところで、天皇の即位式といえば、美濃国は長い間とくに深くかかわってきたのだが、このことについては、いずれお話しすることにしよう。
さて、少し時代をくだって、21代雄略天皇時代のことである。吉備(現在の岡山県辺り)の豪族が謀反を企てているという噂が立ち、天皇は身毛津君大夫なる人物−大碓命の末裔にあたる−を吉備に派遣して様子を探らせた結果、謀反が発覚し、一族70人が誅殺されたと伝えている。身毛津氏もこの頃には現在の関市・美濃市あたりを本拠地として奥美濃を支配していたのではないだろうか。また、天皇のときの事として、天皇と当時の名匠・闘鶏御田や猪名部真根との逸話が記されている。この二人の名匠はいずれも伝説では飛騨の出身だと信じられている。
昭和60年(1985)に、国府町の「一之宮神社」の神宝である大型鉄鏡がX線調査で「鳥と文字」が浮かび、ちょうど「倭の五王」の頃に中国で作られた「き鳳鏡」と判明した。なぜ、このような貴重な鏡が飛騨に伝来していたのか。ということについて、毎年都に徴用することが定められた『斐陀匠条』(701年)が定められる以前に、すでに飛騨の匠たちは都の宮殿づくりに従事していたから、その統率者がもらったものであろうと、この鉄鏡を調査した三重大学の八賀晋教授は語っていた。とすると、「倭の五王」の一人、雄略天皇の頃のことかも知れないと、私はひそかに思っているが、こんなところにも岐阜県と天皇とのつながりがあったのかも知れない。