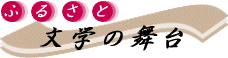
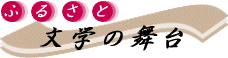
天心ら中山道を歩く
文・道下 淳
岐阜女子大学講師
| 整備される前の大井宿本陣-中山道は左に折れる。 天心らは乗合馬車でここを通った。 |
 |
明治30年、岐阜県を起点に中山道を歩き、長野県入りをした5人組みがいた。彼らの中心になったのは、明治時代における美術界の指導者で後に日本美術院を創設した岡倉天心であった。一行は川端玉章・寺崎廣業ら日本画壇の重鎮・中堅をはじめ、作家の大橋乙羽、天心が校長をしている東京美術学校教師、剣持忠四郎など、豪華な顔ぶれであった。
この旅の前、天心ら京都で古社寺巡りをしていた。そのとき、中山道を歩き善光寺参りをしようということになった。まず汽車で岐阜に直行、玉井屋に泊まった。乙羽が所用のためやや遅れ、夜遅く合流した。4月23日のことである。
旅の模様を乙羽が雑誌「太陽」に連載中の『千山萬水』のなかで紹介した。そのおかげで天心らの行動や、街道のありさまなどが今に残った。うち本県関係の記述は、「木曽五鶏行」「太田の渡」「日吉峠」の三章にまとめられている。出発すると間もなく天心が言い出し、ニックネームがつけられた。天心が「錦鳥」・玉章が「烏骨鳥」・廣業が「野鶏」・剣持が「軍鶏」・乙羽が「水鶏」である。
鶏のニックネームを付けたのは、玉井屋を出るとき鶏が鳴いた。めでたいことである。晴れの門出を「鹿島立ち」といい、「啓行」とも記す。啓行を音読みすると鶏行になる。一行は5人だから「五鶏行」。そこで旅行記の冒頭の章を乙羽は「木曽五鶏行」とした。
5人はいずれも和服に脚絆、ぞうりに紺足袋という旅姿であった。うち天心は紋付の着物に羽織という旅らしからぬいでたちだった。玉章はネルの着物に白いもも引きをはき、京都の大原女が用いる脚絆をつけていた。廣業と乙羽は、岐阜で脚絆を買った。
また、旅に山高帽でもなかろうと、桧笠を求めたり、腰のひさごに酒を満たしてのスタートであった。一行はいずれも酒豪ばかり。酒は欠かせなかった。
各務野(各務原市)の松並木で廣業と剣持がこうもり傘を刀に敵討ちのものまねをしたり、勝山(坂祝町)では乙羽が暗箱を組み立て写真を撮るなど、とにかく気ままな旅であった。
薮垣や鶏三羽落ち椿 天心
木曽入や松原三里つぼ菫 乙羽
以上は、鵜沼(各務原市)辺りで詠まれた句である。
中山道は鵜沼宿から東進すると「うとう坂」「観音坂」を越え勝山に至る山道で、なかなかの難路である。そのため、木曽川の右岸沿いに宝積寺(同市)経由の新道が開かれた。今の国道21号線のルートで、一行はこの平坦な新道を歩いた。
「長坂にかかる崖を切り崩して、道を水辺に通ぜるなり。松原を越せば、景色ひとしお美しく、天地を二分して左は峩峩たる山そばたてば、右は木曽川雪代水の青く湛えて、早瀬を下る舟は飛ぶよりもなお早く見ゆ」
乙羽が記す日本ライン沿いの描写である。
太田の渡しで木曽川を越え、今渡(可児市)で名物のうどんを食べひと休みした。ここから人力車で御高宿(御高町)に行き、升屋に1泊した。
同夜乙羽がふろ場にメガネを忘れた。探しに戻ったところ、ふろ場の板壁が燃えていた。大声を出して人を呼び、消し止めるというハプニングもあった。
中山道は御高宿から東へ進むと丘陵地帯に入り、細久手宿・大久手宿(いずれも瑞浪市)と続く。これが上街道である。天心らは上街道を敬遠して、日吉峠を越え釜戸(同市)に出る中街道を歩いた。この道は昔の東山道だといわれる。山続きの上街道を避けるために、明治になってから整備された。正岡子規や長塚節ら明治の文人たちも、天心と前後してこの街道を通っている。
『小川あり、水車小屋あり、橋を行く蓑笠の人、野牛を追いつつ駆ける村の童、麦は伸びて雨に露草の蛍を思わせ、木は裸にして、ここにはまだ春の来ぬかと疑う。』
『村の下口に桜美しう咲けり、谷川の水白く流れて青山の腰をめぐり、四五の草の家の杉に隠れ、枯木に見えて、げにここは日吉月吉の眺望なるべし』
『小川あり』のくだりは、次月(御高町)の風景。また『村の下口』の一節は、日吉峠を下った日吉辺の描写。いずれも日本画の世界そのものである。
中街道は瑞浪市内で名古屋に結ぶ下街道(国道19号線)と重複する。江戸時代からの重要な街道だが、大変な悪路で、ちょっと雨が降るとすぐぬかるみとなった。そのため肥満して足の弱い玉章が遅れ気味となり、天心が気を使って彼に付き添って歩いた。その『情けの厚さ、誰れか高士ならず、とせむや』と、乙羽も天心の人柄について記している。
釜戸近くで道が悪いには『県治の宜しからざる』ためと、話しながら歩いていたら、新任知事が騎馬で通り過ぎた。知事もこの悪路には、気付いたことだろうと、乙羽は書いている。
釜戸から乗合い馬車を貸し切り、大井宿(恵那市)へ急いだ。『道は石出で、泥深ければ馬飛び、車躍り車中めいめい鉢合わせをして、額に手をあつるも可笑』という悪路が続いた。
ところで天心らが出会ったのは、湯本義憲知事で、さる4月7日に発令されたばかり。おそらく初巡視の途中だったのであろう。湯本知事は在任期間は短かったが、治山治水に力を入れたことで知られている。
馬車は走り続けた。坂本(中津川市)辺りで日はとっぷり暮れたが、馬車は室内灯もつけなかった。余りにも暗いため一行は、『冥土をたどる心地』だったという。馬車は、もうこりごりだと話し合った。
中津川では橋利喜旅館に泊まった。あすからは木曽路、早立ちに備えすぐ床についた。遅く着いての早立ち。木曽路こそ『かわいい児に旅さすべきところ』
と、乙羽は思った。