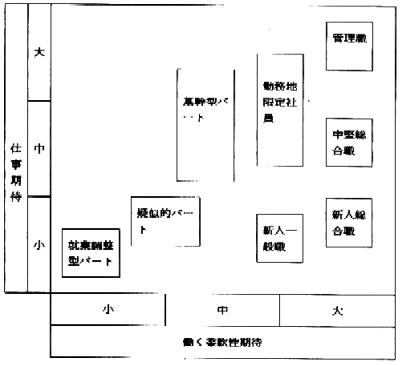| 論 文 | ||
| 労働市場の流動化と企業内賃金決定システム
| ||
| 今 野 浩 一 郎 (学習院大学 経済学部教授)
| ||
1. 賃金にとっての労働市場流動化の意味 | ||
|
労働市場が流動化し、 それが賃金に大きな影響を及ぼすであろうことに異論はないが、 この 「賃金への影響」 に二つの面があることに注意してほしい。 一つは、 「流動性の高い情報技術者の賃金水準が上昇している」 などと言われるように、 流動化によって市場における賃金の水準や構造が変化することであり、 もう一つは、 流動化によって企業内の賃金決定システム (さらに、 その結果としての企業内の賃金構造) が変化することである。 今回は後者の問題に焦点を当てたいと考えているので、 まず企業内賃金決定システムにとって流動化とは何なのかを明らかにしておく必要がある。 「労働市場の流動化」 というと、 長期勤続を予定していた総合職型の労働者の移動を思い浮かべる読者が多いと思う。 しかし、 企業の賃金管理にとって、 それにも増して重要な点は、 雇用形態が多様化し、 相対的にみて流動的な層であるパートタイマーや派遣労働者等のいわゆる非正社員が増加しつつあることである。 というのは、 それによって企業が雇用契約、 働き方、 キャリアの異なる多様な労働者をいかに管理するのかという人事管理上の課題に直面するからであり、 そうしたなかで賃金管理の面では、 多様な労働者間の賃金の均衡をいかにはかるかが大きな問題になる。 労働市場の流動化が企業内賃金決定システムに及ぼす影響の中心はこの点にある。
| ||
2. 二つの賃金 | ||
|
(1) 日本型賃金制度の特徴と限界 これまでの日本企業の賃金管理は、 正社員としての労働者に画一的な賃金制度を適用する、 より正確に言うと、 多様な仕事に従事しているにもかかわらず同種の労働者とみなすことによって正社員に画一的な賃金制度を適用する点に特徴があった。 それでも画一化された賃金制度の適用が難しい労働者に対しては、 子会社に分離して異なる賃金制度を適用する、 あるいは企業内で雇用する場合でも例外的な労働者として扱い例外的な賃金制度を適用するという方法で対処してきた。 しかし、 これほどまでに雇用形態の多様化が進み、 非正社員が増加し、 彼ら (彼女) らの戦力化が進むと、 こうした例外的な措置で対応することが難しくなる。 さらに正社員についても、 キャリアや働き方の違いから一般職、 総合職、 勤務地限定社員、 専門職、 専任職などなどの多様化が進みつつあり、 それらを 「同じとみなす」 ということが難しくなりつつある。 そうなると、 雇用形態や働き方の異なる労働者には、 それぞれの事情に合わせた最適な賃金制度を適用することが必要になるが、 そのさいに問題になる点は、 異なる労働者の、 したがって異なる賃金制度によって決定される賃金の間の均衡をいかにはかるかである。 この点を検討するには、 まず異なる労働者に、 どのような異なる賃金決定システムが適用されているかを確認することが必要になろう。 | ||
|
(2) 「内部化された賃金」 と 「外部化された賃金」 正社員とくに企業内で長期にわたり養成され、 基幹労働者としての活躍を期待されている総合職的な労働者の賃金決定システムには、 流動性が低く長期勤続を前提とした労働者群であるが故に外部労働市場を直接意識する必要がない、 したがって、 長期的な観点に立ち、 組織内部での基幹労働者間の均衡 (一般的には 「内部公平性」 と呼ばれる) を考えて賃金を決定するという 「内部化された賃金決定」 の特徴をもっている。 それに対して、 長期勤続を期待されない非正社員の場合には、 外部労働市場との出入りが激しい、 したがって、 企業側に長い期間をかけて内部養成するつもりがないために、 外部労働市場を意識した 「外部化された賃金決定」 の形態をとる。 そうなると雇用形態の多様化のなかで発生する賃金の均衡問題は、 まずは、 組織内での内部均衡を重視した 「内部化された賃金」 と、 外部労働市場と連結した 「外部化された賃金」 の間の均衡問題として登場する。 さらにこの二つの賃金の間には、 つぎのような重要な違いがあることを強調しておきたい。 第一に、 「内部化された賃金」 が長い期間をかけて個人のパフォーマンスが反映されればよいという意味で 「長期決済型賃金」 であるのに対して、 「外部化された賃金」 は頻繁な移動を前提にしているが故に 「短期決済型賃金」 としての特性をもっている。 もう一つは、 「外部化された賃金」 は市場が決める、 したがって企業が自由に決めることのできない賃金であるのに対して、 「内部化された賃金」 は企業にかなりの程度裁量権が与えられた賃金である、 という違いである。 | ||
3. 賃金の二つの均衡 | ||
|
(1) 企業を越えた 「外部均衡」 これまでの日本企業の 「内部化された賃金」 は、 外部労働市場から遮断された企業のなかで人材が養成され、 活用されることを前提にしているので、 組織内での均衡 (「内部均衡」) のみを配慮して決められてきた、 と考える人は多いだろう。 しかし、 いかなる 「内部化された賃金」 でも、 二つの面から 「外部」 との均衡がはかられねばならない。 第一は、 他社 (外部市場) の 「内部化された賃金」 との均衡である。 「内部化された賃金」 は流動性の低い 「内部化された労働者」 を対象にした賃金であるので、 企業を越えた均衡などありえないと思われるかもしれない。 しかし、 いかに流動性が低くても、 「内部化された労働者」 が 「内部化された賃金」 に納得するには、 それが組織内序列とともに、 他社 (市場で) の同種の 「内部化された労働者」 の水準を適切に反映していることが必要であろう。 そういうと、 これまでの年功賃金制度をみると、 個別賃金の市場相場 (「外部均衡」 によって決まる賃金相場) が形成されていたとはとうてい思えない、 との反論が出てこよう。 しかし年功賃金制度のもとでも、 「外部均衡」 をはかるための相場形成システムは間違いなく機能していた。 年功賃金制度とは、 「年功 (あるいは能力)」 に基づいて賃金を決める仕組みであるが、 その年功 (能力) を、 他社と比較可能なように客観的に測定することは難しいだろう。 そこで年功 (能力) の代理指標として学歴・勤続・年齢が用いられ、 新規学卒採用で入社し平均的に昇進した標準労働者の年功 (能力) は企業を越えて等しいだろうとの前提にたって、 モデル賃金を 「外部均衡」 をはかる、 つまり個別賃金の市場相場を形成するための道具として活用してきたのである。 しかし、 この相場形成システムも、 いま変化の圧力を受けている。 それは年功賃金制度が新しい成果・業績主義型の賃金に改革されようとしているからである。 もし成果・業績型賃金に移行するのであれば、 従来の年功・能力 (その代理指標としての標準労働者) に代わって、 企業を越えて何らかの形で成果・業績を表現する指標と、 それに基づいて 「外部均衡」 をはかる仕組みが開発されねばならないはずである。 「内部化された賃金」 の決め方が変化するなかで起きている、 新しい均衡問題の一つである。 | ||
|
(2) 求められる組織内 「外部均衡」 の形成 もう一つの均衡問題は、 「内部化された賃金」 と、 同一企業内で働く長期雇用・育成型でない労働者の 「外部化された賃金」 との均衡、 つまり企業内での組織内 「外部均衡」 をいかにはかるかという問題である。 前述したように 「内部化された賃金」 と 「外部化された賃金」 の決定システムの間には、 もともと内部均衡重視型と外部労働市場直結型、 長期決済型と短期決済型という点で基本的な相違点がある。 このことを現行の賃金制度にてらして説明すると、 「内部化された労働者」 には職能資格制度に基づく職能給型の制度が、 「外部化された労働者」 には職務分類制度をベースにした仕事給型の制度が適用されている。 ここで後者については、 パートタイマーやアルバイトの間で一般化している賃金制度を思い浮かべてほしい。 彼ら (彼女ら) には年齢、 学歴等の個人属性にかかわらず 「この仕事で幾ら」 のルールで賃金が支払われ、 その水準は外部労働市場の相場に強く規定されている。 しかしながら、 雇用形態の多様化が進み、 「外部化された労働者」 が増加し戦力化されてくると、 彼ら (彼女ら) を例外に扱うことは難しくなるうえに、 「内部化された労働者」 と 「外部化された労働者」 が同じ職場に混在することが普通のことになり、 さらに両者が同じ仕事に従事するということも珍しくなくなる。 こうした 「内部化された労働者」 (正社員) と 「外部化された労働者」 (非正社員) の境界がますます曖昧になりつつある現象は、 パートタイマーの戦力化を進めているスーパー・マーケット等の小売業で典型的にみられることである。 このようにして組織内 「外部均衡」 の問題が問われることになり、 それは労働市場の流動化が賃金決定システムに及ぼす最大の影響である。 | ||
|
(3) 新しい組織内 「外部均衡」 形成の考え方 このような状況のなかで新しい組織内 「外部均衡」 を形成する仕組みを作るには、 幾つかのシナリオが考えられる。 第一に内外無差別の原則をとる、 つまり 「内部化された賃金」 と 「外部化された賃金」 に同じ賃金決定システムを適用するというシナリオが考えられるが、 「基幹的労働者は企業内で長期間かけて養成する」 という基本戦略の有効性が支持されている限り採用は難しい。 それは 「内部化された賃金」 のなかに教育投資的要素が入るからであり、 そのため外部労働市場直結型で短期決済型の 「外部化された賃金」 と同じ決定システムを適用することは難しい。 そうなると 「内部化された賃金」 と 「外部化された賃金」 は異なる賃金決定システムを適用する、 という第二のシナリオを取らざるをえない。 しかし具体的な賃金決定システムを決めるには、 誰に 「内部化された賃金」 を適用し、 誰に 「外部化された賃金」 を適用するのかという 「賃金決定の内外区分」 を如何にするのかと、 その後に 「内部化された賃金」 と 「外部化された賃金」 が均衡するように、 それぞれについてどのような賃金決定システムをとるのかが問題になる。 | ||
4. 賃金決定の 「内外区分」 | ||
|
(1) 「内外区分」 を決める二つの基準 まず 「賃金決定の内外区分」 については、 これまでは 「内部化された賃金」 は正社員、 「外部化された賃金」 は非正社員という政策がとれてきたが、 雇用形態の多様化や労働市場の流動化のなかで、 その見直しが迫られており、 そのさい何が望ましい 「内外区分」 の新しい基準であるかが問われる。 理論的に考えると、 あるいは 「内部化された賃金」 の定義からしても、 最も望ましい基準は 「長期勤続が期待され、 長期的な観点に立って育成することが予定されている対象者 (つまり、 長期的な観点に立った教育投資の対象者) であるか否か」 であり、 これを 「長期的キャリア期待」 基準と呼ぶことにする。 この従来と同じにみえる基準をとったとしても、 新しい状況のなかで賃金制度は大きく変わることになろう。 もともと 「内部化された労働者」 であることが期待されていないにも関わらず 「内部化された賃金」 が適用されてきた一般職等の労働者がいるからであり、 雇用形態の多様化が進むなかで、 彼ら (彼女ら) には 「外部化された賃金」 が適用されていくことになろう。 他方で、 もともと勤続が短く流動的であることが想定されて雇用された労働者である 「外部化された労働者」 (非正社員) であっても、 結果として勤続が長期化し、 将来の勤続と教育投資効果が期待できるような 「内部化された労働者」 に実質的になった場合には、 「内部化された賃金」 が適用される必要があろう。 「内外区分」 のための、 考えられるもう一つの基準は、 企業の労働者に対する 「いまの役割期待」 であり、 その内容は、 企業が労働者に何を期待しているのかを具体的に考えてみればよい。 まずは当然のことながら、 「これこれの仕事をして、 これこれの成果を出してほしい」 という期待 (「仕事期待」) があり、 この面から 「内」 と 「外」 との距離を測るには、 いま従事している仕事の具体的な内容 (難しさ、 職責、 権限等) を検証すればよい。 もう一つは 「変化する業務ニーズに働き方を合わせてほしい」 という労働力の柔軟性に関わる期待 (「働く柔軟性期待」) であり、 具体的には、 担当する業務、 働く職場 (地域)、 働く時間が問題になろう。 | ||
|
(2) 「内外間距離」 と賃金制度 これまで 「内外区分」 を決める二つの基準について説明してきたが、 現実には、 労働者を 「内部化された労働者」 と 「外部化された労働者」 に明確に区分することは難しい。 たとえば 「内部化された労働者」 (正社員) の現状をみると、 転勤のない勤務地限定社員は明らかに 「外部化された労働者」 に近い存在である。 また 「外部化された労働者」 (非正社員) についてみると、 家庭の都合に合わせて短時間、 補助的な仕事に従事する就業調整型のパートタイマーのように 「内部化された労働者」 から遠い位置にいる労働者から、 労働時間と仕事が正社員とほとんど変わらない基幹型パートタイマーのように 「内部化された労働者」 にきわめて近い所に位置する労働者まで多様である。 このようにみてくると、 正社員と非正社員といったように 「内外」 を明確に二分割することは難しく、 労働者の特質は 「内」 から 「外」 へと連続的に変化し、 その間に多様なタイプが存在しうるのである。 雇用形態の多様化は、 「内」 と 「外」 を区分する垣根を確実に壊しつつある。 そうなると二つのことが課題になる。 第一は、 連続的に変化する 「内」 と 「外」 の距離を如何に測るかであり、 上述した 「いまの役割期待」 と 「長期的キャリア期待」 の二つの基準はそのための尺度でもある。 測定された距離と人事労務管理の現状を踏まえて、 第二の課題は、 どのような労働者のタイプを抽出するかであり、 このタイプの多様性に合わせて賃金制度は設計されることになる。 | ||
5. 新しい賃金決定システムの考え方 | ||
(1) 「教育投資的要素」 を考えた新賃金
こうした違いをもつ二つの賃金の均衡をはかるには、 「外部化された労働者」 の賃金は少なくとも、 「内部化された労働者」 の賃金のなかの 「仕事期待」 部分と同等であることが必要になろう。 このことを現行の賃金制度のなかで考えると、 次のようになる。 職能給ベースの現行の 「内部化された労働者」 の賃金が、 「仕事期待」 部分と 「期待能力」 部分を明確に分けていない、 職能資格に対応した範囲給の形態をとっていることを踏まえると、 「外部化された労働者」 の賃金は少なくとも、 彼ら (彼女ら) と同等の仕事に従事する 「内部化された労働者」 の資格に対応する最低レベルの賃金に合わせる。 それはある資格に対応する最低レベルの賃金が、 当該資格に格付けされている 「内部化された労働者」 が当該資格に対応する仕事を行ううえで必要とされる最低限の能力に対応した賃金であると考えられるからである。 ただし 「内部化された労働者」 でも、 能力発揮期である管理職レベルになれば、 賃金のなかに教育投資的要素 (「期待能力」 要素) がなくなると考えられるので、 この段階では 「仕事期待」 ベースの賃金が 「内外」 無差別に適用される必要があろう。 最近の賃金改革の動きをみると、 管理職レベルの賃金は職能給的要素が薄まり、 仕事給的傾向を強めているので、 そうした適用の基盤は形成されつつある。 | ||
|
(2) 「働く柔軟性期待」 を考えた新賃金 賃金の内外区分を行うもう一つの観点は、 図表に示した 「働く柔軟性期待」 の尺度である。 業務ニーズに合わせて柔軟に働いてくれる労働者は、 会社にとって価値の高い労働者であるが、 個人の立場からしても、 仕事、 働く時間、 働く場所が変わるということはリスクとコストを伴うことである。 そうなれば、 それにみあった賃金プレミアムがあって当然である。 実務的にいえば、 こうした変化に伴い個人が負担するコストを計算することは可能であり、 それを基礎に 「内部化された労働者」 と 「外部化された労働者」 の賃金の適正な格差を設定することが必要になろう。 これまで労働市場の流動化、 雇用形態の多様化に対応する企業内賃金決定システムのあり方について検討してきた。 それを踏まえると、 企業は 「内部化された労働者」 と 「外部化された労働者」 の賃金の新しい均衡をはかるために、 賃金の何が 「仕事期待」 部分であり、 何が 「期待能力」 部分であるかを明確に表現する賃金制度を構築する必要がある。 このことは職能給のなかで曖昧にされてきた仕事要素と能力要素を明確に分ける方向で、 賃金改革を進めるべきであることを示している。 |
|
■ 今野 浩一郎 (いまの こういちろう) 1946年東京生まれ。 71年東京工業大学卒業 80年東京学芸大学講師 82年同大学助教授 現在 学習院大学経営学部教授 主な著書 「勝ち抜く賃金改革」 (日本経済新聞社)、 「人事管理入門」 (日経文庫)、 「資格の経済学」 (共著・中公新書)、 「研究開発のマネジメント入門」 (日経文庫)。 |
岐阜県産業経済研究センター
| 今号のトップ |