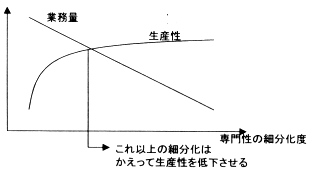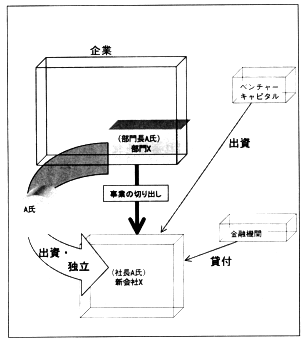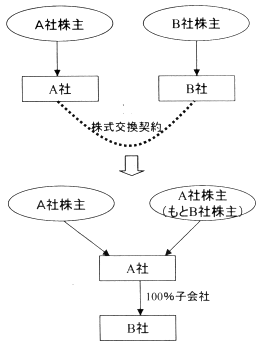| 論 文 | ||||
| 終身雇用の行方と新しい雇用形態
| ||||
| 武 藤 泰 明 (三菱総合研究所 主席研究員)
| ||||
はじめに | ||||
|
「ピーターと狼」 という童話がある。 ピーターという少年が、 狼が来たと告げて回る。 嘘である。 村中が大騒ぎになる。 同じことが二度くり返される。 そして三度目に本当に狼が来る。 しかし、 またピーターの嘘だろうと思って誰も信じない。 終身雇用制の崩壊というテーマは、 この狼に似たところがある。 甚大な不況が訪れると、 企業は雇用調整を行う。 採用も手控える。 マスコミは終身雇用制崩壊を唱え、 何人かの 「有識者」 もこれを支持する。 しかし狼は来ない。 雇用制度は昔のままである。 人材の流動性も、 雇用統計を見ている限り、 高まったという事実はない。 これは今回の不況でも同様である。 こういうことの繰り返しに吾々は馴れてきてしまったのだろう。 一時に比べると未来論はずいぶん少なくなった。 それだけ先が読み難くなった (これもよく言われる台詞だが後述するように真実である) のだろうが、 その数少ない未来論においても、 終身雇用制の崩壊を主張するものは少なくなってきたように思う。 問題はここから先である。 次にやって来る狼は、 果たして本物なのか。 それとも例によって 「ピーターの嘘」 なのか。 多くの論調は、 ピーターの嘘にあきあきして、 「またか」、 「そんなことはない」 というものになっている。 私自身も、 基本的にはこの考えに同調する−つまり終身雇用制・・というより長期雇用制度は消滅しないと考えるものだが、 恐いのは、 「狼は来ない」 と考えることが、 思考の停止につながる恐れがあるという点である。 比喩を続けることを許していただくなら、 狼が来ないということは 「何も来ない」 ことを保証するものではないのである。 では何が来るのだろうかというのが本稿のテーマである。 | ||||
終身雇用の背景とその崩壊 | ||||
|
終身雇用制の行方をたしかめるためには、 これまで同制度が成り立つ背景となっていたさまざまな事象がどのように変化しているのかを検討することが有効であろう。 具体的には、 つぎのような背景が終身雇用制を支えてきた。 1.経済成長 2.慢性的な人手不足 3.低賃金 4.外部労働市場の未整備 5.技術環境 「6.暗黙知」 型の知識移転システム このうち、 からまでは何度となく語られてきたものなので説明の必要はないだろう。 そしていずれも最早成立していない。 の外部労働市場については意見がわかれるところだろう。 市場が整備されたかどうかは、 実際に市場を通じての転職が増加したかどうかという基準で判断せざるを得ないからである。 要は結果論ということである。 転職というのも不思議なテーマで,人手不足 (たとえば80年代後半のような) になればキャリアアップ型の転職が増えるだろうと言われ、 不況になるとリストラで転職がふえるという話になる。 そして統計的には、 好不況を問わず転職率は実に安定的なのである。 吾々はもう少しまともに転職を議論するべき段階にさしかかっている。 では何を見て判断すればよいのか。 解の一つは、 フローの転職率ではなく、 ストックの「転職経験率」である。 日本人の転職経験率は意外に高い。 総務庁の調査(平成4年)によれば、 30歳代の男性の転職経験率は50%、 2回以上という人が29%である。 硬直的な長期雇用というのは大企業に限定された話なのかもしれない。 また少なくとも45歳までは、 転職によって賃金の上がる人のほうが下がる人より多い。 日本の外部労働市場は意外に整備されているのである。 つまり、 日本の企業社会というのは制度は長期雇用でありながら実際には人間が流動している。 制度論と実体論とを分けて考えていく必要がある。 そしてこの調査では40歳代の転職経験率もほぼ5割であった。 経験率なので数字が下がることはない。 すなわち、 この調査の時点で30歳代であった人々の転職経験率は、 彼らが10年後に40歳代になったとき、 10年前の40歳代の転職経験率より明らかに高くなるのである。 ついでに言えばこの調査で20歳代の転職経験率は45%であった。 すでに日本は転職経験があることが当たり前の国になっているのであるし、 この傾向は高まりつつあるのだ。 次にの技術環境の変化である。 これには2つの要素がある。 第1は、 前述のように先が読めなくなってきたという点である。 この理由は、 未確立の技術に基いてビジネスが展開されるようになったことである。 村上泰亮によれば、 戦後日本の高度成長は、 戦前、 遅くとも戦中までに欧米で確立し、 産業化された技術に支えられてきた。 すなわち、 日本企業は欧米ですでに行なわれている産業を日本に導入する為に設備投資を行ったのである。 産業が消滅するリスクはなかった。 あり得るとすれば 「つくり過ぎ」 に伴う過当競争であるが、 多くの場合この 「つくり過ぎ」 は内需拡大と輸出で吸収され、 好運にもこのつくり過ぎが価格低下と市場拡大をもたらすことで企業成長が実現されてきた。 このように、 未来の技術が 「読めている」 という前提の下では、 人材を早目に確保して育成することが合理的である。 とくに日本経済全体が成長し、 慢性的な人手不足であればこれは尚更である。 状況は、 たとえばビデオカセットレコーダーにVHSとベータという互換性のない二つの仕様が登場したあたりからおかしくなる。 一つの仕様、 標準が圧倒的優位に立ち、 劣後した仕様の為の設備投資が、 極端に言えばすべてムダになるという事態が生じはじめたのである。 そして周知のとおりこの傾向は増幅され続けている。 先端技術でいろいろな製品が生まれる。 すべて仕様が異なる。 数年後にどれが生き残るかは分からない。 消費者にとってもこれは困った事態だが、 供給者である企業の悩みはもっと深い。 自分達の仕様が負ければ設備投資費用を回収できないからである。 そしてこのような環境の下では、 技術者を確保して中長期の観点から育成することのリスクは言うまでもなく大きくなる。 技術のもう一つの大きな変化は、 イノベーションに大量の資本や組織を必要としないものがふえたという点である。 もうすぐ終わろうとしている20世紀は、 言わば巨大科学の時代であった。 航空・宇宙産業がその典型である。 このような産業では、 大きな資本と高度に組織化された研究開発部門を持つことがイノベーションの条件であり、 この条件を充たすのは国家と大企業だけである。 すなわち、 巨大科学の時代には、 大企業とは、 イノベーション発生装置としての希少価値を持つ存在だったということができる。 しかし今日情報通信やバイオテクノロジーの分野で急速にすすめられているイノベーションは、 資本も巨大組織も必要としていない。 アップルもマイクロソフトもベンチャーであった。 そしてこの2社を現在おびやかしているリナックスは、 言うならば 「インターネット上のボランティア団体」 である。 あるいは人間の遺伝子の解読は、 結局は個人が最も早く実現し、 国や大企業は遅れをとっている。 大企業には、 イノベーション発生装置としての希少価値がなくなってしまったということである。 そしてそうであるならば、 少くともイノベーションという観点からは、 企業規模が大きいことにはメリットがなくなっている。 そしてこれにかわるのが、 シリコンバレー・モデルと呼ばれるようなネットワーク型組織である。 そこでは人と企業は最新のイノベーションに応じて集まり、 優位性がなくなればネットワークは解消される。 そこには長期雇用などない。 最後はの知識伝達システムである。 日本の長期雇用とは、 社員の熟練を、 野中郁次郎の言を使えば 「暗黙知」 のままで、 時間をかけて伝えていく為の仕組みであった。 いわく、 ・ 門前の小僧ならわね経を読む ・ 一を聞いて十を知る ・ 子供は父親の背中を見て育つ 文化人類学的には、 日本人は欧米人に比べて 「ハイ・コンテクスト型」 である。 すなわち伝達したいことを文字や言葉などの記号に置き換える部分が少ない。 知識伝達にも記号が用いられる度合が低いのである。 このような傾向は、 企業や経営学がどうこう言って即座に変わっていくような性格のものではないのだろう。 会社は変われるが人はなかなか変わることができない。 しかし、 暗黙知で知識伝達が行なわれることには、 大きな短所がある。 それは、 伝達 (即ち育成) に時間がかかるという点である。 このような伝達システムは、 長期雇用とうまくマッチしていたといえるだろう。 とは言え、 知識伝達が短期間のうちに実現できるのならば、 そのほうが効率的である。 そしてそれが可能であるならば、 長期雇用は意味を一つ失うということである。 | ||||
誰が人材を育成するのか | ||||
|
環境変化についての議論はこれ位にしておこう。 長期雇用のインフラの多くが、 崩壊とまでは言わぬものの、 弱化・縮小しているのは間違いのない事実である。 しかし、 どれだけこの議論をすすめたところで、 長期雇用のメリットを語る人は依然存在するし、 その主張の多くが正しいという点は、 長期雇用否定論と同じである。 二元論には出口がない場合が多い。 観点を変えなければならない。 では、 吾々は何に注目し、 何を検討すれば良いのだろうか。 結論の第一は、 「人材の短期育成が可能なら、長期雇用が可能だ」 というものである。 前述のように、 日本企業は暗黙知による時間のかかる人材育成、 知識伝達を行ってきた。 しかしそれではコストがあわなくなった。 またイノベーションがこれまで以上に頻繁に起き、 個人の仕事も変わらざるを得ないとすると、 育成・訓練を短期間に実現する必要が増す。 面白いのは、 ○人材の短期育成が可能なら長期雇用は不要である。 ○人材の短期育成が可能なら長期雇用が可能である。 という命題がどちらも正しいという点である。 長期雇用と言う前提があったので、 暗黙知システムがうまく機能していたのがこれまでであった。 暗黙知システムから形式知システムに乗りかえるのであれば、 少なくとも暗黙知システムを守るために長期雇用を維持する必要はなくなる。 そうすると、 別のところに、 長期雇用を積極的に支持する理由があるかどうかという議論になる。 この問題を検討しはじめると長くなる。 ここでは前提としての短期的な人材育成の問題を取り上げるにとどめよう。 育成・訓練を行うのは誰か。 選択肢は3つである。 第一は社員個人である。 第二は企業である。 そして第三はよその企業である。 米国の大企業を見ていると、 一定のポストにつくためには、 学位、 資格、 キャリアが必要とされる場合が多い。 だから個人はより上のポストと待遇を目指して自分で費用を負担して学位や資格を取る。 ただしこれは今勤めている会社に長期雇用されたいからではない。 おそらく社員個人の自己啓発型教育というのは、 長期雇用の観点からはニュートラルな事象であろう。 少なくとも長期雇用を支えるものではない。
この場合の解決策は、 第三の道−すなわち外部の人材育成力を活用するというものである。 具体的にはアウトソーシングがある。 仕事の専門分化がすすむと、 その専門性を使えるような仕事量が減少する。 結果として専門性は向上しても生産性が低下することになる。 (図)。 これまで、 この問題の有効な解の一つは多能工化であった。 職種別労働組合のない日本ならではの解決策である。 しかし、 業務量が少ないという前提の下では生産性だけでなく専門性も向上して行かない。 ということはお家芸の暗黙知システムも機能しないということである。 結果として選択されるのがアウトソーシングである。 アウトソーサーの側は、 発注企業側で行うにしては量の少ない業務を集めることで専門性と生産性を実現する。 この場合、 発注企業の側は長期雇用制度を維持している。 但し、 この制度の適用対象となる社員の数は、 アウトソーシングを利用しない場合と比べると減っているはずである。 ここで、 アウトソーサーの側も長期雇用制度を採用しているとすれば、 マクロ的に見た場合、 仕事の担い手が発注企業の社員からアウトソーサーの社員に変わっただけであり、 産業界全体としては長期雇用が維持されることになる。 こう書くと一見何も変わっていないように思えるだろう。 しかし視点を変えると、 大きな変化があることに気付く。 アウトソーサーのほうが発注企業より専門性と生産性が高いという前提を置くと、 社会全体として、 その仕事に携わる人数が減るのである。 言うなれば、 企業単体ではなく、 社会レベルで合理化が行われているのである。 ここで思い起こさなければならないのは、 日本の長期的な労働力需給である。 生産年齢人口のピークは1995年、 およそ8700万人であった。 そして2015年にかけて、 20年間でおよそ1000万人の減少が見込まれている。 長期的な経済成長の為には労働力が不可欠であるが、 現在の日本は、 少くとも量的にはこの条件を充たしていない。 労働力減少の下で成長を実現するためには、 生産性の飛躍的な上昇が不可欠なのである。 そしてこれを実現する為の手段の一つが、 人材の社会的再配置なのである。 メイテックの前社長 (現相談役) の大槻三男氏は、 同社の社内報で、 人材の 「社会財」 化の必要性を説いているが、 この発想には企業の論理を超えた真理がある。 | ||||
組織ぐるみで転職する時代 | ||||
ここでは例として二つの制度を取りあげる。 第一はMBO (マネジメント・バイアウト) である。 MBOとは、 社員が実施している事業を別会社化し、 スピンオフしたその社員自身が出資をし、 経営にあたることを指す。 そう言うと、 まるで江戸時代の商人の 「のれん分け」 のようであるし、 これまでの日本企業では、 社内ベンチャー等を切り出す時に、 この 「のれん分け」 の方法がよく採用されていた。 つまり、 形態としてはさほど目新しいものではない。 しかし、 米国で普及したMBOには、 これとは徹底的に違うところがある。 それは、 親会社と切り出された企業の間に資本関係がなくなるという点である。 手続としては、 親会社が子会社を設立するに際し営業譲渡を行う。 現物出資である。 当然、 親会社は株主になるが、 この株式はベンチャーキャピタルや投資ファンドに売却される。 ここで親子の縁が切れる。 なぜ縁が切れることが重要なのか。 本格的な連結の時代を迎え、 親会社は親会社としてコア・コンピタンスを追求し、 選択と集中をすすめている為である。 小さな事業を切り出しても、 それが連結の対象になるのであればあまり切り出した意味はないのである。 社員の立場で考えるなら自分が馴れ親しみ、 ずっと続けて行こうと考えていたビジネスや研究開発から企業が手を引こうとする時、 そのビジネスを続けさせてくれるのがMBOである。 ただし、 親会社は手を引くのでそれだけ資金的には厳しい。 うまく投資ファンドやベンチャーキャピタルから資金を調達できたとしても、 相手は純粋にキャピタルゲインを求めるので、 事業には成長性が不可欠だし、 株式公開が想定されていなければならない。 この問題に対する最近の解決策としては、 金融業以外の企業、 すなわち事業会社が出資者になるというものがある。 出資の目的は、 優良な取引先の育成と確保である。 この場合投資主体はキャピタルゲインを求めないので、 MBOで設立された企業は短期的な収益性を気にせずに事業を続けることができる。 良い製品やサービスを効率的に生み出していればよいということである。 MBOという制度自体はいわゆる「舶来もの」であるが、 すでにその日本的な活用方法が生まれはじめている。 新たな和魂洋才というべきであろう。
まず手法である。 A社 (買収する側) とB社 (される側) という二つの企業がある。 両社が株式交換を行うということは ・ A社は自社の株式をB 社の株主に渡す。 この株式はB社株主が保有しているB社株と等価である。 ・ かわりに、 B社株主は保有するB社株式を A社に渡す。 ということである。 この手法の特徴は次の二点である。 B社はA社の100%子会社になる。 もしA社が市場で B社株を集めようとすると、 どうしても売らないという株主が残ることが多い。 そうすると、 A社はB社を100%子会社にすることができない。 株式交換の場合、 B社の株主総会でA社との株式交換に応じることが求められているので、 B社株主は例外なく株式交換に応じることとなる。 新規資金の調達が不要である B社株式と交換されるA社株式は、 原則として増資により調達される。 このA社株式の引受け手は、 予めB社株式と決まっている。 これまでであれば、 A社はB社を買収しようとすると、 その為の資金を、 内部保留、 新規借入、 あるいは増資により調達していた。 株式交換の場合、 増資は行うので形式的には資金調達というプロセスは残るものの、 資金供給者は決まっているので新たに資金の貸し手を募る必要がない。 株式交換の解禁によって期待されるのは、 第一に、 友好的な企業結合の促進である。 そして第二に本稿の文脈との係わりで重要なのは、 これが中堅・中小企業による大企業子会社の買収を可能にするものだという点である。 株式交換に際しては買収側は新規の資金調達を要しない。 これまで買収というと買い手は資金量の豊富な大企業、 買われる側は中小企業というのが一般的であったが、 株式交換により逆のパターンが生まれ易くなる。 大企業は現在、 コア・コンピタンスの論理により周辺事業の整理をすすめているが、 株式交換制度はこれを促進するものとして機能するだろう。 雇用への影響であるが、 企業が特定の事業分野から撤退しようというとき、 撤退部門の社員は、 その会社に残るのであれば自分の専門性と異なる分野に再配置される。 内部労働市場である。 これに対してこの部門が株式交換の対象になり他の企業に買収されるならば、 自分が培った専門性を活かし続けることができる。 専門性は維持されるということである。 以上の2つの例で示したかったことは、 個人レベルではなく、 いわば「組織ぐるみの転職」というのが有り得る時代になったという点である。 日本の長期雇用制度というのは、 個人が専門的な仕事を継続的に実施し、 生産性をあげていく仕組みとして理解されてきた。 しかし実際には、 長期雇用を実現するために、 社員を専門的な仕事から「引き剥がす」ことも多い。 そして「引き剥がす」制度が維持され、 かつ雇用が保証される仕組みが崩壊するというのが最も不幸な状態である。 これが現状であることはいうまでもない。 上記のような「組織ぐるみの転職」は、 個人を熟練した仕事から引き剥がさぬことにより雇用を保証しようというものである。 もちろんこの保証はこれまで企業が行ってきた保証ほどには確かなものではないが、 専門性を発揮できる環境が維持されることは間違いない。 結果として個人の生産性は高まり、 雇用可能性も高まることになるだろう。 | ||||
すべての企業が派遣会社化する時代 | ||||
|
最後は昨年の派遣法改正の影響である。 この改正によりホワイトカラーの派遣が原則自由化された。 結果として人材派遣業以外の企業−すなわち一般的な事業会社が「専門性はあるが余剰の人材」を派遣することができるようになる。 これも「専門性を維持しながら長期雇用を実現する」ことの手段となる。 残念ながら事業会社には派遣の営業力・ノウハウがない。 しかし早晩事業会社の余剰人員に仕事を斡旋することをビジネスとする企業が現われるだろう。 日本の労働市場に、 人材の需給のミスマッチが大きいことは間違いのない事実である。 しかしミスマッチの大きさは、 新たな展開の機会にもなるのである。 企業結合にせよ人材斡旋にせよ、 これまでは規制によってこれらの機会を実現することが妨げられてきた。 自由化はまだ始まったばかりだが、 従来では考えられなかったような新たな需給システムが拡大していくことに期待したい。 |
|
■ 武藤泰明 1955年生まれ。 80年、 東京大学大学院修士課程修了、 三菱総合研究所入社。 現在、 主席研究員、 経営コンサルティング部長。 主な著書に 「新・雇用革命」 (共著・経済界)、 「牧野昇のアウトソーシング経営革命」 (共著・経済界)、 「持株会社のすべて」 (日本経済新聞社) |
岐阜県産業経済研究センター
| 今号のトップ |