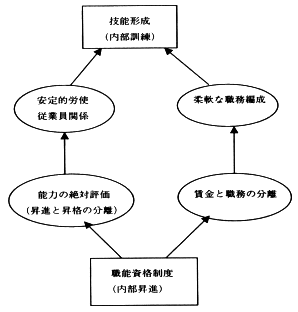| 論 文 | ||
| 日本型雇用システムの行方
| ||
| 宮 本 光 晴 (専修大学経済学部 教授)
| ||
1 はじめに | ||
|
改めて指摘するまでもなく、 日本の雇用システムは大きな変容に迫られている。 日本型雇用慣行と呼ばれきた諸制度は急速に変化しつつある。 一般化して言えば、 相互に関連し合った諸制度の複合体として一個のシステムが構成されるのであれば、 既存の諸制度の変更がシステムの変化につながることは間違いない。 問題は、 この変化の意味を正確に理解することにある。 つまり、 システムを構成する諸制度の変化の結果、 システムはその基本的な構造自体を変化させるのか、 それともそのような変化を組み込むことの結果、 むしろその構造を維持した上での変化にとどまるのか、 より正確には、 その構造を維持するために変化を組み込むのか。 既存のシステムをXと表現すれば、 前者はXからYへの構造転換を意味するのに対して、 後者はXからX' への変化を意味するものとなる (富永1995)。 言うまでもなく、 現在の支配的見解は、 X→Y型の変化である。 既存の日本の雇用システムを定着型のシステムとみなすなら、 それは定着型から流動型の雇用システムへと構造転換を遂げるであろうことが想定されている。 果たしてそうであるかを検討したい。 現在の制度変更を子細に検討すれば、 それは定着型というシステムの基本構造を維持した上での変化、 すなわちX→X' 型の変化ではないのか。 このように問題を設定する理由は、 これまでにないシステムの変化を目の当りにすることからの認識上の関心からだけではない。 システムの性格に応じてその内部の人間の行動が異なるのであれば、 現在進行しつつあるシステムの変化をX→Y型と理解するのか、 X→X' 型と理解するのかでは、 システムを構成する人々の行動は大きく違ってくる。 この意味は重大である。 もしシステムの現実の変化がX→X' 型であるにもかかわらず、 人々がそれをX→Y型とみなして行動すれば、 その結果は、 人々の行動だけではなく、 システムの運営そのものの混乱となるかもしれない。 この意味でシステムの現実の変化を正確に理解する必要がある。 そのためにはまずは既存の日本型と呼ばれる雇用システムに関して正確な理解が必要となる。 その理解において誤るなら、 現在の変化の理解においても誤ることになる。 | ||
2 職能資格制度 | ||
|
既存の日本型雇用システムはもはや存続できない、 それは定着型から流動型の雇用システムへと構造転換を遂げる必要があるといった議論に接するとき、 どうしても腑に落ちない点がある。 つまり、 このような議論の前提として、 日本型と呼ばれる雇用システムは年功賃金と終身雇用から成り立つものとみなされている。 すると、 ここから業績給や年俸制の導入をもって、 あるいは大規模な雇用調整や短期契約型の雇用の導入をもって、 XからYへの構造転換を主張することも当然となる。 しかし、 年功賃金と終身雇用をもって日本の雇用システムを理解することの誤りに関しては、 すでに多くの議論があるはずだ。 もしその二つをもって、 賃金の調整も雇用の調整も排除するのが日本型雇用システムであるとみなすなら、 あるいは平等主義と集団主義の経営とみなすなら、 それは誤解も甚だしい。 これについて繰り返すことは避け、 ここでは既存の日本型雇用システムの構造を明示しよう。 問題は、 現在のさまざまな制度変更が、 その構造そのものの変化を意味するのか、 それともそのような構造を維持するための変化であるのかという点にある。 そこでまず、 その構造を 「職能資格制度」 として捉えよう (宮本1999)。 雇用システムは、 採用から始まって、 訓練や配置、 報酬や昇進、 そして解雇などの諸制度から構成されているのであるが、 これを一つのまとまりとして組み立てるのが、 日本の雇用システムに関しては、 職能資格制度であると考えることができる。 またそれゆえに、 職能資格制度においてさまざまな制度変更が進行することになる。 上記の問題設定に即して言えば、 それが職能資格制度そのものの変更であるのか、 それともその制度を維持するための変更であるのかが、 現在のシステムの変化をX→Y型と考えるか、 X→X' 型と考えるかのカギとなる。 そのためにも職能資格制度を正確に理解する必要がある。 まず職能資格制度を簡単に説明しよう。 従業員は 「職能」 という概念に基づいて等級 (ランク) づけられる。 職能は、 職務能力(competence)として定義される。 この意味で、 職能の等級はcompetence-rankと表現できるものとなる(Marsden1999)。 その等級は職務あるいは職種ごとに定義されるのではなく、 すべての職務を含めて一律に定義される。 職能の等級ごとに賃金が設定され、 職能等級の上昇すなわち昇格が、 賃金の増額すなわち昇給となる。 従業員はその職務遂行能力を評価され、 職能等級の上を上昇する。 このように決まる賃金が職能給や資格給と呼ばれることになる。 それは職能すなわち職務遂行能力の等級に対応したという意味で、 能力給の性格を持つ。 この意味で日本型雇用システムの賃金を年功賃金と呼ぶことは単純に誤っている。 職能等級の昇格と昇給を通じて賃金カーブは上昇するが、 個人間の昇格の格差は年齢とともに拡大し、 これに応じて個人間の賃金の格差は拡大する。 ただし、 従業員の賃金のすべてが資格給によって構成されるわけではない。 資格給とともに年齢給の部分があり、 さらに同一の等級において自動的な昇給、 すなわち定期昇給がある。 この年齢給と定期昇給の部分が固有の意味での年功賃金となる。 後述するように、 この意味での年功賃金の廃止が進んでいる。 このように職能資格制度は、 まずは職能という能力概念に基づいた昇格と昇給の制度として形成された。 それはまた昇進の制度となるのであるが、 さらには技能形成の制度でもあることにより、 日本型雇用システムの骨格となる。 このことを概念的に示すなら、 下図のようになる。
以上のように職能資格制度が理解できるなら、 次の課題は、 このようなシステムに進行する制度変更をどのように理解するのかにある。 その前に次のことを指摘する必要がある。 すなわち雇用の継続性であり、 それは職能資格制度の前提でもあり、 結果でもあると考えることができる。 つまり、 このシステムにおいて、 職能として定義される能力は、 技能のレベルにおいて企業特殊的となるだけでなく、 その評価において企業特殊的となる。 この二つの理由から、 従業員にとっては移動可能性が制約される。 ゆえに、 このようなシステムを従業員が受け入れるためには、 雇用の継続性が前提となる。 他方、 企業にとっては、 このようなシステムを維持するためには、 従業員の定着が前提となる。 たとえ移動可能性が制約されていたとしても、 ひとたび従業員が離職すれば、 企業にとってはそれまでのコストの回収の機会は奪われるのであり、 ゆえに離職の可能性を抑えるためには、 雇用の継続性に対する何らかの言質が必要となる。 この意味で、 雇用保障の観念が成立する。 もちろん、 絶対的な保障があるわけではない。 雇用調整そのものはこれまでにもなされてきたのであり、 ただしそれは雇用の継続を前提とした上での調整であるという意味で、 アメリカ企業のレイオフの制度と区別される。 ただし後者に関しても、 先任権を前提とすることにより、 事実上の雇用保障を与えるものであった。 いずれにせよ、 これが定着型雇用システムであり、 それは職能資格制度が維持されるための前提条件であると同時に、 このようなシステムが現実に維持されることの結果として、 従業員の定着が事実として成立させるものでもあった。 すると、 このように職能資格制度と定着型の雇用が表裏一体のものであれば、 前者の変更が後者の変更を生み出すことも必然となる。 このように理解した上で、 現在の制度変更について考えよう。 | ||
3 職能資格制度の問題 | ||
|
職能資格制度が抱え込む問題は二つある。 一つはその昇格と昇進そして報酬の制度を運営するためのコストであり、 もう一つはその前提となる雇用の継続性を維持するためのコストである。 この二つから、 職能資格制度はいわば高コストのシステムということになる。 と同時に、 このシステムは、 その技能形成を通じて高パフォーマンスのシステムであることにより、 高コストと両立できるものであった。 すると問題は二つに限られる。 一つは、 このシステムに付着したコストが過大になるということであり、 もう一つは、 このシステムが生み出すパフォーマンスが低下するということであり、 いずれにおいても高コストと高パフォーマンスのバランスが崩れる。 ゆえに、 これに対処することに迫られるのも当然であり、 その方向もまた明らかである。 すなわち、 コストの削減であり、 パフォーマンスの向上である。 そのための制度変更が進むことになる。 職能資格制度のコストの面に関してもう少し述べよう。 職能等級に基づく賃金、 昇格に基づく昇給を制度化することにより、 職能資格制度そのものは能力主義のシステムを意図するものであった。 と同時に、 そこにはこの意味での能力主義を緩和する装置が組み込まれてきた。 一つは、 上述したように、 年齢給と定期昇給の存在であり、 それは資格給という能力主義に、 年功賃金という平等主義を組み込むものであった。 これによって前者が生み出す個人間の格差を、 後者によって埋め合わすことが意図された。 これがいわゆる集団主義の経営であった。 誤解を避けるために付言すれば、 平等主義や集団主義は、 能力主義や個人主義に張り合わされたものであり、 後者を無視して前者が成立するわけではない。 しかしこの結果、 従業員の年齢構成の上昇にともなって、 賃金コストは増大する。 能力主義を緩和するもう一つの装置は、 昇格における絶対評価であると言える。 もし昇格が、 昇進と同様の相対評価であれば、 昇格の機会は限定され、 昇給を通じた個人間の報酬の格差はそれだけ大きくなる。 この意味で、 昇格における絶対評価と昇進における相対評価の二重性は、 もう一つの形で、 能力主義に平等主義を組み込むものであった。 この点に関しても付言すれば、 日本の雇用システムだけではなく、 一般にシステムあるいは何らかの集合体は、 その内部に能力主義と平等主義、 個人主義と集団主義の原理を組み込むことによって成立する。 ただし、 絶対評価自体は、 能力主義と抵触するわけではない。 むしろ能力の絶対評価によって、 能力主義のシステムは、 公正なものとして受け入れられたと解釈できる。 しばしば指摘されるように、 従業員の関心は能力の正当な評価にあるのであって、 能力主義そのものへの反対ではない、 というのが日本企業あるいは日本社会の特徴であれば、 このことは絶対評価の能力主義によって可能になったと理解できる。 このような能力主義が、 安定的な労使関係と安定的な従業員関係の形成に大きく寄与したことは間違いない。 しかしこの結果、 昇格の人数が多くなり、 これに応じて賃金コストが過大となる。 ただし、 これもまた昇格の絶対評価だけの問題ではない。 絶対評価の基準とその運営の問題でもあり、 結果として、 それは年功的な昇格に傾いた。 その理由の一つは、 職能として定義される能力が、 経験としての要素を多くすることにある。 これはOJTの方式による技能形成においては不可避と言える。 しかしこの結果、 経験の評価が在職によって、 つまりは年功として評価されることも不可避となる。 これが定期昇給の制度となる。 もう一つの理由は、 職能の定義が職務や職種ごとではなく、 企業内部で一律のものとされることにある。 これによって評価の基準は、 個々の職務に即して具体的に定義されるというより、 一般的あるいは抽象的に定義されることになる。 このことは評価の主観性や恣意性がそれだけ強まることを意味している。 これを避けるために、 先と同様、 在職年数が昇格の基準とされがちとなる。 この結果がラインから離れた中高年管理職の過剰であると言える。 さらにこの結果、 管理職ポストへの昇進もまた年功的となるのであった。 以上のような理由から、 職能資格制度に付着するコストが過大になったことは間違いない。 そしてもう一つは、 雇用の継続性を維持するためのコストである。 このことが過剰雇用の抱え込みとなり、 あるいは雇用調整を遅らせることの結果、 労働コストを過大とすることもまた間違いない。 この二つがとりわけ中高年管理者において重なり、 かくしてこの部分での雇用調整が急速に進むことになる。 以上のことは、 職能資格制度のコストの面での問題である。 と同時に、 それがパフォーマンスの面で問題を抱えていることもまた間違いない。 コストの削減が緊急の課題であったとしても、 システムの存続のためには、 パフォーマンスの向上が不可欠であることはいうまでもない。 この二つの課題から、 職能資格制度の制度変更が進むことになる。 | ||
4 職能資格制度の変更 | ||
|
コストの削減とパフォーマンス向上を課題とした職能資格制度の変更が、 まずは年功賃金の部分に向かうことは容易に理解できる。 年齢給や定期昇給の廃止であり、 これに代わって業績給や年俸制が導入されつつある。 先に述べたように、 職能資格制度が本来意図する能力主義を緩和する装置が年齢給や定期昇給の制度であれば、 この廃止は、 職能資格制度を本来の能力主義として組み立て直すことだとみなすことができる。 いや、 正確には次のように理解すべきである。 つまり、 ここでの課題は二つであり、 一つは職能資格制度を本来の能力主義のシステムとすることであり、 もう一つは能力主義とは区別されるものとして業績主義の制度を導入することであり、 前者の観点から年齢給や定期昇給の廃止が打ち出され、 後者の観点から業績給や年俸制の導入が図られる。 そしてさらに、 この二つと区別された問題がある。 それが固有の意味での雇用の問題であり、 過剰化した雇用の調整と新たな形態の採用をどのように行うのかが問われている。 このように問題を整理することができる。 ここからまず指摘すべきは、 年齢給や定期昇給などいわゆる年功賃金の廃止は、 日本型雇用システムの破棄や崩壊を意味するわけではないということだ。 それは職能資格制度を本来の能力主義とすることであり、 事実、 職能資格とその資格給の部分に変更があるわけでなく、 これに加えて、 年齢給の部分を業績給に置き換える、 あるいはボーナスの部分を業績評価に基づく年俸制とすることが試みられている。 この意味で、 職能資格制度をその骨格とした日本型雇用システムは、 修正を加えた上で維持されるとみなすことができる。 だがそのためにも、 留意すべき問題がある。 第一に、 職能資格制度を本来の能力主義とすることは、 職能等級とその昇格に関して、 能力評価の厳密化を要求する。 このことは職能の絶対評価と対立するわけではない。 しかしそのためには評価と等級の基準が明示される必要がある。 そのためには職能を職種や職務ごとに定義する必要がある。 この結果、 職種や職務間の移動は制約されることになるかもしれない。 第二に、 職能としての能力が経験の要素を含むものである以上、 あるいは経験を離れては定義されないものである限り、 在職を基準とした能力の評価を全面的に廃止することはできない。 この意味で、 経験を積み重ねることが不可欠となる職務等級に関しては、 たとえその規模を縮小するとしても、 定期昇給の制度が維持されるべきとなる。 第三に、 能力評価の厳密化から、 昇格の絶対評価の方式が変更されるかもしれない。 昇格の人数自体が限定されるのであり、 この結果、 昇格は相対評価に近づくことになる。 もしそうだとすると、 それは職場における協力や情報共有を妨げることになるかもしれない。 その結果は、 職場を単位とした技能形成の障害となるかもしれない。 第四に、 同じく業績給や年俸制に関しても、 業績あるいは成果の基準を明示することが要求される。 そのためには職務の明確化が必要となり、 この結果、 同じく職種や職務間の移動は制約されることになるかもしれない。 さらに次のこともまた重大な問題となる。 すなわち業績給や年俸制の導入は、 年齢給や定期昇給を集団主義の報酬であるとし、 これに代わるべき個人主義の報酬として主張されるのであるが、 果たして業績や成果を個人を単位として評価することは妥当であるのか。 それは職場やチームを単位とした活動と対立するかもしれない。 要するに、 現在の制度変更は、 能力主義と業績主義を通じて個人間の格差の拡大を図り、 そのことが一方では過大となったコストの削減となり、 他方では個人のインセンティブを高め、 パフォーマンスの向上につながるものと想定されている。 そしてこのことが集団主義に代わる個人主義のシステムであるとみなされている。 しかしこの結果、 職場やチームを単位とした集団としての活動は、 協力関係や情報の共有を損ない、 あるいは技能形成の低下となることにより、 パフォーマンスの低下に見舞われるかもしれない。 おそらく留意すべきは次の点にある。 現実の活動が集団を単位とする以上、 少なくともそのような部門においては、 個人主義の原理だけではなく、 何らかの形で集団主義の原理を必要とする。 すると、 能力主義が個人を単位として成り立つ以上、 業績主義こそが集団を単位とすべきものとなる。 つまり、 業績給や年俸制は、 職場やチームあるいは企業業績の全体と連動したものとなるべきであり、 この意味で現在の業績給や年俸制は反対方向に向かっているのではないのか。 資格給を個人ごとの能力主義とするのであれば、 業績給や年俸制はむしろ組織や集団と結び付けるべきなのである。 付言すれば、 この意味での業績主義は、 報酬に関してのものである。 他方、 管理職ポストへの昇進に関しては、 選抜あるいは相対評価として、 個人ごとの業績評価が強まることは当然となる。 と同時に、 それゆえに、 昇格に関しては、 絶対評価の能力主義を堅持すべきと思われる。 いずれにおいても評価の厳密化が要求されるのであるが、 昇進においては選抜の意味での個人ごとの業績評価、 昇格においては共通の基準に基づく個人ごとの能力評価となるのである。 そのためにも、 上述したように、 職能の定義と評価の明確化が必要とされる。 ただし、 それは職務給のように狭く限定する必要はない。 現実には仕事分野ごとに職能の範囲が成立しているのであり、 しかしその等級が、 これまでは一律に定義されてきた。 これを仕事分野ごとの職能等級とすればよい。 その上で資格給に基づく賃金と職務の分離が可能になる。 もしこのように職能資格制度が再編成されるなら、 このことは雇用の流動化とは何の関係もない。 雇用の流動化が雇用調整を意味するのであれば、 それは既存の日本型雇用システムにおいても組み込まれてきた。 確かに10年以上にわたる日本経済の低迷と直近の2年連続のマイナス成長のため、 雇用調整の規模とスピードはこれまでにないものであり、 とりわけ製造業を中心として、 定着型の雇用は縮小を続けている。 と同時に、 将来の不確実性というより見通しのなさのため、 パートや派遣や委託など、 短期契約型の雇用は増大を続けている。 この結果、 産業全体としては、 正社員 (定着型雇用) の比率は低下を続け、 非正社員 (流動型雇用) の比率が急増している。 しかし、 これをもって日本型雇用システムが崩壊した、 定着型から流動型へのシステムの転換が生じているとみなすのは短絡である。 現に成長産業の代表である情報サービス業においては、 正社員比率は産業全体や製造業よりも高い水準にある (『労働白書』 1999)。 それも当然のことであり、 職能資格制度を本来の能力主義のシステムとする、 あるいはそこに業績主義を組み入れることをもって競争優位のシステムを追求する、 というのが現在の制度変更の目的であれば、 そのためにも定着型の雇用が不可欠となる。 雇用調整に関しては、 それが雇用の継続性を前提とした上での調整であるのか、 それとも継続性そのものの否定であるのかが問われている。 これまでの雇用調整が前者を意味するものであれば、 この点が不明となっていることは間違いない。 選択定年制や退職金の廃止は後者の印象を強めるものであるのに対して、 ワークシェアリングの提唱や、 定年延長や再雇用の制度化は、 雇用の継続性をさらに制度化することでもある。 あるいは勤続年数のデータが示すように、 現実には雇用の継続性そのものが低下しているわけではなく、 そして現実の雇用調整のプロセスは、 雇用保障の観念自体を排除したレイオフ型とはまったく異なるものである。 要するに、 システムとして定着型の雇用自体が否定されているわけではない。 むしろ留意すべきは、 もし雇用の継続性そのものの否定という印象が強まるなら、 企業にとっては従業員の定着の保障自体も奪われるということだ。 職能資格制度を組み立て直すために過剰となった中高年層の削減が不可避となる、 それも大規模になさざるを得ないというのが現在の雇用調整であったとしても、 ここから自ら率先して雇用流動化といったスローガンを掲げ、 その結果、 雇用の継続性そのものを否定するとの印象が強まるなら、 30代・40代の定着自体が危うくなる。 この結果、 職能資格制度そのものの基盤が崩れるなら、 このことは現在の制度変更の意図自体を自ら否定することにほかならない。 単純なことであるが、 50代の雇用を維持することのコストは、 30代・40代の雇用からの利益と見合うだけのことであり、 確かにこのバランスが現在崩れていると言うことはできる。 そのために中高年の雇用調整に迫られているとしても、 しかしこのことは、 このようなシステム自体の否定を意味するわけではない。 しかし、 このように日本型雇用システムが維持されるとしても、 その上で雇用の流動化が不可避であることもまた間違いない。 これについて最後に述べよう。 | ||
5 雇用の流動化か | ||
|
本稿の議論の焦点は、 職能資格制度の観点から日本型雇用システムを理解することにあった。 そして職能資格制度と雇用の継続性が表裏一体の関係であれば、 前者の制度変更が、 後者の変化を生み出すことも不可避となる。 果たしてそれは雇用の流動化を進めるものであるのだろうか。 この見通しはある意味で簡単であり、 能力主義と業績主義をもって職能資格制度を維持する限り、 それに応じて定着型の雇用が制度化されるということであり、 なぜなら能力の形成と評価は個別の企業を単位とし、 同じく業績の評価と報酬も個別の企業を単位とする以外にないからである。 反対に言えば、 このような職能資格制度に組み込む必要のない労働、 あるいは組み込むことが不適切な労働に関しては、 短期契約型の雇用が制度化されることになる。 それは既存の日本型雇用システムにおいても制度化されてきたのであり、 その主たる形態がパートやアルバイトであれば、 これに加えて、 派遣や委託の形態での雇用の利用可能性が拡大することにより、 短期契約型の雇用の範囲が拡大するだけのことでもある。 これまでに述べたように、 職能資格制度は、 一方では内部の昇格と昇進の制度であり、 他方では内部の技能形成の制度であった。 そしてその背後には、 職場やチームを単位とした活動があった。 このような条件にかなうことのない労働は、 短期契約型の雇用に置き換えられるということであり、 この傾向が一気に進んでいると言うことはできる。 それがまったく低い水準からの増加であれば、 その伸び率が際立つことも当然となる。 さらには派遣や委託の形態だけでなく、 その技能の内部形成が困難な労働、 その内容が高度に専門化された労働に関しても、 短期契約型の雇用の利用可能性が高まっているということはある。 しかし、 こうしたことはあくまでもマージナルな現象にすぎない。 マージナルという意味は、 それがシステムの構造になるわけではないということであり、 昇進と報酬と技能形成の制度として職能資格制度が維持される限り、 それに応じて定着型の雇用が制度化されるというだけのことである。 別の観点からいえば、 短期契約型の雇用がシステムの構造となるということは、 それによってシステムが再生産されることを意味している。 これまでに見たように、 雇用システムは同時に技能形成のシステムである以上、 このことは短期契約型の雇用によって技能形成が再生産されることを意味している。 果たしてこのようなシステムは可能であるのか。 そのためには個々の企業の外部に技能形成のシステムが制度化されることを必要とする。 あるいは企業間の移動を通じて技能形成を図ることができるようなシステムを必要とする。 もちろん、 このような雇用システムが存在しないわけではない。 前者はいわゆる専門職 (プロフェッショナル) の雇用システムであり、 後者は職人型の雇用システムであった。 このような領域が次第に拡大する、 あるいはそれを意図的に形成する、 ということはあったとしても、 それが直ちに日本の雇用システムとして確立されるわけではない。 当面のところその可能性はない以上、 技能形成とその評価のシステムとしての日本型雇用システムの意義を過小評価すべきではない。 留意すべきは、 どのようなシステムであれ、 技能形成自体はストックとして形成される必要があるということだ。 それを企業内部の形成ではなく、 社会的な形成とするためには、 企業を単位とするのと同様、 その訓練から評価に至るまで、 高度に組織化された社会的な制度を必要とする。 いずれにせよ、 ストックとしての技能形成を無視して、 フローとしての短期契約型の雇用だけからシステムが成り立つわけではない。 せいぜいは、 ストックからの引き抜きがあるだけとなる。 もし引き抜きが支配的となるなら、 ストックの形成自体が衰退する。 この結果は、 システム自体の衰退となりかねない。 もし雇用の流動化を課題とするのであれば、 職能資格制度を通じたストックとしての人材形成と、 フローとしての人材利用をどのように接合させるのかを考えるべきである。 その一つの可能性が、 現在の職能資格制度の変更であるかもしれない。 これによって職能の範囲が、 企業の全体を単位としたものから、 職種や職務を単位としたものに変更されるなら、 技能形成とその評価の企業特殊性の度合いはそれだけ弱まることになる。 これに加えて、 ポータブルな退職金や企業年金が制度化されるなら、 同じく企業特殊性の制約は弱まることになる。 あるいは職能の昇格とポストの昇進がより明確に切り離されることの結果、 ポストの昇進ではなく、 職能の昇格がこれまでよりもより強く動機づけられることになる。 こうして言葉の本来の意味での職能、 すなわちコンピタンスを基盤としたキャリアの意識が強まると思われる。 さらに、 このような方向に向けて職能資格制度を変革するための最大の課題は、 技能形成とその評価の中に標準化の要素を積極的に付加することにある。 そのためにも職務のデザインやキャリアの組み方や評価の基準に関して、 労働の側の積極的な関与や発言を図る必要がある。 このようなプロセスの結果、 雇用の流動化が進むなら、 このことがエンプロイアビリティを高めるものとなる。 と同時に、 再雇用の受け皿が成長力のある中堅・中小企業であれば、 この意味で日本型雇用システムは産業構造の転換に貢献することになる。 そのためにも、 ストックとしての人材形成の装置としての日本型雇用システムの重要性が認識されるべきである。 むしろ最大の課題は、 このようなものとして日本型雇用システムが維持できるのかということにある。 そのためにはその中核部分での定着型の雇用が必要となるのであり、 しかし先に述べたように、 この条件が失われつつあるかもしれない。 過去においても定着を促進するために日本型雇用システムが形成されたのであれば、 その制度変更とともに、 実はこのことが新たな課題となるのである。 | ||
参考文献 |
|
■宮本 光晴 一九四八年大阪市生まれ。 横浜国立大学卒業後、 一橋大学大学院を経て、 現在、 専修大学教授。 専攻は企業経済論。 主な著書 「日本の雇用をどう守るか」 (PHP新書)、 「人と組織の社会経済学」 「日本型システムの深層」 (東洋経済新報社)、 「企業と組織」 (新世社)、 「日本人はなぜイギリス人に憧れるか」 (PHP新書)。 |
岐阜県産業経済研究センター
| 今号のトップ |