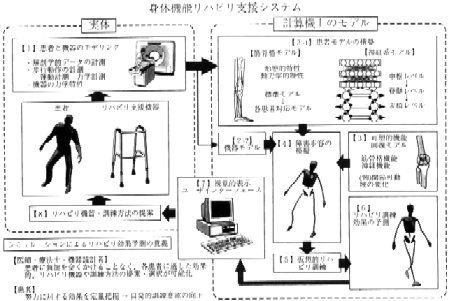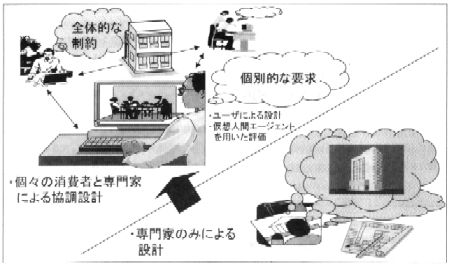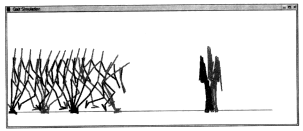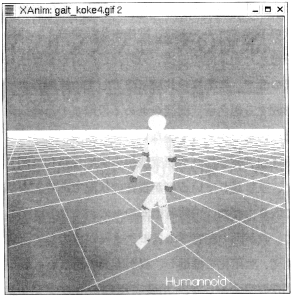| 論 文 | |||||||||
| 消費者指向のものづくりの実現に向けて
| |||||||||
| 宮 下 和 雄 (通産省 工業技術院 電子技術総合研究所 主任研究官)
| |||||||||
1. はじめに | |||||||||
|
現在、 我が国においては過剰な種類や量の製品が溢れんばかり存在する一方、 消費者が各製品に求めるニーズは従来より一層多様化しており、 個々の消費者にとって本当に欲しい製品が現実には見つからないことも多い。 今後、 急速な少子化、 高齢化が進展する中で、 消費者が製品に求める内容も益々個別化していくものと考えられる。 高齢者や身障者への総合的なサポートも含め、 多様化する個々の消費者の要求に応えることができる製品を、 設計から製造、 保守、 廃棄、 再生など、 その製品の全ライフサイクルに関してユーザが希望する形態で、 個々の製造企業が安価に製品を提供・サービスすることが21世紀における一層豊かな国民生活にとって望ましい。 しかしながら、 従来の企業におけるものづくりのシステムでは、 製品の開発設計から製造による供給までが、 企業などの製品製造者からの視点を中心としたものであり、 そこには実際に製品を日常生活において使用するユーザからの視点が組み入れられてこなかった。 そこで、 今後はユーザが製造者と種々の情報を共有・融合することにより、 機能やサービス面で新たな付加価値をもつ製品を企画・設計、 生産して、 その製品ライフサイクルにわたりユーザの高い満足度を適切なコストで提供することのできる新しいものづくりのシステムに変えていく技術開発が期待されている。 ものづくりの技術を巡っては、 現在、 コンピュータやインターネットなどの情報技術基盤の革新を踏まえた次世代生産システムの具体的、 国家的な研究開発が世界的な競争状況の下で展開されつつある。 わが国でも実施されている、 IMS (注1)、 インバースマニュファクチャリング (注2) やCALS (注3) などのプロジェクトはその代表例である。 こうした状況は、 製造技術が国や地域の重要戦略であることを反映しており、 国際社会における貢献とナショナルセキュリティの確保の面からも、 ものづくり技術の重要性は今後も増大していくと考えられる。 しかしながら、 従来のものづくりにおける研究開発は、 生産効率を重視した製造者主体の研究開発であって、 ユーザ主導の製品概念とその製造技術に関する研究開発は未だに殆んど見ることができない。 (注1) 財団法人 製造科学技術センターが中心となって実施している生産に関する統合的な国際プロジェクト。 本プロジェクトの下に多数の研究テーマが実施されている。 詳細は http://www.ims.mstc.or.jp/ を参照のこと。 (注2) 環境に配慮した製品開発や、 設計・生産・廃棄の効率化、 適正化に関する技術の研究開発を目的にしたプロジェクト。 詳細は http://www.mstc.or.jp/inverse/main.htm を参照のこと。 (注3) 製品のライフサイクルに関わる全ての人が、 ライフサイクルにわたって発生する全ての情報を電子化 (デジタル化) し、 それぞれ (組織の内外ともに) が必要な情報を共有することにより、 業務、 製品の品質及び生産性を向上させ、 ライフサイクル全体でのコストの低減 (、 期間の短縮、 品質の向上) を図るというコンセプトを実現するための研究開発を行うプロジェクト。 詳細は http://www.cif.or.jp/index.html を参照のこと。 ユーザ主導型の消費者指向のものづくりに関しては、 政府の技術予測調査委員会でも、 2010年頃の工業製品 (機械製品) とその生産に関して、 「社会、 文化の多様な発展へ貢献する工業製品」 などを求めており、 その重要性が徐々に認知され始めている。 具体的には、 先の調査では、 消費と生産の結びつきの強化、 店舗と工場のネットワーク化の進展によるメーカーと卸・小売業、 製造業と流通業の融合、 高齢者の機能劣化 (ブレインおよびフィジカル面) や身障者を総合的にサポートする製品や生産システムなどの技術の重要性が高いことを指摘している。 ここで提言する消費者指向のものづくりは、 このような社会的な要請に応える重要かつ必要な課題であり、 今後の研究開発に向けて産官学が互いに協力して総合的な取り組みを行う必要がある。 | |||||||||
2. 期待される効果 | |||||||||
|
消費者指向のものづくりが実現すれば、 その直接的な効果として、 個々の消費者が各々のニーズや生活環境に最も適した製品を安価にかつ迅速に手にいれることができ、 日常生活をより充実させることができるということがあげられる。 しかし、 消費者指向のものづくりが実現した際にもたらされる効果は、 個々の個人生活上の便宜の改善にとどまらず、 更に個人や社会にとって以下のような効果が期待できると考えられる。
| |||||||||
(1) 市場の拡大 (新産業創出) | |||||||||
|
ユーザ満足度の高い製品やサービスというユーザメリットの視点が、 製造者側においても、 より消費者の立場に立った新たな製品知識や製造技術の高付加価値化をもたらし、 その結果、 高品質の新製品やサービスが開発提供され、 新たな市場が発展する可能性が生まれる。 消費者が製造に積極的に関われる環境が整うことにより、 これまでは生産者から消費者へと一方通行であった情報の流れが双方向となり、 生産者と消費者のインタラクションが活発化することで、 新たな市場や産業が創出され、 ビジネスの機会が拡大することが期待される。 | |||||||||
(2) ものづくり強化 | |||||||||
|
我が国において製造分野の海外シフトや若者の理工学離れが進む中、 技能や技術の空洞化が懸念され、 「ものづくり」 とその技術体系としての工学が見直されつつある。 消費者指向のものづくりを実現する中で、 ユーザと製造者の協調設計・製造を実現することにより、 新たな技術開発が促進されるだけではなく、 熟練者に蓄積された技能の見直しが進められ、 その再利用化や次の世代への継承などの成果も期待される。 また、 通産省の新産業創出環境整備プログラムにおいては、 製造業の空洞化が懸念される今こそ、 引き続きわが国が 「世界の母工場」 の役割を果たすことが必要であり、 情報通信システムと融合した高度生産システムなどが新製造システム分野の成長に関する重要課題であるとしている。
| |||||||||
(3) 環境負荷低減 | |||||||||
|
消費者が自分自身にとって必要不可欠な機能のみをもつ製品を設計したり、 製品ライフサイクルから総合的に見た適正品質を持つ製品仕様を決定したりすることが可能になるという点で、 消費者指向のものづくりは製品の過剰仕様の排除につながり、 省エネルギーや環境負荷低減面での効果も期待できる技術である。 更に、 消費者にとって不必要な機能を予め製品に持たせないことは、 廃棄やリサイクルに要する社会的な負荷を削減するのみならず、 製造企業にとっても、 材料コストの削減や無駄な在庫の低減につながり、 企業の収益力の向上に貢献する。
| |||||||||
3. 技術的課題 | |||||||||
|
消費者指向のものづくりを実現するためには、 企業による製品の企画、 設計、 製造から消費者による製品の使用、 廃棄のプロセスにおいて、 ユーザと製造者が常時情報を共有・融合することにより、 ユーザ側は満足度の高い製品とサービスを受けることができ、 かつ、 製造者側はユーザからの直接的なニーズ情報が獲得できるものづくり環境が構築されなければならない。 具体的には、 適正品質を保証する製品の企画・設計における企業とユーザとの協調作業を支援する技術、 製品の性能を実際に生産する以前にできるだけ正確に評価するためのエンジニアリングシミュレーションモデル作成技術、 個々のユーザが欲する多種少量の製品を効率的に製造するための生産技術などが中核技術課題として解決される必要がある。 さらに、 研究開発成果を円滑に実用化するためには、 住宅、 家庭用品、 介護機器、 生産システムなどの多くの分野における製品に関して、 消費者指向のものづくりの在り方を実証実験により評価し、 その実現のためのより具体的な技術課題の抽出を行うことが重要である。 消費者指向のものづくりに伴う、 基本的な技術開発課題として、 現時点で我々が想定しているものには以下のものがあげられる。 | |||||||||
(1) 企画・設計技術 | |||||||||
|
消費者と企業内の専門技術者が協調して作業を行うことにより、 消費者が望む製品としての適性な機能・性能・品質・コストなどを設定したり、 それを実現する設計解を探索することを支援するための技術が必要である。 消費者と技術者が同時に同じ場所にいなくても作業できるように、 ネットワークに接続された計算機による支援が前提となる。 また、 一般に消費者は技術的な専門用語を理解しておらず、 自らの要求する内容も整然と伝えることが困難である。 こうした状況を克服し、 消費者と専門技術者との相互理解と意思疏通を支援するための技術や、 消費者の出した曖昧な仕様に基づいても技術的な設計を進めることを可能とするための設計支援技術が必要となる。
| |||||||||
(2) 評価技術 | |||||||||
|
消費者と技術者の協調作業によって設計された製品が、 本当に消費者の出した要望を満たしているのかを評価し、 その結果を企画・設計にフィードバックする技術が必要である。 そのためには、 計算機を用いたよりインタラクティブなエンジニアリングシミュレーション技術の研究や、 製品のプロトタイプを評価可能な形で低コスト、 短時間で製作 (試作) 提供するラピッドプロトタイピング技術の研究が必要となる。
| |||||||||
(3) 生産技術 | |||||||||
|
個々の消費者のニーズを低コストに実現するためには、 今までとは異なる生産技術の開発が必要である。 即ち、 これまでの大量生産によるコスト削減を前提とした効率化ではなく、 如何にきめ細かく生産の無駄を無くすかという点で、 よりフレキシブルな加工・組み立て技術や、 資材計画や生産計画などのリアルタイムな最適化技術の研究などが重要である。 更に、 企業によって製造された後に、 消費者が実際に製品を使用しながら、 自由に製品の構造や働きを自分自身の手で改良していく 「オンサイトマニュファクチャリング」 が可能であることが望ましい。 そうした要求を実現するためには、 現在の形状記憶性合金のような材料やFPGA (書き換え可能ゲートアレイ) のような電子回路素子をより改良していく研究開発が、 消費者指向のものづくりを実現する上で非常に重要である。
| |||||||||
4. 消費者指向のものづくり事例 | |||||||||
消費者指向のものづくりの有効性やその実現における課題を見極めるためには、 具体的な事例において実証的な適用実験を行う必要がある。 現在、 介護・リハビリ機器と集合住宅を例題として取り上げて、 消費者指向のものづくりの在り方に関して検討を進めている。
介護・リハビリ機器に関しては (図1参照)、 使用する人の体格や病状・障害の様子に応じてきめ細かな機器設計が求められる。 しかし、 病状や障害の程度の変化により、 ユーザにとっての介護やリハビリの必要性は時と共に変化していく。 したがって、 当初購入した機器がいつまでも最適であるとは限らず、 ユーザが実際に使用しながらも病状や障害の程度の変化に従って、 ユーザ自身が機器の構造や機能を、 簡単に変更できることが望ましい。 さらに、 機器の構造や機能を決定する際も、 実際に使用するユーザにとって、 その人の体力、 体格、 病状・障害の程度を考慮したときに、 そうした構造や機能で効果があるかどうかを、 実際に使用しながら試行錯誤で決めるのではなく、 計算機シミュレーションにより事前に確認できることが望ましい。 介護・リハビリ機器に関しては、 ユーザが肉体的・精神的にハンディキャップを負っている場合が多いと考えられるので、 できる限りユーザに負担を与えないで、 なおかつユーザにとって最も有効な機器を提供できるアプローチとして、 消費者指向のものづくりの考え方を進めていく必要がある。 身体に障害を持った個々のユーザに対して、 個々の障害の特質に応じて使いやすい食器などを提供する取り組みは欧米や日本の会社でも既に行われている。 こうした取り組みの枠を広げて、 様々な介護・リハビリ機器にも適用していくことが、 消費者指向のものづくりの一つの大きな目標である。
こうした事例を考えていく中で見出された一つの知見は消費者 (ユーザ) の身体的個性の重要性である。 即ち、 介護・リハビリ機器や住宅などの設計に当たって、 最も重要な要素の一つは実際に製品を使用する人の身体的な特徴を十分に考慮することである。 このことは従来の製品設計においては、 標準的な種々の規格などに従うことによって考慮されてきた。 しかしながら、 障害などの後天的な変化も含め、 実際の人間の体は実に多様で、 標準的な人体モデルを使った設計では、 個々の消費者にとって本当に満足の行く製品を作ることは困難である。 更に、 スプーンやペン、 部屋や鞄など、 日常使用される機器の多くは、 ユーザが静止した状態で使用するのではなく、 何らかの動作を行いながら使用するものである。 このような機器を設計する際には、 個々の使用者の動きのモデルも考慮して、 個々のユーザにとって好ましい製品にする必要がある。 しかしながら、 人間は非常に複雑な動作が可能であり、 筋肉や骨格の少しの違いにより、 個々の人にとっての自然な動きは当に千差万別である。 したがって、 個々のユーザにとって使いやすい機器を提供するためには、 個々のユーザの動作モデルを生成する技術が不可欠である。 現在、 筆者の研究室では仮想人間エージェントとして、 個々の人の筋骨系を忠実に再現した計算機上のモデルを用いて歩行などの様々な動きを自動的に生成するシステムの研究開発を行っている (図3、 図4参照)。 このような柔軟な動作を自動的に生成できるモデルがあれば、 ユーザの動きの特性に適した製品が設計できているかどうかの正確な評価を効率的に低コストで実施できる。 こうした基礎的な研究に基づく技術の積み重ねが、 「消費者指向のものづくり」 という大きな目標達成のために必要である。 | |||||||||
5. おわりに | |||||||||
|
ここで提唱している 「消費者指向のものづくり」 という概念や開発成果は幅広い分野の製品やその製造に対して適用できる基盤技術としての価値を有している。 この消費者指向のものづくりは、 高いユーザ満足度というユーザメリットが同時に製造に関する知識の高付加価値化と、 新たな生産技術として製造者側メリットにつながることを意図した 「適性品質製品の適正な供給」 を実現する技術研究開発であることが特徴である。 即ち、 消費者指向のものづくりに関連する研究開発や事業を進めることにより、 技能や技術の空洞化が懸念されるわが国において、 熟練者技能の再利用化や技能の継承など製造業の持続的発展や、 新たな分野の製造業の創出が期待できる。 また、 製品ライフサイクルから総合的に見た適正な製品仕様という点では無駄な仕様の排除につながり、 省エネルギーや環境負荷低減面の貢献も期待できる。 我が国にとって製造業は今後とも重要な位置づけを持ち続けることから、 国の施策としても、 新たな製造技術関連の研究開発の重要性は高まっている。 生産技術に関する情報化やメカトロニクス化技術に関して、 従来のCIM (計算機統合生産) やコンカレントエンジニアリングの概念が、 改めて、 今後10年から15年の現実的な主導概念として語られている。 また、 インターネットの爆発的な普及により、 バーチャルファクトリーなどのより先導的な構想も提出され、 先進国の間では取り組みが進みつつある。 しかしながら、 わが国の現状の市場メカニズムは、 欧米と比較すると、 分野を超えた企業間の連携、 分野共通技術の重要性などの面で、 産業界の共通基盤としての技術資産を形成する総合研究開発を進める段階まで基礎技術と技術基盤が熟していない。 その結果、 国際的な研究連携体制作りや研究成果の国際規格化に関して、 立ち遅れているのが現在の状況である。 本稿で取り上げた 「消費者指向のものづくり」 に関して、 我が国の産官学の各セクターが協力して研究開発、 実用化を推進し、 我が国発の新しいものづくりの概念として、 「消費者指向のものづくり」 の考えを広く世界に発信していけるよう、 今後も努力を続ける必要がある。 |
|
■宮下和雄 (みやした・かずお) 1983年東京大学工学部精密機械工学科卒業。 1985年同大学院工学系研究科修了。 同年松下電器産業入社。 1990-92年カーネギーメロン大学ロボティクス研究所客員研究員。 1995年通産省工業技術院電子技術総合研究所に入所。 1999年筑波大学連携大学院助教授併任。 工学博士(大阪大学)。 知的生産システム、 分散協調問題解決などに関する研究に従事。 AAAI、 IEEE、 人工知能学会、 情報処理学会、 スケジューリング学会各会員。 |
岐阜県産業経済研究センター
| 今号のトップ |